論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子曰君子欲訥於言而敏於行
校訂
諸本
- 論語集釋:史記萬石君傳贊「仲尼有言」云云,徐廣注曰:「訥字多作『詘』,音同耳,古字假借。」玉篇「呐」字下引論語:「君子欲訥於言。」云:「或作『呐』。」
※『史記』万石君伝「太史公曰:仲尼有言曰『君子欲訥於言而敏於行』」。
東洋文庫蔵清家本
子曰君子欲訥於言而敏於行
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
(なし)
標点文
子曰、「君子欲訥於言而、敏於行。」
復元白文(論語時代での表記)












※欲→谷・訥→吶(甲骨文)。論語の本章は、「欲」「行」の用法に疑問がある。
書き下し
子曰く、君子は言於訥し而、行於敏きを欲む。
論語:現代日本語訳
逐語訳

先生が言った。「貴族は言葉を控えめにして行動は敏速であろうとする。」
意訳

諸君。くっちゃべって働かないような奴は、貴族ではないぞ。
従来訳
先師がいわれた。――
「君子は、口は不調法でも行いには敏活でありたいと願うものだ。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子說:「君子要言談簡潔,要行動敏捷。」
孔子が言った。「君子はしゃべる言葉を簡潔にせよ、行動は敏速にせよ。」
論語:語釈
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。


(甲骨文)
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
君子


論語の本章では”貴族”。論語の本章は孔子の言葉が「君子欲…」で始まるから、弟子の”諸君”と解した場合、「諸君が欲する」という文になってしまい意味が通じない。立派な人格者とかいった面倒くさい語義が付け加わったのは、孔子より一世紀後の孟子から。ただし本章が後世の創作の場合、孟子の解釈が適切。詳細は論語における君子を参照。
欲(ヨク)


(楚系戦国文字)
論語の本章では”…でなければならない”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は楚系戦国文字。新字体は「欲」。同音は存在しない。字形は「谷」+「欠」”口を膨らませた人”。部品で近音の「谷」に”求める”の語義がある。詳細は論語語釈「欲」を参照。
訥(トツ)
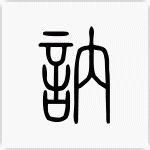
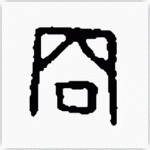
(篆書)/「」(甲骨文)
論語の本章では”寡黙・黙っている”。初出は後漢の『説文解字』。同音は存在しない。字形は「言」+「甲骨文から存在する。字形は「内」”向かい合わせの大ガマ一組”「吶」+「𠙵」”くち”で、発言を止められたさま。原義は”沈黙”。詳細は論語語釈「訥」を参照。
於(ヨ)


(金文)
論語の本章では”…について”。初出は西周早期の金文。ただし字体は「烏」。「ヨ」は”~において”の漢音(遣隋使・遣唐使が聞き帰った音)、呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)は「オ」。「オ」は”ああ”の漢音、呉音は「ウ」。現行字体の初出は春秋中期の金文。西周時代では”ああ”という感嘆詞、または”~において”の意に用いた。詳細は論語語釈「於」を参照。
言(ゲン)


(甲骨文)
論語の本章では”ことば”。初出は甲骨文。字形は諸説あってはっきりしない。「口」+「辛」”ハリ・ナイフ”の組み合わせに見えるが、それがなぜ”ことば”へとつながるかは分からない。原義は”言葉・話”。甲骨文で原義と祭礼名の、金文で”宴会”(伯矩鼎・西周早期)の意があるという。詳細は論語語釈「言」を参照。
而(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”~かつ~”。初出は甲骨文。原義は”あごひげ”とされるが用例が確認できない。甲骨文から”~と”を意味し、金文になると、二人称や”そして”の意に用いた。英語のandに当たるが、「A而B」は、AとBが分かちがたく一体となっている事を意味し、単なる時間の前後や類似を意味しない。詳細は論語語釈「而」を参照。
敏(ビン)


(甲骨文)
論語の本章では”素早い”。新字体は「敏」。初出は甲骨文。甲骨文の字形は頭にヤギの角形のかぶり物をかぶった女性+「又」”手”で、「失」と同じく、このかぶり物をかぶった人は隷属民であるらしく、おそらくは「羌」族を指す(→論語語釈「失」・論語語釈「羌」)。原義は恐らく、「悔」と同じく”懺悔させる”。論語の時代までに、”素早い”の語義が加わった。詳細は論語語釈「敏」を参照。
行(コウ)


(甲骨文)
論語の本章では”行動”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。「ギョウ」は呉音。十字路を描いたもので、真ん中に「人」を加えると「道」の字になる。甲骨文や春秋時代の金文までは、”みち”・”ゆく”の語義で、”おこなう”の語義が見られるのは戦国末期から。詳細は論語語釈「行」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章は、春秋戦国の誰一人引用せず、『史記』で孔子の言葉として司馬遷が紹介する例が一つ、その焼き直しが『漢書』に一例あるに止まる。同時期の董仲舒は「訥」も「吶」も言わないので、作者ではないだろう。戦国末期の荀子は「吶」を用いて、別の説教をしている。
君子必辯。凡人莫不好言其所善,而君子為甚焉。是以小人辯言險,而君子辯言仁也。言而非仁之中也,則其言不若其默也,其辯不若其吶也。言而仁之中也,則好言者上矣,不好言者下也。故仁言大矣。

君子は口が回らなくてはならない。なべて人は、自分のやった善行を誉められると気分がよい。そこで君子は語彙が豊富であることから、誉めるにも物言いが耳に心地よい。小人の言葉がとげとげしいのに対し、君子の言葉は情け深く聞こえる。
情け深い物言いが出来ないなら、むしろ黙っているか、言いにくそうに言った方がいい。情け深い物言いが出来るのに、しゃべろうとしない奴は腹黒い。(何か企んでいるに違いない。)だから情け深い言葉には、価値があるのだ。(『荀子』非相11)
つまり論語の本章は、前漢中期には出来ていたわけだが、文字史的に春秋時代に遡るのは不可能ではないが、母なる河を目指すシャケの遡上なみには難しく、漢字の用法が怪しく春秋戦国の引用が無いことから、董仲舒ではない初期前漢儒の誰かの作品と考えるのが一つ筋が通る。
だが孔子の言葉ではないとも断じ難い。「しゃべってないで働け」は、春秋の君子=貴族にはよく当てはまるからだ。孔子生前の君子とは、すなわち戦士に他ならず、君子は戦場働きが出来なければならない。戦国の縦横家とは違うし、しゃべって武器を振るうと舌を噛む。
しかし君子の仕事には、ほかに外交官もある。「お勉強ばかりで外交交渉をしくじる奴には見所がない」と孔子も言っている(論語子路篇5)。荀子が言うように、口が回らないではいられない。戦士だって、いくさの前では演説して、部下の士気を高めなければいけない。
あるいは弟子の中に、口先ばかりの男がいたのだろうか? そういう奴への説教なのかも。
解説
本章からは後世、論語里仁篇22と、以下のような別伝が作られた。
孔子觀周,遂入太祖后稷之廟,廟堂右階之前,有金人焉。參緘其口,而銘其背曰:「古之慎言人也,戒之哉!無多言,多言多敗;無多事,多事多患。安樂必戒,無所行悔。勿謂何傷,其禍將長;勿謂何害,其禍將大;勿謂不聞,神將伺人。焰焰不滅,炎炎若何;涓涓不壅,終為江河;綿綿不絕,或成網羅,毫末不札,將尋斧柯。誠能慎之,福之根也。口是何傷,禍之門也。強梁者不得其死,好勝者必遇其敵。盜憎主人,民怨其上。君子知天下之不可上也,故下之;知眾人之不可先也,故後之。溫恭慎德,使人慕之;執雌持下,人莫踰之;人皆趨彼,我獨守此;人皆或之,我獨不徙;內藏我智,不示人技;我雖尊高,人弗我害;誰能於此?江海雖左,長於百川,以其卑也;天道無親,而能下人。戒之哉!」孔子既讀斯文也,顧謂弟子曰:「小人識之!此言實而中,情而信。《詩》云:『戰戰兢兢,如臨深淵,如履薄冰。』行身如此,豈以口過患哉!」

周の都・洛邑留学中の若き日の孔子が、周の開祖・后稷の霊廟に詣でたところ、右の階段前に銅像がある。口を三針縫い付けられ、背中に次のような由来が書いてあった。
「昔の言葉を慎んだ人である。これに倣って慎め。
口を慎め。口数が多いと失敗が多い。行いを慎め。行いが多いと憂いが多い。気楽に構えて慎みを怠らなければ、行いに後悔は残らない。
大した事ではない、と言うな。今も大きくなろうとしているぞ。何のことも無いと言うな。損害はどんどん増えているぞ。誰も聞いていないというな。精霊のたぐいが人を監視しているぞ。灯し火の間に消さないと、燃え上がってからではどうしようもないぞ。しずくの間に締めないと、ついには川になってしまうぞ。細い間に刈り取っておかないと、はびこってどうしようもないぞ。細い間に抜かないと、まさかりでしか切り倒せなくなるぞ。
実に実に、慎むことが幸せの元である。口は全てを傷付ける、諸悪の元である。強がりをいう者はろくな死に方をしない。人を言い負かす者は敵だらけになる。逃亡者は元の主人を憎み、民はお上を恨む。君子は人の風上に立つ道理が無いのを知り、だからへり下る。人々の先頭に立てない道理を知り、だから後ろを付き従う。
温和、丁寧、慎みの作用に、人は引き寄せられるのだ。高みを譲って大人しくしていれば、人は踏み越えようとはしてこない。人々がわあわあと走り回る中で、自分一人自分を守る。人々がうろたえ騒ぐ中で、自分は関わらずにいる。智恵は心の奥に仕舞っておき、技は人前にさらさぬようにする。となれば一人で孤高を守っても、人は危害を加えてこない。
この教えを誰がよく守るだろうか? 長江は左に流れ、海はさらにその左にあるが、全ての河川の長であるのは、低い位置にいるからだ。天の計らいには依怙贔屓が無いが、それでも人を底から支えている。これを思って慎め。」
孔子は読み終えると、振り返って弟子に言った。「君、これを知りたまえ。この戒めはまことに当を得ている。人の心を分かった上で、事実を教えている。詩に”ぶるぶると深い沼を覗くように、薄い氷を踏み歩くように”という。行動がこのように慎重なら、口を慎むなどわけはない。」(『孔子家語』観周3)
定州漢墓竹簡の発掘により、『孔子家語』が王粛による偽作だという説は、清儒の誣告と判明したが、だからといって全部が史実でないこと、論語と同じ。孔子の洛邑留学に従ったのは、門閥家老家の一員である南宮敬叔だけだし、敬叔は「小子」と呼ばれる小僧でもない。
余話
だから悪相に描かれる
新注には、とある儒者の個人的な思いつきを記している。
新注『論語集注』
胡氏曰:「自吾道一貫至此十章,疑皆曾子門人所記也。」
胡氏曰く、「吾が道一貫自り至る此の十章、疑うらくは皆な曾子の門人の記所す所也」と。

胡寅「”吾が道は”以降ここまでの十章は、たぶん曽子の門人が書き記したのではなかろうか。」
この胡寅という男は論語里仁篇16に既出の楊時の弟子で、同様に宋の儒者らしい悪党。
北宋が滅亡に瀕した時、徽宗皇帝が素直に「ワシが悪かった」と謝ったので、気の毒がった民百姓の義勇軍が、続々と都の開封に詰めかけた。胡寅はすでに官途にあり、開封にいたにもかかわらず、義勇軍には加わりもせず、大学構内に逃げ隠れた後、さっさと行方をくらました。→『宋史』胡寅伝
胡寅は亡命政権である南宋が成立する頃合いを見計らって朝廷に現れ、ちゃかり官職にありついたが、逃げたくせにわあわあとウソ泣きしながら、その実政敵の悪口ばかり言うので、うんざりした宰相により左遷された。およそ儒者という生き物は、常人の感覚では捉えがたい。
胡寅は子供の頃からずる賢かったのを、佐渡のおやじに折檻され、書物千巻の物置に閉じこめられたが、一年あまりでそれを全部暗記したという。同じく佐渡のおやじを持った朱子と同じで、マゾになるよう育てられた子供は大人になると、必ず佐渡になるのだろう。
宋儒については論語雍也篇3余話「宋儒のオカルトと高慢ちき」を参照。



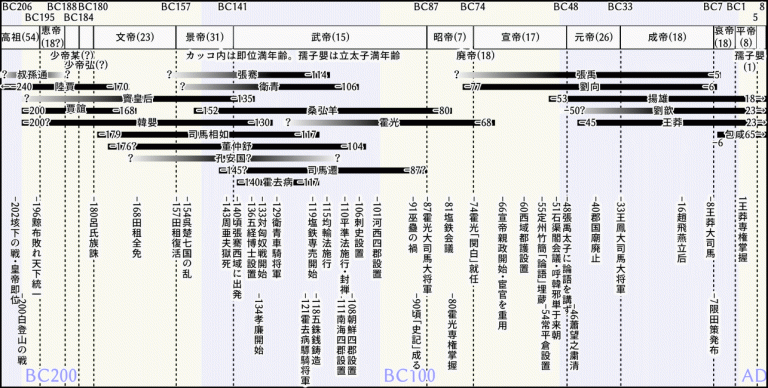


コメント