論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子曰君子喻於義小人喻於利
校訂
東洋文庫蔵清家本
子曰君子喻義小人喻於利
後漢熹平石経
…君子喩…
※「喩」字:断片〔口〕〔亼〕のみ。
定州竹簡論語
[子曰:「君子踰a於]義,小人踰[於]利。」73
- 踰、今本作「喩」。『説文』無「喩」
※「喩」は無くとも「喻」は親字以外にあり。念のため『釋文』を検索したが該当する文字列無し。
→子曰、「君子踰於義、小人踰於利。」
復元白文(論語時代での表記)












※「踰」→「兪」。論語の本章は、「小人」が論語の時代に存在しない。本章は戦国時代以降の儒者による創作である。
書き下し
子曰く、君子は義しき於踰え、小人は利於踰ゆ。
論語:現代日本語訳
逐語訳

先生が言った。「君子は正しさに過剰になる。小人は利益に過剰になる。」
意訳

立派な君子は、片時も正義から道を踏み外さず、下らない小人は、片時も利益を忘れぬのであるぞよ。
従来訳
先師がいわれた。――
「君子は万事を道義に照らして会得するが、小人は万事を利害から割出して会得する。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子說:「君子通曉道義,小人通曉私利。」
孔子が言った。「君子は道義に能く通じている。小人は私利に良く通じている。」
論語:語釈
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。


(甲骨文)
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
君子(クンシ)・小人(ショウジン)

論語の本章では、「君子」は”地位も教養もある立派な人”。「小人」は”卑しく無知な下らない人”。孔子の生前、「君子」とは従軍の義務がある代わりに参政権のある、士族以上の貴族を指した。「小人」とはその対で、従軍の義務が無い代わりに参政権が無かった。つまり「君子」を賞賛し「小人」を罵倒する理由がなかった。詳細は論語における「君子」を参照。また春秋時代の身分については、春秋時代の身分秩序と、国野制も参照。
漢語「君子」の物証は西周からあるが、「小人」の物証は戦国時代にならないと見られない。従って仮に論語の本章が史実でも、単に「貴族と庶民」を意味するだけだが、「小人」の中で謙遜の語としての「小人」(わたくしめ)ではなく、”くだらない奴”の一例は次。
子曰:唯君子能好其駜(匹),小人剴(豈)能好亓(其)駜(匹)。古(故)君子之友也
子曰く、唯だ君子のみ好く其の匹たるを能う。小人豈に好く其の匹たるを能うや。故に君子の友也。(『郭店楚簡』緇衣42・戦国中期或いは末期)
”君子だけが友人付き合いするに値する。小人ごときがよい友になるわけがない。だから君子の友というのだ。”緇衣とは現伝『小載礼記』の一篇で、この竹簡はその遠い材料の一つなのだろうが、同じ話は現伝『小載礼記』に無い。似た話だと次になろうか。
子曰:「唯君子能好其正,小人毒其正。故君子之朋友有鄉,其惡有方;是故邇者不惑,而遠者不疑也。《詩》云:『君子好仇。』」
先生が言った。「君子だけが正しい者を好む事が出来、小人は正しい人をけなしいじめる。だから君子の友人は近所に住んでいるもので、人を嫌う理由にも筋目がある。だからすぐ側で見ている人にも解り易く、遠くでうわさを聞きつける人も疑わない。(『小載礼記』緇衣20)
ともあれ漢語「小人」は戦国の産物。従って本章を史実とは断じがたく、後世理解された上掲のような語義で「君子・小人」を解釈するべき。
孔子の生前、「君子」=戦士は誰にも明らかで、わざわざ説明する必要が無かった。春秋末期、「卒」”徴集兵”と「弩」”クロスボウ”の組み合わせが実用化されると、戦士としての「君子」の価値が暴落した。このため「君子」は、わざわざ説明する必要のある言葉になった。
そこに登場したのが孔子没後一世紀に現れた孟子で、孟子は「君子」を「小人」と対比させ、ありがたそうな意味合いをつけ加えた。そして激しく「小人」をバカにし始めるのは、孟子より半世紀以上のちに生まれた、戦国末期を代表する儒者・荀子だった。
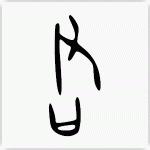

(甲骨文)
「君」の初出は甲骨文。甲骨文の字形は「丨」”通路”+「又」”手”+「口」で、人間の言うことを天界と取り持つ聖職者。春秋末期までに、官職名・称号・人名に用い、また”君臨する”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「君」を参照。


(甲骨文)
「小」の初出は甲骨文。甲骨文の字形から現行と変わらないものがあるが、何を示しているのかは分からない。甲骨文から”小さい”の用例があり、「小食」「小采」で”午後”・”夕方”を意味した。また金文では、謙遜の辞、”若い”や”下級の”を意味する。詳細は論語語釈「小」を参照。


(甲骨文)
「人」の初出は甲骨文。原義は人の横姿。「ニン」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。甲骨文・金文では、人一般を意味するほかに、”奴隷”を意味しうる。対して「大」「夫」などの人間の正面形には、下級の意味を含む用例は見られない。詳細は論語語釈「人」を参照。
喩(ユ)→踰(ユ)


(後漢隷書)
論語の本章では、”さとる”。テキストによっては異体字の「喻」と記されることがある。中国や台湾では、こちらが正字とされる。初出は後漢の『説文解字』で、論語の時代に存在しない。同音に「兪」とそれを部品とする漢字群、臾”すすめる”とそれを部品とする漢字群。部品の兪の字に、”さとす・たとえる”の語釈は『大漢和辞典』にも「国学大師」にもない。従って論語の時代の置換候補は無い。字形は「口」+「兪」”くりぬく”で、口でもののことわりを掘り下げて語り聞かせること。原義は”さとす”。詳細は論語語釈「喩」を参照。
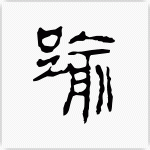

(前漢隷書)
定州竹簡論語の「踰」は、論語の本章では”優れる”。初出は前漢の隷書で、論語の時代に存在しない。字形は「足」+「兪」”超える”で、原義は”超える”・”越える”。「兪」→”越える”の語義は『大漢和辞典』にあり、そう読めなくもない用例が春秋時代以前にあるが、異論もある。詳細は論語語釈「踰」を参照。

「踰」が「喩」になった経緯は不明。「唐石経」では「喻」と記し、それ以前に日本に伝来した古注『論語義疏』でも「喻」と記す。つまり前漢中期に埋蔵された定州竹簡論語までは「踰」で、その後後漢末期までに「喻」に書き改められたことになる。
ただし、上掲のように前漢までの「踰」は「足」をはっきり書かず、明らかに「足」と読めるように書くようになったのは後漢になってからだから、定州竹簡論語の釈文が間違っている可能性がある。損傷の激しい2,000年以上昔の竹簡を判読するのだから、この程度の釈文間違いは起こりうる。
ただし元の竹簡は、地震と紅衛兵の乱暴によって既に破壊され、中国は竹簡の画像を公開しないから、事実は知りようがない。
於(ヨ)


(金文)
論語の本章では”~を”。初出は西周早期の金文。ただし字体は「烏」。「ヨ」は”~において”の漢音(遣隋使・遣唐使が聞き帰った音)、呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)は「オ」。「オ」は”ああ”の漢音、呉音は「ウ」。現行字体の初出は春秋中期の金文。西周時代では”ああ”という感嘆詞、または”~において”の意に用いた。詳細は論語語釈「於」を参照。
義(ギ)


(甲骨文)
論語の本章では”正義”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は「羊」+「我」”ノコギリ状のほこ”で、原義は儀式に用いられた、先端に羊の角を付けた武器。春秋時代では、”格好のよい様”・”よい”を意味した。詳細は論語語釈「義」を参照。
利(リ)


(甲骨文)
論語の本章では”利益”。初出は甲骨文。字形は「禾」”イネ科の植物”+「刀」”刃物”。大ガマで穀物を刈り取る様。原義は”収穫(する)”。甲骨文では”目出度いこと”、地名人名に用い、春秋末期までの金文では、加えて”よい”・”研ぐ・するどい”の意に用いた。詳細は論語語釈「利」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章は春秋戦国の誰一人引用せず、事実上の初出は定州竹簡論語で、その後も先秦両漢の再録が無い。似たようなことを戦国末期の『呂氏春秋』、前漢中期の『淮南子』が説くに止まる。
行不可不孰。不孰,如赴深谿,雖悔無及。君子計行慮義,小人計行其利、乃不利。有知不利之利者,則可與言理矣。

およそあらゆる行動は、やり方をよく知ってから行わねばならない。知りもしないで、深い谷底へ迷い込んで「もう帰れなくなった」と騒いでも、もう遅いからだ。君子は行動の原則を正義に置く。小人は行動の原則を利益に置く。だが利益を求めれば利益を失う。不利が利益であることを知るならば、やっとこの世の道理を語り合えるようになる。(『呂氏春秋』慎行1)
君子非仁義無以生,失仁義,則失其所以生;小人非嗜欲無以活,失嗜欲,則失其所以活。故君子懼失仁義,小人懼失利。

君子は仁義が無くては生きてはいけない。仁義を失ったら、生きる理由を失うのだ。小人は利益を貪らないでは生きてはいけない。貪る利益を失ったら、生きる理由を失うのだ。だから君子は仁義を失うのを恐れ、小人は利益を失うのを恐れる。(『淮南子』繆称訓1)
上記した「君子」と「小人」を対比して論じることが、そもそも孔子の生前にはあり得ないことに加え、このように「君子」を持ち上げ「小人」を馬鹿にする議論は、戦国時代以降の産物で、論語の本章は文字史に加えて、孔子の史実の発言ではないと断じうる。
論語の本章では、定州竹簡論語に従って「喩」→「踰」へと改訂したが、上記のように竹簡の判読間違いの可能性はありうる。だがもし現伝の論語の通り「喩」だったとすると、この字は論語の時代に存在せず、論語時代の置換候補も無い。
その場合の訓読と現代語訳は次の通り。
子曰く、君子は義於喻る、小人は利於喻る。
先生が言った。君子は道理で理解する。小人は利益で理解する。
これは「小人」の、春秋時代の不在と相まって、論語の本章が偽作であることをより証すことになる。また「踰」も論語の時代に存在せず、論語の時代の置換候補として「兪」を挙げうるに止まるが、「兪」が”超える”の意である用例は西周末期「不𡢁𣪕」(集成4328)にあるものの、異論もあって”辺境”の意であるとするのが中国での通説らしい。
いずれにせよ論語の本章の史実性は、極めて疑わしい。
解説
論語の本章は史実ではないが、それでも論語を読もうとする現代人にとって、必須の警告を与えている。従来訳のように、儒者は本章の解釈を、小人と君子の違いをうるさく言うことで、自らの立場を高めようとした、言うまでもないが、儒者は自分を君子だと思っていた。
それも論語時代の意味ではなく、「君子」=”教養があって高潔な人格”という解釈にこだわった。だが孔子の生前、「君子」とは単に参政権のある住民を言ったに過ぎず、人格だとかは関係が無い。身分も領主貴族とは限らず、単に城壁内に住んで戦時に従軍すれば君子だった。
論語の本章を、新古の注は以下のように解している。
古注『論語義疏』
喻曉也君子所曉於仁義小人所曉於財利故范甯曰棄貨利而曉仁義則為君子曉貨利而棄仁義則為小人也孔安國曰喻猶曉也
喻は曉る也。君子仁義於曉る所、小人財利於曉る所。故に范甯曰く、貨利を棄て而仁義に曉らば、則ち君子為り。貨利に曉り而仁義を棄たば、則ち小人為る也。孔安國曰く、喻は猶お曉る也。


喻は明らかに知ることである。君子は仁義に従って明らかに知るが、小人は財産や利益で明らかに知る。だから范甯が言った。財産や利益を捨てて仁義に従ってあきらかに知るなら、それはつまり君子である。財産や利益に従って明らかに知り、仁義を捨てるなら、それはつまり小人である、と。孔安国が言った。喻は明らかに知ることである、と。
*范甯:東晋の儒学者・官僚・教育家。字は武子。本貫は南陽郡順陽県。
新注『論語集注』
喻,猶曉也。義者,天理之所宜。利者,人情之所欲。程子曰:「君子之於義,猶小人之於利也。唯其深喻,是以篤好。」楊氏曰:「君子有舍生而取義者,以利言之,則人之所欲無甚於生,所惡無甚於死,孰肯舍生而取義哉?其所喻者義而已,不知利之為利故也,小人反是。」
喻は猶お曉る也。義者、天理之宜しき所なり。利者、人情之欲所なり。程子曰く、「君子之義に於けるや、猶お小人之利に於けるがごとき也。唯だ其れ深く喻らば、是れ以て篤く好むなり」と。楊氏曰く、「君子生を舍て而義を取る者有り。利を以て之を言わば、則ち人之欲する所生於甚しきは無く、惡む所死於甚しきは無し。孰か肯えて生を舍て而義を取らん哉。其れ喻る所者義而已、利之利を為す故りを知ら不る也。小人是に反く」と。


喻とは明らかに知ることである。義とは、天のことわりが正しいとする事柄を言う。利は、人の感情が求める物事を言う。
程伊川「君子が義に基づいて行動するのは、小人が利益に基づくのと同じである。ただ義に従って深く悟るなら、篤く義を好むのである。」
楊時「君子の中には、命を捨てて義を選び取る者がいる。欲得ずくでこれを説明すれば、人にとっては命より大事なものはなく、死より嫌うものはない。すると誰が命を捨てて、義を択ぶのだろうか。義にしか自分の価値判断を置かず、利益が利益をもたらすことの弊害に関わったことが無い者だろう。小人はこの反対である。」
*楊時:1053-1135。北宋末から南宋初の儒者。字は中立。号は亀山先生。諱は文靖。
互いに偽善の競争をしている点で、新古の注は変わらない。

例えば上掲新注に偉そうな説教を残した楊時という男は、北宋が金に都を攻め落とされ、皇帝が拉致され滅ぶという大事件さえ、「利にさとって」政敵の新法党を弾劾する好機に変え、それ以外は何もせずのうのうと逃げ延び、特に「義に踰れ」ることなく南宋で出世した。
→『宋史』楊時伝
学問的には程兄弟と朱子を繋ぐ重要人物と言うが、むしろ極めつけの悪党と言うべきだろう。
- 論語雍也篇3余話「宋儒のオカルトと高慢ちき」
余話
小人になると君子が分かる
以下は自省と共に言うのだが、こんにち論語を読もうとする人で、読んだ結果「自分は小人である」と反省する人を見たことが無い。たいていはそんなことは思いもよらず、戦国時代以来の高慢ちきな儒者同様、自分は高潔で教養ある君子だと思っている論語読みは少なくない。
確かに参政権があるという意味で現代人は君子なのだが、そういう読者に限って、「君子」=”高潔な教養人”と信じて疑わない。ずいぶんと間抜けな高慢ちきだろう。そういう人は論語など古典を読もうとする動機も不純で、たいていまわりを見下すために読んでいる。
長い間、漢文業界とその周囲を見てきたが、古典を読んで人格が破壊された例は山ほど見てきたが、人格が陶冶された例をほとんど知らない。もともと高潔な人か、たまたまその素質があった人が、苦労の末古典を人格修養に役立てうる。だから論語は趣味に留めておくのがいい。
これには客観的証拠がある。無慮二千年の間、中国政府は儒教経典を官僚採用に用いてきた。その結果選ばれたのは、ポエム書きとワイロ取りだけが能の者ばかりで、僅かな例外があるに過ぎない。これほど膨大な時間と量のある実験は、人間界にそうそうあるものではない。
そのさまを、『笑府』はこう書く。
官值暑月。欲覔避暑之地。同僚紛義成曰。某山幽雅。或曰某寺清閒。一老人進曰。搃不如此。公㕔上最涼也。官問何故。答曰此地有天無日頭。
夏が来た。官僚が集まって避暑の相談をする。ある官僚が言った。「某山は静かでよい。」別の官僚が言った。「某寺はすがすがしくてよい。」下働きの老人が進み出て言った。「そのどの場所より、このお役所ほど涼しい所はございません。」なぜだね、と一同が聞くと、「ここにも空はありますが、お天道様が照りません。」(『笑府』巻一・避暑)
官僚どもがこぞって、役所で真っ暗な悪事ばかりにふけったのをからかっているのである。
そもそも、よい人間になりたくて聖賢の言葉を聞かねばならないようでは、その人はもう終わっている。誰でも知っていることだ、誰かに、生き物に、非生物に対してよいことをする人が、よい人なのだ、なぜに二千年も前の古証文を、取り出して読む必要がある?
論語は暇つぶしに読むべきだ。決して、孔子の権威を身につけようとしてはならない。





コメント