論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子曰古者言之不出恥躬之不逮也
校訂
東洋文庫蔵清家本
子曰古者言之不出也恥躬之不逮也
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
……[者言之不出a,恥躬]之不逮也。」76
- 者言之不出、高麗本作「者言之不出也」、皇本作「古之者、言之不妄出也」。
※「高麗本」とは正平本の誤り。「皇本」は清代に日本から逆輸入し校訂した版本。「皇本」の文字列は文明本による改竄。
標点文
子曰、「古之者言之不出。恥躬之不逮也。」
復元白文(論語時代での表記)








 恥
恥




※躬→身。論語の本章は、恥の字が論語の時代に存在しない。「逮」「也」の用法に疑問がある。本章は戦国時代以降、おそらく前漢の儒者による創作である。
書き下し
子曰く、古之者、言之出さ不ざる。躬之逮ば不るを恥ぢれば也。
論語:現代日本語訳
逐語訳

先生が言った。「昔の人、言葉を言わない。自らの行いが及ばないのを恥じたからだ。」
意訳

昔の人と、軽々しく口を利かなかい人は、どちらも言ったことを実行できないのを恥じるからだ。
従来訳
先師がいわれた。――
「古人はかろがろしく物をいわなかったが、それは実行の伴わないのを恥じたからだ。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子說:「古人不輕易說話,是怕自己說到做不到。」
孔子が言った。「古人が軽々しく話さなかったのは、まことに自分の話が実現不能なのを恐れたからだ。」
論語:語釈
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。


(甲骨文)
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
古(コ)


(甲骨文)
論語の本章では”むかし”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「口」+「中」”盾”で、原義は”かたい”。甲骨文では占い師の名、地名に用い、金文では”古い”、「故」”だから”の意、また地名に用いた。詳細は論語語釈「古」を参照。
者(シャ)


(金文)
論語の本章では”…は”。旧字体は〔耂〕と〔日〕の間に〔丶〕一画を伴う。新字体は「者」。ただし唐石経・清家本ともに新字体と同じく「者」と記す。現存最古の論語本である定州竹簡論語も「者」と釈文(これこれの字であると断定すること)している。初出は殷代末期の金文。金文の字形は「木」”植物”+「水」+「口」で、”この植物に水をやれ”と言うことだろうか。原義は不明。初出では称号に用いている。春秋時代までに「諸」と同様”さまざまな”、”~する者”・”~は”の意に用いた。漢文では人に限らず事物にも用いる。詳細は論語語釈「者」を参照。
『中日大字典』
(4) 〈文〉…というもの.…なるもの.…とは:主語の後に置かれて,断定・判断の主体をはっきりさせる.
〔廉颇者,赵之良将也〕廉頗という人は,趙の立派な大将であった.
〔仁者人也,义者宜也〕仁とは人なり,義とは宜なり
言(ゲン)


(甲骨文)
論語の本章では”ことば”。初出は甲骨文。字形は諸説あってはっきりしない。「口」+「辛」”ハリ・ナイフ”の組み合わせに見えるが、それがなぜ”ことば”へとつながるかは分からない。原義は”言葉・話”。甲骨文で原義と祭礼名の、金文で”宴会”(伯矩鼎・西周早期)の意があるという。詳細は論語語釈「言」を参照。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章では”~の”。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”…の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。
不(フウ)


(甲骨文)
論語の本章では”~でない”。漢文で最も多用される否定辞。初出は甲骨文。原義は花のがく。否定辞に用いるのは音を借りた派生義。詳細は論語語釈「不」を参照。現代中国語では主に「没」(méi)が使われる。
出(シュツ/スイ)


(甲骨文)
論語の本章では”(口に)出す”。初出は甲骨文。「シュツ」の漢音は”出る”・”出す”を、「スイ」の音はもっぱら”出す”を意味する。呉音は同じく「スチ/スイ」。字形は「止」”あし”+「凵」”あな”で、穴から出るさま。原義は”出る”。論語の時代までに、”出る”・”出す”、人名の語義が確認できる。詳細は論語語釈「出」を参照。
古之者言之不出
論語の本章では”昔の人、言葉を言わないこと”。”りんご、みかん”と同様に、同格の名詞的な言葉を二つ置き並べた形。
ここでの「之」は前後の主述関係をまとめて名詞節を作る働きをする。「古之者」が”昔の人”であることはもちろんだが、「言之不出」も「之」の存在によって名詞句になっているので、訓読は「言の出さざる」。
二句を主述関係として読みたい場合、「古の者は言の出さざるあり」とするが、原文に忠実な読みとは言えない。二句はあくまで並列関係だからだ。
古之者 ┐ ├恥躬之不逮也 言之不出┘
従って訳は、”昔の人も、(今の)言葉を言わない人も、言った事を実行できないのを恥じるからだ”。”昔の人が言葉を言わなかったのは…”と解するのは誤り。
『中日大字典』之条
(5) 主述構造の間に用いて,修飾関係を持つ語句に変える.
〔战斗之激烈,难以想像〕闘いの激しさといったら想像もできないほどである.
〔如水之就下〕水の低きに就くが如くである.
〔兴之所适,到哪儿算哪儿〕興の趣くところ,どこに到ってもそれはそれでよい.
なお定州本の校勘記が『皇本作「古之者、言之不妄出也」』というのは、本願寺坊主の手に成る文明本以降の日本伝承古注系論語で、文明本には本章以外にも改竄が見られる。
文明本より先行する清家本・正平本は「古者言之不出也」と記す。また「古寫」とのみある年代不明の国会図書館蔵の龍雩本(本サイトでの仮称)も同じ。文明本以降の足利本・根本本は文明本を踏襲している。
恥(チ)


(楚系戦国文字)
論語の本章では”はじる”。初出は楚系戦国文字。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補も無い。字形は「耳」+「心」だが、「耳」に”はじる”の語義は無い。詳細は論語語釈「恥」を参照。
”はじ”おそらく春秋時代は「羞」と書かれた。音が通じないから置換字にはならないが、甲骨文から確認できる。
躬(キュウ)

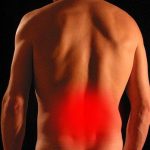
(楚系戦国文字)
『大漢和辞典』の第一義は”身”で、論語の本章では”自らする”。この文字の初出は戦国文字で、論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補は部品の「身」。字形は「身」+「呂」”背骨”で、原義は”からだ”。詳細は論語語釈「躬」を参照。
逮(タイ)


(金文)
論語の本章では、『大漢和辞典』の第一義と同じく”およぶ”。初出は東周初期の金文。ただし字形はしんにょうを欠く。現行字体の初出は春秋末期の石鼓文。字形は〔辶〕”みち”+「隶」で、「隶」は「尾」の原形+「又」”て”で、しっぽをとらえるさま。全体で、路上でつかまえるさま。原義は”捕らえる”。詳細は論語語釈「逮」を参照。
也(ヤ)


(金文)
論語の本章では、「なり」と読んで断定の意。この語義は春秋時代では確認できない。「かな」と読んで詠歎に解してもよいが、上記「恥」の春秋時代に於ける不在により、論語の本章は後世の創作が確定するので、その必要がない。
初出は事実上春秋時代の金文。字形は口から強く語気を放つさまで、原義は”…こそは”。春秋末期までに句中で主格の強調、句末で詠歎、疑問や反語に用いたが、断定の意が明瞭に確認できるのは、戦国時代末期の金文からで、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「也」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章は、春秋戦国の誰一人引用せず、前漢中期の塩鉄会議で、宰相の桑弘羊が、押しかけてきた文学=メルヘンおたくをこじらせたはな垂れ儒者を追い散らす言葉として用いている。孔子の言葉として引用した可能性はあるが、明記されていない。
大夫曰:「盲者口能言白黑,而無目以別之。儒者口能言治亂,而無能以行之。夫坐言不行,則牧童兼烏獲之力,蓬頭苞堯、舜之德。故使言而近,則儒者何患於治亂,而盲人何患於白黑哉?言之不出,恥躬之不逮。故卑而言高,能言而不能行者,君子恥之矣。」

桑弘羊「目が見えなくとも、口で白黒の違いを言い分けることは出来る。目が見えなくとも、区別は出来るのだ。だがそれに意味があるか? 儒者は口では治乱のゆえんや行く末を語るが、自分で政務を処理など出来ない。口先ばかりでやりもせず、まるで羊飼いの子供が天下に二つと無き名弓矢を持ち、じゃんじゃら頭のくせに聖王の堯舜になったつもりでいるようなものだ。だから口を回して政務の要点をあげつらうが、儒者如きになんで天下の仕置きが理解出来るか。目が見えないのに、白い物を「黒い黒い」と嫌がって見せている馬鹿さ加減に気が付かないか。まともな人間は、たやすくものを言わないものだ。出来もしないことを言うのが恥ずかしいからだ。下劣な人間が偉そうにものを言い、そして言った事がやれもしないのは、教養のある人間から見れば恥ずかしくて目にも見られない。(『塩鉄論』能元1)
塩鉄会議とは、長い治世で戦争による散財を繰り返した武帝の不始末の後始末のため、執政の一人だった霍光が全国からはな垂れを集め、上掲のように騒がせて奪権の手下にしようとした出来事だが、切れ者の宰相相手に歯が立たず、結局無理押しで奪権せざるを得なかった。
また論語の本章は、文字史的に論語の時代に遡れないこともあり、塩鉄会議とほぼ前後して記された定州竹簡論語が事実上の初出で、前漢儒による創作と考えるのが筋が通る。
解説
既存の論語本では吉川本に「古い時代に対する尊敬は、中国の思想家に普遍な感情であるが、論語にもそれはときどきあらわれる。不言実行の教えとしては…同趣旨である。」とある。訳者としては、孔子が説いたのは不言実行ではなく、有言実行、言行一致だったと考えている。
不言実行は説明責任への免責の根拠となるからで、不言実行は、第一に帝国官僚として、第二に自分だけ口車を回して金を取る教師として、そしてなにより戦場に出ずに済むようになった、帝政期の儒者にとってのみ一方的に都合のよい、図々しい理屈と言ってよい。
重複をおそれず記せば、孔子存命中の君子=貴族は、口数が多くないと務まらなかった。そうでないと政論や外交交渉をしくじるし、何より戦場で演説して兵の士気を高められないからだ。寡黙をよしとする価値観はあって良いが、孔子とその直弟子たちはそうもいかない。
春秋の君子=戦士であることについては、論語における「君子」を参照。
孔子は「剛毅木訥仁に近し」(論語子路篇27)と言ったからには、口数少ないのを好んだのだろうが、孔子は”くっちゃべってないで働け/勉学と稽古に励め”と言っただけで、”黙ってろ”とは言わなかった。沈黙では貴族になれず、弟子は成り上がれず、塾を辞めたに違いない。
論語で口車を「佞」と記すが、この文字は論語の時代に存在しない(論語語釈「佞」)。ゆえに「佞」を含んだ論語の章は全て偽作ということになる。加地伸行が「巫女が客に媚びるのを、仁に女を足して佞といった」という説は、もはやこんにちでは真に受けるわけにはいかない。
「佞」についてさらには、論語衛霊公篇11余話「これで口利かん」を参照。
論語の本章に話を戻せば、新古の注は次の通り。
古注『論語義疏』
子曰古之者言之不妄出也恥躬之不逮也註苞氏曰古人之言不妄出口者為恥其身行之將不及也疏子曰至逮也 躬身也逮及也古人不輕出言者恥身行之不能及也故子路不宿諾也故李充曰夫輕諾者必寡信多易者必多難是以古人難之也


本文「子曰古之者言之不妄出也恥躬之不逮也」。
注釈。包咸「昔の人がベラベラしゃべらなかったのは、身の程が及んでいない事を恥じたからである。」
付け足し。先生は及ぶことを言ってそれが記された。躬とは身である。逮は及である。昔の人が軽々しくしゃべらなかったのは、行ったことが出来ないのを恥じたからである。だから子路は引き受けたことを宵越ししなかったのである。
だから李充が言った。「気軽な引き受けは信用も軽い。言動に軽さが多い者は必ず困難も多い。だから昔の人は、言動が軽いと厄介だ、と思ったのだ。」
新注『論語集注』
言古者,以見今之不然。逮,及也。行不及言,可恥之甚。古者所以不出其言,為此故也。范氏曰:「君子之於言也,不得已而後出之,非言之難,而行之難也。人惟其不行也,是以輕言之。言之如其所行,行之如其所言,則出諸其口必不易矣。」


「古」と言ったのは、今のやり口が間違っていることを言ったのである。逮とは及である。言ったことが出来ないと、とてつもなく恥ずかしい。昔の人がしゃべらなかった理由はそれである。
范氏「君子がものを言うときは、やむを得ずしてしゃべるのである。言うのが難しいのではない、実行が難しいのである。人は後先考えないから、軽々しくものを言う。行えることを言い、言った事を行うなら、口からものを言うのは難しいはずだ。」
范氏とは范祖禹のことで、司馬光を補佐して『資治通鑑』の編纂に携わり、れっきとした進士合格者なのに、珍しくあまり官界での出世を求めなかった、とされる。難しい顔をした謹厳居士だったようで、「無駄口を聞いたことが無い」と口数の多い蘇東坡が言っている。
余話
モジャの一声
論語の本章は、今日的意義も持っている。「言論の自由」がある国と地域と身分は、人類史上ごくまれな例外で、現在でも権力者の気に入らないことを言うと、どこかへ連れて行かれてしまう国はあまたある。現在の中国もそのうちの一国で、過去の中国もそうだった。
「いにしえより言の出さざるあり、脳袋の搬家しを恐るればなり。」訳者若年時は、台湾からの留学生もまだ「言論」に怯えた時代だったし、日本でも戦前には憲兵や特高がいた。現在でも政治権力に限らないなら、力ある者の気に入らないことを言えば社会的に抹殺される。
事実上の独裁が続くロシアがそうだし、過去のソ連もそうだった。
ソ連でのホロドモールが早くから外国に名を知られたのは、ミハイル・ショーロホフの『静かなドン』にかなり赤裸々に書かれたからだ。もちろん共産党と時の権力者だったスターリンにとって都合の悪い話であり、ショーロホフは告発されてシベリア送りになりかけたらしい。
のちにスプートニクを打ち上げたコロリョフ博士を北極圏の金鉱掘りに流して半死半生にし、ツポレフ技師を収監して軍用機を設計させ、カラシニコフとその家族を富農認定してシベリア流刑にした当時のソ連である。少年カラシニコフは脱走して生き延びた希有の例だった。
ショーロホフは哀れシベリアの土になるはずだった。が、ここでロシア史らしい番狂わせが起きる。『静かなドン』を連載で読んでいたスターリンが、「続きが読みたい」と言った。この鶴の一声で無罪放免、ショーロホフはノーベル文学賞まで貰いソ連を代表する作家になった。
対して中国では、武帝の暴君ぶりに懲りて司馬遷は『史記』に、漢帝室について控えめに書いた。だが一旦漢が滅んだ後の班固が編んだ『漢書』は、油断したのか前漢帝室の暗部をかなり記した。前漢について知ろうとするなら、『史記』より『漢書』のほうがよほど役立つ。
しかし班固が仕えた光武帝は、王莽や赤眉や更始帝を倒して後漢を起こした。だからこれらに関する記述はどこまで本当か分からない。また班固は獄死したが、通説では外戚の竇憲に連座したからだとされる。だが存外前漢帝室についての記述に、時の和帝が怒ったからだろう。
本当の事でヤバいことは記さないのが史書に限らず漢籍というもので、その裏を知るにはウソをウソと見抜けるだけの読書が要る。訳者が春秋末期の論語を読むために、はるか古代の甲骨文から読まざるをえないのはそのためだ。



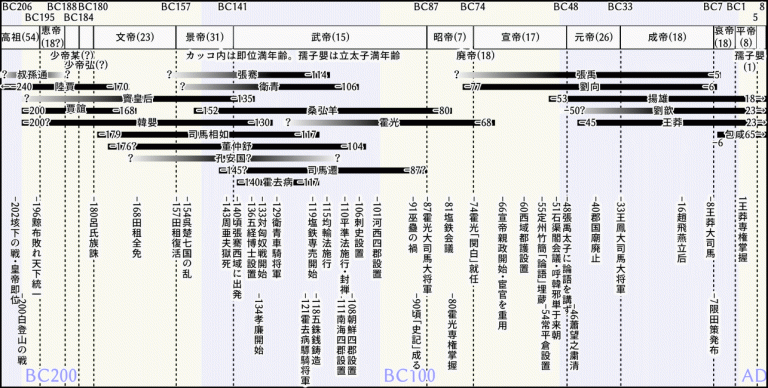


コメント