論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
孟武伯問孝子曰父母唯其疾之憂
校訂
東洋文庫蔵清家本
孟武伯問孝子曰父母唯其疾之憂
※前章と区切り無しで続けて記されている。
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
……武伯問孝。子曰:「父母□……憂。」9
標点文
孟武伯問孝。子曰、「父母唯、其疾之憂。」
復元白文(論語時代での表記)














※論語の本章は、「問」の用法に疑問がある。
書き下し
孟武伯、孝を問ふ、子曰く、父母は唯、其の之疾むは憂ひなり。
論語:現代日本語訳
逐語訳

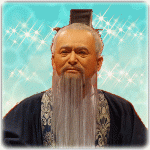
孟武伯が孝行を問うた。先生が言った。「父母はひたすらに、それ(=子供)がまさに病むことが憂いです。」
意訳
まことに、子の病気を親は気にかけています。心配掛けないようにしなさい。
従来訳
孟武伯が孝の道を先師にたずねた。先師はこたえられた。――
「父母はいつも子の健康のすぐれないのに心をいためるものでございます。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孟武伯問孝,孔子說:「父母只有在子女生病時才擔憂。」
孟武伯が孝を問うた。孔子が言った。「父母とは、もっぱら子供が病気になった時、最も心を痛めるものです。」
論語:語釈
孟武伯(モウブハク)
魯国門閥三家老(三桓)の一家、孟氏(孟孫氏)の跡取り息子。『左伝』によると、第10代当主となってからはさらに公室への圧力を強め、哀公が「私を殺す気か」と聞いたところ「知りません」と答え、恐れた哀公は国外逃亡して越国で客死した。
哀公十一年(BC484)に孔子が帰国する直前、魯は斉の侵攻を受けたが、その際右軍を率いて戦った。『左伝』では父の孟懿子が存命だったからか、「孟孺子」=”孟孫家の坊ちゃん”と記している。なお左軍は、孔子の弟子の冉有が指揮し、同じく弟子の樊遅が戦車に同乗した。
孟孫氏は最初に孔子の後ろ盾となった家老家であり、洛邑留学の費用も、そしておそらくその後の孔子の仕官も、孟孫氏の後援によるもので、孔子とは縁が深かった。ただし孔子が亡命するきっかけとなった、「三都破壊」の失敗は、孟孫氏の黙認から始まっている(→史記)。
昨日の友が今日は敵という政界のめまぐるしさは、現代も春秋時代も変わらない。


「孟」(金文)
「孟」の初出は殷代末期の金文。字形は「皿」”たらい”+「子」で、赤子が産湯を使っているさま。原義は”長子”。男児に限らない。春秋時代までに原義のほか、”始まりの”の意に用いた。詳細は論語語釈「孟」を参照。
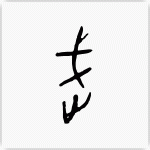

「武」(甲骨文)
「武」の初出は甲骨文。字形は「戈」+「足」で、兵が長柄武器を執って進むさま。原義は”行軍”。甲骨文では地名、また殷王のおくり名に用いられた。金文では原義で用いられ、周の事実上の初代は武王とおくりなされ、武力で建国したことを示している(作冊大方鼎・西周早期)。また武力や武勇を意味した(虢季子白盤・西周末期)。加えて「文」の対語で用いられた(𠫑羌鐘・戦国早期)。詳細は論語語釈「武」を参照。
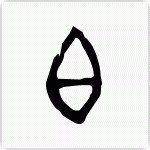

「白」(甲骨文)
「伯」*の字は論語の時代、「白」と書き分けられていない。初出は甲骨文。字形の由来は蚕の繭。原義は色の”しろ”。甲骨文から原義のほか地名・”(諸侯の)かしら”の意で用いられ、また数字の”ひゃく”を意味した。金文では兄弟姉妹の”年長”を意味し、また甲骨文同様諸侯のかしらを意味し、五等爵の第三位と位置づけた。戦国の竹簡では以上のほか、「柏」に当てた。詳細は論語語釈「伯」を参照。
問(ブン)


(甲骨文)
論語の本章では”問う”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。「モン」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。字形は「門」+「口」。甲骨文での語義は不明。西周から春秋に用例が無く、一旦滅んだ漢語である可能性がある。戦国の金文では人名に用いられ、”問う”の語義は戦国最末期の竹簡から。それ以前の戦国時代、「昏」または「𦖞」で”問う”を記した。詳細は論語語釈「問」を参照。
孝(コウ)


(甲骨文)
論語の本章では、”年下の年上に向けた付き合い方”。初出は甲骨文。原義は年長者に対する、年少者の敬意や奉仕。ただしいわゆる”親孝行”の意が確認できるのは、戦国時代以降になる。詳細は論語語釈「孝」を参照。
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
父(フ)


(甲骨文)
論語の本章では”父”。初出は甲骨文。手に石斧を持った姿で、それが父親を意味するというのは直感的に納得できる。金文の時代までは父のほか父の兄弟も意味し得たが、戦国時代の竹簡になると、父親専用の呼称となった。詳細は論語語釈「父」を参照。
母(ボウ)
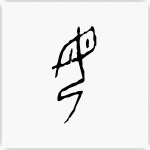

(甲骨文)
論語の本章では”母”。初出は甲骨文。「ボ」は慣用音。「モ」「ム」は呉音。字形は乳首をつけた女性の象形。甲骨文から金文の時代にかけて、「毋」”するな”の字として代用もされた。詳細は論語語釈「母」を参照。
唯(イ)


(甲骨文)
論語の本章では”ひたすらに”。初出は甲骨文。「ユイ」は呉音。字形は「𠙵」”くち”+「隹」”とり”だが、早くから「隹」は”とり”の意では用いられず、発言者の感情を表す語気詞”はい”を意味する肯定の言葉に用いられ、「唯」が独立する結果になった。古い字体である「隹」を含めると、春秋末期までに、”そもそも”・”丁度その時”・”ひたすら”・”ただ~だけ”の語義が確認できる。詳細は論語語釈「唯」を参照。
其(キ)


(甲骨文)
論語の本章では、”それ”。本章では明記されていないが、具体的には子供を指す。「此」に対してやや離れた事物を指す言葉で、直前の「父母」ではあり得ない。
父母唯其疾之憂
字の初出は甲骨文。甲骨文の字形は「𠀠」”かご”。かごに盛った、それと指させる事物の意。金文から下に「二」”折敷”または「丌」”机”・”祭壇”を加えた。人称代名詞に用いた例は、殷代末期から、指示代名詞に用いた例は、戦国中期からになる。詳細は論語語釈「其」を参照。
疾(シツ)


(甲骨文)
論語の本章では”病気になる”。漢文では、”にくむ”の意味で用いられることも多い。初出は甲骨文。字形は「大」”人の正面形”+向かってくる「矢」で、原義は”急性の疾病”。現行の字体になるのは戦国時代から。別に「疒」の字が甲骨文からあり、”疾病”を意味していたが、音が近かったので混同されたという。甲骨文では”疾病”を意味し、金文では加えて人名と”急いで”の意に用いた。詳細は論語語釈「疾」を参照。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章では”まさに”。以前に指すべき名詞がないので、指示代名詞”この”ではない。直前が動詞であることを示す記号で、意味内容を持たない。強いて訳すなら強意の”まさに”。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”。足を止めたところ。原義は”これ”。”これ”という指示代名詞に用いるのは、音を借りた仮借文字だが、甲骨文から用例がある。”…の”の語義は、春秋早期の金文に用例がある。詳細は論語語釈「之」を参照。
「之」が指示(代名)詞でも、同類の「此」が直近の事物を指し、「其」がやや遠い事物を指すのに対し、「之」は足元を指さすように、”まさにこれ”と取り立てて指す場合に用いる。
憂(ユウ)
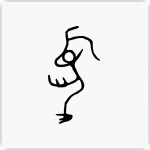

(金文)
論語の本章では”心配である”。主語が悩みのタネになる、の意。主語が”心配する”ではない。
述語動詞:憂”心配である”。
字の初出は西周早期の金文。字形は目を見開いた人がじっと手を見るさまで、原義は”うれい”。『大漢和辞典』に”しとやかに行はれる”の語釈があり、その語義は同音の「優」が引き継いだ。詳細は論語語釈「憂」を参照。
父母唯、其疾之憂
論語の本章では、”父母はひたすら、それ(=子供)がまさに病むのが心配である”。
伝統的な論語解釈には、論語の本章での「之」は倒置を表し、「憂疾」(やまいをうれう)の「疾」を強調した語法と解説するものがある(「憂疾」→「疾之憂」)。それらは「憂」を使役に理解する。『学研漢和大字典』ではこれに従い、以下のように訳す。しかし典拠として挙げられているのは諸本いずれも論語の本章で、証明としては循環論理になる。
「父母唯其疾之憂。」
父母には唯其の疾いを之憂えしめよ。
”父母にはただ自分の病気のことだけを心配させるようになさい。”
「父母唯其疾之憂」が本来「父母唯憂其疾之」の語順であるべき所を倒置したと解釈するのは文法的誤りではまないが、「之」を直前が動詞であると示す強意と見る方が無理がない。語形変化が無く、助詞や前置詞のたぐいも省略されることが多い漢文では、語順は語の品詞や意味を決める重要なしつらえで、むやみに変えると文意が通じなくなる。
だが何を恐れ憂うのかは問題となるが、論語の本章では「之」を指示代名詞でない。無理やり指示代名詞とすると、「之を疾む」”まさにこのことを病む”と解するしかなくなり、何を病むのかわけが分からない。また文中に憂うべき「其」の対象は書いていない。「其」は「此」が近くを指すのに対し、「やや遠い所の物をさす指示詞」と『学研漢和大字典』「其」条は言う。
従って漢文が対句表現を好む事に着目し、「父母」に対する「其」だから”子供”と考えるのが妥当となる。「父母」が「父母」自身の病気を心配すると解釈出来なくはないが、「其」が「父母」に近すぎるし、”父母は病気怖い怖いとブツブツ言うものですぞ”という言葉が、「孝」の回答になるとは言えないだろう。
論語:付記
検証
論語の本章は、後漢初期の王充が『論衡』に再録するまで、誰一人引用していない。本章は前漢の儒者が偽作したと考えるのが一番筋が通る。だがブツとしての文字が論語の時代に全て遡れることから、とりあえず史実性を疑わずに話を進める。
解説
その王充は、次のように言う。
孟武伯問孝,子曰:「父母唯其疾之憂。」武伯善憂父母,故曰「唯其疾之憂」。武伯憂親,懿子違禮。攻其短,荅武伯云「父母唯其疾之憂」,對懿子亦宜言「唯水火之變乃違禮」。周公告小才勑,大材略。子游之、大材也,孔子告之勑;懿子、小才也,告之反略,違周公之志。攻懿子之短,失道理之宜,弟子不難,何哉!

孟武伯が孝行の道を問うた。孔子先生は言った。”父母はひたすら子の病を心配するものです。”武伯はやんちゃが過ぎて父母に心配ばかりかけていたから、”子の病を心配する”と説教したのである。
武伯はやんちゃ、父の懿子は礼法破り、だから親子の過ちを正すため、武伯には”子の病を…”と説教し、孟懿子には”礼法を破っていいのは洪水と火事の時だけ”と教えた。
周初の摂政だった周公は、小ヂエの回る者には説教し、大ヂエの回る者にはだいたいの方針だけ教えた。だが孔子先生の弟子の子游は、大ヂエの回る男だったが、それでも先生は小言を言った。孟懿子は小ヂエが回るだけの男だったが、先生はだいたいのことしか言わなかった。周公のやり方とは違ったのである。
孟懿子のタワケを放置して、真人間に仕立ててやらなかったわけだが、弟子にまでそういう面倒を見てやらなかったら、いったいどういうことになっていただろうか。(『論衡』問孔7)
王充が生まれたのは後漢帝国の創業とほぼ同じ時で、論語の時代とは550年ほど遅れるのだが、こういう見てきたようなデタラメをせっせと書き付けて全然悪いとも思っていない点で、他章をも含め王充もまた現伝論語の贋作集団の一味と認めた方が話の分かりがよい。
王充は共産党の政策から、中国でむやみにもてはやされた時期があり、wikipediaの解説もほぼその筋に沿っており、あまり信用しない方がいい。王充が古論語・魯論語・斉論語などというでっち上げをこしらえたせいで、真に受けた日中の論語業界は大混乱のはめに至った。
詳細は論語解説「後漢というふざけた帝国」を参照。

訳者が史料を読む限り、子游は葬儀の司会がうまくて喪主からお布施をせびるだけが能の、「孔門十哲」では一番人格と才能が如何わしい人物で、対して孟懿子は門閥の当主として領民から慕われた名君(下記)、孟武伯は大国斉の軍勢に一番駆けをした頼もしい若武者だった。
論語の本章の問い手・孟武伯にとって、孔子は子供の頃から可愛がってくれた”おじさま”であり、問答の時期も、おそらく孔子の帰国後、父の孟懿子が死去する前後だろう。孔子と共に洛邑へ留学した武伯の叔父が孔子と同世代とすれば、孔子亡命前の孟武伯はまだ子供に過ぎない。
つまり論語の本章は、これから政界に打って出る覚悟を、孟武伯が固めた時期だった。
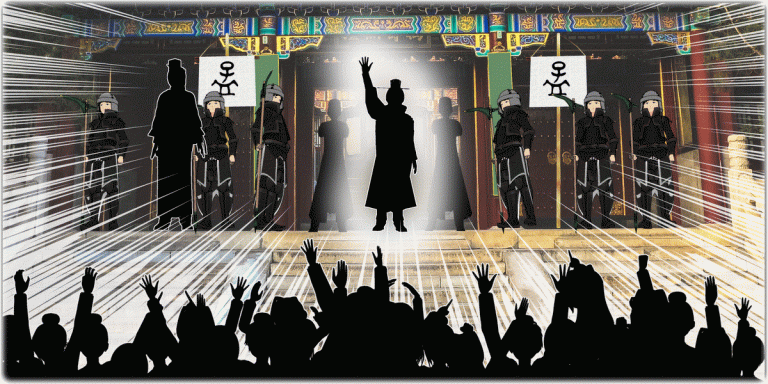
中国は古代から現中共政府が言うのとは別の意味で「独特の民主主義」であり、春秋の大貴族は譜代の家臣や領民にそっぽを向かれると、まず天寿を全うできない。少なくとも地位は追われる。孟武伯は哀公にそっぽを向いて客死させ、二代前の昭公も同じ目に遭った。
劇画『東周英雄伝』で、鶴マニアの衛の懿公をご存じの諸賢もおられるかも知れない。蛮族が押し寄せた時、「殿は鶴に高位高禄をはずんだんでしょ? じゃ鶴に戦ってもらえばよろしい」と言って領民が参戦せず、結局負けた懿公はバーベキューにされて蛮族に食われた。
中国に「忠」の字が現れるのは戦国時代になってからだ。要するに論語の時代、「孝子」はあり得ても「忠臣」はあり得ない。事は孟孫家にとっても同じで、孔子失脚の発端となった三都破壊の失敗は、孟孫家の譜代家臣が抵抗したのを、孟懿子が黙認せざるを得なかったからだ。
その代わり孟懿子は、領民に慕われていたことが『左伝』に見える。
哀公十四年…秋,八月,辛丑,孟懿子卒,成人奔喪,弗內,袒免哭于衢,聽共,弗許,懼,不歸。

哀公十四年(BC480)…秋八月かのとうしの日、孟懿子が死去した。孟孫家の根城である成邑の住人が葬儀の会葬に走り来たが、孟孫家は都城曲阜の屋敷に入るのを許さなかった。住人は衣を脱いで左肩をあらわにし、冠を取ってもとどりのまま、街路で泣きまねをし、葬列に加わることを願ったが許さなかった。そこで住人は、「どうしよう」と互いに顔を見合わせたまま、それでも帰らなかった。(『春秋左氏伝』哀公十四年2)
つまり孟武伯にとり、自分が父に対していかに「孝」であることを世間に知らしめるかが、政治生命の一端を握っていた。それゆえに”おじさま”に問うたわけだし、どうすれば「孝」と世間が言ってくれるか、その演技法の質問を含めて論語の本章は成立している。
なお「忠」が出現した戦国時代でも、戦場から逃げた「五十歩百歩」の、「どちらが卑怯者か」と孟子が梁王に問うているが、以来現代に至るまで、中国兵はいくさになったら当然逃げた。その兵隊に逃げる気を起こさせないのが、孟武伯の当主としての腕の見せ所でもある。
「忠」や「孝」をすり込むこと、つまり人を洗脳して自爆攻撃の如き無残をさせるのが、政治家と役人の図々しい役得というもので、孔子の時代にはまだそこまでのデタラメを構築する技術が無かった。だが孔子なら、あるいはそれを知っているかも、と孟武伯は問うた。
それに対して孔子は、あっさり「病気で親に心配かけないように」と言った。後世の儒者は孝行を見せ物にして官職獲得に狂奔し、そのためなら我が子を殺しまでしたが(郭巨)、孔子はそんなデタラメを許さなかった。ごく当たり前に、親に心配かけないことを説いたに過ぎない。
重複を恐れず記せば、儒教と言えば親孝行という「常識」は、少なくとも孔子の教えではない。後漢に流行った郭巨の如き残忍な偽善には、帝国滅亡直後に葛洪という証言者がいるが(『抱朴子』内編・微旨5)、孔子の教説はそうした見せ物やでっち上げとは無縁である。
最後に、儒者の注釈を検討しよう。
古注『論語集解義疏』
註馬融曰武伯懿子之子仲孫彘也武諡也言孝子不妄為非唯有疾病然後使父母之憂耳

注釈。馬融「武伯は懿子の子で、仲孫彘のことである。武はおくり名である。文の意味は、”孝行な子供とはむやみに悪事を働かないものだが、ただ病気にかかるのは仕方がない。だから父母に心配を掛けるのは、病気だけに限るべきだ”ということである。」
彘とは”めすぶた”のことで、ひどい名を付けたものだ。幼時に病魔が取り付くのを恐れたおまじないだろうか。ぶたの生命力にあやかったのだろうか。それはともかく、使役の記号が無いのに、勝手に使役に解するのは賛成できない。
新注『論語集注』
武伯,懿子之子,名彘。言父母愛子之心,無所不至,惟恐其有疾病,常以為憂也。人子體此,而以父母之心為心,則凡所以守其身者,自不容於不謹矣,豈不可以為孝乎?舊說,人子能使父母不以其陷於不義為憂,而獨以其疾為憂,乃可謂孝。亦通。

武伯は懿子の子で、名は彘。文の意味は、父母が子を愛する心には、至らないところが無く、ひたすらに子供の病気を恐れて、いつも心配している。人の子たる者はそれを意識して、もし父母の心配を自分の心配と心得るなら、つまり自分の健康に気遣う心掛けとして、自分で気を付けないわけにはいかないのだ。そうすればどうして孝行者だと言えないだろうか、ということである。
なお古い解釈では、人の子たる者は、自分が悪事を働いて父母に心配を掛けることのないようにし、ただ病気だけを心配させるなら、そのまま孝行者だと言って良い、という。こちらも意味が通じる。
「旧説」は頂けないが、朱子の言う解釈は無理が無く、合理的だと思う。また日本の伊藤仁斎は、次のように解釈したという。
『論語古義』

「父母はただその疾いをこれ憂えよ。」
父母が老人になると、お世話する日はもう少ない。まして一度病気にかかられると、孝行をつくそうとしてもできなくなる。そこで父母の病気をいちばん気にかけるようになれば、少ない一日一日を大切にする真心がどうしてもやまれず、愛慕する情がくまなく行き渡り、孝行しないでおこうと思ってもできないのだ。(貝塚茂樹編『日本の名著13 伊藤仁斎』を引用)
語順から「父母唯其疾之憂」の主語は父母であって、子ではないから賛成しかねる。仁斎先生の人の良さを訳者は疑わないが、だからといって漢文を好き勝手、かつデタラメに読んでいい事にはならない。
余話
アンナ・カレーニナの法則
孟懿子と孟武伯親子は、貴族でありながら幸福な親子関係だったようだ。
それが春秋時代の当たり前の親子関係だったのか、それともとりわけ幸福な例だったのかは分からない。おそらく現代社会と同じだろう。『春秋左氏伝』『史記』が描く春秋時代では、不幸な親子関係の方が目立つように思うが、幸福な家庭は当たり前すぎて記さなかったのか。
それとも訳者が不幸な親子の記事ばかり記憶しているせいか。これもどちらかは分からない。
Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по–своему.
およそ幸福な家庭というものはお互いよく似ているが、不幸な家庭はそれぞれ別の理由で不幸になっている。(トルストイ『アンナ・カレーニナ』)
古今東西、貴族は財産や利権の相続でもめる例が多く、春秋時代もお家争いは珍しくない。文豪の言葉と違って、不幸な理由がよく似ている。古い方から言えば鄭の荘公が母親に嫌われて弟と跡目を争わねばならなかったし、孔子と同世代だと衛の霊公が息子と仲が悪かった。
春秋時代も、長子相続が一応の原則ではあったが、霊公の息子・蒯聵は長男ではあったようだが出来が悪かったらしく、その上継母の南子を暗殺しようとして失敗し、晋に出奔している。衛にとって西北の大国晋は、領土を削り取りに来る脅威で、敵対関係にあったのだが。
霊公が没すると蒯聵は晋のヒモ付きで帰国してクーデターを起こし、その乱により孔子の一番弟子だった子路は命を落としている。だが孔子も南方の大国・楚の跡目争いで陰謀を働き、手懐けた白公にクーデターを起こさせた、と孔子とすれ違うように生きた墨子が証言している。
孔子自身も一人息子の鯉に冷たかった。その理由は伝わっていない。主な創業皇帝にも、幸せそうな者は少ない。
- 始皇帝:父との縁が薄く、息子に冷たくて死後の陰謀を引き起こした。実父は宰相の呂不韋だったという説が根強い。
- 漢高祖劉邦:父親が項羽の捕虜になり、煮て食われそうになったが「俺にも一杯分けてくれ」と言った。皇帝になってからは優遇した。息子にも娘にも冷たく、やはり項羽に逐われたとき逃げる車から突き落とした。
- 隋高祖楊堅:父との関係不明。長男の太子と仲が悪く、次男の煬帝にすげ替えたが、その煬帝に殺された。
- 唐高祖李淵:父との関係不明。その助平に付け込んだ次男の太宗李世民にだまされて挙兵せざるを得なかった。長男の太子を李世民に殺され、隠居。
- 宋太祖趙匡胤:父との関係不明。息子との関係不明。弟の次代太宗趙光義に暗殺された説が根強い。
- チンギス=ハン:父とは幼少期に死別。長男のジョチを生涯自分の子ではないと疑い続けた。モンゴルは末子相続が原則だから帝位を継がせなかったのは当然としても、次男のチャガタイとジョチの抗争に何も出来なかったし、言えなかった。
- 明洪武帝朱元璋:幼少期に一家離散。長男に厳しく先立たれた。没後は孫が即位したが四男の永楽帝に殺される。
- ヌルハチ:父との関係が悪く出奔。没後は跡目争いに。



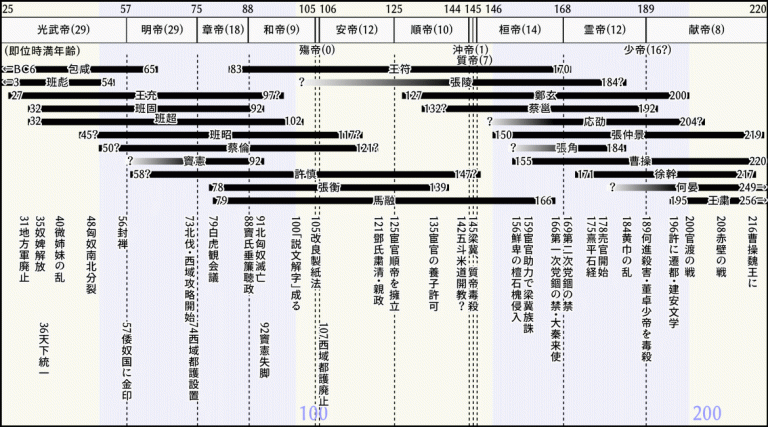


コメント