論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子張問政子曰居之無倦行之以忠
校訂
東洋文庫蔵清家本
子張問政子曰居之無倦行之以忠
定州竹簡論語
……子曰:「居之勿卷a,[行之以忠]。」317
- 勿卷、今本作”無倦”、『釋文』云”無倦、亦作勿卷”。
標点文
子張問政。子曰、「居之勿卷。行之以忠。」
復元白文(論語時代での表記)












 忠
忠
※張→(金文大篆)。論語の本章は、「忠」が論語の時代に存在しない。「卷」「行」の用法に疑問がある。本章は戦国時代以降の儒者による創作である、または改作の可能性がある。
書き下し
子張政を問ふ。子曰く、之に居るに卷む勿かれ。之を行ふに忠を以ゐよ。
論語:現代日本語訳
逐語訳


子張が政治を問うた。先生が言った。「為政者の立場で怠けることなく、政治を行うのに真心で行うことだ。」
意訳

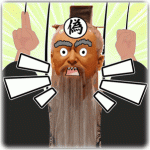
子張「先生ッ! 政治とはッ?」
孔子「飽きずに政務にいそしむこと、そして自分の良心に恥じないように仕事することだ。」
従来訳
子張が政治のやり方についてたずねた。先師はこたえられた。――
「職務に専念して、辛抱づよく、真心をこめてやりさえすれば、それでいいのだ。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
子張問政。孔子說:「勤勉為公,忠心報國。」
子張が政治を問うた。孔子が言った。「公共のために勤勉に働き、忠実に国に報いよ。」
論語:語釈
子張

孔子の弟子。「何事もやりすぎ」と評された。張の字は論語の時代に存在しないが、固有名詞なので論語の本章を偽作と断定できない。詳細は論語の人物・子張参照。


(甲骨文)
「子」の初出は甲骨文。論語ではほとんどの章で孔子を指す。まれに、孔子と同格の貴族を指す場合もある。また当時の貴族や知識人への敬称でもあり、孔子の弟子に「子○」との例が多数ある。なお逆順の「○子」という敬称は、上級貴族や孔子のような学派の開祖級に付けられる敬称。「南子」もその一例だが、”女子”を意味する言葉ではない。字形は赤ん坊の象形で、もとは殷王室の王子を意味した。詳細は論語語釈「子」を参照。


(楚系戦国文字)
「張」の初出は楚系戦国文字。論語の時代に存在しないが、固有名詞のため、同音近音のあらゆる漢語が置換候補になり得る。字形は「弓」+「長」で、弓に長い弦を張るさま。原義は”張る”。「戦国の金文に氏族名で用いた例がある。論語語釈「張」を参照。
問(ブン)


(甲骨文)
論語の本章では”質問する”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。「モン」は呉音。字形は「門」+「口」。甲骨文での語義は不明。西周から春秋に用例が無く、一旦滅んだ漢語である可能性がある。戦国の金文では人名に用いられ、”問う”の語義は戦国最末期の竹簡から。それ以前の戦国時代、「昏」または「𦖞」で”問う”を記した。詳細は論語語釈「問」を参照。
政(セイ)(まつりごと)
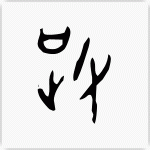

(甲骨文)
論語の本章では”政治(の要点)”。初出は甲骨文。ただし字形は「足」+「丨」”筋道”+「又」”手”。人の行き来する道を制限するさま。現行字体の初出は西周早期の金文で、目標を定めいきさつを記すさま。原義は”兵站の管理”。論語の時代までに、”征伐”、”政治”の語義が確認できる。詳細は論語語釈「政」を参照。
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。


(甲骨文)
「曰」の初出は甲骨文。原義は「𠙵」=「口」から声が出て来るさま。詳細は論語語釈「曰」を参照。
居(キョ)


(金文)
論語の本章では”座る”→”座ってその立場にいる”。政治を指揮する立場に立つこと。初出は春秋時代の金文。字形は横向きに座った”人”+「古」で、金文以降の「古」は”ふるい”を意味する。全体で古くからその場に座ること。詳細は論語語釈「居」を参照。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章では”それ”。子張が問うた”政治の要点”を指す。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”~の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。
無(ブ)→勿(ブツ)
論語の本章では”…するな”。


(甲骨文)
「無」の初出は甲骨文。「ム」は呉音。甲骨文の字形は、ほうきのような飾りを両手に持って舞う姿で、「舞」の原字。その飾を「某」と呼び、「某」の語義が”…でない”だったので、「無」は”ない”を意味するようになった。論語の時代までに、”雨乞い”・”ない”の語義が確認されている。戦国時代以降は、”ない”は多く”毋”と書かれた。詳細は論語語釈「無」を参照。


(甲骨文)
定州竹簡論語では「勿」と記す。初出は甲骨文。金文の字形は「三」+「刀」で、もの切り分けるさまと解せるが、その用例を確認できない。甲骨文から”無い”を意味し、西周の金文から”するな”の語義が確認できる。詳細は論語語釈「勿」を参照。
倦(ケン)→卷(ケン)
論語の本章では(くたびれて)”飽きる”。


「倦」の初出は楚系戦国文字。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。字形は「人」+「卷」。「卷」の原義ははっきりせず、おそらく音符。原義は”あきる”。同音に「権」・「卷」(巻)など多数。戦国の竹簡に”あきる”の用例があり、また「劵」を「倦」と釈文する例がある。詳細は論語語釈「倦」を参照。
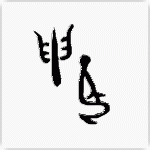

(金文)
定州竹簡論語「卷」(巻)の初出は殷代末期の金文。両手+棒状のもの+背中を向けた人で、人に見えないように何かを”抱え込む・隠す”と解するのが理にかなうと思う。ただし殷周の用例は全て族徽(家紋)か人名で、何を意味しているのかわからない。戦国最末期の竹簡で、”引き返す”と解せる例がある。詳細は論語語釈「巻」を参照。
「倦」は論語の時代に存在せず、論語時代の置換候補も無く、「卷」には春秋末期までに”うみつかれる”の用例が無い。
行(コウ)


(甲骨文)
論語の本章では”行う”。この語義は春秋時代では確認できない。字の初出は甲骨文。「ギョウ」は呉音。十字路を描いたもので、真ん中に「人」を加えると「道」の字になる。甲骨文や春秋時代の金文までは、”みち”・”ゆく”の語義で、”おこなう”の語義が見られるのは戦国末期から。詳細は論語語釈「行」を参照。
以(イ)


(甲骨文)
論語の本章、”用いる”。初出は甲骨文。人が手に道具を持った象形。原義は”手に持つ”。論語の時代までに、名詞(人名)、動詞”用いる”、接続詞”そして”の語義があったが、前置詞”~で”に用いる例は確認できない。ただしほとんどの前置詞の例は、”用いる”と動詞に解せば春秋時代の不在を回避できる。詳細は論語語釈「以」を参照。
忠(チュウ)

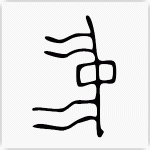
「忠」(金文)/「中」(甲骨文)
論語の本章では”忠実”→”(仕事に)まじめ”。初出は戦国末期の金文。ほかに戦国時代の竹簡が見られる。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。字形は「中」+「心」で、「中」に”旗印”の語義があり、一説に原義は上級者の命令に従うこと=”忠実”。ただし『墨子』・『孟子』など、戦国時代以降の文献で、”自分を偽らない”と解すべき例が複数あり、それらが後世の改竄なのか、当時の語義なのかは判然としない。同音に部品の「中」。「忠」が戦国時代になって現れた理由は、諸侯国の戦争が激烈になり、領民に「忠義」をすり込まないと生き残れなくなったため。詳細は論語語釈「忠」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章は「忠」の字の論語時代における不在から、史実の孔子の発言ではない。ただし論語の本章に限れば、春秋時代に遡れない漢字がこの「忠」一字のみであることから、もとは「中」だったのが書き換えられた可能性がある。その場合、「行之以中」の訓読は「之を行うに中らを以ゐよ」となり、解釈は”政治を行うのに、中=ほどの良さを用いる(片寄りや、極端なことをしない)”となる。
本章は前漢中期の定州竹簡論語に含まれ、それまでには論語の一章として成立していた。「忠」→「中」を明かす物証が無い以上、戦国時代以降の儒者による創作と判断するのが理にかなう。
解説
父親が誰かも分からない、流浪の巫女の子という社会の底辺に生まれた孔子は(孔子の生涯1)、そのまじめさ「無倦」と、血統貴族から見た突飛さ、非「中」によって世に出た。若年期の孔子は、国公や宰相家の家畜番や倉庫番を務め、その有能さが認められて出世の糸口になったと『史記』孔子世家は言う。
その手段はおそらく、後に孔子が必須科目として教えた「数」で、つまり算術と帳簿付けだった。春秋の貴族はまず戦士であり、読み書きは出来たが、地道に統計的データを取って対処するのは苦手だったのだろう。だから孔子が注目されたわけで、「中ら」でなかったことが孔子を押し上げた。
その結果知事として、大法官・宰相として「中ら」を欠いた極端を庶民と貴族に強いて嫌われた。「男女が一緒に道を歩いてはいかん」というのは庶民の反発を買い、斉との国境近くの砦の規模を「規則違反だから」といって取り壊しにかかったのは貴族の反発を買った。
その結果弟子を仕官させづらくなり、他国に活路を求めて、弟子共々亡命するはめになったが、孔子に付き合って辞めた子路に代わり、冉有のように宰相家の執事として孔子より先に魯に帰った者もおり、孔子は積極的に追い出されたのではない。だが十四年の放浪生活は孔子に老成をもたらした。
一方論語の本章で対話相手になっている子張は、『史記』弟子伝によれば孔子より48歳も年下で、孔子が放浪に出たのは55歳の時だから、まだ弟子になっていない。なったのは孔子68歳で魯に帰国した頃だろうから、老成した孔子が政治の要点として「中ら」を説くことはありうる。
この点が、論語の本章が文字史上の疑問を抱えながら、あるいは史実の可能性がある理由になる。また孔子の他の教説とも、一致するところがある。
なお子路が孔子の亡命に付き合って宰相家の執事を辞める前に、『史記』孔子世家によると「夫子可以行矣」”先生、こんなふざけた国からは出て行ってやりましょう”と孔子をけしかけたとされる。だが理由は他にもあって、義理の兄の顔濁鄒が隣国衛に住まっていたからでもあった。
顔濁鄒は当時の諸侯国に傭兵団を貸し出すほどの力があった、国際的任侠団体の大親分で、山塞のほかに衛の都城に屋敷を建てて住まっていた。亡命した孔子と弟子は真っ先に顔濁鄒親分の屋敷に向かってわらじを脱いだのだから、通説のようにしおたれて魯国から出たわけではない。
「新時代の官界を担うにふさわしい技能集団が、諸侯も恐れる武装団体と結託しましたよ、さてどうしますか、殿さまがた。」こういう脅しが利いたのである。なお孔子の母は顔徴在といい、有力弟子には顔回子淵がいる。おそらく顔濁鄒と同族だろう。孔子は存外、凄みを利かせられるコネにも恵まれていたわけだ。
論語の本章、新古の注は次の通り。
古注『論語集解義疏』
子張問政子曰居之無倦行之以忠註王肅曰言為政之道居之於身無得懈倦行之於民必以忠信也
本文「子張問政子曰居之無倦行之以忠」。
注釈。王粛「本章が説くのはこう言うことである。政治を行う原則は、自分については飽きていい加減にならないよう心がけ、民に対しては、まじめさと信頼を心掛けることである。」
新注『論語集注』
子張問政。子曰:「居之無倦,行之以忠。」居,謂存諸心。無倦,則始終如一。行,謂發於事。以忠,則表裏如一。程子曰「子張少仁。無誠心愛民,則必倦而不盡心,故告之以此。」
本文「子張問政。子曰:居之無倦,行之以忠。」
居とは、”これを心に留めよ”の意である。無倦とは、始めから終わりまで変わらないことを言う。行とは、仕事をを始めることを言う。以忠とは、思っていることと、言うこと為すことが一致していることである。
程頤「子張には仁の憐れみが少ない。心から民を愛したことが無く、だから必ず途中で嫌になって一生懸命仕事をしない。だからこのように説教された。」
余話
(思案中)
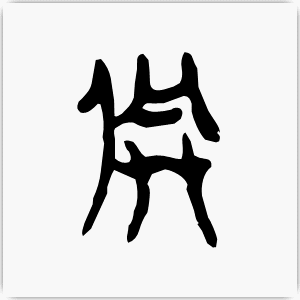




コメント