論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎
- 「猶」字:つくり〔酋〕。
校訂
東洋文庫蔵清家本
子曰聽訟吾猶人也/必也使無訟乎
- 「猶」字:つくり〔酋〕近似。
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
……□訟,吾猶人也。[必也使□訟乎]!316
標点文
子曰、「聽訟、吾猶人也。必也使無訟乎。」
復元白文(論語時代での表記)














※論語の本章は、「猶」「必」の用法に疑問がある。
書き下し
子曰く、訟を聽くは、吾猶ほ人のごとき也。必ず也訟無から使めむ乎。
論語:現代日本語訳
逐語訳

先生が言った。「裁判の判事は、私は人並みに務まるね。だが必ず訴訟そのものを無くしてみせたいものだな。」
意訳

行政官が片手間に判事を務めればいいというものではない。訴訟そのものを無くすよう統治せねばならない。
従来訳
先師がいわれた。――
「訴訟ごとの審理判決をやらされると、私もべつに人と変ったところはない。もし私に変ったところがあるとすれば、それは、訴訟ごとのない世の中にしたいと願っていることだ。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子說:「審案,我跟別人一樣。我想做的是:使案件消失!」
孔子が言った。「裁判は、私は他人と同じだ。私はこれについて、無くしてしまいたい!」
論語:語釈
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。


(甲骨文)
「子」の初出は甲骨文。論語ではほとんどの章で孔子を指す。まれに、孔子と同格の貴族を指す場合もある。また当時の貴族や知識人への敬称でもあり、孔子の弟子に「子○」との例が多数ある。なお逆順の「○子」という敬称は、上級貴族や孔子のような学派の開祖級に付けられる敬称。「南子」もその一例だが、”女子”を意味する言葉ではない。字形は赤ん坊の象形で、もとは殷王室の王子を意味した。詳細は論語語釈「子」を参照。


(甲骨文)
「曰」の初出は甲骨文。原義は「𠙵」=「口」から声が出て来るさま。詳細は論語語釈「曰」を参照。
聽(テイ)


(甲骨文)
論語の本章では”聞く”→”裁判で言い分を聞き取る”。初出は甲骨文。新字体は「聴」。「チョウ」は呉音。字形は「口」+「耳」+「人」で、人の口から出る音を耳で聞く人のさま。原義は”聞く”。甲骨文では原義、”政務を決裁する”、人名、国名、祭祀名に用いた。金文では”聞き従う”の意に、また人名に用いた。詳細は論語語釈「聴」を参照。
耳で直接聞く、の意の他に、政治や裁判など”行政行為を行う”の意味がある。清の西太后が幼少の同治帝に代わり、玉座の後ろに御簾を掛け、その後ろに座って大臣達に指示を出したのを、「垂簾聴政」(スイレンチョウセイ)と言った。
訟(ショウ)


(金文)
論語の本章ではでは”争う”→”訴訟”。『大漢和辞典』の第一義は”訴える”。初出は西周早期の金文。字形は「公」”口を開けてものを言う”+「言」”ことば”で、口に出して人を責めること。原義は”責める”。春秋末期までの金文では、”責める”・”争う”の意に用いた。詳細は論語語釈「訟」を参照。
吾(ゴ)


(甲骨文)
論語の本章では”わたしの”。初出は甲骨文。字形は「五」+「口」で、原義は『学研漢和大字典』によると「語の原字」というがはっきりしない。一人称代名詞に使うのは音を借りた仮借だとされる。詳細は論語語釈「吾」を参照。
古くは中国語にも格変化があり、一人称では「吾」(藤堂上古音ŋag)を主格と所有格に用い、「我」(同ŋar)を所有格と目的格に用いた。しかし論語で「我」と「吾」が区別されなくなっているのは、後世の創作が多数含まれているため。
猶(ユウ)
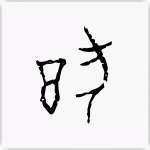

(甲骨文)
論語の本章では、”…も…のようだ”。「なほ…のごとし」と読む再読文字。ただしこの語義は春秋時代では確認できない。
初出は甲骨文。字形は「酉」”酒壺”+「犬」”犠牲獣のいぬ”で、「猷」は異体字。おそらく原義は祭祀の一種だったと思われる。甲骨文では国名・人名に用い、春秋時代の金文では”はかりごとをする”の意に用いた。戦国の金文では、”まるで…のようだ”の意に用いた。詳細は論語語釈「猶」を参照。
人(ジン)


(甲骨文)
論語の本章では”他人”。自分以外の全ての人。初出は甲骨文。原義は人の横姿。「ニン」は呉音。甲骨文・金文では、人一般を意味するほかに、”奴隷”を意味しうる。対して「大」「夫」などの人間の正面形には、下級の意味を含む用例は見られない。詳細は論語語釈「人」を参照。
也(ヤ)


(金文)
論語の本章、「人也」では「なり」と読んで”~である”、断定の意を示す。または「かな」と読んで”…だぞ”、詠嘆の意。断定の語義は春秋時代では確認できない。本章は文字史的に春秋時代に遡れるため、詠嘆の意に解するのが適切。
「必也」では詠嘆の意、”是非とも”。ただし句末にも詠嘆を示す「乎」があるため、読んで字の如く”かならずや”と解して可。
初出は事実上春秋時代の金文。字形は口から強く語気を放つさまで、原義は”…こそは”。春秋末期までに句中で主格の強調、句末で詠歎、疑問や反語に用いたが、断定の意が明瞭に確認できるのは、戦国時代末期の金文からで、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「也」を参照。
必(ヒツ)


(甲骨文)
論語の本章では”必ず”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。原義は先にカギ状のかねがついた長柄道具で、甲骨文・金文ともにその用例があるが、”必ず”の語義は戦国時代にならないと、出土物では確認できない。『春秋左氏伝』や『韓非子』といった古典に”必ず”での用例があるものの、論語の時代にも適用できる証拠が無い。詳細は論語語釈「必」を参照。
使(シ)(…しむ)


(甲骨文)
論語の本章では”~させる”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「事」と同じで、「口」+「筆」+「手」、口に出した事を書き記すこと、つまり事務。春秋時代までは「吏」と書かれ、”使者(に出す・出る)”の語義が加わった。のち他動詞に転じて、つかう、使役するの意に専用されるようになった。詳細は論語語釈「使」を参照。
無(ブ)


(甲骨文)
論語の本章では”無くす”。消失させる、の意。初出は甲骨文。「ム」は呉音。甲骨文の字形は、ほうきのような飾りを両手に持って舞う姿で、「舞」の原字。その飾を「某」と呼び、「某」の語義が”…でない”だったので、「無」は”ない”を意味するようになった。論語の時代までに、”雨乞い”・”ない”の語義が確認されている。戦国時代以降は、”ない”は多く”毋”と書かれた。詳細は論語語釈「無」を参照。
乎(コ)


(甲骨文)
論語の本章では、「か」と読んで詠嘆の意。決意を示す。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は持ち手の柄を取り付けた呼び鐘を、上向きに持って振り鳴らし、家臣を呼ぶさまで、原義は”呼ぶ”こと。甲骨文では”命じる”・”呼ぶ”を意味し、金文も同様で、「呼」の原字となった。句末の助辞として用いられたのは、戦国時代以降になるという。詳細は論語語釈「乎」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章は文字史的に全て春秋時代まで遡ることが出来る。前漢中期の定州竹簡論語にも含まれている。漢語の用法的に論語の時代から確認出来ない語義はあるのだが、史実の孔子の言葉と解して差し支えない。
内容的には、「民どもを法で縛り付けて躾けてやる」と意気込んでいた50歳ごろまでの孔子の伝記とは異なり(前々章、論語顔淵篇11付記参照)、「訴訟そのものがなくなるような政治をしてみせる」という、老成した考え方になっている。
解説
前章(論語顔淵篇12)でも記した通り、中国では清末に至るまで、裁判官はその土地の地方官(知事や周辺の村落をも管掌する中心都市の市長)が兼任した。つまり司法の独立という概念が無かった。加えて伝統的に中国の地方は、中央政府の任命でやって来る知事や市長の世話焼きが要らない、強固な自治集団だった。
言い換えるとその地法ごとに、ヤクザの親分と商家の旦那を兼ねた地方ボスが万事取り仕切っており、知事や市長は裁判ぐらいしかいじらせて貰えなかった。そうでもしないと、地方ボスからたっぷりワイロを受け取っている上役に難癖をつけられて、クビになってしまったからだった。
だがこういう景色は官僚制の確立した帝政期以降の特徴で、孔子の生きた春秋時代後半は、多くの土地と領民が大貴族の所領と属民だった。領主貴族は領主裁判を行ったのだろうが、領民に嫌われると徴税や動員に差し支えるので、刑事裁判でむやみに厳罰を科せないのはもちろん、民事裁判では世論を気にしながら判決するしか道が無かった。
これは春秋時代とはどんな時代だったかを語るために、何度も繰り返し記すのだが、春秋の貴族は家臣や領民にそっぽを向かれると、まず地位を保てないし、少なからず天寿も全うできない。社会の生産力がか細くて、飢餓状態が常態だから、貴族が贅沢を見せつけるなんてとんでもなかった。
范文子謂欒武子曰,季孫於魯,相二君矣,妾不衣帛,馬不食粟,可不謂忠乎。
(晋の大貴族)范文子が(これも晋の大貴族)欒武子に言った。「魯国では季孫家が、すでに二代の国公にわたって宰相を務めている。だが家族の女性に絹を着せず(に麻布や葛布の服を着せ)、馬に穀物を与えない(で草を食ませている)と聞く。こういうのが、「忠」=”まじめ”(な貴族)というものではないか。」(『春秋左氏伝』成公十六年)
※「忠」の字が漢語に現れるのは戦国時代なので、この一節は話自体が怪しいのだが、もとは「中」”片寄りが無い、常識に外れない”と書かれていたとするなら話は通る。
ペニシリンどころか病原菌の概念も無いから、庶民だと30ほどで死んでしまう。ささいな怪我や病気が、すぐさま死に直結した。そもそも腹一杯食べる事ができず、当時の主要穀物であるアワ1リットルは、現代換算で1万円もした(論語雍也篇4解説参照)。
そんな生存の危機を貴族も分かち合っていた。もちろん貴族に逆らえば庶民は殺されてしまったが、貴族もまたゆえなく庶民にひどいことは出来ないばかりか、蛮族や敵国から守ってやらねばならなかった。だから春秋の貴族は戦士を兼ねていたのだし、社会に余裕が無いゆえに、庶民との間は持ちつ持たれつだった。
一方国公の天領は、50ごろの孔子が就任したように役人が長官として行政と司法を兼任したが、世論を気にしないで厳罰を科したため孔子は嫌われて、のちに亡命せざるを得なくなったことも前々章に記したとおり。対して本章での孔子は、まるで人が変わったようになっている。
こうした老成後の孔子の考え方を受け継ぎ強調したのが、孔子没後一世紀過ぎて生まれた孟子だった。
若民,則無恆產,因無恆心。苟無恆心,放辟,邪侈,無不為已。及陷於罪,然後從而刑之,是罔民也。

民という者は、財産がありませんから、不動心など持ちようがありません。不動心が無いから、悪さはする、図乗りはする、やりたい放題するしかないのです。その結果捕まって、その後で王殿下のような為政者が、そういう者に刑罰を加える。これを民に目隠ししたままいじめる、というのですぞ。(『孟子』梁恵王上)
有名な「恒産無くして恒心無し」の出典だが、孟子は上掲の梁の恵王だけでなく、滕の文公にも同じ説教をしている。孟子はすでに滅びていたも同然だった儒家を、自分の商売道具に仕立てた世間師ではあるが、こういう人道的なことを言い張ったから、後世から好かれた。
だが孟子は世間師として、そんなに成功していない。理由は戦国の乱世に人道を説いてしまったからで、大国の殿さま連には相手にされず、滅びかかった小家の殿さま(滕の文公)だけが話を熱心に聞いてくれたが、孟子の言う通りにしたら滕は滅びてしまった。
孟子のせいだと言えなくは無いが、そもそも戦国の世で滕のような小国が生き残るのは極めて困難で、孟子も「これはどうにもなりませんから、殿さまを廃業しなさい」と遠回しに説教している(論語為政篇7余話「犬馬の労」参照)。
だがそんな孟子と開祖の孔子の弟子を自称する後世の儒者は、古注の書かれた漢から南朝ごろまでは、まだ貴族や他の諸派と抗争の関係にあって緊張していたから、論語の本章についてもあっさりとしたことしか書き付けていない。
古注『論語集解義疏』
子曰聽訟吾猶人也註苞氏曰言與人等也必也使無訟乎註王肅曰化之在前也
本文「子曰聽訟吾猶人也」。
注釈。包咸「自分も人と同じだ、と言ったのである。」
本文「必也使無訟乎」。
注釈。王粛「訴訟の起こらないような政治を実践して、それから人々を道徳的に教育しようとしたのである。」
だが貴族と他派が消滅し、政界官界を儒者が独占すると、まるで孔子が老成前に退化したかのような書き付けをしている。
新注『論語集注』
子曰:「聽訟,吾猶人也,必也使無訟乎!」范氏曰:「聽訟者,治其末,塞其流也。正其本,清其源,則無訟矣。」楊氏曰「子路片言可以折獄,而不知以禮遜為國,則未能使民無訟者也。故又記孔子之言,以見聖人不以聽訟為難,而以使民無訟為貴。」
本文「子曰:聽訟,吾猶人也,必也使無訟乎!」
范祖禹「裁判とは、分不相応の者を叩き直し、低俗な行いをやめさせるためにある。社会の秩序を本来の姿に整え、世の中の風潮を清潔にすれば、必ず裁判そのものが必要無くなる。」
楊時「子路は片方の言い分だけを聞いて判決を下せたが(前章)、礼儀作法と謙遜で国を治めるべきことをりを知らなかった(論語先進篇25)。だから民が訴訟を起こすのを止めることが出来なかった。だから孔子の言葉をここに記してあるのだが、聖人にとって裁判など簡単で、それより民が訴訟を起こさないようにした方が立派であると考えていたことがわかる。」
閲覧者諸賢はあるいは、江戸の松平定信をご存じであろうか。庶民の娯楽をあれも禁止これも禁止と取り締まり、自分は没収したエロ本の収集を趣味とした愚劣な男だが、新注の宋儒と共に、役人の本質とは何かがよく分かるし、司法の身勝手を含め現代人にとっても無関係では無いように思う。
余話
(思案中)




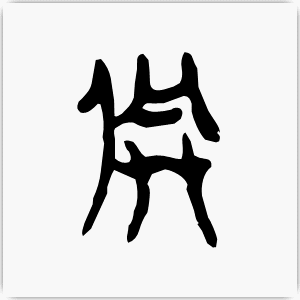
コメント