論語:原文・白文・書き下し
原文・白文
曾子曰、「堂堂乎張也、難與並爲仁矣。」
復元白文(論語時代での表記)


 堂堂
堂堂








※張→(金文大篆)・仁→(甲骨文)。論語の本章は「堂」の字が論語の時代に存在しない。「乎」「與」の用法に疑問がある。曽子は孔子家の家事使用人であって弟子ではない。定州竹簡論語にも存在しない。本章は後漢儒による創作である。
書き下し
曾子曰く、堂堂乎たり張也、與に並びて仁を爲し難き矣。
論語:現代日本語訳
逐語訳
曽子が言った。「大きく広いな、子張さんはまことに。一緒に並んで仁を実践するのは実に難しい。」
意訳


曽子「子張めは押しが強すぎて、とてもじゃないが仁の情けがあるようには見えないし、図々しくて付き合いきれない。」
従来訳
曾先生がいわれた。―― 「堂々たるものだ、張の態度は。だが、相たすけて仁の道を歩める人ではない。」
下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
曾子說:「子張雖然外表堂堂,但難於和他一起做大事。」
曽子が言った。「子張は外見は堂々としているが、ただし彼と共に大仕事をするのは難しい。」
論語:語釈
曾子

論語では孔子の若い弟子とされた人物で、「魯」=ウスノロと評された曽参子輿のこと。曽子が孔子家の使用人だった可能性はあるが、弟子だった可能性は極めて疑わしい。文字的には論語語釈「曾」(曽)・論語語釈「子」を参照。
堂

「堂」(金文)
論語の本章では”大きく広いさま”。「堂」の字の初出は戦国中期の金文で、本章が後世の創作であることを証拠立てる。
『学研漢和大字典』によると、尚(ショウ)は、窓から空気が高くたちのぼるさまを示し、広く高く広がる意を含む。堂は「土+(音符)尚」の会意兼形声文字で、広く高い土台のこと。転じて、広い高い台上にたてた表御殿、という。詳細は論語語釈「堂」を参照。
乎(コ)


(甲骨文)
論語の本章では、形容詞・副詞の後ろにつけて、その状態を示す助辞。初出は甲骨文。甲骨文の字形は持ち手を取り付けた呼び鐘の象形で、原義は”呼ぶ”こと。甲骨文では”命じる”・”呼ぶ”を意味し、金文も同様で、「呼」の原字となった。句末の助辞として用いられたのは、戦国時代以降になる。ただし「烏乎」で”ああ”の意は、西周早期の金文に見え、句末でも詠嘆の意ならば論語の時代に存在した可能性がある。詳細は論語語釈「乎」を参照。
張

論語では孔子の若い弟子で、何事もやり過ぎと評された顓孫師子張を指す。「張」の字は論語の時代に存在しないが、固有名詞のため、同音近音のいかなる漢字も置換候補となりうる。詳細は論語語釈「張」を参照。
也(ヤ)


(金文)
論語の本章では、「や」と読んで下の句とつなげる働きに用いている。初出は事実上春秋時代の金文。字形は口から強く語気を放つさまで、原義は”…こそは”。春秋末期までに句中で主格の強調、句末で詠歎、疑問や反語に用いたが、断定の意が明瞭に確認できるのは、戦国時代末期の金文からで、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「也」を参照。
難


(金文)
論語の本章では”難しい”。初出は西周末期の金文。『学研漢和大字典』による原義は、焼き鳥を作るさま。詳細は論語語釈「難」を参照。
與(ヨ)


(金文)
論語の本章では”~と”。新字体は「与」。初出は春秋中期の金文。金文の字形は「牙」”象牙”+「又」”手”四つで、二人の両手で象牙を受け渡す様。人が手に手を取ってともに行動するさま。従って原義は”ともに”・”~と”。詳細は論語語釈「与」を参照。
並

(金文)
論語の本章では”並ぶ”。初出は甲骨文。「竝」は正字体。『学研漢和大字典』によると人が地上にたった姿を示す立の字を二つならべて、同じようにならぶさまを示したもの。同じように横にならぶこと。略して並と書く。また、併(ヘイ)に通じる、という。詳細は論語語釈「並」を参照。
爲(イ)
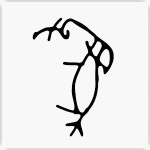

(甲骨文)
論語の本章では”実践する”。新字体は「為」。字形は象を調教するさま。甲骨文の段階で、”ある”や人名を、金文の段階で”作る”・”する”・”~になる”を意味した。詳細は論語語釈「為」を参照。
仁(ジン)


(甲骨文)
論語の本章では、”常に憐れみの気持を持ち続けること”。初出は甲骨文。字形は「亻」”ひと”+「二」”敷物”で、原義は敷物に座った”貴人”。詳細は論語語釈「仁」を参照。
仮に孔子の生前なら、単に”貴族(らしさ)”の意だが、後世の捏造の場合、通説通りの意味に解してかまわない。つまり孔子より一世紀のちの孟子が提唱した「仁義」の意味。詳細は論語における「仁」を参照。
つまり素のままの自分に手を加えて、常時無差別の愛を現実化する自分になること。


子を亡くした子夏に「自業自得だ」と放言した曽子(論語学而篇4付記)に、常時無差別の愛などあったものではない。「おまゆう」とはこのことだ。
矣(イ)


(金文)
論語の本章では、”(きっと)…である”。初出は殷代末期の金文。字形は「𠙵」”人の頭”+「大」”人の歩く姿”。背を向けて立ち去ってゆく人の姿。原義はおそらく”…し終えた”。ここから完了・断定を意味しうる。詳細は論語語釈「矣」を参照。
論語:付記
(思案中)





コメント