論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子曰關雎樂而不淫哀而不傷
校訂
東洋文庫蔵清家本
子曰關雎樂而不滛哀而不傷
※「滛」字は「淫」の異体字。「石經尚書殘碑」刻。
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
(なし)
標点文
子曰、「關雎、樂而不淫、哀而不傷。」
復元白文(論語時代での表記)

 關雎
關雎 

 淫
淫 

 傷
傷
※論語の本章は赤字が論語の時代に存在しない。本章は後世の儒者による創作である。
書き下し
子曰く、關雎は樂しん而淫ら不、哀しん而傷ら不。
論語:現代日本語訳
逐語訳

先生が言った。「詩経のミサゴの歌は、楽しんでもふけるほどでなく、哀しんでもひたるほどではない。」
意訳

ミサゴの歌は男女の求愛を歌うが、愛の喜びを歌っても節度があって、ふけりきっていない。かなわぬ思いの悲しみを歌っても節度があって、後ろ向きな喜びにひたっていない。
従来訳
先師がいわれた。――
「関雎の詩は歓楽を歌っているが、歓楽におぼれてはいない。悲哀を歌っているが、悲哀にやぶれてはいない。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子說:「《關雎》這篇詩,快樂卻不淫穢,悲哀卻不傷痛。」
孔子が言った。「関雎、この詩は、快楽を歌いながら却ってワイセツでなく、悲哀を歌いながら痛そうでない。」
論語:語釈
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指すが、そうでない例外もある。「子」は生まれたばかりの赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来る事を示す会意文字。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例があるが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。おじゃる公家の昔から、日本の論語業者が世間から金をむしるためのハッタリと見るべきで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
關雎(カンショ)


「關」(金文)/「雎」(前漢隷書)
論語では、『詩経』の開巻第一に記されている古詩。
「關」の新字体は「関」。初出は戦国初期の金文。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。同音は慣・串など。字形は「門」+「卝」で、門を閉じたさま。「卝」の初出は後漢の『説文解字』。詳細は論語語釈「関」を参照。
「雎」の初出は前漢の隷書。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。同音は「且」を部品に持つ漢字群。字形は「且」(音符)+「鳥」で、ミサゴを意味するとされる。上掲の隷書はおそらく、戦国末期の縦横家范雎の名を記したもの。詳細は論語語釈「雎」を参照。
論語時代の楽譜や曲は伝わっていないし、下記現伝の「関雎」が、春秋時代以前の成立とする根拠は何も無い。
參差荇菜、左右流之。 窈窕淑女、寤寐求之。
求之不得、寤寐思服。悠哉悠哉、輾轉反側。
參差荇菜、左右采之。窈窕淑女、琴瑟友之。
參差荇菜、左右芼之。窈窕淑女、鍾鼓樂之。
關關となく雎鳩は、河之洲に在り。 窈窕たる淑女は、君子の好き逑。
かつ參くかつ差き荇菜は、左右に之を流む。 窈窕たる淑女を、寤ても寐めても之を求む。
之を求めて得られ不、寤ても寐めても思い服がる。悠哉悠哉と、輾轉と側をば反つ。
かつ參くかつ差き荇菜は、左右に之を采る。窈窕たる淑女を、琴瑟のごとく之を友とせん。
かつ參くかつ差き荇菜は、左右に之を芼る。窈窕たる淑女を、鍾鼓のごとく之を樂ません。
關雎の歌が現伝の『詩経』に載っているからと言って、必ずしも論語の時代にあったとは言えない。また『定州論語』には、八佾篇を含め關雎の歌の記述が無い。その部分の簡が欠けてしまった可能性はあるが、ともあれ現伝最古の論語に記載が無い。
なお「雎」は鳥のミサゴのことで、英語ではOsprey。

Photo via http://free-photo.net/
樂(ラク)


(甲骨文)
論語の本章では”楽しむ”。初出は甲骨文。新字体は「楽」。原義は手鈴の姿で、”音楽”の意の方が先行する。漢音(遣隋使・遣唐使が聞き帰った音)「ガク」で”奏でる”を、「ラク」で”たのしい”・”たのしむ”を意味する。春秋時代までに両者の語義を確認できる。詳細は論語語釈「楽」を参照。
而(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”~かつ~”。初出は甲骨文。原義は”あごひげ”とされるが用例が確認できない。甲骨文から”~と”を意味し、金文になると、二人称や”そして”の意に用いた。英語のandに当たるが、「A而B」は、AとBが分かちがたく一体となっている事を意味し、単なる時間の前後や類似を意味しない。詳細は論語語釈「而」を参照。
不(フウ)


(甲骨文)
論語の本章では”~でない”。漢文で最も多用される否定辞。初出は甲骨文。原義は花のがく。否定辞に用いるのは音を借りた派生義。詳細は論語語釈「不」を参照。現代中国語では主に「没」(méi)が使われる。
哀(アイ)


(金文)
論語の本章では”かなしむ”。初出は西周早期の金文。字形は「𠙵」”くち”のまわりをなにがしかで囲む形で、由来と原義は不詳。金文では”かなしむ”の意に、”いとおしむ”の意に用い、戦国の竹簡でも同様。詳細は論語語釈「哀」を参照。
淫(イン)


(楚系戦国文字)
論語の本章では”ふける”。初出は楚系戦国文字。論語の時代に存在せず、論語時代の置換候補も無い。同音は存在しない。初出の字形は「氵」”かわ”+”目を見開いた人”+「一」”地面”で、なすすべもなく洪水が広がっていくのを地に立って茫然とみるさま。字形の由来は、「氾」”うずくまって洪水を見る”「濫」洪水をじっと見る”に近い。原義は”ひたひたと広がる”。広がりすぎることから、のちに”ふける”の意味が派生した。”みだら”の語義はさらに時代が下る。詳細な語釈は論語語釈「淫」を参照。
傷*(ショウ)


(燕系戦国文字)
論語の本章では、”ひたる”。何かの外的要因で悪影響が体に居座り続けること。「傷寒」の用例と同じ。初出は燕系戦国文字。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。同音は「商」「賞」「湯」「傷」とつくりを同じくする漢字群、「殤」”若死に・そこなう”、「觴」「禓」”道の祭・追儺”。字形は「昜」”木漏れ日”+「人」。字形の由来や原義は明瞭でない。戦国文字では、〔昜刂〕〔昜戈〕の字形も「傷」字に比定されている。部品「昜」の初出は甲骨文。詳細は論語語釈「傷」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章は、もう少し膨らませた話を前漢初期の『韓詩外伝』が載せている。
子夏問曰:「關雎何以為國風始也?」孔子曰:「關雎至矣乎!夫關雎之人,仰則天,俯則地,幽幽冥冥,德之所藏,紛紛沸沸,道之所行,如神龍變化,斐斐文章。大哉!關雎之道也,萬物之所繫,群生之所懸命也,河洛出圖書,麟鳳翔乎郊,不由關雎之道,則關雎之事將奚由至矣哉!夫六經之策,皆歸論汲汲,蓋取之乎關雎,關雎之事大矣哉!馮馮翊翊,自東自西,自南自北,無思不服。子其勉強之,思服之,天地之間,生民之屬,王道之原,不外此矣。」子夏喟然嘆曰:「大哉!關雎乃天地之基也。」《詩》曰:「鍾鼓樂之。」
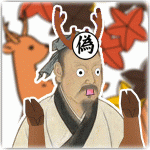
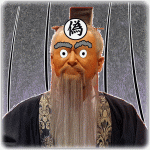
子夏「関雎の歌は、なぜ国風篇の始めに収められたのですか?」
孔子「関雎は素晴らしいなあ! 関雎の歌い手は、仰向けば天、うつむけば地で、ぼんやりもやもや、徳の仕舞いどころは、むらむらぐつぐつ、道の行ったあとは、神竜のように変化して、言葉の綾が美しい。スバラシイねえ! 関雎が道であることは、万物に関係があり、生物の命が関わる所だ。黄河や洛水が預言書を(神獣の背に乗せて)出し、目出度い麒麟や鳳凰が郊外を舞い踊ったが、もし関雎の道がなかったら、どうやって関雎の事が実現して今のようになっただろうか。そもそも儒教の六科目の教えでは、クドクドといろいろな説明をしたが、実はその根源は関雎にあるのだ。関雎とは偉大だねえ! 天下に満ちてしかも慎ましい。東西南北、関雎を思って慕わないものはいない。君は関雎に努力し、思って慕いなさい。天地の間、人々の属性、王道の原則は、関雎を離れては成立しない。」
子夏がため息をつき、「偉大ですねえ! 関雎が天地の根源であることは。『詩経』に”チンチンどんどんをしなさい”と言うのももっともだ。」(『韓詩外伝』巻五の1)
あまりにメルヘンで、まじめに訳す気が失せかけた。
ともあれ「関雎」の文字は前漢初期にはあったが、論語の本章は定州竹簡論語に無いことから、成立は後漢以降にまで下る可能性がある。上記の通り、「関雎」の歌には後漢にならないと見られない文字がぞろぞろあり、前漢までの歌詞とまるで違えられた可能性が高い。
論語の本章では、古注に前漢の孔安国が注を付けているが、この男は実在が疑わしい。新注は元の歌を引いて御託を並べているだけだし、大して難しくもないので、訳は略す。
古注『論語集解義疏』
註孔安國曰樂而不至淫哀而不至傷言其和也
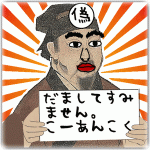
注釈。孔安国「楽しみてみだらに至らず、哀しみて傷つくに至らずとは、その調和を言ったものだ。」
なお「関雎」の語は論語泰伯編15にもみえるが、その章は『史記』孔子世家に再録があるから、本章とは異なり前漢中期にはあっただろう。ただし想定されている歌詞は、現行のとはまるで違ったことは本章の事情と同様。
解説
論語の本章、『詩経』関雎に用いられた漢字の初出をざっと調べたのが以下の表。赤字は論語の時代までに存在せず、存在する字も必ずしも現伝詩経で解釈される語義を持っていたわけではない。これを孔子が「曰く」とは、うそデタラメと断じるほかは無い。ただ、調べようによってはもう少し時代を遡れる漢字があるかも知れない。
| 關 | 關 | 雎 | 鳩 | 在 | 河 | 之 | 洲 |
| 戦国 | 前漢 | 前漢 | 甲骨 | 甲骨 | 甲骨 | 甲骨 | |
| 窈 | 窈 | 淑 | 女 | 君 | 子 | 好 | 逑 |
| 後漢 | 西周 | 甲骨 | 甲骨 | 甲骨 | 甲骨 | 戦国 | |
| 參 | 差 | 荇 | 菜 | 左 | 右 | 流 | 之 |
| 殷 | 春秋 | 戦国 | 西周 | 甲骨 | 甲骨 | 戦国 | 甲骨 |
| 窈 | 窕 | 淑 | 女 | 寤 | 寐 | 求 | 之 |
| 後漢 | 後漢 | 西周 | 甲骨 | 後漢 | 西周 | 甲骨 | 甲骨 |
| 求 | 之 | 不 | 得 | 寤 | 寐 | 思 | 服 |
| 甲骨 | 甲骨 | 甲骨 | 甲骨 | 後漢 | 西周 | 戦国 | 甲骨 |
| 悠 | 哉 | 悠 | 哉 | 輾 | 轉 | 反 | 側 |
| 後漢 | 西周 | 後漢 | 西周 | 後漢 | 戦国 | 甲骨 | 西周 |
| 參 | 差 | 荇 | 菜 | 左 | 右 | 采 | 之 |
| 殷 | 春秋 | 戦国 | 西周 | 甲骨 | 甲骨 | 甲骨 | 甲骨 |
| 窈 | 窕 | 淑 | 女 | 琴 | 瑟 | 友 | 之 |
| 後漢 | 後漢 | 西周 | 甲骨 | 戦国 | 戦国 | 甲骨 | 甲骨 |
| 參 | 差 | 荇 | 菜 | 左 | 右 | 芼 | 之 |
| 殷 | 春秋 | 戦国 | 西周 | 甲骨 | 甲骨 | 前漢 | 甲骨 |
| 窈 | 窕 | 淑 | 女 | 鍾 | 鼓 | 樂 | 之 |
| 後漢 | 後漢 | 西周 | 甲骨 | 西周 | 甲骨 | 甲骨 | 甲骨 |
司馬遷は「関雎」を、「夫周室衰而關雎作,幽厲微而禮樂壞」と言っているから、早くとも西周末期の成立と思っていたようだ。
だがその後になると、西周第三代康王の時代の作とされるようになり、また慎み深い婦人の徳を意味する、と解されるようになった。もちろんここでの「徳」は道徳のことで、孔子生前の語義、利益を生み出す機能、とは異なる。詳細は論語における「徳」を参照。
「樂而不淫」については、『春秋左氏伝』魯襄公二十九年(BC623)条に、呉の公子李札が魯国を訪れた際の発言として記載がある。宴会で豳の民謡を歌ったところ、「美哉,蕩乎,樂而不淫,其周公之東乎」”よろしいですな。人を感動させる歌です。楽しい曲ですがのめり込ませる手前で止まって控えめです。これはきっと周公の作でしょう”。
「哀而不傷」については、前漢の劉向『列女伝』に南宋になってからつけ加えられた『続列女伝』班婕妤篇6が再出。『漢書』では暗君成帝を諌める賢女として記されるだけだが、宋儒の作文では成帝の跡を追って殉死したことになっているが多分ウソ。wikipediaを参照。
結局論語の本章は、関雎の歌共々でっち上げである他方で、真に受けて現在復元され、演奏されている音楽があるようだ。いくら元がでっち上げだからといって、復元の努力と音楽そのものに、罪があるわけではない。
余話
美男美女より美食がいい
色事禁止を説く宗教は多いが、孔子の教説も帝国儒教も、そう言わなかった。前者はともかく後者は、それを言い出すと最大の顧客である皇帝から取引禁止を言い渡されるし、中国人の根本欲求である福禄寿に背くから、社会全体からそっぽを向かれて滅亡する羽目になる。
司馬遼太郎がどこかで、鍋島閑叟に「儒者とは好色な者だ」と言わせていた記憶があるが、儒者は「先祖の祭祀を絶やさぬため」という大義名分を考え出し、好色を不道徳ではないと言えるようにはしておいた。だが取引先でない相手には色事禁止を言い放題で、油断がならない。
だがどの宗教も社会を圧倒すると高位聖職者が助平だらけになることは人類史の通例で、ローマ教会はその点で悪名高かった。それを批判したルターも尼さんと結婚してマイホームパパを演じたから、一つにはそれもあってドイツの民衆から「うそつき博士」とこき下ろされた。
対して正教会も色事禁止はローマ教会並みには厳しかったが、意外にも最下級の聖職者である司祭には、妻帯が許されているらしい。ただし既婚者が出家した場合に限ると条件は付いているが、「神が結んだものを人が引き離してはならない」という旧約の教えによるのだろうか。
正教会の戒律は現代日本人にとって、むしろ厳しく感じるのは食事の斎戒で、毎週斎戒日があるばかりでなく、オリーブ油もギリシア語の”よろこび”を語源とするからなまぐさだという。どの宗教も真面目に修行すれば大変だろうが、訳者には正教の信者は務まりそうにない。





コメント