論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣
校訂
東洋文庫蔵清家本
子曰禘自旣灌而往復者吾不欲觀之矣
※「禘」字のへんは〔示〕でなく〔礻〕
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
子曰:「[禘]□45……
標点文
子曰、「禘自旣灌而往者、吾不欲觀之矣。」
復元白文(論語時代での表記)















※灌→盥・欲→谷。
書き下し
子曰く、禘旣に灌ぎ而自り往者、吾之を觀ることを欲め不る矣。
論語:現代日本語訳
逐語訳

先生が言った。「禘の祭りは、酒を撒いた後は、私は見たいと思わない。」
意訳

禘の祭りでは酒を撒き、それでご先祖様のたましいを呼び申す、ことになっておる。たましいが降りてきた振りした神官どもの、偽善めいた振る舞いは、阿呆らしくて見るに堪えない。
従来訳
先師がいわれた。――
「禘の祭は見たくないものの一つだが、それでも酒を地にそそぐ降神式あたりまではまだどうなりがまんが出来る。しかしそのあとはとても見ていられない。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子說:「現在天子舉行的祭祖禮儀,從一開始我就看不下去了。」
孔子が言った。「現在周王が行っている祖先の祭祀儀礼は、その始まりから、私には実に見届けるのに耐えられない。」
論語:語釈
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指すが、そうでない例外もある。「子」は生まれたばかりの赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来る事を示す会意文字。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例があるが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。おじゃる公家の昔から、日本の論語業者が世間から金をむしるためのハッタリと見るべきで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
禘(テイ)


(甲骨文)
論語の本章では、”祖先を祀る大祭礼”。初出は殷墟の甲骨文。西周中期の「剌鼎」に、「隹五月、王在衣。辰在丁卯。王禘」とあるという(谷秀樹「西周代天子考」)。『字通』に「啻は禘の初文」とあり、論語の時代までは「啇」「啻」「敵」などと書き分けられていない。
『字通』「啇」条
[会意]初形は帝+口。帝は大きな祭卓の形。口は祝告の𠙵(さい)。卜文・金文に啻に作り、禘祭の禘の初文。嫡祖を祭る。嫡子にして嫡祖を祭ることができるので、啇に正啇の意がある。嫡の初文。
詳細は論語語釈「禘」を参照。

「帝」も甲骨文よりあり、「神」を意味した。早稲田大学所蔵の甲骨に、「帝我にせ不り、其れ土方に又けを畀うか」(神は私にではなく、蛮族どもに力を貸すか)とあり、殷22代目の武丁の甲骨とされる(早稲田大学會津八一記念博物館所蔵甲骨文字考釈)。

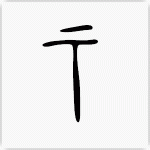
「帝」「示」(甲骨文)
では「帝」とはどんな神か。『字通』によると、それは交差させた脚を束ねた上に板をのせた、天上界にいる祖先の霊向けの祭壇の形で、まだ昇天していない父祖の霊である「示」(これも祭壇の形だが一本足)と区別したという。尊さによって祭壇の脚に区別を付けたか。
「禘」はその二つを足しっぱなしにした文字=言葉であり、帝国の儒者による儀式にもったいが付けられる前は、漠然と祖先一般を祀る祭だったことになる。ただし、「禘」がどのような祭祀だったか分からないと、孔子がなぜ見るのを嫌がったかが分からない。ところがこの点について、漢文資料はすさまじく頼りない。
後漢の『説文解字』では、「諦祭のことだ」とだけあり、文字が「諦」になっていることが知れるのみ。前漢の『爾雅』も、「大きな祭だ」とだけいい、祭の内容は分からない。当時すでに、分からなくなっていたのだ。
現在でも中国や台湾や韓国の孔子廟で、「禘」と称するちんちんドンドンは行われているようだが、無論論語時代のそれではない。
「禘」が復活したのは、後漢の光武帝になってのことで、それまで久しく絶えていた。
二十六年,詔純曰:「禘、祫之祭,不行已久矣。『三年不為禮,禮必壞;三年不為樂,樂必崩』。宜據經典,詳為其制。」

〔オカルトマニアで偽善者の〕光武帝が、治世の二十六年(AD50)に、大臣の張純に命令を下した。「禘と祫の祭は、廃れてから長くなった。三年サボれば礼儀を忘れてダメになる、音楽もダメになる、と言うではないか。古記録をよく調べて、やり方を整理して提出するように。」(『後漢書』張曹鄭列傳)
祫もまた君主が行う祖先祭だが、禘と同様、その内容が分からない。だから儒者官僚が一生懸命偽作した『礼記』は、相互に記述が矛盾している。
天子、諸侯宗廟之祭:春曰礿,夏曰禘,秋曰嘗,冬曰烝。天子犆礿,祫禘,祫嘗,祫烝。諸侯礿則不禘,禘則不嘗,嘗則不烝,烝則不礿。諸侯礿,犆;禘,一犆一祫;嘗,祫;烝,祫。
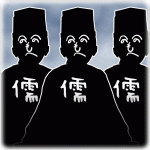
天子と諸侯の祖先祭は、春に行うのを礿、夏に行うのを禘、秋に行うのを嘗、冬に行うのを烝という。天子は天下にただ一人、礿・禘・嘗・烝の祭を四つとも行う。諸侯は一つだけ行ってよい。だから礿をやったら禘はやらず、禘をやったら嘗はやらず、嘗をやったら烝はやらない。礿・禘・嘗・烝、どれか一つだけ行うのである。(『礼記』王制)
諸侯が禘をやってはイカンと書いてない。ところが同じ本で。
孔子曰:「於呼哀哉!我觀周道,幽、厲傷之,吾舍魯何適矣!魯之郊禘,非禮也,周公其衰矣!杞之郊也禹也,宋之郊也契也,是天子之事守也。故天子祭天地,諸侯祭社稷。」

孔子先生が泣きながら言った。「うああああおああああ。哀しいのう。周の歴史を読んでいると、バカ殿幽王と厲王が滅茶苦茶にした。しかし、周公の末裔であり、周の文化を引き継ぐ魯国から、ワシは出ていっても、行くあてが無い。魯公が禘の祭を行うのは礼に背いている。周公はもう忘れられてしまったのだ。シクシク。杞国が開祖の禹を祀り、宋国が開祖の契を祀るのは、もと天子だった伝統を守るためだ。だから天子は天地を祀り、諸侯は土地神と穀物神を祀るのだ。」(『礼記』礼運)
「行くあてが無い」はウソ八百で、孔子は宰相代理として魯国で無茶をやらかす一方、いざというときに備えて、当時の国際的任侠道の大親分、顔濁鄒と盃を交わしており、実際国を叩き出さた時には真っ先に親分の住む衛国に向かい、その屋敷にわらじを脱いだ。
そもそも「天子」の言葉が中国語に現れるのも西周早期で、殷の君主は自分から”天の子”などと図々しいことは言わなかった。詳細は論語述而篇34余話「周王朝の図々しさ」を参照。
こういう、滅茶苦茶の偽作が元ネタだから、もはや真相は誰にも分からない。こうまで証拠が無いという事は、天の神を祀る大祭という意味での禘そのものが、後世の儒者のでっち上げで、単に法事を意味しただろう。
閔公二…夏,五月,乙酉禘于莊公。
閔公元年(BC661)…夏、六月。辛酉の日、我が君荘公を葬った。
閔公二年…夏、五月。乙酉の日、荘公を禘った。(『春秋左氏伝』閔公)
自(シ)
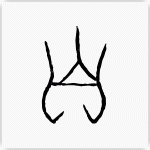
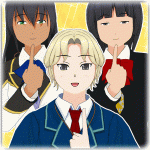
(甲骨文)
論語の本章では”~から”。初出は甲骨文。「ジ」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。原義は人間の”鼻”。春秋時代までに、”鼻”・”みずから”・”~から”・”~により”の意があった。戦国の竹簡では、「自然」の「自」に用いられるようになった。詳細は論語語釈「自」を参照。
既(キ)


(甲骨文)
論語の本章では”すでに”。初出は甲骨文。字形は「皀」”たかつきに盛っためし”+「旡」”口を開けた人”で、腹いっぱい食べ終えたさま。「旣」は異体字だが、文字史上はこちらを正字とするのに理がある。原義は”…し終えた”・”すでに”。甲骨文では原義に、”やめる”の意に、祭祀名に用いた。金文では原義に、”…し尽くす”、誤って「即」の意に用いた。詳細は論語語釈「既」を参照。
灌(カン)


(秦系戦国文字)
論語の本章では”そそぐ”。「潅」は異体字。初出は秦系戦国文字。字形は「氵」+「雚」”フクロウ”で、「雚」は意味には関係しない音符。同音の「盥」(上/去)はたらいに水を注ぎ、手を洗う様で、初出は甲骨文。論語時代の置換候補となる。詳細は論語語釈「潅」を参照。
禘祭の後半に、地面に酒を撒いて神霊を迎える儀式という。既存の論語本では吉川本によると、鬱鬯というチューリップでにおいを付けた酒を、藁に注ぎかけて先祖の魂を招くという。だが元ネタは例によって儒者の個人的感想で、根拠が無い。
古注『論語集解義疏』
註孔安國曰禘祫之禮為序昭穆也故毀廟之主及羣廟之主皆合食於太祖灌者酌鬱鬯灌於太祖以降神也既灌之後别尊卑序昭穆而魯為逆祀躋僖公亂昭穆故不欲觀之矣

注釈。孔安国「禘や祫の祭は、祖先の霊位に順序を付けるために行う。だから個別の祖先廟を一旦壊して、開祖のまします、おまとめ安置堂に位牌を並べ直し、一括してお供えを差し上げるのだ。祭の際にはチューリップ酒を開祖以来の位牌群に振りかける。すると全自動で霊位の順位が決まるのだ。ところが魯では禘の祭を勝手にやって、とうとう僖公から出た分家が、魯公よりも威張り返る結果になった。だから見たくないと言ったのだ。」
孔安国は実在そのものが怪しい人物で、孔子の子孫という事になっている。だからといって数百年前の史実を知っているとは限らない。「全自動」は訳者のシャレだが、酒を掛けるだけで順位が定まるなら、魯で順位が滅茶苦茶になる理由が無いではないか。
要するに論語時代の魯国で家老が威張っているのを、ケシカランと怒る振りをしているのだ。
新注『論語集注』
灌者,方祭之始,用鬱鬯之酒灌地,以降神也。魯之君臣,當此之時,誠意未散,猶有可觀,自此以後,則浸以懈怠而無足觀矣。蓋魯祭非禮,孔子本不欲觀,至此而失禮之中又失禮焉,故發此歎也。

灌ぐと書いてあるのは、祭を始めるときに、チューリップ酒を地面に撒き散らし、それで霊位を呼び降ろす。魯国の君主と臣下はこの時ばかりは、真面目な顔をしていたが、撒き終えてしまうとだらけて見るに堪えないありさまになった。多分魯国の祭は、礼法に背いていたのだろう。だからもともと、孔子は見たくなかったのだ。その上さらにこのだらけようでは、ブツブツと文句を言わざるを得なかったのだ。
もちろん訳者だって、論語時代の祭で何が撒かれていたかは知らない。ただし偽作でありながら、こういう記述を元に想像は出来る。
夏后氏尚明水,殷尚醴,周尚酒。

夏王朝は貧乏くさい真水を尊び、殷王朝は甘ったるい濁り酒を尊んだ。だが周王朝になってやっと、濁り酒を布袋に入れてチュウと漉し取った、清んだ酒を尊ぶ。(『小載礼記』明堂位)
貧乏くさい真水を撒かれて、神様が降りてくるとは論語時代の人間は考えなかっただろう。アサガオに水やりするたび先祖の亡霊が化けて出ては、はなはだ迷惑だ。従って酒に違いないと想像するのである。
而(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”そして”。初出は甲骨文。原義は”あごひげ”とされるが用例が確認できない。甲骨文から”~と”を意味し、金文になると、二人称や”そして”の意に用いた。英語のandに当たるが、「A而B」は、AとBが分かちがたく一体となっている事を意味し、単なる時間の前後や類似を意味しない。詳細は論語語釈「而」を参照。
往(オウ)


(甲骨文)
論語の本章では”…のあと”。初出は甲骨文。ただし字形は「㞷」。現行字体の初出は春秋末期の金文。字形は「止」”ゆく”+「王」で、原義は”ゆく”とされる。おそらく上古音で「往」「王」が同音のため、区別のために「止」を付けたとみられる。甲骨文の字形にはけものへんを伴う「狂」の字形があり、「狂」は近音。「狂」は甲骨文では”近づく”の意で用いられた。詳細は論語語釈「往」を参照。
者(シャ)


(金文)
論語の本章では、助詞のような働きをし”…は”。上の文句を「それは」と、特に提示することば。旧字体は〔耂〕と〔日〕の間に〔丶〕一画を伴う。新字体は「者」。ただし唐石経・清家本ともに新字体と同じく「者」と記す。現存最古の論語本である定州竹簡論語も「者」と釈文(これこれの字であると断定すること)している。初出は殷代末期の金文。金文の字形は「木」”植物”+「水」+「口」で、”この植物に水をやれ”と言うことだろうか。原義は不明。初出では称号に用いている。春秋時代までに「諸」と同様”さまざまな”、”…は”の意に用いた。漢文では人に限らず事物にも用いる。詳細は論語語釈「者」を参照。
吾(ゴ)


(甲骨文)
論語の本章では”わたし”。初出は甲骨文。字形は「五」+「口」で、原義は『学研漢和大字典』によると「語の原字」というがはっきりしない。一人称代名詞に使うのは音を借りた仮借だとされる。詳細は論語語釈「吾」を参照。
古くは中国語にも格変化があり、一人称では「吾」(藤堂上古音ŋag)を主格と所有格に用い、「我」(同ŋar)を所有格と目的格に用いた。しかし論語で「我」と「吾」が区別されなくなっているのは、後世の創作が多数含まれているため。論語語釈「我」も参照。
不(フウ)


(甲骨文)
漢文で最も多用される否定辞。初出は甲骨文。「フ」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)、「ブ」は慣用音。原義は花のがく。否定辞に用いるのは音を借りた派生義だが、甲骨文から否定辞”…ない”の意に用いた。詳細は論語語釈「不」を参照。
欲(ヨク)


(楚系戦国文字)
論語の本章では”~したい”。初出は楚系戦国文字。新字体は「欲」。同音は存在しない。字形は「谷」+「欠」”口を膨らませた人”。部品で近音の「谷」に”求める”の語義があり、全体で原義は”欲望する”。論語時代の置換候補は部品の「谷」。詳細は論語語釈「欲」を参照。
觀(カン)


(甲骨文)
論語の本章では”見る”。新字体は「観」。『大漢和辞典』の第一義は”みる”、以下”しめす・あらはす…”と続く。初出は甲骨文だが、部品の「雚」の字形。字形はフクロウの象形で、つの形はフクロウの目尻から伸びた羽根、「口」はフクロウの目。原義はフクロウの大きな目のように、”じっと見る”こと。詳細は論語語釈「観」を参照。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章では”これ”。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”~の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。
矣(イ)


(金文)
論語の本章では、”(きっと)~である”。初出は殷代末期の金文。字形は「𠙵」”人の頭”+「大」”人の歩く姿”。背を向けて立ち去ってゆく人の姿。原義はおそらく”…し終えた”。ここから完了・断定を意味しうる。詳細は論語語釈「矣」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章は、孔子の意図を誰も読み解けなかったからか、先秦両漢の誰一人引用していない。「死んだらそれまで。幽霊も神もおらん」とする孔子の徹底した合理は、現代人でもなお多くの人間には理解しがたい。古代中国人ならなおさら無理もないことだろう。
「者」の用法に疑問があるものの、無しでも文意が変わらない。また上掲『礼記』礼運編の孔子のうそ泣きは、論語の本章を理解できなかった前漢の儒者が、禘祭りを魯国が行うことそのものが間違っているというでっち上げをこしらえ、本章に理屈を付けたものだろう。
解説
論語の本章の解釈は、これまでみな「難解である」と匙を投げた。だが丁寧に本章から始まる章を読んでいけば、孔子が「見たくない」と言った理由を推定できる。結論として孔子は、先祖の霊が居る振りをする偽善が、バカバカしかったのだ。
「子は怪力乱神を語らず」と論語述而篇に言う。「鬼神を敬して遠ざく」と論語雍也篇に言う。孔子の回復を神頼みする子路を、論語述而篇ではたしなめた。「神に仕える法など知らん」と論語先進篇では突き放した。孔子は、その目に神が見える人ではなかったのだ。
これは古代人として、極めて珍しいことである。だがそれゆえに、孔子の口から出た教説は、極めて明るい合理性を持っていた。それを淵源とする儒教が世間をたぶらかす商材に成り下がったのは孟子以降であり、それが漢帝国によって国教化され、宋学によって黒魔術化した。
詳細は論語解説「後漢というふざけた帝国」、また論語雍也篇3余話「宋儒のオカルトと高慢ちき」参照。
だから現伝の儒教から孔子を観察しても分からない。上記に加え次章では、「禘=祖先祭の所作に意味など無い」と言い切り、次々章では「降りても来ない神霊にお供えなどしても無意味だ」と言い切った。本章もまた、酒を撒いた所で霊などおらん、と思っていたのである。
禘の式次第は、上掲古注で孔安国が記すまで、誰にも分からなくなっていた。だからその詳細を後漢の光武帝が問うたわけだが、前漢の孔安国による注が残っているのに、後漢の光武帝が知らないというのは論理矛盾で、孔安国の実在が疑われる根拠の一つがここにもある。
だから「灌ぎ而自り往者」で注がれる何かは、実は分からない。古注が成立したのは後漢末から南北朝にかけてだから、後漢儒が孔安国を創作して語らせたと見るべきだろう。だが祭そのものは、『春秋左氏伝』などにあるから論語の時代から存在したと見ていい。
余話
政治と色
ところで慶應義塾の塾旗は、上下に紺ー赤ー紺となっており、当時から一般的だった赤白の幔幕は、仕舞っておくと白色が赤茶けてきて汚らしく、新調することが多かった。それを見た福沢翁が、「もったいないから紺赤にしなさい」といってあの意匠になったと聞く。
対して中華世界では色も政治の一環で、それぞれの組み合わせに吉ー不吉の判断があった。魯の25代昭公(位BC541-BC510)と言えば、孔子に一人息子鯉が生まれた時、お乳の出が良くなる妙薬であるコイを贈って祝ってやったという殿様だが、9代武公の禘祭を行おうとした。
十五年,春,將禘于武公,戒百官,梓慎曰,禘之日,其有咎乎,吾見赤墨之祲,非祭祥也,喪氛也,其在蒞事乎,二月,癸酉,禘,叔弓蒞事,籥入而卒,去樂卒事,禮也。
昭公十五年(BC527)、春、武公の禘祭を行おうとして、百官に”潔斎せよ”と命じた。梓慎が言った。「禘の日に、天のお咎めがあるだろう。私には赤黒の不吉な気が漂っているのが見える。祭は目出度く終わらないだろう。この気は災いの前兆だろう。出席したものかどうか。」二月、癸酉の日、禘祭を行った。陸相を務めていた叔弓が司会しようとしたところ、笛役が亡くなったばかりであり、祭の締めくくりに音楽を演奏しなかった。これは礼法にかなっている。(『春秋左氏伝』昭公十五年2)
「赤墨之祲」と原文にあるのを、とりあえず”赤黒の不吉な気”と訳したが、赤-黒のだんだら模様のことか、それとも暗い赤色のことか、その実は分からない。血の色は赤黒いものだが、周時代人は前王朝を「殷」と呼んだ。”人の生きギモを取り出す野蛮人”の意である。

「殷」保卣・西周早期
そして同時に、”赤黒い”も意味した。「殷賑を極める」というように、”さかん”・”さかえる”の意もあるが、この多語義性はいちいち出土物をほじくっていかないと語義の系統も付けられない。だが想像するに春秋時代では、梓慎の言う通り不吉な色だったろう。
殷がむやみに生け贄を供え物にする野蛮性を持っていたこと、周になると生け贄そのものが野蛮視されるようになったことはすでに書いた。占いの方法にキモ占いがあり、生きた動物や人間のキモを取り出して、その様子で吉凶を占う。その必要から殷は「人狩り」をやった。
だから周辺民族から嫌われて、袋叩きに遭って滅ぼされたのだが、そうでなくとも人は血の色を想像するだけで顔色が変わる人も居る。その感覚は時に偽善に陥る危険もあるが、もし無差別に人命を重んじて顔色が変わるなら、現代人として当たり前の感覚だと思う。
だが前世紀後半まではそうでも無かった。世界の半分は共産圏だったが、その多くの国が国旗に赤色を用い、革命の血の色だと言われていた。現中国国旗も赤い地色で、国歌は「把我们的血肉 筑成我们新的长城」”我らの血と肉で新しい長城を築こう”と歌う。
独裁政権がこの世に在る限り、色も又、政治の一部であり得るのだろう。





コメント