
婁(ル/ロウ・11画)
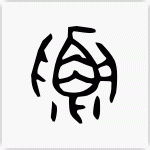
伯要簋・西周早期
初出は西周早期の金文。漢音「ル」で”ひく”、「ロウ」で星座の一つ。字形は蚕の繭を左右と下の「廾」”て”で手繰っているさまで、原義は”手繰る”。西周中期から下の「廾」は、「女」に書き換えられた。カールグレン上古音は「ル」gli̯u(平)または「ル」glu(平)。前者の同音は「婁」を部品とする漢字群。後者の同音は無い。
「漢語多功能字庫」では金文で人名に用いたとある以外、見るべき情報がない。
学研漢和大字典
会意。「母+中+女」で、母も女も女性であって、女性を捕らえて、じゅずつなぎにしてひっぱるさまであろう。縷(ロウ)(ずるずると連なる紐(ヒモ))・樓(ロウ)(=楼。幾重にも上へと連なった家)・瘻(ロウ)(連なるおでき)などの原字。
語義
- 「ル」{動詞}ひく。ずるずるとひっぱる。ひき寄せる。
- 「ロウ」{名詞}二十八宿の一つ。規準星は今のおひつじ座にふくまれる。たたみ。
字通
[象形]婦人の髪を高く巻きあげた形。高く重ねる、すかすなどの意がある。〔説文〕十二下に「空なり。毋(くわん)に從ひ、中女に從ふ。婁空の意なり」(段注本)という。婁空とは髪を軽く巻き重ねて、透かしのある意であろう。目の明らかなことを離婁といい、まどの高く明るいことを麗廔(れいろう)という。すべて重層のものをいい、建物には樓(楼)、裾(すそ)の長い衣には「摟(ひ)く」という。〔詩、唐風、山有枢〕「子に衣裳有るも 曳(ひ)かず婁(ひ)かず」とあるのは摟の意。糸には縷といい、婁は女の髪、これをうって乱すを「數數(さくさく)」という。〔繫伝〕に「一に曰く、婁務は愚なり」とあって畳韻の語であるが、用例をみない語である。
屢(ル・14画)
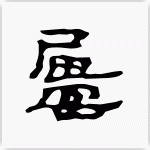
「武威簡」前漢隷書
初出:初出は前漢の隷書。
字形は「尸」”ひとのさま”+「婁」”蚕の繭を手繰る女”。原義は不明。
音:カールグレン上古音はgli̯u(去)。同音は婁”むなしい・あらい”を部品とする漢字群。
用例:戦国時代の「郭店楚簡」成之5に「是古(故)畏(威)備(服)型(刑)罰之婁(屢)行也」とあり、「婁」が「屢」と釈文されている。”しばしば”と解せる。
論語時代の置換候補:結論として存在しない。
春秋末期までに「婁」には”しばしば”の用例が無い。
『大漢和辞典』で「しばしば」と読む字は下掲で全てだが、音を共有する文字は無い。部品の「尸」からは”しばしば”の語義は導けない。
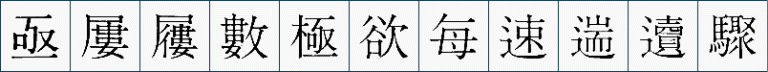
備考:「漢語多功能字庫」には、見るべき情報は無い。
学研漢和大字典
会意兼形声。婁(ル)は「母+中+女」の会意文字で、女性をとらえてじゅずつなぎにすることを示す。屢は「尸(ひと)+(音符)婁」で、連なっておこること。
語義
- {副詞}しばしば。引き続いておこる意をあらわすことば。しょっちゅう。たびたび。《類義語》数。「鮭憎於人=鮭人に憎まる」〔論語・公冶長〕。「員瓢屢空=員瓢屢空し」〔陶潜・五柳先生伝〕
字通
(条目無し)
中日大字典
しばしば.たびたび.何度も.
〔屡屡〕同前.
〔屡创chuàng新记录〕幾度も新記録を出す.
〔屡有发明〕たびたび発明をした.
誄(ルイ・13画)
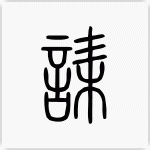

『説文解字』・後漢/「耒」甲骨文合集8212.1
初出:初出は後漢の説文解字。
字形:「言」+「耒」。「耒」は原字で、「讄」(𧮢)li̯wər(上)”いのる”(初出は説文解字)と同音同訓。「耒」”いのり”の「言」”ことば”を示す。
音:カールグレン上古音はli̯wər(上)。部品の「耒」も同音同調。
用例:論語述而篇34に「誄曰」”祈祷文に曰く”とあるほか、『荀子』礼論23に「其銘誄繫世」とあり、”祈祷文を記して代々伝える”と読める。
論語時代の置換候補:部品の「耒」。「甲骨文合集」8212に「鼎(貞):自□…人于河。」とあり、は「耒耒」と表記され、”いのる”と解せる。大勢で祈る様か、両手で祈る様だろう。
「耒」の字形は「又」”手”+「月」”からだ”で、手を上げて祈る様。「漢語多功能字庫」が農具の”すき”と解するのは、戦国以降の金文で「㠯」と混同されたのに引きずられており、間違いではないが妥当でもない。
また「甲骨文合集」7.1に「王才(在)茲(耒耒)成(狩)」とあり、城を”築く”意であるらしい。この例では”すき”と解すべきだが、別の字だと思った方がいい。「耒」はそのほか甲骨文・金文共に、固有名詞の部品として多く見られる。
備考:『大漢和辞典』で同音同訓は、上記「讄」(𧮢)のみで、初出は後漢の『説文解字』。「しのびごと」と訓読した場合、”死者の冥福を祈る”の意になる。論語述而篇の例では生きた孔子に対して用いており、「いのり」と訓むべきで、”生者の徳行を神霊に告げて祈る”の意。
学研漢和大字典
会意。耒(ライ)は、田畑にすじめをつけるすきを描いた象形文字。誄は「言+耒(すじめをつける)」で、生きている時の行跡を順序よくならべて整理したことばをあらわす。
語義
- {名詞}死者の生前の功績・徳行を整理してほめたたえることば・文章。
- (ルイス){動詞}死者をたたえることばをつくって贈る。「賤不誄貴、幼不誄長=賤は貴を誄せず、幼は長を誄せず」〔礼記・曾子問
字通
[形声]声符は耒(るい)。〔説文〕三上に「諡(おくりな)するなり」とあり、生前の事功を述べて哀悼し、諡することをいう。〔論語、述而〕に「誄に曰く、爾(なんぢ)を上下(しやうか)の神祇に禱る」とあり、〔釋文〕に、〔説文〕は字を讄に作り、纍(るい)声に従う字であるという。その辞はわが国の祝詞のように、くりかえしや層累法の多い荘重な文体であったのであろう。
縲(ルイ・17画)
初出:初出は後漢の『説文解字』にも見えない。唐開成石経『論語』には見られる。
字形:「糸」+「累」”つなぐ”。ものをつなぎ止める綱のこと。
音:カールグレン上古音はli̯wər(平)。
用例:論語に次ぐ文献上の再出は、『国語』斉語に「諸侯甲不解縲」とあり、晋語に「縲虎」(人名)とある。また『六韜』に「環利小徽縲,長二丈以上,萬二千枚。」とある。
論語時代の置換候補:『大漢和辞典』で同音同訓は存在しない。部品の「累」li̯wăr(上/去)に”つなぐ”意があるが、初出は漢代の隷書。
備考:「漢語多功能字庫」には見るべき情報がない。
学研漢和大字典
会意兼形声。「糸+(音符)累(ルイ)(重なりつらなる)」。
語義
- 「縲絏(ルイセツ)」とは、罪人をしばる長いなわ。また、転じて牢屋(ロウヤ)。《同義語》⇒縲紲。「雖在縲絏之中、非其罪也=縲絏の中に在りと雖も、其の罪に非ざるなり」〔論語・公冶長〕
字通
[形声]声符は累(るい)。累に繋留する意がある。縲紲(るいせつ)は罪人を捕える黒縄。獄につながれることをいう。
類/類(ルイ・18画)

(定州漢墓竹簡)
初出は秦系戦国文字。論語の時代に存在しない。カールグレン上古音はli̯wəd(去)。同音は存在しない。定州竹簡論語では「![]() 」と記すが、この字は『大漢和辞典』にも見られず、「類」の異体字として扱うしか無い。
」と記すが、この字は『大漢和辞典』にも見られず、「類」の異体字として扱うしか無い。
学研漢和大字典
会意。「米(たくさんの植物の代表)+犬(種類の多い動物の代表)+頁(あたま)」で、多くの物の頭かずをそろえて、区わけすることをあらわす。多くの物を集めて系列をつける意を含む。累(かさねてつらねる)・塁(ルイ)(かさねつらねた防壁)などと同系。律(リツ)・率(リツ)は、その語尾がtに転じたことば。類義語に似・族。旧字「類」は人名漢字として使える。▽草書体をひらがな「る」として使うこともある。
語義
- {名詞}たぐい(たぐひ)。なかま。よくにて同じグループに属するもの。またその区わけ。「種類」「類別」「方以類聚=方は類を以て聚る」〔易経・壓(繋)辞上〕
- (ルイス){動詞}にる。「類似」「非君也、不類=君に非ざるなり、類せず」〔春秋左氏伝・荘八〕
- (ルイス){動詞}にたものを集めてグループにわける。「類族=族を類す」。
- (ルイス){名詞・動詞}常例の祭りににせた臨時の祭礼。また、臨時の祭礼を行う。「類祭」「類乎上帝=上帝に類す」〔礼記・王制〕
- {副詞}おおよそ(おほよそ)。おおむね(おほむね)。全体として。だいたい。《類義語》概・率。「類常如翁帰言=類ね常に翁帰の言のごとし」〔漢書・尹翁帰〕
- 「非類(ヒルイ)」とは、同族でない者。血縁のない他人。
字通
[会意]旧字は類に作り、米+犬+頁(けつ)。米と犬とは神に供えるもの。頁は儀礼のときの儀容で、類とは天を祭る祭名。その字はのち禷(へんはしめすへん。ネで代用)に作る。〔説文〕十上に「種類相ひ似たり。唯だ犬を甚だしと爲す。犬に從ひ、頪(らい)聲」とするが、犬は犬牲。天を祭るのには、犬を焼いて、その臭いを昇らせた。〔書、舜典〕「肆(ここ)に上帝に類す」、〔詩、大雅、皇矣〕「是(ここ)に類し是に禡(ば)す」など、みな天を祭ることをいう。〔皇矣〕にまた「克(よ)く明にして克く類」のように、類善の意に用いる。天意にかなうということであるらしく、〔楚辞、九章、懐沙〕「吾(われ)將(まさ)に以て類(のり)と爲さんとす」のように、典則・規範の意ともなる。倫と声義の関係があろう。〔段注〕に頪と類とを古今の字とし、「種の繁多なること、米の如きなり」とするが、当時の米がそのように多種であったとは考えがたい。類の原義は、のち形声字の禷(るい)によって示されている。



コメント