原文
齊有彗星,齊侯使禳之,晏子曰,無益也,祇取誣焉,天道不諂不貳,其命若之何,禳之,且天之有彗也,以除穢也,君無穢德,又何禳焉,若德之穢,禳之何損,詩曰,惟此文王,小心翼翼,昭事上帝,聿懷多福。厥德不回。以受方國,君無違德,方國將至,何患於彗,詩曰,我無所監,夏后及商,用亂之故,民卒流亡,若德回亂,民將流亡,祝史之為,無能補也,公說,乃止。
齊侯與晏子坐于路寢,公歎曰,美哉室,其誰有此乎,晏子曰,敢問何謂也,公曰,吾以為在德,對曰,如君之言,其陳氏乎,陳氏雖無大德,而有施於民,豆區釜鍾之數,其取之公也薄,其施之民也厚,公厚斂焉,陳氏厚施焉,民歸之矣,詩曰,雖無德與女,式歌且舞,陳氏之施,民歌舞之矣,後世若少惰陳氏而不亡,則國其國也已,公曰,善哉,是可若何,對曰,唯禮可以已之,在禮家施不及國,民不遷晨,不移工,賈不變士,不濫官,不滔大夫,不收公利,公曰,善哉,我不能矣,吾今而後知禮之可以為國也,對曰,禮之可以為國也久矣,與天地並,君令臣共,父慈子孝,兄愛弟敬,夫和妻柔,姑慈婦聽,禮也,君令而不違,臣共而不貳,父慈而教,子孝而箴,兄愛而友,弟敬而順,夫和而義,妻柔而正,姑慈而從,婦聽而婉,禮之善物也,公曰善哉,寡人今而後聞此,禮之上也,對曰,先王所稟於天地,以為其民也,是以先王上之。
書き下し
齊に彗星有り、齊侯之を禳わ使む。晏子曰く、益無き也,祇だ誣(し)うるを取り焉。天道諂わ不貳(そむ)か不れば、其れ之を命じて之を禳うは若何。且つ天之彗有る也、以て穢れを除く也。君に德を穢す無くんば、又た何ぞ禳い焉ん。若し德之穢れあらば、之を禳うも何ぞ損さん。詩に曰く、惟れ此の文王、小心翼翼、昭かに上帝に事えて、聿(ここ)に福多からんを懷う。厥の德回(や)ま不。以て方國を受く、と。君德に違う無くんば、方國將に至らん。何ぞ彗於患えん。詩に曰く、我が監る所無くんば、夏后の商に及ぶあらん。亂用(あ)る之故に、民卒に流れ亡びぬ、と。若し德回みて亂るらば、民將に流れ亡ばん。祝史之為すや、補う能無き也と。公說び、乃ち止む。
齊侯晏子與路寢于坐せり。公歎じて曰く、美しき哉室、其れ誰か此を有たん乎と。晏子曰く、敢えて問う、何の謂いぞ也と。公曰く、吾れ以為えらく、德の在らんかと。對えて曰く、如しや君之言、其れ陳氏乎。陳氏大いなる德無しと雖も、し而民於施す有り。豆區釜鍾之數、其れ之を公に取る也薄く、其れ之を民に施す也厚し。公厚く斂り焉、陳氏厚く施し焉れば、民之に歸す矣。詩に曰く、女に與うる德無しと雖も、歌を式(もち)いて且つ舞わんと。陳氏之施すや、民之を歌い舞い矣。後世若し少(や)や惰(おとろ)え、陳氏し而亡ば不らば、則ち國其の國也る已と。公曰く、善き哉、是れ可なるは若何と。對えて曰く、唯だ禮のみ以て之を已む可し。禮に在らば家(わたくし)に施すも國に及ば不、民は晨(とき)を遷さ不、工は移ら不、賈は變ら不、士は官を濫りにせ不、大夫滔(はびこ)ら不、公の利を收め不らんと。公曰く、善き哉、我れ能わ不る矣。吾今にし而後は禮之以て國を為む可きを知る也と。對えて曰く、禮之以て國を為む可き也久しき矣。天と與にし地並べり。君令(おし)うらば臣共(うやうや)しく、父は慈しみ子は孝たり、兄は愛し弟は敬い、夫は和み妻は柔に、姑慈しみ婦聽くが、禮也。君令え而違わ不らば、臣共しくし而貳びせ不、父慈しみ而教え、子孝たり而箴(つつし)み、兄愛し而友たり、弟敬い而順い、夫和み而義しく、妻柔にし而正しく、姑慈しみ而從い、婦聽きて而婉(おだや)かなり。禮之善き物也と。公曰く、善き哉。寡人今にし而後此を聞くは、禮之上なるもの也と。對えて曰く、先王天地於り稟けし所、以て其の民を為めたる也。是れ以て、先王之を上とす。
現代日本語訳
昭公二十六年(BC516)
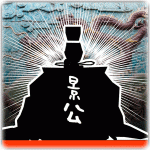

斉国に彗星が現れた。斉の景公は不吉に思って、みこにお祓いを命じた。晏嬰が言った。
「無駄です。単にみこのデタラメを真に受けることにしかなりません。天体の運行には、ご機嫌取りが無くウソもありません。それをお祓いなんかでどうにかしようというのですか。それに天にほうき星が現れるのは、ゴミ掃除のためです。殿が無茶な命令を出していないなら、どうして掃除なんかしなけりゃいけないんですか。もし無茶な命令を出しているなら、お祓いなんかで彗星が落ちるわけがありません。詩にも言うではありませんか。
この周の文王は、何事にも慎重慎重。
素直に天の神に仕えて、それでやっと僅かなお恵みを願う。
そうした地道な日常が実って、諸国が慕い寄ってきた。(大雅・大明)
殿の命令にウソが無ければ、諸国が慕い寄ってきます。なんで彗星なんかに怯える必要がありますか。別の詩にも言います。
私がもし忘れでもしたら。あの夏の滅亡を。
政治が滅茶苦茶だったから、民はすっかり逃げ散った。(逸詩)
もし殿がやる気を無くしたせいで政治が混乱しているなら、ほどなく我が斉国の民も逃げ散るはずです。みこ如きがチンチンドンドンを派手にやらかした所で、何の助けにもなりませんぞ。」
景公「その通りじゃな。」お祓いは取りやめになった。
他日、景公と晏嬰が国公宮の正殿で対座していた。景公がため息混じりに言った。
「あーあ。立派な宮殿じゃが、いったい誰の手に渡ってしまうのじゃろうか。」
晏嬰「お気を確かに。何を仰りたいのですか。」
景公「多分徳(=物理的力)のある奴が持って行ってしまうんじゃろうなー。」
晏嬰「はぐらかさないで下さい。陳氏(=田氏)のことでしょう。陳氏にものすごい徳があるわけではありませんが、着々と民に恩を売っています。我が斉の枡目は、豆(4升)・区(4豆)・釜(4区)・鐘(10釜)の順と決まっています。ところが行政を牛耳る陳氏は、納税の際には底上げした枡で取り、配給の際にはふちを足した枡で配っています。つまり税収でバラマキをやっているのですが*、足りないからと言って殿は、改めて重く取り立ているではありませんか。そんな恨みの中で陳氏が厚くばらまけば、民の信望が陳氏に集まるのは当たり前です。詩に言うではありませんか。
何もお返しできませんが、
せめて歌を歌って舞いましょう。(小雅・車舝)
陳氏がバラマキをするたびに、民は歌い舞い踊っておりますぞ。殿のご子孫が政治を少しでも怠り、その時陳氏がまだ滅んでなければ、斉国は陳氏の国になるでしょうな。」
景公「言う通りじゃなあ。じゃが何とかワシの子孫が生き残る道は無いか。」
晏嬰「ただ礼の定めだけが、この動きを押しとどめられます。礼の定めが生きている間は、勝手に施しをしようと、国とは関係がありません。農民は夜明けから耕作にいそしみ、職人は手職を変えようとはせず、商人も商売替えしようとせず。役人は無茶な行政をせず、家老が殿より威張り返ることも無く、おおやけの税収を勝手に使うことは出来ません。」
景公「その通りじゃな。じゃが、ワシは今まで礼をないがしろにしてきた。今になってやっと、礼で国が治まると知ったぞ。」
晏嬰「礼で国が治まるのは、天地の始めからの道理です。俸禄を払う君主が命じ、貰う臣下が従う。父が可愛がり、子が孝行する。兄が愛し、弟が敬う。夫が気を遣い、妻が従う。姑が可愛がり、嫁が従う。お互い様の当たり前の関係が、礼なのです。だから殿が公約を反故にしなければ、役人は従いウソをつきません。見習って世の父親も子を可愛がって仕事を教え、子は孝行して行いに気を付けます。兄が弟を愛して助けになってやれば、弟は敬って従います。夫が妻に気を遣い言っている事に無理が無ければ、妻は穏やかになって言動を正しくします。姑が嫁を可愛がって言うことを聞けば、嫁も姑の願いを聞きいれて穏やかになります。これが礼の持つ、よき効果です。」
景公「その通りじゃな。今やっと、ワシは礼に使い道があるのを聞いた。」
晏嬰「これはいにしえの聖王が天から受けた教えです。それに従って民を治めたのです。だから礼を、最も尊いものとして従ったのです。」
訳注
※税収でバラマキをやっているのですが:
左伝・昭公三年では、公定レートが豆・区・釜を4倍ごとに繰り上げ、10釜で1鐘としたのに対し、陳氏は3倍ごとに繰り上げた枡で配り、公定レートで収税したとある。つまり小さい枡で配り、大きい枡で取ったわけで、恩を売るのではなく仇を売っている。
二十数年の内に陳氏が政策を変えたか、どちらかが間違いだということになる。


コメント