論語:原文・白文・書き下し
原文・白文
宰我問、「三年之喪、期*已久矣。君子三年不爲禮、禮必壞。三年不爲樂、樂必崩。舊穀既沒、新穀既升、鑽燧*改火、期可已矣。」子曰、「食夫稻*、衣夫錦*、於女安乎。」曰、「安*。」「女安、則爲之。夫君子之居喪、食旨不甘、聞樂不樂、居處不安、故不爲也。今女安、則爲之。」宰我出。子曰、「予之不仁也。子生三年、然後免於父母之懷。夫三年之喪、天下之通喪也。予也有三年之愛於其父母乎*。」
校訂
武内本
清家本により、稻の下、錦の下に也の字をそれぞれ補う。安の下に之の字を補う。釋文云、期一本其に作る。蓋し期は其の借字、已は甚と同じ。燧は火を取る木、古は四時に従って異なる木より火を取る、漢石経章末乎の字なし。
後漢熹平石経
…三年之…有三年愛於父母
- 「年」字:〔十三〕
- 「愛」字:〔厂心四夂〕
定州竹簡論語
宰我問:「三年之喪,其a已久[乎b。君子三年不為禮,禮必壞];539三年不為樂,樂[必項c。舊穀![]() d]沒,新穀
d]沒,新穀![]() d升,銹e[□改火]540……可已矣。」子曰:「食夫稻也f,衣夫錦也f,於女安乎?」曰:「安。」「女g541……安,故弗為[也。今女安,則]542……[也]!子h三年,然后i免於父[母之]懷。夫三年之喪,天下之543通喪也。予也又j三年之愛於其父母。」544
d升,銹e[□改火]540……可已矣。」子曰:「食夫稻也f,衣夫錦也f,於女安乎?」曰:「安。」「女g541……安,故弗為[也。今女安,則]542……[也]!子h三年,然后i免於父[母之]懷。夫三年之喪,天下之543通喪也。予也又j三年之愛於其父母。」544
- 其、今本作”期”、『釋文』云、”一本作朞”。
- 乎、今本作”矣”。
- 項、今本作”崩”。作項誤。
 、今本作”旣”。
、今本作”旣”。- 銹、今本作”鑽”字。
- 也、阮本無、皇本、高麗本有。
- 皇本”女”字上有”曰”字。
- 今本”子”。字下有”生”字。
- 后、今本作”後”。
- 又、今本作”有”。
→宰我問、「三年之喪、其已久乎。君子三年不爲禮、禮必壞。三年不爲樂、樂必崩。舊穀![]() 沒、新穀
沒、新穀![]() 升、銹燧改火、期可已矣。」子曰、「食夫稻也、衣夫錦也、於女安乎。」曰、「安。」「女安、則爲之。夫君子之居喪、食旨不甘、聞樂不樂、居處不安、故弗爲也。今女安、則爲之。」宰我出。子曰、「予之不仁也。子生三年、然后免於父母之懷。夫三年之喪、天下之通喪也。予也又三年之愛於其父母。」
升、銹燧改火、期可已矣。」子曰、「食夫稻也、衣夫錦也、於女安乎。」曰、「安。」「女安、則爲之。夫君子之居喪、食旨不甘、聞樂不樂、居處不安、故弗爲也。今女安、則爲之。」宰我出。子曰、「予之不仁也。子生三年、然后免於父母之懷。夫三年之喪、天下之通喪也。予也又三年之愛於其父母。」
復元白文(論語時代での表記)



























 崩
崩 






 銹燧
銹燧












 錦
錦




















































































※久→舊・壞→褱・没→勿・予→余・仁→(甲骨文)・愛→哀。論語の本章は赤字が論語の時代に存在しない。「之」「則」の用法に疑問がある。本章は前漢帝国の儒者による創作である。
書き下し
宰我問ふ、三年之喪は、其れ已だ久しからん乎。君子三年禮を爲さずんば、禮必ず壞れむ、三年樂を爲さずんば、樂必ず崩れむ。舊き穀![]() に沒き、新しき穀
に沒き、新しき穀![]() に升り、燧銹びしめて火を改む。期にして已む可から矣。子曰く、夫の稻を食ふ也、夫の錦を衣る也、女於安き乎。曰く、安し。女安からば則ち之を爲せ。夫れ君子の喪に居るは、旨きを食うて甘からず、樂を聞いて樂しからず、處に居りて安からず、故に爲さ弗る也。今女安からば、則ち之を爲せ。宰我出づ。子曰く、予之不仁なる也。子生れて三年、然る后父母之懷於免る。夫れ三年之喪は、天下之通なる喪也。予也三年之愛其の父母に於りしか。
に升り、燧銹びしめて火を改む。期にして已む可から矣。子曰く、夫の稻を食ふ也、夫の錦を衣る也、女於安き乎。曰く、安し。女安からば則ち之を爲せ。夫れ君子の喪に居るは、旨きを食うて甘からず、樂を聞いて樂しからず、處に居りて安からず、故に爲さ弗る也。今女安からば、則ち之を爲せ。宰我出づ。子曰く、予之不仁なる也。子生れて三年、然る后父母之懷於免る。夫れ三年之喪は、天下之通なる喪也。予也三年之愛其の父母に於りしか。
宰我問、「三年之喪、其已久乎。君子三年不爲禮、禮必壞。三年不爲樂、樂必崩。舊穀![]() 沒、新穀
沒、新穀![]() 升、銹燧改火、期可已矣。」子曰、「食夫稻也、衣夫錦也、於女安乎。」曰、「安。」「女安、則爲之。夫君子之居喪、食旨不甘、聞樂不樂、居處不安、故弗爲也。今女安、則爲之。」宰我出。子曰、「予之不仁也。子生三年、然后免於父母之懷。夫三年之喪、天下之通喪也。予也又三年之愛於其父母。」
升、銹燧改火、期可已矣。」子曰、「食夫稻也、衣夫錦也、於女安乎。」曰、「安。」「女安、則爲之。夫君子之居喪、食旨不甘、聞樂不樂、居處不安、故弗爲也。今女安、則爲之。」宰我出。子曰、「予之不仁也。子生三年、然后免於父母之懷。夫三年之喪、天下之通喪也。予也又三年之愛於其父母。」
論語:現代日本語訳
逐語訳


宰我が質問した。「三年の喪は長すぎます。君子が三年礼を行わなければ、礼を必ず忘れます。三年音楽を演じなければ、音楽を必ず忘れます。前年の穀物が尽き、今年の穀物が実り、火打ち金が錆びた頃、火を切り直して改めます。一年で止めてよいでしょう。」先生が言った。「そのような穀物を食べ、そのような錦を着るのは、お前にとって平気なのか。」(宰我が)言った。「はい。」(先生が言った。)「お前が平気なら、そうしなさい。そもそも喪中の君子は、うまいものを食べてもうまいと感じず、音楽を聴いても楽しくなく、居場所にいても落ち着かない。だからそうしないのだ。今お前が平気なら、そうしなさい。」宰我が(孔子の部屋を)出た。先生が言った。「予(=宰我)は仁の情けが無いものだよ。子は生まれてから三年で、(やっと)父母の懐から離れる。(だから)そもそも三年の喪は、天下の常識的な喪なのだ。予には三年の愛が、父母にあったのだろうか。」
意訳

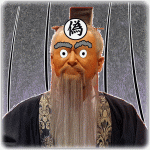
宰我「親に対する三年の喪は長すぎます。そんなに引き籠もっていては、君子がせっかく身につけた礼法も音楽も、ダメになってしまいます。前年の穀物が尽きて新米を食べる頃、火打ち金が錆びる頃には、火を切り直すではありませんか。喪も一年で十分です。」
孔子「お前はそれで平気なのか。」
宰我「ええ。」
孔子「じゃ、そうしなさい。君子たる者、親が亡くなれば、何を食べてもうまいと感じず、何を聞いても楽しいと思わず、一日中落ち着かないものだ。だが平気というなら、かまわない。」
宰我が部屋を出ていった。先生が言った。
孔子「宰我には人の情けが無いのだな。子は生まれて三年間は父母に抱かれて、やっとひとりで歩けるようになる。宰我の親には、その三年の愛が無かったのだろうか。」
従来訳
宰我がたずねた。――
「父母の喪は三年となっていますが、一年でも結構長過ぎるぐらいではありますまいか。もし君子が三年間も礼を修めなかったら、礼はすたれてしまいましょう。もし三年間も楽がくに遠ざかったら、楽がくがくずれてしまいましょう。一年たてば、殻物も古いのは食いつくされて新しいのが出てまいりますし、火を擦り出す木にしましても、四季それぞれの木が一巡して、またもとにもどるわけです。それを思いますと、父母の喪にしましても、一年で十分ではありますまいか。」
先師がいわれた。――
「お前は、一年たてば、うまい飯をたべ、美しい着物を着ても気がおちつかないというようなことはないのか。」
宰我――
「かくべつそういうこともございません。」
先師――
「そうか、お前が何ともなければ、好きなようにするがよかろう。だが、いったい君子というものは、喪中にはご馳走を食べてもうまくないし、音楽をきいてもたのしくないし、また、どんなところにいても気がおちつかないものなのだ。だからこそ、一年で喪を切りあげるようなことをしないのだ。もしお前が、何ともなければ、私は強いてそれをいけないとはいうまい。」
それで宰我はひきさがった。すると先師はほかの門人たちにいわれた。――
「どうも予は不人情な男だ。人間の子は生れて三年たってやっと父母の懐をはなれる。だから、三年間父母の喪に服するのは天下の定例になっている。いったい予は三年間の父母の愛をうけなかったとでもいうのだろうか。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
宰我問:「三年守孝期太長了,君子三年不行禮,禮必壞;三年不奏樂,樂必崩。陳谷吃完,新谷又長,鑽木取●的老方法也該改一改了,守孝一年就夠了。」孔子說:「三年內吃香飯,穿錦衣,你心安嗎?「心安。「你心安你就做吧。君子守孝,吃魚肉不香,聽音樂不樂,住●宅不安,所以不做,現在你心安,那麽你就做吧。」宰我走後,孔子說:「宰我真不仁德,嬰兒三歲後才能離開父母的懷抱。三年的喪期,是天下通行的喪期。難道他沒得到過父母三年的懷抱之愛嗎?」
宰我が問うた。「三年間の服喪は長すぎます。君子が三年礼を行わなければ、礼は廃れます。三年間音楽を奏でなければ、音楽は必ず下手になります。旧米を食べ終え、新米が実ると、火切り木で●を取る方法を改めます。服喪は一年で十分です。」
孔子が言った。「三年以内にうまい飯を食い、錦を着ても、お前の心は平静か。」「平静です。」「お前が平静なら、つまりその通りにしたらよい。君子は喪に服すと、魚や肉を食べても旨いと思わず、音楽を聴いても楽しくなく、●な家に住んでも落ち着かない、だからしないのだが、今のお前は心が平静なら、つまりそのようにしたらよいだろう。」宰我が去った後、孔子は言った。
「宰我には全く情けの人徳が無い。赤ん坊は三歳になってやっと父母に抱かれるのを終える。三年間の喪は、天下の常識となる服喪の期間だ。ひょっとすると、彼は父母に三年間抱かれた愛情の経験が無いのだろうか。」
論語:語釈
宰 我 問、「三 年 之 喪、其(期) 已 久 乎(矣)。君 子 三 年 不 爲 禮、禮 必 壞。三 年 不 爲 樂、樂 必 崩。舊 穀 ![]() (旣) 沒、新 穀
(旣) 沒、新 穀 ![]() (旣) 升、銹(鑽) 燧 改 火、期 可 已 矣。」子 曰、「食 夫 稻 也、衣 夫 錦 也、於 女 安 乎。」曰、「安。」「女 安、則 爲 之。夫 君 子 之 居 喪、食 旨 不 甘、聞 樂 不 樂、居 處 不 安、故 弗(不) 爲 也。今 女 安、則 爲 之。」宰 我 出。子 曰、「予 之 不 仁 也。子 生 三 年、然 后(後) 免 於 父 母 之 懷。夫 三 年 之 喪、天 下 之 通 喪 也。予 也、又(有) 三 年 之 愛 於 其 父 母 (乎)。」
(旣) 升、銹(鑽) 燧 改 火、期 可 已 矣。」子 曰、「食 夫 稻 也、衣 夫 錦 也、於 女 安 乎。」曰、「安。」「女 安、則 爲 之。夫 君 子 之 居 喪、食 旨 不 甘、聞 樂 不 樂、居 處 不 安、故 弗(不) 爲 也。今 女 安、則 爲 之。」宰 我 出。子 曰、「予 之 不 仁 也。子 生 三 年、然 后(後) 免 於 父 母 之 懷。夫 三 年 之 喪、天 下 之 通 喪 也。予 也、又(有) 三 年 之 愛 於 其 父 母 (乎)。」
宰我

孔子の弟子で合理主義者。姓は宰、名は予、あざ名は子我。したがって論語の本章では、宰我を敬称で呼んでいることになる。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章では”…の”・”これ”。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”~の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。
三年之喪
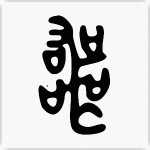

「喪」(金文)
論語の本章では、両親のための三年の服喪。「喪」の初出は甲骨文。『学研漢和大字典』による原義は、各人それぞれに死者を悼んで泣くこと、という。詳細は論語語釈「喪」を参照。
期→其
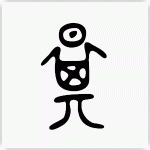

(金文)
論語の本章では”一年”。ひとめぐりする一定の時間を指し、一ヶ月を意味する場合もある。動詞としては”期待する・待つ”。
初出は春秋末期の金文。『学研漢和大字典』によると其(キ)は、もと四角い箕(ミ)を描いた象形文字。四角くきちんとした、の意を含む。箕の原字。期は「月+(音符)其」の会意兼形声文字で、月が上弦→満月→下弦→朔をへてきちんともどり、太陽が春分→夏至→秋分→冬至をへて、正しくもとの位置にもどること、という。詳細は論語語釈「期」を参照。
定州竹簡論語の「其」は”その”。初出は甲骨文。原義は上掲の通りちりとりのたぐい。詳細は論語語釈「其」を参照。
久

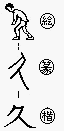
(金文)
論語の本章では”長い”。確実な初出は秦系戦国文字。ただし本章は後世の創作が確定しているので問題が無い。原義は人を後ろからつっかい棒で支える姿で、”ひさしい・ながい”という伝統的な語釈は、「旧」と音が通じて後世に生まれた語義。詳細は論語語釈「久」を参照。
禮
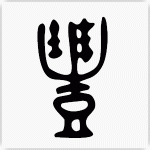
(金文)
論語の本章では”君子らしい礼儀作法”。新字体は「礼」。初出は甲骨文。へんのない豊の字で記された。『学研漢和大字典』によると、豊(レイ)(豐(ホウ)ではない)は、たかつき(豆)に形よくお供え物を盛ったさま。禮は「示(祭壇)+(音符)豊」の会意兼形声文字で、形よく整えた祭礼を示す、という。詳細は論語語釈「礼」を参照。
もとは字形通り、たかつきに山盛りに盛ったおそなえのご飯。
壞/壊
論語の本章では”廃れる”。現行書体の初出は戦国末期の秦の金文。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補は「褱」。ただし周代から前漢にかけて、「壊」と「懐」はまとめて「褱」と書かれたり、「壊」が「懐」を意味したりした。『学研漢和大字典』によると「土+(音符)褱(カイ)(ふところ、うつろに穴があく)」の会意兼形声文字、という。詳細は論語語釈「壊」を参照。
樂(ガク)


(甲骨文)
論語の本章では”音楽”。初出は甲骨文。新字体は「楽」原義は手鈴の姿で、”音楽”の意の方が先行する。漢音(遣隋使・遣唐使が聞き帰った音)「ガク」で”奏でる”を、「ラク」で”たのしい”・”たのしむ”を意味する。春秋時代までに両者の語義を確認できる。詳細は論語語釈「楽」を参照。
崩→項×
論語の本章では”ダメになる。初出は前漢の隷書。論語の時代に存在しない。『学研漢和大字典』によると朋(ホウ)は、二つ並んだ貝飾りの姿。二つ並んでくっつく意は、朋友の朋(仲よくくっついた友達)に残るが、二つに離れる意をも含む。崩は「山+(音符)朋」の会意兼形声文字で、△型の山が両側にくずれ落ちること、という。詳細は論語語釈「崩」を参照。
定州竹簡論語の「項」の初出は楚系戦国文字。『大漢和辞典』に”くずれる・こわれる・すたれる”系統の語義が無く、定州竹簡論語の注釈に従い、「崩」の誤字と判断した。
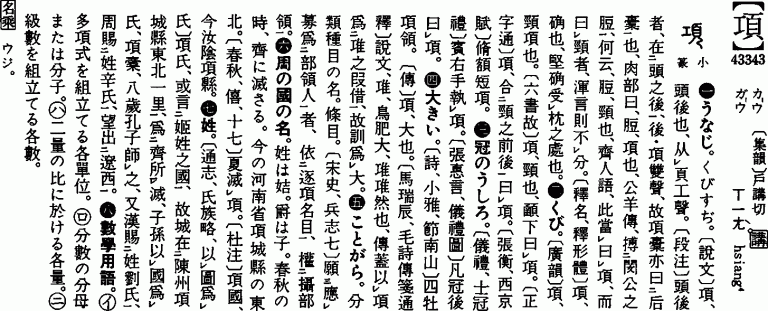
なお定州竹簡論語はおそらく隷書で書かれていたと思われるが、「崩」と「項」の字形の違いは大きく、なぜ誤記したのかは分からない。「小学堂」より引用。
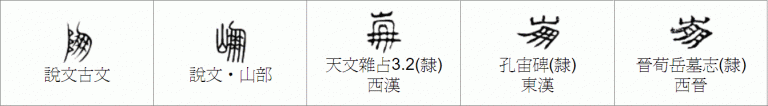

旣/既→

(金文)
論語の本章では”すでに”。初出は甲骨文。『学研漢和大字典』によると旡(キ)は、腹いっぱいになって、おくびの出るさま。既はもと「皀(ごちそう)+(音符)旡」の会意兼形声文字で、ごちそうを食べて腹いっぱいになること。限度まで行ってしまう意から、「すでに」という意味を派生する、という。詳細は論語語釈「既」を参照。
定州竹簡論語の「![]() 」はフォントも無く『大漢和辞典』にも無く、「小学堂」に従い「旣」の異体字と判断するしかない。
」はフォントも無く『大漢和辞典』にも無く、「小学堂」に従い「旣」の異体字と判断するしかない。
沒/没

(金文大篆)
論語の本章では”尽きる・なくなる”。初出は戦国末期の金文。『学研漢和大字典』による原義は水に潜ることであり、潜って見えなくなること、隠されて分からなくなることを意味する、という。詳細は論語語釈「没」を参照。
升
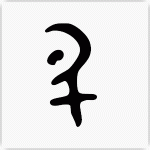
(金文)
論語の本章では”実る”。初出は甲骨文。『学研漢和大字典』による原義は穀物や液体を升で量るさまであり、穀物が実り、収穫されて升で量れるようになったことを意味する、という。詳細は論語語釈「升」を参照。
鑽燧→銹燧
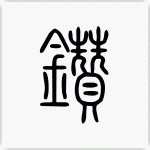

(篆書)
論語の本章では、「鑚燧」はきりもみで火種を得ること。「鑚」は「うがつ」と読んで穴を開けることであり、「燧」は火起こしの道具を意味する。
「鑚」の初出は後漢の『説文解字』。論語の時代に存在しない。『学研漢和大字典』によると「金+(音符)贊(力をあわせる、中心に集まる)」の会意兼形声文字。力を一点に集中して穴をあけること、という。詳細は論語語釈「鑚」を参照。
「燧」の確実な初出は不明。論語の時代に存在が確認できない。論語時代の置換候補は「遂」。論語では本章のみに登場。『学研漢和大字典』によると遂の右側の字(音スイ・ツイ)は、ぶたを描いた象形文字。遂はそれを単なる音符とした形声文字で、奥深く進み入ること。燧は「火+(音符)遂」の会意兼形声文字で、きりを木の中に奥深くもみこんでまさつによって発火させること、という。詳細は論語語釈「燧」を参照。
中国の神話や歴史では、人に火を使う事を教えた燧人氏なる人物が登場するが、文献に現れるのは戦国時代の『荘子』や『荀子』になってからであり、この神話そのものが新しいことを示している、
論語の時代の火起こし事情については、鉄器の普及や石器の発達いかんによって変わってくる。フリントと鉄片があったとすると火打ち金による発火になるが、おそらくは火打ち金はまだ無く、木片と木棒を激しくこすり合わせて発火させていたと思われる。
それを証するように、『春秋左氏伝』での「燧」はすべて”たいまつ”の意で、発火具と解せる文は無い。これは論語の本章が偽作であることの傍証になるだろう。
武内本に「改火」について、「古は四時に従って異なる木より火を取る」と記しているが、元ネタは古注の記述で、もちろん言い出した馬融による根拠無きデタラメである。
馬融曰周書月令有更火春取榆柳之火夏取棗杏之火季夏取桑柘之火秋取柞楢之火冬取槐檀之火一年之中鑽火各異木故曰改火也

馬融「『書経』周書部によると、月の満ち欠けを暦とし、春にはニレやヤナギの木で火を起こし、夏はナツメやアンズの木で火を起こし、またはクワやザクロで火を起こし、秋はクヌギやナラの木で火を起こし、冬はエンジュやマユミの木で火を起こす。同じ年でも、火起こしの付け木は違うのである。だから”火を改める”と言ったのだ。」(『論語集解義疏』)
現伝『書経』(尚書)にそんなことは全く書いていないが、『書経』もほぼでっち上げなのだから、怪しむに足りない。
定州竹簡論語の「銹燧」は意味が異なる。「銹」は”サビ”であり、「燧」=”火打ち金”が錆びることを意味する。「銹」の初出は不明。論語の時代に存在が確認できない。論語では本章のみに登場。『学研漢和大字典』によると秀は、作物の穂がのびて、細く浮き出ること。銹は「金+(音符)秀(表面に浮きでる)」の会意兼形声文字、という。詳細は論語語釈「銹」を参照。
稻(稲)・錦
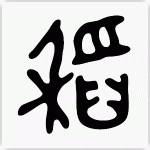
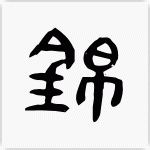
「稲」(金文)・「錦」(秦系戦国文字)
論語の本章では、粘りけのある穀物と、金糸を織りこんだ絹織物が転じて、上等の布。
「稲」の初出は西周末期の金文。論語では本章のみに登場。『学研漢和大字典』によると「禾(いね)+(音符)舀(ヨウ)・(トウ)(うすの中でこねる)」の会意兼形声文字。詳細は論語語釈「稲」を参照。論語の時代の華北に、コメの栽培が一般的だったかどうかは未詳。語義からは、粘りけがある穀物であれば「稲」と呼べるので、コメ以外だった可能性が高い。
「錦」の初出は楚系戦国文字。論語の時代に存在しない。論語では本章のみに登場。カールグレン上古音は不明(上)。王力系統ではkǐəm。『大漢和辞典』で音キン訓にしきは他に存在しない。部品の「帛」bʰăk(入)の初出は甲骨文。訓は良く通じるが音がまるで違う。論語語釈「錦」を参照。
則(ソク)


(甲骨文)
論語の本章では、”~の場合は”。初出は甲骨文。字形は「鼎」”三本脚の青銅器”と「人」の組み合わせで、大きな青銅器の銘文に人が恐れ入るさま。原義は”法律”。論語の時代=金文の時代までに、”法”・”則る”・”刻む”の意と、「すなわち」と読む接続詞の用法が見える。詳細は論語語釈「則」を参照。
旨・甘
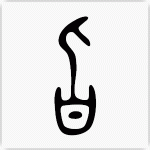
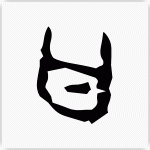
「旨」(金文)・「甘」(甲骨文)
論語の本章では、ともに”うまい”こと。
「旨」の初出は甲骨文。論語では本章のみに登場。『学研漢和大字典』によると「匕+甘(うまい)」の会意文字。匕印は人の形であるが、まさか人肉の脂ではあるまい。匕(さじ)に当てた字であろう。つまり「さじ+甘」で、うまい食物のこと。のち指(ゆびで示す)に当て、さし示す内容の意に用いる、という。詳細は論語語釈「旨」を参照。
「甘」の初出は甲骨文。論語では本章のみに登場。『学研漢和大字典』によると「口+●印」の会意文字で、口の中に●印で示した食物を含んで味わうことを示す。ながく口中で含味する、うまい(あまい)物の意となった、という。詳細は論語語釈「甘」を参照。
出(シュツ/スイ)


(甲骨文)
論語の本章では”孔子の居間から出る”。初出は甲骨文。「シュツ」の漢音は”出る”・”出す”を、「スイ」の音はもっぱら”出す”を意味する。呉音は同じく「スチ/スイ」。字形は「止」”あし”+「凵」”あな”で、穴から出るさま。原義は”出る”。論語の時代までに、”出る”・”出す”、人名の語義が確認できる。詳細は論語語釈「出」を参照。
予
論語の本章では、宰我の本名。
初出は戦国時代の金文で、論語の時代に存在しない。カールグレン上古音はdi̯o。同音に余、野などで、「余・予をわれの意に用いるのは当て字であり、原意には関係がない」と『学研漢和大字典』はいう。「豫」は本来別の字。詳細は論語語釈「予」を参照。
仁(ジン)


(甲骨文)
論語の本章では、”常に憐れみの気持を持ち続けること”。初出は甲骨文。字形は「亻」”ひと”+「二」”敷物”で、原義は敷物に座った”貴人”。詳細は論語語釈「仁」を参照。
仮に孔子の生前なら、単に”貴族(らしさ)”の意だが、後世の捏造の場合、通説通りの意味に解してかまわない。つまり孔子より一世紀のちの孟子が提唱した「仁義」の意味。詳細は論語における「仁」を参照。
予之不仁也(ヨのフジンなるや)
ここでの「之」は「a之b」の形で、”aがbであること”という名詞句を形成する。それに文末助詞の「也」がつき、”aはまことにbであることよ”という詠嘆の文となる。
懷/懐
論語の本章では”ふところ”。初出は西周時代の金文。『学研漢和大字典』によると褱(カイ)は「目からたれる涙+衣」の会意文字で、涙を衣で囲んで隠すさま。ふところに入れて囲む意を含む。懷は「心+(音符)褱」の会意兼形声文字で、胸中やふところに入れて囲む、中に囲んでたいせつに暖める気持ちをあらわす、という。詳細は論語語釈「懐」を参照。
天下
論語の本章では”この世の中”。
「天」の初出は甲骨文。『学研漢和大字典』によると、大の字にたった人間の頭の上部の高く平らな部分を一印で示した指事文字で、もと、巓(テン)(いただき)と同じ。頭上高く広がる大空もテンという。高く平らに広がる意を含む、という。詳細は論語語釈「天」を参照。
「下」の初出は甲骨文。『学研漢和大字典』によると、おおいの下にものがあることを示指事文字で、した、したになるの意をあらわす。上の字の反対の形、という。詳細は論語語釈「下」を参照。
天下之通喪也(テンカのツウソウなり)
父母に対して三年間喪に服するのが「通例」だ、との意だが、そうだった証拠は無い。
愛(アイ)

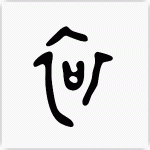
「愛」(金文)/「哀」(金文)
論語の本章では”愛すること”。初出は戦国末期の金文。一説には戦国初期と言うが、それでも論語の時代に存在しない。同音字は、全て愛を部品としており、戦国時代までしか遡れない。
「愛」は爪”つめ”+冖”帽子”+心”こころ”+夂”遅れる”に分解できるが、いずれの部品も”おしむ・あいする”を意味しない。孔子と入れ替わるように春秋時代末期を生きた墨子は、「兼愛非行」を説いたとされるが、「愛」の字はものすごく新奇で珍妙な言葉だったはず。
ただし同訓近音に「哀」があり、西周初期の金文から存在し、回り道ながら、上古音で音通する。論語の時代までに、「哀」には”かなしい”・”愛する”の意があった。詳細は論語語釈「愛」を参照。
論語:付記
論語の本章の史実性について、武内義雄『論語之研究』は異議を挟んでいない。だが上記の通り漢帝国にならないと現れない文字があり、また孔子生前の発火技術と事情が違っている。
宰我は殿様におちゃらけを言った(論語八佾篇21)、昼寝をした(論語公冶長篇9)、君子を小ばかにした(論語雍也篇26)などの理由で、その都度孔子に怒られている「悪い弟子」とされる。だが実際に孔子に怒られた、またダメな弟子だったという証拠は無い。
いずれも戦国時代以降の儒者による冤罪であり、その実は孔子と同様、古代人には珍無類な、ほとんど無神論に近い立場に立つ合理主義者だった。
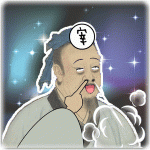
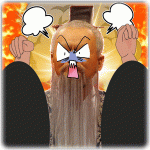
宰我「黄帝は三百歳も生きたなんて、そりゃ人ですか、それとも何か妖怪のたぐいですか。」
孔子「こうらぁ~! このバチあたりがッ!」(『大載礼記』五帝徳篇。論語衛霊公篇42付記を参照)
『大載礼記』の成立は前漢時代で、孔子の生前、黄帝は無論、堯舜禹が創作される前だったが、「あいつならこう言うことを言いそうだ」と後世の儒者に思われ、宰我が据えられたに過ぎない。もし当時黄帝が知られていたら、「でっち上げじゃよ」と孔子も言ったろう。
だからこそ、宰我は楚王とその宰相にまで恐れられる「仕事人」だった(『史記』孔子世家)。後世の儒者に悪く書かれた理由はよく分からない。宰我は自派閥を残さなかったから、おそらく記録がほとんど残っていらず、言いたい放題に言うには都合がよかったからだろう。





コメント