論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子曰泰伯其可謂至德也巳矣三以天下讓民無得而稱焉
- 「民」字:「叚」字のへんで記す。唐太宗李世民の避諱。
校訂
諸本
- 武内本:釋文得一本亦徳に作る、後漢書丁鴻伝此章を引く皆徳に作る、一本と同じ。(→武英殿二十四史『後漢書』丁鴻伝)
東洋文庫蔵清家本
子曰泰伯其可謂至德也已矣三以天下讓民無得而稱焉
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
(なし)
標点文
子曰、「泰伯、其可謂至德也已矣。三以天下讓、民無得而稱焉。」
復元白文(論語時代での表記)















 讓
讓 



 焉
焉
※泰→大。論語の本章は、「讓」「焉」が論語の時代に存在しない。ただし「焉」は無くとも文意が変わらない。「德」「也」「已」の用法に疑問がある。本章は戦国時代以降の儒者による創作である。
書き下し
子曰く、泰伯は其れ德に至ると謂ふ可き也已矣。三たび天下以讓り、民得め而稱える無かり焉。
論語:現代日本語訳
逐語訳

先生が言った。泰伯の評価はただ一つ、最高の人格力を持っていたと言える。三度天下を譲ったが、民はその話を聞いて讃えることができなかった。
意訳

孔子「まことに呉国の開祖泰伯さまこそ、最高の人徳を持ったお方でござる。三度天下を譲り、それを民にも知らせたまわなかった。」
従来訳
先師がいわれた。――
「泰伯こそは至徳の人というべきであろう。固辞して位をつがず、三たび天下を譲ったが、人民にはそうした事実をさえ知らせなかった。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子說:「泰伯的品德高尚極了!三次讓出王位,百姓無法用語言來稱贊他。」
孔子が言った。「泰伯の人徳は高尚の極みだ。三度王位を譲り、人民はどう言って讃えたら良いかも分からなかった。」
論語:語釈
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。


(甲骨文)
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
泰伯(タイハク)
おそらく想像上の、呉国の開祖。周王朝の開祖文王の叔父とされる人物。周の大王とのちに呼ばれた古公亶父の長男。まだ殷王朝の頃、弟の季歴の出来が良かったため、周を出て南方の蛮地、呉に移り住んだ。二度と戻らない決意を示すため、蛮族の風習に倣って髷を切り落とし、体に入れ墨を入れたという。
親子兄弟だろうと叩き売る中華文明(論語学而篇4余話)から見ればあり得ない人物で、こういう卑屈な行為は全てでっち上げと見るしかない。呉は孔子存命中に勃興した長江下流域の国で、南隣の越が明確に周王朝とは異族であることを主張したのに対し、中華の一員だという虚構を執拗に主張した。
呉は孔子死去の直後に越に滅ぼされたため、その国人がどのような人々だったかは分からない。ただ孔子の存命中、古くさい「覇者」を名乗ろうとして諸国へさかんに攻め入った。覇者の責務に「尊皇攘夷」があるからには、覇者自身が中華人でなければならず、したがって呉は中華の一員であり、その開祖は周王朝と同源だという虚構が必要になった。


(秦系戦国文字)
「泰」の初出は秦系戦国文字。同音に大・太。従って”大きい”・”太い”の意を持つ場合にのみ、大・太が論語時代の置換候補となりうる。字形は「大」”人の正面形”+「又」”手”二つ+「水」で、水から人を救い上げるさま。原義は”救われた”→”安全である”。
『説文解字』や『字通』の言う通り、「太」が異体字だとすると、楚系戦国文字まで遡れるが、漢字の形体から見て、「泰」は水から両手で人を救い出すさまであり、「太」は人を脇に手挟んだ人=大いなる人の形で、全く異なる。詳細は論語語釈「泰」を参照。
論語の本章に関しては、「大伯」”大いなる諸侯”の大の字にもったいをつけて書き換えただけで、つまり他者に対するハッタリで、自己の精神的幼稚を示す行為。
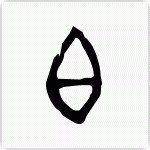

「白」(甲骨文)
「伯」の字は論語の時代、「白」と書き分けられていない。初出は甲骨文。字形の由来は蚕の繭。原義は色の”しろ”。甲骨文から原義のほか地名・”(諸侯の)かしら”の意で用いられ、また数字の”ひゃく”を意味した。金文では兄弟姉妹の”年長”を意味し、また甲骨文同様諸侯のかしらを意味し、五等爵の第三位と位置づけた。戦国の竹簡では以上のほか、「柏」に当てた。詳細は論語語釈「伯」を参照。
其(キ)


(甲骨文)
論語の本章では”その人”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「𠀠」”かご”。それと指させる事物の意。金文から下に「二」”折敷”または「丌」”机”・”祭壇”を加えた。人称代名詞に用いた例は、殷代末期から、指示代名詞に用いた例は、戦国中期からになる。詳細は論語語釈「其」を参照。
可(カ)


「可」(甲骨文)
論語の本章では”…できる”。「可」の初出は甲骨文。字形は「口」+「屈曲したかぎ型」で、原義は”やっとものを言う”こと。甲骨文から”…できる”を表した。日本語の「よろし」にあたるが、可能”~できる”・勧誘”~のがよい”・当然”~すべきだ”・認定”~に値する”の語義もある。詳細は論語語釈「可」を参照。
謂(イ)


(金文)
論語の本章では”…だと言う”。本来、ただ”いう”のではなく、”~だと評価する”・”~だと認定する”。現行書体の初出は春秋後期の石鼓文。部品で同義の「胃」の初出は春秋早期の金文。金文では氏族名に、また音を借りて”言う”を意味した。戦国の竹簡になると、あきらかに”~は~であると言う”の用例が見られる。詳細は論語語釈「謂」を参照。
至(シ)
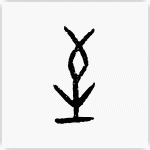

(甲骨文)
論語の本章では”至る”。甲骨文の字形は「矢」+「一」で、矢が届いた位置を示し、”いたる”が原義。春秋末期までに、時間的に”至る”、空間的に”至る”の意に用いた。詳細は論語語釈「至」を参照。
德(トク)
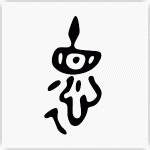

(金文)
論語の本章では”道徳”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。新字体は「徳」。甲骨文の字形は、〔行〕”みち”+〔丨〕”進む”+〔目〕であり、見張りながら道を進むこと。甲骨文で”進む”の用例があり、金文になると”道徳”と解せなくもない用例が出るが、その解釈には根拠が無い。前後の漢帝国時代の漢語もそれを反映して、サンスクリット語puṇyaを「功徳」”行動によって得られる利益”と訳した。孔子生前の語義は、”能力”・”機能”、またはそれによって得られる”利得”。詳細は論語における「徳」を参照。文字的には論語語釈「徳」を参照。
也(ヤ)


(金文)
論語の本章では、「なり」と読んで断定の意。この語義は春秋時代では確認できない。初出は事実上春秋時代の金文。字形は口から強く語気を放つさまで、原義は”…こそは”。春秋末期までに句中で主格の強調、句末で詠歎、疑問や反語に用いたが、断定の意が明瞭に確認できるのは、戦国時代末期の金文からで、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「也」を参照。
已(イ)
論語の本章では”すでに”。
現存最古の論語本である定州竹簡論語では本章全体を欠き、唐石経は同じく「巳」と記し、東洋文庫蔵清家本は「已」と記す。清家本は唐石経より前の古注系論語を伝承しており、唐石経を訂正しうる。
「巳」字であれ「已」字であれ語義は”すでに”で変わらないし、論語では「己」字も「巳」字や「已」字で記される例がある。つまり唐代頃までは「巳」”へび”と「已」”すでに”と「己」”おのれ”は相互に異体字として通用した。従って本章でも異体字として扱い、また意味上から「巳」字→「已」字へと校訂した。
論語の伝承について詳細は「論語の成立過程まとめ」を参照。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)


(甲骨文)
唐石経は「巳」と記し、慶大蔵論語疏は本章を欠くが、現存する章ではやはり同じく「己」「已」を「巳」と記す。「巳」の初出は甲骨文。字形はヘビの象形。「ミ」は呉音。甲骨文では干支の六番目に用いられ、西周・春秋の金文では加えて、「已」”すでに”・”ああ”・「己」”自分”・「怡」”楽しませる”・「祀」”まつる”の意に用いた。詳細は論語語釈「巳」を参照。


(甲骨文)
「已」の初出は甲骨文。字形と原義は不詳。字形はおそらく農具のスキで、原義は同音の「以」と同じく”手に取る”だったかもしれない。論語の時代までに”終わる”の語義が確認出来、ここから、”~てしまう”など断定・完了の意を容易に導ける。詳細は論語語釈「已」を参照。
矣(イ)


(金文)
論語の本章では、”(きっと)~である”。初出は殷代末期の金文。字形は「𠙵」”人の頭”+「大」”人の歩く姿”。背を向けて立ち去ってゆく人の姿。原義はおそらく”…し終えた”。ここから完了・断定を意味しうる。詳細は論語語釈「矣」を参照。
也已矣(ヤイイ)
逐語訳すれば「であるに、なりきって、しまった」。アルツハイマーに脳をやられた大隈重信が、演説で「あるんであるんである」と言ったように、もったいの上にもったいを付けたバカバカしい言葉。断定を示したいなら「也」「已」「矣」のどれか一字だけで済む。
つまり「也已矣」以前がうそデタラメだから、大げさに言って読む者聞く者をびっくりさせ、信じさせてしまおうという、見え透いた悪辣の表現。


漢文業界では「也已」の二字で「のみ」と訓読する座敷わらしだが、確かに「也已」は”であるになりきった”の意だから「のみ」という限定に読めなくはないが、それは正確な漢文の翻訳ではない。意味の分からない字を「置き字」といって無視するのと同じ、平安朝の漢文を読めないおじゃる公家以降、日本の漢文業者が世間を誤魔化し思考停止し続けた結果で、現代人が真似すべき風習ではない。
曹銀晶「談《論語》中的”也已矣”連用現象」(北京大学)によると、「也已矣」は前漢宣帝期の定州論語では、そもそもそんな表現は無いか、「矣」「也」「也已」と記されたという。要するに、漢帝国から南北朝にかけての儒者が、もったいを付けて幼稚なことを書いたのだ。
三(サン)


(甲骨文)
論語の本章では”三たび”。初出は甲骨文。原義は横棒を三本描いた指事文字で、もと「四」までは横棒で記された。「算木を三本並べた象形」とも解せるが、算木であるという証拠もない。詳細は論語語釈「三」を参照。
以(イ)


(甲骨文)
論語の本章では”用いる”→”~を”。初出は甲骨文。人が手に道具を持った象形。原義は”手に持つ”。論語の時代までに、名詞(人名)、動詞”用いる”、接続詞”そして”の語義があったが、前置詞”~で”に用いる例は確認できない。ただしほとんどの前置詞の例は、”用いる”と動詞に解せば春秋時代の不在を回避できる。詳細は論語語釈「以」を参照。
天下(テンカ)

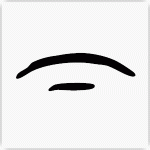
(甲骨文)
論語の本章では”天下”。天の下にある領域全て。
「天」の初出は甲骨文。字形は人の正面形「大」の頭部を強調した姿で、原義は”脳天”。高いことから派生して”てん”を意味するようになった。甲骨文では”あたま”、地名・人名に用い、金文では”天の神”を意味し、また「天室」”天の祭祀場”の用例がある。詳細は論語語釈「天」を参照。
「下」の初出は甲骨文。「ゲ」は呉音。字形は「一」”基準線”+「﹅」で、下に在ることを示す指事文字。原義は”した”。によると、甲骨文では原義で、春秋までの金文では地名に、戦国の金文では官職名に(卅五年鼎)用いた。詳細は論語語釈「下」を参照。
なお殷代まで「申」と書かれた”天神”を、西周になったとたんに「神」と書き始めたのは、殷王朝を滅ぼして国盗りをした周王朝が、「天命」に従ったのだと言い張るためで、文字を複雑化させたのはもったいを付けるため。「天子」の言葉が中国語に現れるのも西周早期で、殷の君主は自分から”天の子”などと図々しいことは言わなかった。詳細は論語述而篇34余話「周王朝の図々しさ」を参照。
讓(ジョウ)


(晋系戦国文字)
論語の本種では”譲渡する”。新字体は「譲」。初出は晋系戦国文字で、論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補も無い。同音は旁に襄を持つ一連の漢字群。字形は「言」+「口」+「羊」で、”羊を供えて神に何かを申す”ことだろう。従って『大漢和辞典』の語釈の中では、”祭りの名”が原義と思われる。さらに”ゆずる”の語義は派生義となる。詳細は論語語釈「譲」を参照。
三以天下讓
論語の本章では”三度天下を譲った”。だが現伝の伝説で泰伯が譲ったと何とか言えるのは、周の後を弟にゆだねた一回だけであり、譲ったのも殷王朝下の諸侯である周の跡取りの地位で、その当時では天下ではない。だが古注の儒者は真に受けて間の抜けた御託を書き記している。
古注『論語集解義疏』
泰伯周太王之元子故號泰伯其徳𢎞逺故曰至也云三以天下讓者此至徳之事也其讓天下之位有三跡故云三以天下讓也所以有讓者少弟季歴生子文王昌昌有聖人徳泰伯知昌必有天位但升天位者必須階漸若從庶人而起則為不易太王是諸侯已是太王長子長子後應傳國今欲令昌取王位有漸故讓國而去令季歴傳之也其有三跡者范寗曰有二釋一云泰伯少弟季歴生子文王昌昌有聖徳泰伯知其必有天下故欲令傳國於季歴以及文王因太王病託採藥於呉越不反太王薨而季歴立一讓也季歴薨而文王立二讓也文王薨而武王立於此遂有天下是為三讓也又一云太王病而託採藥出生不事之以禮一讓也太王薨而不反使季歴主喪死不𦵏之以禮二讓也斷髪文身示不可用使季歴主祭禮不祭之以禮三讓也繆協曰泰伯三讓之所為者季歴文武三人而王道成是三以天下讓也
泰伯は周太王のもと子である。だから泰伯と名乗った。その人徳は広大で、だから三度天下を譲ったと言われた。これは人徳の極みを尽くした行為である。泰伯が天下を譲ったことで、三つの史実をもたらすことになった。だから三度譲ったと言われた。
譲った理由は次の通り。弟の季歴がのちの周の文王昌を生んでおり、昌も聖人の人徳を備えていたので、昌は行く先必ず天下を取るだろうと思った。取るには庶民から順次身を起こして取るのが変えようのない原則である。太王はすでに諸侯であり、泰伯はすでに諸侯の長男である。諸侯の長男はあとを継ぐのだから、もし昌に天下を取らせたいなら、その過程として諸侯にならせるべく、跡継ぎの地位を季歴に譲って国を出た。
譲った結果が三つ出たことについて、范寗は次のように言った。「二つの見解がある。一つは、弟の季歴がのちの周の文王昌を生み、昌に聖人の徳があったので、行く末必ず天下を取るだろうと泰伯はふんで、世継ぎの地位を季歴に譲りその先昌に国を持たせようと図った。そこで太王が病気になったのにかこつけて、呉越へ薬草を取りに行くと言って、行ったまま帰らなかった。そこで太王が死んで季歴が世を継いだのが譲りの一つ目である。季歴が死んで文王が世を継いだのが譲りの二度目である。文王が死んで武王がとうとう天下を取ったのが譲りの三つ目である。
今一つの説がある。太王の病気にかこつけて薬を取りに行き、生きて太王に仕えなかったのが譲りの一つ目である。太王が死んでも帰らず季歴を喪主に葬儀をやらせたのが譲りの二つ目である。髷を切ってざんばら髪にし、入れ墨を入れて蛮族に成り下がったから、季歴が先祖の祭祀をやらざるをえないように仕向けたのが譲りの三つ目である」と。
繆協は別のことを言っている。「泰伯が三度譲ったのは、季歴と文王と武王の三人が王道を施したので、だから三度譲ったと言われた」と。
ここまで愚劣なかこつけを書いたことで、後漢から南北朝にかけての儒者という生物は、現代の常人にとって理解不能だと分かるだろう。こういう御託をうそデタラメ知りつつ創作し、あるいは書き記したのは、全て金儲けになるからで、サギには自分も心中する覚悟がないと他人はだまされてくれないから、結果としてウソ八百を儒者自身も信じている。それで精神に異常を来さないのだから、中国儒者は何か別の生物だと思った方がよい。
- 論語解説「後漢というふざけた帝国」
- 論語為政篇16余話「魏晋南朝の不真面目」
新注になると「三度」をあっさり「固遜」”断固として遠慮した”と解しておしまい。
新注『論語集注』
子曰:「泰伯,其可謂至德也已矣!三以天下讓,民無得而稱焉。」泰伯,周大王之長子。至德,謂德之至極,無以復加者也。三讓,謂固遜也。無得而稱,其遜隱微,無跡可見也。蓋大王三子:長泰伯,次仲雍,次季歷。大王之時,商道寖衰,而周日強大。季歷又生子昌,有聖德。大王因有翦商之志,而泰伯不從,大王遂欲傳位季歷以及昌。泰伯知之,即與仲雍逃之荊蠻。於是大王乃立季歷,傳國至昌,而三分天下有其二,是為文王。文王崩,子發立,遂克商而有天下,是為武王。夫以泰伯之德,當商周之際,固足以朝諸侯有天下矣,乃棄不取而又泯其跡焉,則其德之至極為何如哉!蓋其心即夷齊扣馬之心,而事之難處有甚焉者,宜夫子之歎息而贊美之也。泰伯不從,事見春秋傳。
本文「子曰:泰伯,其可謂至德也已矣!三以天下讓,民無得而稱焉。」
泰伯とは、周大王の長子である。至徳とは、人徳の究極を言う。これ以上何もつけ加えるべき事が無い状態である。三譲とは、固く譲ったことを言う。無得而称とは、その謙遜が回りくどかったというのである。だから誰にも分からなかった。
そもそも大王の三子は、長男が泰伯、次男が仲雍、三男が季歷だった。大王の時、殷の政道が衰えて、周は日増しに強大になっていった。季歷は子の昌をもうけたが、昌は神聖な人徳を備えていた。大王はいずれ殷を滅ぼすつもりだったが、泰伯が賛成しなかったので、大王はそこであとを季歷に継がせ、やがて昌に伝えようと考えた。泰伯はそれを知り、弟の仲雍と南方の蛮族の国へ逃げた。
かくして大王は季歷を跡継ぎとし、諸侯の位を昌に伝えることにした。かくして天下の三分の二を周は支配する事になったが、その時の王が文王である。文王が世を去り、子の発があとを継いだ。この時になって殷を滅ぼした。これが武王である。
そもそも泰伯の人徳は、殷周革命の時期、諸侯を招き寄せて臣従させるに十分だった。だがそうせずに行方をくらましたのは、なんとも人徳の至りと言うべきである。伯夷叔斉が武王を諌めた精神はともかく、実際にいさめた行動の困難さを思い、孔子先生は深くたたえた。泰伯が従わなかった話は、『春秋』の伝に見える。
なお中国人の物書きは奇数を好み、三は”それほど多くはないがしばしば”の意味で用いられることがある。「白髪三千丈」に代表されるように、数字に関して前近代中国のインテリは極めていい加減で、現代人が真に受けて計算すると混乱する。
奇数を好むのは、二つに割り切れる偶数よりなお余りあるからで、割り切れる=偶数=陰よりも、未来の発展をきざす嘉数として捉えた。それを引き受けた『古事記』の、「なりなりて、なりあまれるところあり」が、豊饒の大地に対してその駆動力を意味するのを思うとよい。
民(ビン)


(甲骨文)
論語の本章では”たみ”。権力者でない全ての人々。初出は甲骨文。「ミン」は呉音。字形は〔目〕+〔十〕”針”で、視力を奪うさま。甲骨文では”奴隷”を意味し、金文以降になって”たみ”の意となった。唐の太宗李世民のいみ名であることから、避諱して「人」などに書き換えられることがある。唐開成石経の論語では、「叚」字のへんで記すことで避諱している。詳細は論語語釈「民」を参照。
無(ブ)


(甲骨文)
論語の本章では”ない”。初出は甲骨文。「ム」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。甲骨文の字形は、ほうきのような飾りを両手に持って舞う姿で、「舞」の原字。その飾を「某」と呼び、「某」の語義が”…でない”だったので、「無」は”ない”を意味するようになった。論語の時代までに、”雨乞い”・”ない”の語義が確認されている。戦国時代以降は、”ない”は多く”毋”と書かれた。詳細は論語語釈「無」を参照。
得(トク)


(甲骨文)
論語の本章では”手に入れる”→”明らかになる”。初出は甲骨文。甲骨文に、すでに「彳」”みち”が加わった字形がある。字形は「貝」”タカラガイ”+「又」”手”で、原義は宝物を得ること。詳細は論語語釈「得」を参照。
而(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”…であって同時に…”。初出は甲骨文。原義は”あごひげ”とされるが用例が確認できない。甲骨文から”~と”を意味し、金文になると、二人称や”そして”の意に用いた。英語のandに当たるが、「A而B」は、AとBが分かちがたく一体となっている事を意味し、単なる時間の前後や類似を意味しない。詳細は論語語釈「而」を参照。
稱(ショウ)


(甲骨文)
論語の本章では”たたえる”。新字体は「称」。初出は甲骨文。ただし字形は「爯」。現伝字形の初出は秦系戦国文字。甲骨文・金文の字形は「爪」”手”+「冉」”髭を生やした口”で、成人男性を持ち上げたたえるさま。戦国最末期の秦国で「禾」”イネ科の植物”が付き、”たたえる”の語義は変わらないが、”穀物の報酬を与える”のニュアンスが付け加わった。甲骨文で”注目する”の意に、春秋末期までの金文で”たたえる”の意に用いた。詳細は論語語釈「称」を参照。
焉(エン)
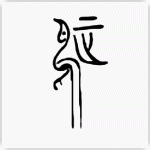

(金文)
論語の本章では「ぬ」と読んで、”し終えた”を意味する断定のことば。初出は戦国早期の金文で、論語の時代に存在せず、論語時代の置換候補もない。漢学教授の諸説、「安」などに通じて疑問辞や完了・断定の言葉と解するが、いずれも春秋時代以前に存在しないか、その用例が確認できない。ただし春秋時代までの中国文語は、疑問辞無しで平叙文がそのまま疑問文になりうるし、完了・断定の言葉は無くとも文意がほとんど変わらない。
字形は「鳥」+「也」”口から語気の漏れ出るさま”で、「鳥」は装飾で語義に関係が無く、「焉」は事実上「也」の異体字。「也」は春秋末期までに句中で主格の強調、句末で詠歎、疑問や反語に用いたが、断定の意が明瞭に確認できるのは、戦国時代末期の金文からで、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「焉」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章は、春秋戦国時代の誰一人引用せず、前漢前期にいわゆる儒教の国教化を推し進め、論語に数多くの偽作を押し込んだ董仲舒の『春秋繁露』に似たような言葉があるのが再出で、定州竹簡論語にも無いことから、董仲舒の時代ですら論語の一章になっていなかった可能性がある。おそらく後漢になってから論語にねじ込まれた偽作と断じてよい。
泰伯至德之侔天地也,上帝為之廢適易姓而子之。讓其至德,海內懷歸之。泰伯三讓而不敢就位。

泰伯は天地を覆うほどの人徳をそなえていたから、天の最高神はその地位を捨てさせ一族からも離脱させて我が子として寵愛することにした。地位を徳の至りである文王・武王の血筋に譲ったから、天下の人々が皆慕い寄って家来になった。これは泰伯が三度譲って世継ぎにならなかったおかげだ。(『春秋繁露』観徳1)
この愚劣な男については、論語公冶長篇24余話「人でなしの主君とろくでなしの家臣」を参照。
解説
ここ論語泰伯編は、もともと孔子と呉の使節の応答として作られた節がある。のちにそれを理解出来ないたわけ儒者が、関係の無い章を間にいくつも押し込んで滅茶苦茶になったのだが、第一章である本章が後漢の偽作であることから分かるように、論語の中では成立が新しい。
呉の使節が孔子のところにやって来て、掘り出された巨大な骨の何たるかを尋ねに来た伝説が『史記』孔子世家にある。孔子は出盛った小便のようにウンチクを垂れているのだが、『史記』の言い分が正しいなら、この時孔子は仕官前で、まだ世に知られる存在ではなかった。
呼ばれもしない門閥貴族の宴会に勝手に押しかけ、先駆者の陽虎に叩き返された頃(『史記』孔子世家)。そんな小僧に過ぎない孔子に、遠方の呉から重い骨を積んだ車をガラガラ牽いて、ウンチクを聞きにわざわざ使者が来るなどあり得ない話で、とうてい史実と認められない。
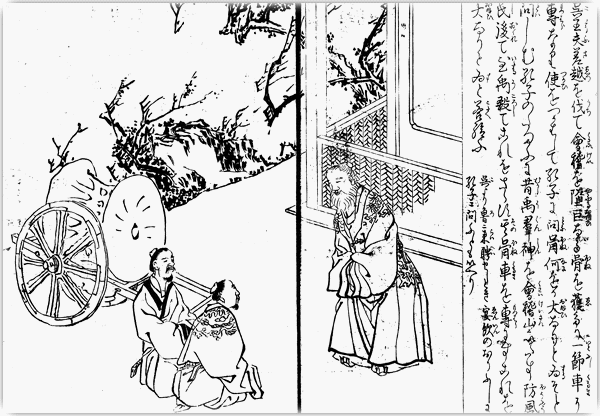
「孔子事跡図解」
だが後世の儒者にとっては、孔子はまず聖人で、仕官などせずとも天下に名が轟いていたのでないと商売に差し支える。本尊がキンキラキンでないと、善男善女を愚夫愚婦に仕立ててお賽銭をせびり取れないからだ。詳細は論語述而篇19余話「せせら笑う漢文書き」を参照。
本章は愚夫愚婦に仕立てる冒頭として、まずニセ孔子がいもしなかった呉の開祖を褒めちぎるもので、何ら史実を伝えないばかりか、現代の論語読者のためになることが少しも書いてない。真に受けてダメになることが書いてあるだけである。
余話
中華文明の体現例(あるDKの厚顔無恥)
この稿を書いている2022年4月現在、論語の全文現代日本語訳を標榜する本で最も新しいのは、訳者の知る限り、カネの亡者NHKのお雇い文化人でもある高橋源一郎『一億三千万人のための『論語』教室』だが、本章を以下の通り記している。
「誰が最高の『徳』の持ち主かというなら、わたしは、周の泰伯の名前を最初にあげたいですね。なにしろ、泰伯さんは、三度もその王位を弟の季歴に譲ったんです。もちろん、譲ったこと自体、半端なくスゴいんですが、もっとスギいのは、それがあまりに自然に行われたので、というか、あまりにも当たり前みたいに譲ったので、民衆は誰も『立派な人だ、誉めたたえよう』とさえ思わなかった、ってことです。『スゴいなあ』と感心されてるうちは、まだまだ、ってことですよ。見習わなくちゃいけませんね」
訳文の幼稚やいちいちの言葉の間抜けな間違いは言うに及ばないが、まるで漢文を読めない男が、「論語教室」を標榜し、論語の各篇を「レッスン」と言い換えて読者に説教しているのこそ、「スゴい」と言うべきだ。一切の他人を食い物と見ていなければ出来ないことである。


このだんだら頭は残忍極まるDK世代(論語子罕篇23余話)の一人で、それも大学在学中に〒囗行為で検挙され有罪判決を受けている筋金入りの𠮷外だった。当時中高大ではDKどもが教師を吊し上げて罵詈雑言の限りを言い殴る蹴るの暴行を働いたが、おそらく高橋もやっただろう。
その高橋が、論語で商売しようとしてこういうことを言い出した。
本書の「訓読」部分につきましては、宮崎市定氏『現代語訳 論語』(岩波現代文庫)を定本として使用いたしております。
高橋が漢文が読めると判断できる材料は一切無い。学生時代には勉強せず〒囗を繰り返し、その後書き物がバブルの時代に乗って売れたから勉強する動機が存在せず、このニセ論語の訳文のどこにも辞書を引いた新解釈はない。訳文は宮崎博士をコピペして言い換えただけである。
高橋はこのニセ論語の中で、他の章に関しては原文と全く関係ないちゃらかし話を書き付けて、読者の知能程度を見くびっているのだが、本章に関しては何一つ書いていない。何が書いてあるかわからないから、ちゃらかしようも無いわけだ。読めていないのを白状している。

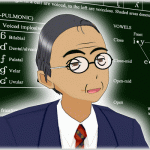
宮崎博士は京大在職中、暴れ回るDKに警告文を発布した硬骨漢で、もちろんDKの罵詈雑言殴る蹴るを体験したか目撃した。戦時中、日本の漢学教授どもが逃げ回る中(論語公冶長篇9解説)、東大の藤堂明保博士と同様に応召し出征した。戦場に比べれば怖くもなかったのだろう。
高橋は頭が悪くて京大には入れなかったのだが、入っていたら間違いなく、宮崎博士を吊し上げただろう。だが受験的な頭の悪さと、中華文明的な図々しさを恥知らずに実践できる能力とはあまり関係が無い。親子兄弟をも叩き売って喰う中華文明を実践するには才が要る。
脳みその中身が猿同然の中華文明実践者の例はすでに記した。
- 論語述而篇21余話「中国人と物理法則」
正確に言えば、向き不向きがある。「中華文明とは何か」(論語学而篇4余話)で記した通り、他人の頭骨をかち割って美味しく脳を味わっているにもかかわらず、食われている者が気付かず時に嬉しがりもするのが、上手な中華文明の実践と言うべきで、高橋の行状はその一例。
たとえばamazonのレビューにこうあった。
この論語から他の沢山の論語を読みたくなるかも
高橋先生の新解釈、最高に面白い。
原文を改めて確認する為に井波律子先生の論語と合わせて読んでいますが、センセイと生徒のその場の雰囲気描写は源一郎先生の方が最高ですね。
キツネに化かされている者に化かされていると言うのがムダなのは、化かされているからだ。

参考動画
参考記事
- 論語雍也篇27余話「そうだ漢学教授しよう」


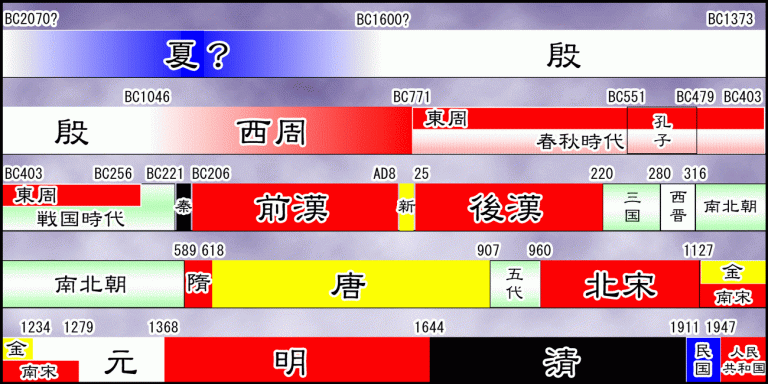

コメント