論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子曰魯衞之政兄弟也
校訂
諸本
- 文明本・足利本・根本本:子曰魯衛之政兄弟
東洋文庫蔵清家本
子曰魯衛之政兄弟也
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
(なし)
標点文
子曰、「魯衞之政、兄弟也。」
復元白文(論語時代での表記)









書き下し
子曰く、魯衞之政は兄弟也。
論語:現代日本語訳
逐語訳
先生が言った。「魯と衛の政治は兄弟だなあ。」
意訳
魯と衛の政治は兄弟のように似ているなあ。
従来訳
先師がいわれた。――
「魯の政治と衛の政治とはやはり兄弟だな。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子說:「魯衛兩國的政事,象兄弟一樣。」
孔子が言った。「魯と衛両国の政治は、まるで兄弟のようにおんなじだ。」
論語:語釈
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。


「子」(甲骨文)
「子」は貴族や知識人に対する敬称。初出は甲骨文。字形は赤ん坊の象形で、古くは殷王族を意味した。春秋時代では、貴族や知識人への敬称に用いた。孔子のように学派の開祖や、大貴族は、「○子」と呼び、学派の弟子や、一般貴族は、「子○」と呼んだ。詳細は論語語釈「子」を参照。


(甲骨文)
「曰」は論語で最も多用される、”言う”を意味する言葉。初出は甲骨文。原義は「𠙵」=「口」から声が出て来るさま。詳細は論語語釈「曰」を参照。
魯(ロ)


(甲骨文)
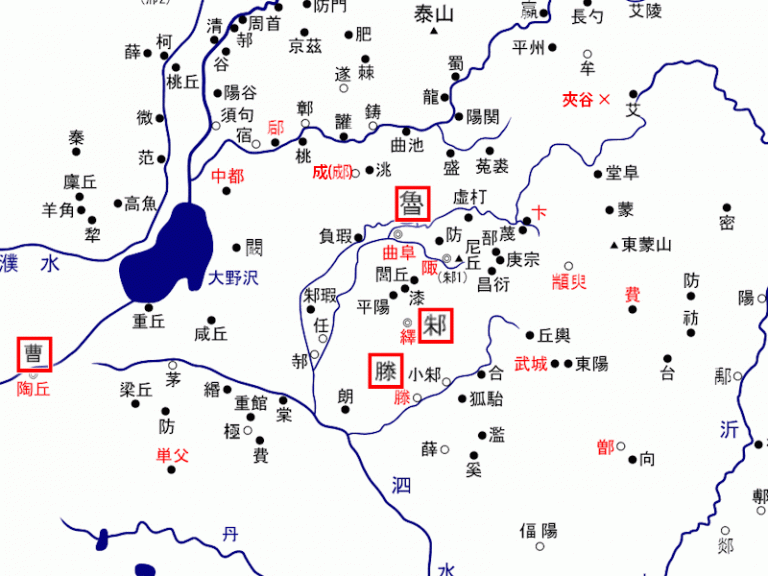
MAP via http://shibakyumei.web.fc2.com/
魯は孔子の生まれた春秋諸侯国の一国。周初の摂政・周公旦を開祖とし、周公旦の子・伯禽が初代国公。現在の中国山東省南部(山東半島の付け根)にあった。北の端には聖山である泰山があり、西の端には大野沢という湖があった。東は大国・斉、南には邾・滕といった小国があった。首邑は曲阜(現曲阜)。wikipediaを参照。また辞書的には論語語釈「魯」を参照。
衞(エイ)


(甲骨文)
論語の本章では、孔子の生国・魯の北にあった中規模諸侯国。
新字体は「衛」。初出は甲骨文。中国・台湾・香港では、新字体がコード上の正字として扱われている。甲骨文には、「韋」と未分化の例がある。現伝字体につながる甲骨文の字形は、「方」”首かせをはめられた人”+「行」”四つ角”+「夂」”足”で、四つ角で曝された奴隷と監視人のさま。奴隷はおそらく見せしめの異民族で、道路を封鎖して「入るな」と自領を守ること。のち「方」は「囗」”城壁”→”都市国家”に書き換えられる。甲骨文から”守る”の意に用い、春秋末期までに、国名・人名の例がある。詳細は論語語釈「衛」を参照。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章では「”~の”。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”~の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。
政(セイ)(まつりごと)
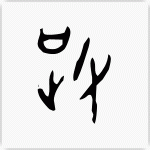

(甲骨文)
論語の本章では”政治(の要点)”。初出は甲骨文。ただし字形は「足」+「丨」”筋道”+「又」”手”。人の行き来する道を制限するさま。現行字体の初出は西周早期の金文で、目標を定めいきさつを記すさま。原義は”兵站の管理”。論語の時代までに、”征伐”、”政治”の語義が確認できる。詳細は論語語釈「政」を参照。
論語の本章は『定州竹簡論語』に欠いているが、そこでは通常「正」と書く。すでにあった「政」の字を避けた理由は、おそらく秦帝国時代に、始皇帝のいみ名「政」を避けた名残。加えて”政治は正しくあるべきだ”という儒者の偽善も加わっているだろう。論語語釈「正」も参照。
兄弟(ケイテイ)


(甲骨文)
論語の本章では”きょうだい”。
「兄」の初出は甲骨文。「キョウ」は呉音。甲骨文の字形は「口」+「人」。原義は”口で指図する者”。甲骨文で”年長者”、金文では”賜う”の意があった。詳細は論語語釈「兄」を参照。
「弟」の初出は甲骨文。「ダイ」は呉音。字形の真ん中の棒はカマ状のほこ=「戈」で、靴紐を編むのには順序があるように、「戈」を柄に取り付けるには紐を順序よく巻いていくので、順番→兄弟の意になったとされる。西周末期の金文で、兄弟の”おとうと”の意に用いている。詳細は論語語釈「弟」を参照。
也(ヤ)


(金文)
論語の本章では「かな」と読んで”…だなあ”。詠嘆の意。「なり」と読んで”~である”、断定の意と解することも出来るが、この語義は春秋時代では確認できない。論語の本章は文字史上、全ての漢字が論語の時代まで遡れるので、当時の語義で解するのが理にかなう。
初出は事実上春秋時代の金文。字形は口から強く語気を放つさまで、原義は”…こそは”。春秋末期までに句中で主格の強調、句末で詠歎、疑問や反語に用いたが、断定の意が明瞭に確認できるのは、戦国時代末期の金文からで、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「也」を参照。
日本伝承古注系論語を時系列で追うと、この言葉は日本の南北朝時代に刊行された正平本まではあり、本願寺坊主の手になる文明本(文明は応仁の次の年号)から欠く。この影響で16世紀後半の筆写とみられる足利本にも欠き、寛延三年刊というから徳川綱吉時代の鵜飼本=根本本以降でも欠くのだが、同時代の中国で欠いた版本を見ないから、本願寺坊主が勝手に削除したか、うっかりして記し忘れたかのいずれかになる。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)
論語:付記
検証
論語の本章は前漢中期の定州竹簡論語に欠くが、文字史上は全て論語の時代に遡れるので、とりあえず史実の孔子の言葉として扱う。上掲語釈の通り、「魯」「衛」「之」「政」「也」はもちろん、「兄弟」という対句も西周の金文から確認出来る。
解説
論語の本章は、「兄弟」をどう解するかで文意が異なっている。上掲語釈の通り、漢語「兄弟」には語義によって、兄が上で弟が下という順位関係を意味し得るから、単に”似ている”と解釈できない可能性があるからだ。
現伝の『史記』によれば、魯の開祖周公旦は、周の初代文王の子で、二代武王の弟とされる。三代成王が若くして即位すると、周公旦は摂政となり、殷の残党が起こした反乱を討伐した。討伐後、周公旦は殷の遺民の一部を同じく武王の弟だった衛康叔に預け、諸侯に任じたのが衛の始まりと記す。
「周公旦懼康叔齒少」”周公旦は衛康叔の幼さに不安を感じ”と『史記』衛康叔世家は続けて記すから、魯の開祖周公旦は、衛の開祖康叔より年長だったことになる。論語の本章が「魯衛」を「兄弟」と言うのは、魯が兄貴分で衛が弟分であることを序列をつけて記していることにもなる。
ゆえに、こんにち日本の近所にある頭のおかしな連中の集まりが思い込んでいるように、”政治については、弟分の衛は兄貴分の魯を見習うべきだ”との言外の意を読み取れなくもない。つまり魯の出身である孔子が、上から目線で偉そうに”衛の政治はなっちゃいない”と論評したとも言える。
従って後世の儒者は、当時の衛の君主を「霊公」”国を滅ぼしたバカ殿”と呼び、そのきさきの一人である南子を”淫乱女で孔子をも惑わそうとした”とけなした(論語雍也篇28)。
しかし誰だかよく分からない左丘明や司馬遷や儒者が見てきたようなことを書き散らした史料を除き、南子が淫乱だったという同時代の記録は無く、霊公は有能な家臣をかかえ領民にも慕われ、大国晋の圧迫からもよく国を守ったやり手の殿さまだった(論語憲問篇20)。
ゆえに論語の本章がもし史実の孔子の発言なら、衛を見下すつもりで「兄弟」と言ったとは考えがたい。従って”兄弟のように似ている”と解するのにより理があるように思えるが、一部の後世の儒者が書き散らしたように、”国公が実権を奪われ権臣が好き勝手している”点が”兄弟”なわけではない。
春秋時代後半、魯の国公は確かに実権を失っていたようだし、門閥三家老家=三桓が国政の実権を握っていたのは確かだろう。だがこの事情は同時代の春秋諸侯国のどこでも同じで、その程度に差があったに過ぎない。魯の場合は昭公がやらかしをし過ぎて、多少程度が甚だしくはあったが。
やらかした昭公は国を追われ、若き日の孔子もその逃避行に付き合って斉国まで行った。その際の出来事が、論語顔淵篇11に記された斉の景公との対話になる。いずれにせよ孔子は”魯と衛の政治は、兄弟のように似ているな”と評したのに止まり、見下したわけではありえない。
ではいつ、誰に向かって、何のために孔子は論語の本章のようなことを言ったか。可能性の一つは亡命の当初で、孔子は魯国を出ると真っ直ぐに衛国に向かい、縁故のあった国際傭兵団の頭領だった顔濁鄒親分のやしきにわらじを脱いだ。だがやって来て早々、親分にこう言う動機が無い。
言うとすればすぐに呼ばれたであろう衛の霊公に向かってであり、霊公が「魯ではどの程度俸禄を貰っていたかね?」と聞くと、孔子は「アワ六万(現代換算で約111億円)」ですと答えた。霊公は特に仕事も命じず、ポンと孔子にアワ六万を与えている(『史記』孔子世家)。
孔子は魯では宰相代行だったから、この俸禄は宰相級で安くはなかったはずだ。仕事を命じられなかったのはすでに衛国に人材が揃っていたからで((論語憲問篇20)、カネと暇を持て余した孔子は衛国乗っ取りを企んだふしがあり、霊公にバレると一目散に逃げ出している。
だがその後もたびたび衛国に舞い戻っては滞在した。逗留したのは顔濁鄒親分の屋敷ではななく衛の大貴族・蘧伯玉の屋敷だが(論語憲問篇26)、武力を持った親分とつるむから霊公も恐れたわけで、孔子は「もう悪さはしません」と霊公に一筆書かされたに違いない。
でないと霊公が許すはずが無いからだ。その後は弟子の子路が衛の蒲邑に領地を与えられるなど、そもそも弟子の仕官先を求めて亡命した孔子は、衛国でそのもくろみを達成できたと言える。
子路が蒲の領主になった。しばらくして孔子の滞在先に出向いて挨拶した。
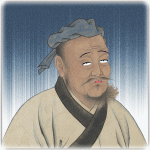
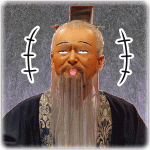
子路「ほとほと参りました。」
孔子「蒲の町人のことじゃな? どんな者どもかね。」
子路「武装したヤクザ者が、町中をぞろぞろと大手を振ってうろついていて、手が付けられません。」(『孔子家語』致思19)
孔子にとって衛は第二の故郷とも言うべきで、たぶん論語の本章は、霊公の機嫌を取るために言った言葉が、後世大げさに騒がれたに過ぎないかも知れない。
論語の本章、新古の注は次の通り。
古注『論語集解義疏』
子曰魯衛之政兄弟註苞氏曰魯周公之封衛康叔之封也周公康叔旣為兄弟康叔睦於周公其國之政亦如兄弟也
本文「子曰魯衛之政兄弟」。
注釈。包咸「魯は周公の領国、衛は康叔の領国である。周公と康叔はもともと兄弟で、康叔は周公によく懐いていた。その国の政治もまた、兄弟のようだった。」
新注『論語集注』
子曰:「魯衛之政,兄弟也。」魯,周公之後。衛,康叔之後。本兄弟之國,而是時衰亂,政亦相似,故孔子歎之。
本文「子曰:魯衛之政,兄弟也。」
魯は周公の末裔で、衛は康叔の末裔である。もともと兄弟の国で、この当時衰えて乱れており、政治もまた互いに似ていたので、だから孔子がこう言って歎いたのである。」
余話
兄弟やめたい
2022年2月21日、軍事侵攻の3日前、ロシアのプーチン大統領は、ロシア・ウクライナ双方の国民に向けて、次のように演説した。原文文字列はロシア連邦大統領府サイトから一部を引用。
Ещё раз подчеркну, что Украина для нас – это не просто соседняя страна. Это неотъемлемая часть нашей собственной истории, культуры, духовного пространства. Это наши товарищи, близкие, среди которых не только коллеги, друзья, бывшие сослуживцы, но и родственники, люди, связанные с нами кровными, семейными узами.
今一度強調しておく。誰が何と言おうと、ウクライナは我々にとって、単なる隣国ではあり得ない。ウクライナは我々がたどってきた独特の歴史、文化、精神風土にとって、欠くことの出来ない一部である。そしてウクライナは我々の同志、近親であり、同僚、友人、元同僚だけでなく、また親戚、血縁、家族の絆を伴う人々であるだけでなく、もっとも近しい人たちでもある。
Издавна жители юго-западных исторических древнерусских земель называли себя русскими и православными. Так было и до XVII века, когда часть этих территорий воссоединилась с Российским государством, и после.
長い間、ロシアの南西部に住む人々は、自分たちをロシア人で、ロシア正教徒だと名乗ってきた。17世紀にこうした地域がロシアに併合される前後から、そうだった。
プーチン大統領はウクライナを「兄弟」のように見立てたばかりでなく、ロシアの一部であると見なしているように聞こえる。一方でウクライナはソ連崩壊以降、親露派と親欧米派の間を行ったり来たりしつつ、ついにはNATO加盟というロシアにとって一線を超えた親欧米路線に舵を切った。
その当否は、両国どちらにとっても外国人である訳者には言う資格が無い。結果として戦争という惨事に至ったことを誰もが知っているだけである。そして抽象化すれば、かつてどんなに一体化した人間関係も、どちらか一方でも離れたがったら、それはもう幸福な関係ではないということだ。
ロシアはウクライナを自分の一部であると思いたがり、巨大な軍事力を用いて、ウクライナが自分から離れていくのを止めようとした。だが鎧袖一触でロシアの勝利に終わると思われていた戦争に、ウクライナが猛然と抵抗したことでロシアの思惑はその通りにはならなかった。
これはロシア人が思うほど、ウクライナ人はロシア人と一体だと思っていないのを示している。что”誰が何と言おうと”とプーチン大統領がЕщё раз подчеркну”もう一度強調し”ても、ウクライナの人々はロシアのчасть”一部”だと思われるのは、もうこりごりだと言っている。
再度プーチン大統領の同じ演説の一部を引用する。
Важно понимать и то, что Украина, по сути, никогда не имела устойчивой традиции своей подлинной государственности.
次の事実を納得するのは重要だ。つまりどう言おうとも、実際に、ウクライナは真の国家としての伝統など持ってこなかったのだ。
つたないながらもロシア語読みとして、これはおかしいと思うしかない。世論に迎合して、ロシア語が分かる分からないにかかわらず、ロシア人の異常さや間抜けを言いふらす者どもを、訳者はずっと毛嫌いしてきたが、だからといって親露派ではないし、ロシアの回し者でも決してない。
ゆえにキエフ大公国がルーシ(東スラヴ人諸国の古称)最古のгосударство”国家”だったのを全く疑ってこなかったし、キエフ大公国とその継承国家が、当時ウクライナと名乗っていなかったからと言って、ウクライナに国家としての実質が無かったという主張は、とうてい史実と認めがたい。
だがプーチン大統領ほどの運と知性と肉体に恵まれても、こう言うしかなかった。戦争による蛮行のどれ一つも「しょうがなかった」などと言えない。言えないが、こんなことを言わないと、核兵器まで持った大国が、自国を保てず、「兄弟」を踏みにじらないと生きていけないとは!
本稿を書いている2023年5月初頭、戦争は一向に終わる気配が見えない。ウクライナの人々が、ロシアの一部に戻るのを承知するとは思えないが、同様にかつてロシア革命の頃、ウクライナはロシアとは別になろうと努力した。それをロシアが暴力で踏みにじって出来たのがソ連だった。
つまりウクライナがロシアの一部でないと、ロシア人が承知するとも思えない。確かにプーチン大統領が演説で指摘した通り、ウクライナ支配下でロシア人を自認する人たちは、文明国とは思えない悲惨な目に遭わされた。だがどちらかが承知しかねることを承知しないと、戦争は終わりそうにない。
どちらが承知すべきだと言う権利など訳者は持たない。ただひたすら、無念に亡くなった両国の人たちを悼み、一刻も早く、この戦争が終わるのを祈るような気持ちで望むことしかできない。だがこうは言えるか。我が彼を必要と感じた時は常に、彼は我を必要としていない。
だからそういう取引には、暴力か嘲笑のいずれかが伴うのだろう。
なお無神論の訳者が戦争の終結を祈るような気持ちで願うのは、偽善ではなくきわめて実利的理由による。ブッダが諸行無常、一切皆苦と見抜いたとおり、現代物理学も全ての存在が一瞬の滞りも無く滅んでいると言っている。そんな宇宙で生きるのはまじめに考えれば苦痛でしかない。
人類界だけはそうでない理性や人情が働く、と思える人が少ないほど、人は怯えて少しでも誰かから奪おうとする。物質的にも、精神的にも。戦争の恐怖がのしかかる世の中は、輪を掛けて生きるのが苦しい。生きるに値しない世の中を、自ら去らないのは恐怖と面倒くささしか理由がない。
だから祈るような気持ちで願っている。一刻も早く、戦争が終わることを。






コメント