論語:原文・白文・書き下し
原文・白文
子夏曰、「日知其所亡、月無忘其所能、可謂好學也已矣。」
復元白文(論語時代での表記)





















※論語の本章は、「也」の用法に疑問がある。
書き下し
子夏曰く、日に其の所の亡きを知り、月に其の所の能ふるを忘るる無からば、學を好むと謂ふ可き也る已矣。
論語:現代日本語訳
逐語訳
子夏が言った。「もしまことに毎日自分にない所を知り、もしまことに毎月自分に出来ることを忘れないのなら、学問を好むと評価してしまってよい。」
意訳
子夏「毎日必ず、自分に出来ない事を身につけようと励み、毎月必ず、出来たことを忘れぬようおさらいするなら、学問好きだと言って良いだろうな。」
従来訳
子夏がいった。――
「日ごとに自分のまだ知らないことを知り、月ごとに、すでに知り得たことを忘れないようにつとめる。そういう心がけであってこそ、真に学問を好むといえるだろう。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
子夏說:「每天都學到些新東西,每月都不忘所學會的東西,就算好學了。」
子夏が言った。「毎日必ず少しでも新しいことを学び、毎月必ず学んだことを忘れないようにすれば、それだけで学問好きと言ってよい。」
論語:語釈
子夏

論語では孔子の弟子で孔門十哲の一人、卜商子夏のこと。師匠の孔子からは「足りない奴」と言われ(論語先進篇15)、陽気な性格が全く見えない陰気くさい人物。その弟子筋について、戦国末期の儒者だった荀子は、遠慮無くこき下ろしている。

冠と装束をもっとももらしく身につけ、取り澄ました表情を見せ、黙ったまま一日中ものを言わないで、お布施だけ貰って帰る連中は、子夏の系統を引く腐れ儒者だ。(『荀子』非十二子篇17)
其(キ)


(金文)
論語の本章では多様な解釈があり得る。原義は農具の箕で、漢文では多くの場合”その”という指示詞。本章では指事代詞として”自分の”として解しうるが、他に疑問の”もし”とも解せるし、意味内容を持たない助辞として解することも出来る。
だが最も明解な解釈は、仮定を強調する意を示すと解することで、「もし”まことに”カクカクシカジカの事をするならば」という、子夏らしいもったいぶったお説教の強めと見ることが出来る。詳細は論語語釈「其」を参照。
所亡


(金文)
論語の本章では”欠けた部分”。「所亡」の句は「亡き所」と読めるように、被修飾語→修飾語という、太古を除き漢語にあり得べからざる語順に見えるが、論語でも頻出だから、修飾関係に読むのは実は正しくない。「所の亡き」と主述関係に捉えるべきで、これは「所能」も同じ。
「所」「亡」について詳細は論語語釈「所」・論語語釈「亡」を参照。
謂(イ)

(金文)
論語の本章では、”~だと評価する”。同じ「いう」でも、価値判断を行って品定めすることを意味する。詳細は論語語釈「謂」を参照。
也(ヤ)


(金文)
論語の本章では、「なり」と読んで断定の意に用いている。初出は事実上春秋時代の金文。字形は口から強く語気を放つさまで、原義は”…こそは”。春秋末期までに句中で主格の強調、句末で詠歎、疑問や反語に用いたが、断定の意が明瞭に確認できるのは、戦国時代末期の金文からで、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「也」を参照。
已矣
伝統的な読みでは、「也已矣」三字で「のみ」と読み下す。「也」は断定、「已」は”終わる”、「矣」もまた断定・完了。直訳すると”~であってしまったのである・~であってしまってしまった”。
論語の本章は定州竹簡論語に無いことから、あるいは後漢になってからの創作とも考えられるのだが、定州竹簡論語にある章でも、句末を本章のようにもったいを付けた言い廻しに引き延ばした例があり、本章もまたこの部分は、後漢以降の改変を受けているかもしれない。
辞書的には論語語釈「已」・論語語釈「矣」を参照。「矣」は論語の時代に存在しない。
論語:付記
論語の本章は、上記の検証通り、文字史的には史実を疑えないが、後漢末の徐幹著、『中論』治学2に、「子夏曰、日習、則學不忘。自勉、則身不墮。亟聞天下之大言、則志益廣。」とあるから↓、定州竹簡論語に無いことも含め、後漢儒の作品である可能性がある。

子夏が言った。「毎日勉強すれば、学んだことを忘れない。自発的に努力すれば、だらしのない人間に落ちない。天下の重大事をいつも耳にしていれば、志はどんどん拡がる。」
古注では前漢の孔安国が注を付けているが、孔安国は存在そのものが疑わしい。
註孔安國曰日知其所未聞也
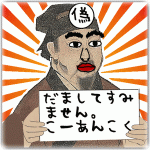
孔安国「”日知其所”とは、まだ聞いていないことだ。」(『論語集解義疏』)

結局本章の印象批評として、「極めてつまらない」「現伝の子夏なら言い出しかねない」と言うしかないが、こういうつまらない話を後世になって、子夏にぺたぺたと貼り付けた可能性もあるから断言できない。だが中国儒者も「つまらない」とは思ったようだ。
だから清末の儒者・陳澧は、一生懸命言い訳している。

子夏が「日知其所亡、月無忘其所能」と言ったのを読むと、実に浅はかで下らない説教に思える。だがこの二つは、実は学問の定法なのだ。
学問の定法とは何かを考えてみると、新しいことを知るのが知る法であり、おさらいするのが忘れない法であり(論語為政篇11)、知ったものは知ったと言えるし、知ったことを仁で守れば忘れない(論語衛霊公篇33)。
良いものを選ぶことは知と言えるし、固執する者は忘れない。よく勉強する者は知と言えるし、自分で推論できる者も忘れない。この二つを知っている者は知と言えるし、ここから離れない者は忘れない。
穏やかさを日頃から保つ者は知と言えるし、無くさないように努める者は忘れない。四書=『論語』『孟子』『大学』『中庸』の書は、このことわりで書かれている。(『東塾読書記』巻一31)
訳者の訳が下手くそなこともあるが、何を言っているかさっぱりわからず、言い訳として成立しているとは思えないが、それは理の当然だ。清儒の公式思想は朱子学で、朱子学は四書を重んじるとともに、儒教に易や理気学を大量に持ち込んだ。要するにオカルトである。
そもそも孔子の思想では、「学を好む」ことにそれほど価値はなかった。論語為政篇14にあるように、「学問を好むだけでは君子と言えない」からだ。学問は修養の入り口であり、本章の言うように、自分に欠けた点を常に意識しているなら、入り口の段階をとうに超えている。
「知るを知るとし、知らざるを知らざる」なら、それはすでに「知」だから(論語為政篇17)でもある。だが現伝の子夏は孔子の意図を理解できなかったか、あるいは儒者は自分たちが独占した「知」というものを、よほど価値あるものとして売り出したかったらしい。
現代の造形師による手作りフィギュアが、時に百万を超える高額で取引されるのは、その貴重さゆえだ。昭和のある時からエロ本のたぐいは、中身が見えないように店頭に並べる規制が入ったが、それで売れなくなったという話は聞かない。かえって想像力が高まるのでは?
朱子学以降の儒学も同様で、わけ分からんからこそ価値があった。この傾向は朱子をはるかにさかのぼる後漢の時代から目立つようになったが、実在の孔子や直弟子は、そういうオカルトで人をたぶらかしはしたろうが、自分まで狂信者になっている余裕は無かった。
さらに詳細は「孔子はなぜ偉大なのか」を参照。






コメント