論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
點爾何如鼓瑟希鏗爾舍瑟而作對曰異乎三子者之撰子曰何傷乎亦各言其志也曰莫春者春服旣成冠者五六人童子六七人浴乎沂風乎舞雩詠而歸夫子喟然歎曰吾與點也
校訂
武内本
鏗爾、説文摼爾。撰鄭本撰に作り読みて詮となす、詮とは善なり。暮、唐石経莫に作る。浴筆解沿に作る。
※詮とは善なり:『経典釈文』巻二十四「鄭作僎讀曰詮詮之言善也」
沿:韓愈『論語筆解』、墨海金壺本、欽定四庫全書本巻二「童子六七人浴乎沂風乎舞雩詠而歸」
東洋文庫蔵清家本
點爾何如鼓瑟希/鏗爾舍瑟而作對曰異乎三子者之撰/子曰何傷乎亦各言其志也/曰莫春者春服旣成冠者五六人童子六七人浴乎沂風乎舞雩詠而歸/夫子喟然歎曰吾與點也
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
「點!壐何如?」鼓瑟[希,□壐舍瑟而]303作,對曰:「[異乎]三子者之[撰]。」[子]曰:「何傷a?亦各言其志也。」304「莫b春者,春服[![]() b成,冠c者五六人,童子六七]人,浴乎沂,305風乎舞雩,咏d而歸e。」夫子喟[然]□[曰]:「吾與點也!」
b成,冠c者五六人,童子六七]人,浴乎沂,305風乎舞雩,咏d而歸e。」夫子喟[然]□[曰]:「吾與點也!」
- 今本”傷”下有”乎”字。
- 莫、皇本作”暮”、『釋文』”莫春、音暮、本亦作暮”。
 、今本作”既”。
、今本作”既”。- 皇本”冠”上有”得”字。
- 咏、今本作”詠”。
- 而歸、『釋文』云”而歸、鄭本作饋、饋酒食也”。
※f:歸ki̯wər(平)、饋gʰi̯wæd(去)で音が合わない。
標点文
「點、壐何如。」鼓瑟希、鏗壐舍瑟而作、對曰、「異乎三子者之撰。」子曰、「何傷。亦各言其志也。」「莫春者、春服![]() 成、冠者五六人、童子六七人、浴乎沂、風乎舞雩、咏而歸。」夫子喟然歎曰、「吾與點也。」
成、冠者五六人、童子六七人、浴乎沂、風乎舞雩、咏而歸。」夫子喟然歎曰、「吾與點也。」
復元白文(論語時代での表記)
點 


 瑟希 鏗
瑟希 鏗
 瑟
瑟












 傷
傷



 志
志





























 喟
喟 歎
歎

 點
點
※撰→選・冠→(甲骨文)・沂→(金文大篆)・風→(甲骨文)。論語の本章は赤字が論語の時代に存在しない。「爾」(壐)「何」「如」「異」「乎」「服」「詠」「咏「然」の用法に疑問がある。本章は前漢帝国の儒者による創作である。
書き下し
點壐は何如。瑟を鼓くこと希なり。鏗壐く瑟を舍い而作ち、對へて曰く、三子者之撰み乎異なれり。子曰く、何ぞ傷まん。亦各〻其の志を言へる也。莫春に者春服![]() に成り、冠者五六人、童子六七人、沂乎浴み、舞雩乎風み、詠ひ而歸らむ。夫子喟然として歎じて曰く、吾は點に與する也。
に成り、冠者五六人、童子六七人、沂乎浴み、舞雩乎風み、詠ひ而歸らむ。夫子喟然として歎じて曰く、吾は點に與する也。
論語:現代日本語訳
逐語訳


先生が言った。「点(曽皙)よ、お前はどうだ。」
曽皙は大琴をつま弾いていたが、手荒に琴を置いて姿勢を正し、答えて言った。「お三方とは異なります。」先生が言った。「何を気にしているのか。同じようにそれぞれの志を言ったまでだぞよ。」曽皙は言った。「晩春、もう春服はすっかり身に付き、若者五・六人、子供七・八人と共に、沂水で水浴びし、雨乞い台の上で風に吹かれ、歌を歌って帰りたいものです。」先生がため息をついて行った。「私は点に賛成だ。」
意訳


孔子「曽皙、お前は。」
曽皙「♪チィ~ン・トォ~ン・シャァ~ン。…ガタン!」
曽皙「失礼しました。私の考えはお三方とは違いますので。」
孔子「遠慮せんでもいい。思うまま言え、と言ったのは私だぞ。」
曽皙「それでは失礼ながら…春の遅い頃、そうですね、もう春服がすっかり体になじんだ頃、若者や子供達を連れて沂水で水浴びし、雨乞い台の上で風に吹かれて乾かし、歌でも歌って帰りましょうか。」
孔子「うむうむ、それがいい!」
従来訳
先師、――
「点よ、お前はどうだ。」
曾皙は、それまで、みんなのいうことに耳をかたむけながら、ぽつん、ぽつんと瑟しつを弾じていたが、先師にうながされると、がちゃりとそれをおいて立ちあがった。そしてこたえた。――
「私の願いは、三君とはまるでちがっておりますので……」
先師、――
「何、かまうことはない。みんなめいめいに自分の考えていることをいって見るまでのことだ。」
曾皙――
「では申しますが、私は、晩春のいい季節に、新しく仕立てた春着を着て、青年五六人、少年六七人をひきつれ、沂き水で身を清め、舞雩で一涼みしたあと、詩でも吟じながら帰って来たいと、まあそんなことを考えております。」
すると先師は深い感歎のため息をもらしていわれた。――
「私も点の仲間になりたいものだ。」下村湖人先生『現代訳論語』
現代中国での解釈例
「曾點,你怎樣?」曾皙彈琴正接近尾聲,他鏗地一聲放下琴,站起來說:「我與他們三位不同。」孔子說:「說說有什麽關繫?衹是各談各的志向而已。」曾點說:「暮春三月,穿上春天的衣服,約上五六人,帶上六七個童子,在沂水邊沐浴,在高坡上吹風,一路唱著歌而回。」夫子感嘆說:「我欣賞曾點的情趣。」
「曽点、お前はどうだ?」曽皙は琴を弾いて終わりかけており、カーンと高く奏でて琴を手放し、立ち上がって言った。「私は彼ら三人とは違います。」孔子が言った。「まあ言いなさい。何の関係がある?ただ各々の志を言ったまでだ。」曽点が言った。「晩春三月、春向けの服を着て、五六人ほどと共に、六七人の子供を連れ、沂水のほとりで水浴びし、堤防の上で風に吹かれ、一通り歌を歌って帰ります。」先生は感嘆して言った。「私は曽点の思いを賞賛する。」
論語:語釈
「 點、壐(爾) 何 如。」 鼓 瑟 希、鏗 壐(爾)、舍 瑟 而 作。對 曰、「異 乎 三 子 者 之 撰。」子 曰、「何 傷 乎。亦 各 言 其 志 也。」(曰、)「莫 春 者、 春 服 ![]() (旣) 成。 冠 者 五 六 人、童 子 六 七 人。浴 乎 沂、風 乎 舞 雩、咏 而 歸。」夫 子 喟 然 歎 曰、「吾 與 點 也。」
(旣) 成。 冠 者 五 六 人、童 子 六 七 人。浴 乎 沂、風 乎 舞 雩、咏 而 歸。」夫 子 喟 然 歎 曰、「吾 與 點 也。」
點*(テン)


(隷書)
曽子の父、曾點(曽点)子皙。曽子が孔子より46年少だから、孔子より25年ほど年下かと思われる。子の曽子に対するサディストとして戦国中期の孟子以降の儒者に知られた(下掲解説参照)。実在はしたのだろうが、そもそも曽子が孔子の弟子ではなく(論語の人物・曽参子輿)、その父親は儒者でも孔子の弟子でもない、名も無き農民だったのはほぼ確実。
「點」は論語では本章のみに登場。新字体は「点」。初出は前漢中期の定州竹簡論語。論語の時代に存在しない。固有名詞のため同音近音のいかなる漢字も置換候補になり得るが、その比定は意味ある作業と思えない。戦国最末期の『呂氏春秋』に曽子の父の名として見えるので、それまでにはそのような存在として知られていた。戦国時代までの用例は全て人名で、漢初の『爾雅』になって初めて人名以外の、”打ち消しを點という”の記述が見える。詳細は論語語釈「点」を参照。
『史記』によるあざ名は「蒧」(テン、草の名)だが、初出も上古音も不明。『史記』異本によるとあざ名は「𪒹」(カン、色が黒い)だが、カールグレン上古音は不明、初出は後漢の説文解字。
爾(ジ)→壐(ジ)
論語の本章、「爾何如」では”お前”。「鏗爾」では”~であるさま”。後者の語義は春秋時代では確認できない。


(甲骨文)
「爾」の初出は甲骨文。字形は剣山状の封泥の型の象形で、原義は”判(を押す)”。のち音を借りて二人称を表すようになって以降は、「土」「玉」を付して派生字の「壐」「璽」が現れた。甲骨文では人名・国名に用い、金文では二人称を意味した。詳細は論語語釈「爾」を参照。


(秦系戦国文字)
定州竹簡論語の「壐」の初出は斉系戦国文字。ただし字体は「鉨」。現行字体の初出は秦戦国文字。下が「玉」になるのは後漢の『説文解字』から。字形は「爾」”はんこ”+「土」または「玉」で、前者は封泥、後者は玉で作ったはんこを意味する。部品の「爾」が原字。「璽」は異体字。同音は無い。戦国最末期「睡虎地秦簡」の用例で”印章”と解せる。論語時代の置換候補は部品の「爾」。詳細は論語語釈「壐」を参照。
何如(いかん)


論語の本章では”どうだ”。「何」が「如」=”同じ”か、の意。対して「如何」は”どうしよう”・”どうして”。
- 「何・如」→何に従っているか→”どうでしょう”
- 「如・何」→従うべきは何か→”どうしましょう”・”どうして”。
「いかん」と読み下す一連の句形については、漢文読解メモ「いかん」を参照。


「何」(甲骨文)
「何」は論語の本章では”なに”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は「人」+”天秤棒と荷物”または”農具のスキ”で、原義は”になう”。甲骨文から人名に用いられたが、”なに”のような疑問辞での用法は、戦国時代の竹簡まで時代が下る。詳細は論語語釈「何」を参照。


「如」(甲骨文)
「如」は論語の本章では”…のような(もの)”。この語義は春秋時代では確認できない。
”あるいは”の語義は前回の「率」と同様、前漢儒者のやらかしたハッタリで、本章を古くさく見せるため、「與」ȵi̯o(平)”…と”→”あるいは”と書くべきところ、音の近い「如」zi̯o(上)を引っ張ってきて、無理やり”…と”という語義をこしらえた。こんな読み方は、後世の猿真似を除けば、やはり前漢儒者がでっち上げた『儀礼』の「公如大夫」ぐらいしかない。
字の初出は甲骨文。字形は「口」+「女」。甲骨文の字形には、上下や左右に部品の配置が異なるものもあって一定しない。原義は”ゆく”。詳細は論語語釈「如」を参照。
鼓(コ)


(甲骨文)
論語の本章では”奏でる”。初出は甲骨文。字形は「壴」”日時計に下げられた皮を張った太鼓”+「攴」”ばちを取って打つ”。太鼓を鳴らすさま。甲骨文では”太鼓を打つ”のほか、地名・人名と解せる例がある。春秋末期までに、”鳴らす”・”太鼓”の意に用いた。詳細は論語語釈「鼓」を参照。
瑟(シツ)


(楚系戦国文字)
論語の本章では”おおごと”。弦の多い琴の一種。『学研漢和大字典』は「もと五十弦」という。事実上の初出は楚系戦国文字。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。戦国文字の字形は多様で、ただし「兀」(ゴツ)形を必ず含む。おそらくテーブル状の楽器を示すか。同音は存在しない。楚系戦国文字に楽器の名として見える。秦系戦国文字には見えない。詳細は論語語釈「瑟」を参照。
希(キ)


(秦代隷書)
論語の本章では”途切れがちに”。間を置いて琴の弦を弾いて音を出すさま。初出は戦国末期の隷書で、論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。同音は「屎」”くそ”のほかは「希」を部品とする漢字群。字形は「爻」”占いの卦”+「巾」”垂れ帯”で、原義は不詳。文献ではまず”まれ”の意に用い、次いで”望む”の意に用いた。詳細は論語語釈「希」を参照。
鏗*(コウ)


(隷書)
論語の本章では”手荒に”。「鏗爾」で”鏗であるさまで”という副詞になる。古注で孔安国が言う「鏗爾者投瑟之聲也」”鏗爾とは琴を放り投げた音である”というのは、めずらしく理にかなっている。
字の初出は不明。定州竹簡論語も欠字となっており存在証明にならない。論語の時代に存在しない。字形は「金」+音符「堅」。カンカンと鐘を打つさま。同音は存在しない。『楚辞』招䰟に「鏗鍾搖虡」とあり、「鐘をうたば鐘柱を搖らす」と読める。詳細は論語語釈「鏗」を参照。
舍(シャ)


(甲骨文)
論語の本章では”(琴を)置く”。初出は甲骨文。新字体は「舎」。下が「𠮷」で「舌」ではない。字形は「𠆢」”屋根”+「干」”柱”+「𠙵」”くち=人間”で、人間が住まう家のさま。原義は”家屋”。春秋末期までの金文では”捨てる”、”与える”、”発布する”、”楽しむ”の意、また人名に用い、戦国の金文では一人称に用いた。戦国の竹簡では人名に用いた。
而(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”そして”。初出は甲骨文。原義は”あごひげ”とされるが用例が確認できない。甲骨文から”…と”を意味し、金文になると、二人称や”そして”の意に用いた。英語のandに当たるが、「A而B」は、AとBが分かちがたく一体となっている事を意味し、単なる時間の前後や類似を意味しない。詳細は論語語釈「而」を参照。
作(サク)


(甲骨文)
論語の本章では”姿勢を正す”。”立ち上がって敬意を示す”とも解せるが、師弟の問答に一人だけ立ち上がってごそごそ言うのは無理があるように思う。初出は甲骨文。金文まではへんを欠いた「乍」と記される。字形は死神が持っているような大ガマ。原義は草木を刈り取るさま。”開墾”を意味し、春秋時代までに”作る”・”定める”・”…を用いて”・”…とする”の意があったが、”突然”・”しばらく”の意は、戦国の竹簡まで時代が下る。詳細は論語語釈「作」を参照。
對曰(こたへていはく)
論語の本章では”回答として言った”。論語では多くの場合、目上から問われて答える場合に用いるが、論語憲問篇14のように身分同格の年長者が答える場合にも用いており、身分差を示す言葉ではない。


(甲骨文)
論語の本章では”回答する”。初出は甲骨文。新字体は「対」。「ツイ」は唐音。字形は「丵」”草むら”+「又」”手”で、草むらに手を入れて開墾するさま。原義は”開墾”。甲骨文では、祭礼の名と地名に用いられ、金文では加えて、音を借りた仮借として”対応する”・”応答する”の語義が出来た。詳細は論語語釈「対」を参照。


(甲骨文)
「曰」は論語で最も多用される”言う”を意味することば。初出は甲骨文。原義は「𠙵」=「口」から声が出て来るさま。詳細は論語語釈「曰」を参照。
異(イ)


(甲骨文)
論語の本章では”ことなる”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。甲骨文の字形は頭の大きな人が両腕を広げたさまで、甲骨文では”事故”と解読されている。災いをもたらす化け物の意だろう。金文では西周時代に、”紆余曲折あってやっと”・”気を付ける”・”補佐する”の意で用いられている。”ことなる”の語義の初出は、戦国時代の竹簡。詳細は論語語釈「異」を参照。
乎(コ)


(甲骨文)
論語の本章では、「に」と読んで”…と比較して”・”…で”の意。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は持ち手の柄を取り付けた呼び鐘を、上向きに持って振り鳴らし、家臣を呼ぶさまで、原義は”呼ぶ”こと。甲骨文では”命じる”・”呼ぶ”を意味し、金文も同様で、「呼」の原字となった。句末の助辞として用いられたのは、戦国時代以降になるという。詳細は論語語釈「乎」を参照。
三子者(サンシシャ)
論語の本章では”お三方”。逐語訳すれば”三人の君子である人”。


(甲骨文)
「三」の初出は甲骨文。原義は横棒を三本描いた指事文字で、もと「四」までは横棒で記された。「算木を三本並べた象形」とも解せるが、算木であるという証拠もない。詳細は論語語釈「三」を参照。


(甲骨文)
「子」の初出は甲骨文。字形は赤ん坊の象形。春秋時代では、貴族や知識人への敬称に用いた。季康子や孔子のように、大貴族や開祖級の知識人は「○子」と呼び、一般貴族や孔子の弟子などは「○子」と呼んだ。詳細は論語語釈「子」を参照。


(金文)
「者」は論語の本章「三子者」ではお三”方”・「暮春者」では晩春”は”・「冠者」では若”者”の意。新字体は「者」(耂と日の間に点が無い)。初出は殷代末期の金文。金文の字形は「木」”植物”+「水」+「口」で、”この植物に水をやれ”と言うことだろうか。原義は不明。初出では称号に用いている。春秋時代までに「諸」と同様”さまざまな”、”~する者”・”~は”の意に用いた。漢文では人に限らず事物にも用いる。詳細は論語語釈「者」を参照。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章では”…の”。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義は”これ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”…の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。
撰*(サン/セン)


論語の本章では”選択内容”。論語では本章今回部分のみに登場。初出は前漢の隷書。論語の時代に存在しない。字形は「扌」+音符「巽」”捧げる”。論語の本章のほかは、漢初になって『礼記』などに見られ、”手に取る”・”栗の実の皮を剝ぐ”・”えらぶ”などの用例がある。論語時代の置換候補は日本語で同音同訓の「選」。詳細は論語語釈「撰」を参照。
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
傷(ショウ)


(燕系戦国文字)
論語の本章では”気に病む”。初出は燕系戦国文字。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。同音は「商」「賞」「湯」「傷」とつくりを同じくする漢字群、「殤」”若死に・そこなう”、「觴」「禓」”道の祭・追儺”。字形は「昜」”木漏れ日”+「人」。字形の由来や原義は明瞭でない。戦国文字では、〔昜刂〕〔昜戈〕の字形も「傷」字に比定されている。部品「昜」の初出は甲骨文。詳細は論語語釈「傷」を参照。
亦(エキ)


(金文)
論語の本章では”また同様に”。初出は甲骨文。字形は人間の両脇で、派生して”…もまた”の意に用いた。”おおいに”の意は甲骨文・春秋時代までの金文では確認できず、初出は戦国早期の金文。のちその意専用に「奕」の字が派生した。詳細は論語語釈「亦」を参照。
論語の本章は前漢代の偽作が確定しているので、”おおいに”と解してもかまわないように見える。だが答えを渋る曽皙に対して、「亦各言其志也」”(わしの問いに対して子路と冉有は)大いにそれぞれの抱負を言ったまでだ”よりも、”同様に抱負を言ったまでだ”と解した方が文意がはっきりする。
各(カク)
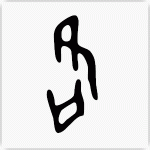

(甲骨文)
論語の本章では”それぞれ”。初出は甲骨文。字形は「夊」”あし”+「𠙵」”くち”で、人がやってくるさま。原義は”来る”。甲骨文・金文では原義に用いた。”おのおの”の意も西周の金文で確認できる。詳細は論語語釈「各」を参照。
言(ゲン)


(甲骨文)
論語の本章では”言う”。初出は甲骨文。字形は諸説あってはっきりしない。「口」+「辛」”ハリ・ナイフ”の組み合わせに見えるが、それがなぜ”ことば”へとつながるかは分からない。原義は”言葉・話”。甲骨文で原義と祭礼名の、金文で”宴会”(伯矩鼎・西周早期)の意があるという。詳細は論語語釈「言」を参照。
其(キ)


(甲骨文)
論語の本章では”その者の”という指示詞。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「𠀠」”かご”。それと指させる事物の意。金文から下に「二」”折敷”または「丌」”机”・”祭壇”を加えた。人称代名詞に用いた例は、殷代末期から、指示代名詞に用いた例は、戦国中期からになる。詳細は論語語釈「其」を参照。
志(シ)


(金文)
論語の本章では”こころざし”。『大漢和辞典』の第一義も”こころざし”。初出は戦国末期の金文で、論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補は”知る”→「識」を除き存在しない。字形は「止」”ゆく”+「心」で、原義は”心の向かう先”。詳細は論語語釈「志」を参照。
「志」が戦国時代になって漢語に現れたのは、諸侯国の戦争が激烈化し、敗戦すると占領され併合さえ、国の滅亡を意味するようになってからで、領民に「忠君愛国」をすり込まないと生き残れなくなったため。つまり軍国美談や戦時スローガンのたぐいと言ってよい。
也(ヤ)


(金文)
論語の本章では、「かな」と読んで”…だよ”・”…なあ”。詠嘆の意。断定の語義は春秋時代では確認できない。初出は事実上春秋時代の金文。字形は口から強く語気を放つさまで、原義は”…こそは”。春秋末期までに句中で主格の強調、句末で詠歎、疑問や反語に用いたが、断定の意が明瞭に確認できるのは、戦国時代末期の金文からで、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「也」を参照。
暮*(ボ)→莫(ボ)


(三国隷書)
論語の本章では”時期的に遅い…”。唐石経・清家本はこの「暮」字で記す。論語では本章のみに登場。定州竹簡論語では「莫」と記すが、もともと「莫」は”日暮れ”の意で、時代と共に多義語化したので、三国時代ごろになって”暮れる”専用の字として「暮」と書くようになった。詳細は論語語釈「暮」を参照。
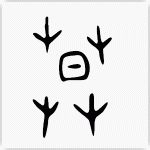

(甲骨文)
定州竹簡論語は「莫」と記す。字の初出は甲骨文。漢音「ボ」で”暮れる”、「バク」で”無い”・”かくす”を示す。字形は「茻」”くさはら”+「日」で、平原に日が沈むさま。原義は”暮れる”。甲骨文では原義のほか地名に、金文では人名、”墓”・”ない”の意に、戦国の金文では原義のほか”ない”の意に、官職名に用いた。詳細は論語語釈「莫」を参照。
論語の伝承について詳細は「論語の成立過程まとめ」を参照。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)
春*(シュン)


(金文)
論語の本章では季節の”はる”。論語では本章のみに登場。初出は甲骨文。甲骨文の字形は多様で、現行字形の祖と思われる形は「木」+”木の芽”+「日」。甲骨文には「今春」「来春」「于春」などが見え、”はる”の意と解せる。西周期には用例が一旦途絶えるが、”はる”を何と記したか明らかでない。詳細は論語語釈「春」を参照。
服(フク)


(甲骨文)
論語の本章では”衣服”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。”衣類”の語義は春秋時代では確認できない。字形は「凡」”たらい”+「卩」”跪いた人”+「又」”手”で、捕虜を斬首するさま。原義は”屈服させる”。甲骨文では地名に用い、金文では”飲む”・”従う”・”職務”の用例がある。詳細は論語語釈「服」を参照。
旣(キ)→ (キ?)
(キ?)


(甲骨文)
論語の本章では”すでに”。唐石経・清家本はこの「旣」字で記す。字の初出は甲骨文。字形は「皀」”たかつきに盛っためし”+「旡」”口を開けた人”で、腹いっぱい食べ終えたさま。「旣」は異体字だが、文字史上はこちらを正字とするのに理がある。原義は”…し終えた”・”すでに”。甲骨文では原義に、”やめる”の意に、祭祀名に用いた。金文では原義に、”…し尽くす”、誤って「即」の意に用いた。詳細は論語語釈「既」を参照。
定州竹簡論語は「![]() 」と記す。上半分が「氵」「既」、その下に「土」で、『大漢和辞典』によると音は「ガイ」、「墍」”ぬる・かざる・とる・いこう”の異体字という。もちろんこの語義では論語の本章を解釈することは出来ない。
」と記す。上半分が「氵」「既」、その下に「土」で、『大漢和辞典』によると音は「ガイ」、「墍」”ぬる・かざる・とる・いこう”の異体字という。もちろんこの語義では論語の本章を解釈することは出来ない。
略体でunicodeに「𡒖」(既の左半分が郎の左半分と同じ)があり、『大漢和辞典』では「![]() 」と同字として扱っている。論語の本章では「爾」をわざわざ「壐」と書いているのと同じく、全く意味の無い漢儒のもったい付けで、まじめに検討する価値を感じない。
」と同字として扱っている。論語の本章では「爾」をわざわざ「壐」と書いているのと同じく、全く意味の無い漢儒のもったい付けで、まじめに検討する価値を感じない。
なお前後の漢帝国を通じて、「爾」「旣」ともに避諱の対象になっていない。
成(セイ)


(甲骨文)
論語の本章では”出来上がる”。初出は甲骨文。字形は「戊」”まさかり”+「丨」”血のしたたり”で、処刑や犠牲をし終えたさま。甲骨文の字形には「丨」が「囗」”くに”になっているものがあり、もっぱら殷の開祖大乙の名として使われていることから、”征服”を意味しているようである。いずれにせよ原義は”…し終える”。甲骨文では地名・人名、”犠牲を屠る”に用い、金文では地名・人名、”盛る”(弔家父簠・春秋早期)に、戦国の金文では”完成”の意に用いた。詳細は論語語釈「成」を参照。
冠者(カンジャ)
論語の本章では”成年男子”。日本語では「かじゃ」と読んで”若者”の意がある。


(甲骨文)/(金文)
「冠」の初出は甲骨文。字形はA形の冠をかぶった頭の大きな人で、この語は殷周革命で一旦滅び、春秋の字形はA形の下に「巾」”垂れ布”+「丨」”ぶら下がるもの”で、単純な頭巾のような殷の冠と異なり、ぞろぞろとぶら下げ物が付いた形。甲骨文の用例は欠損が多くて語義を求めがたいが、春秋の金文では”かんむり”と解せる。詳細は論語語釈「冠」を参照。
五六人(ゴリクジン)
論語の本章では”五六人ほど”。「ゴロクニン」は呉音。読み下した場合は「いつむたり」。


(甲骨文)
「六」の初出は甲骨文。「ロク」は呉音。字形は「入」と同じと言うが一部の例でしかないし、例によって郭沫若の言った根拠無き出任せ。字形の由来と原義は不明。屋根の形に見える、程度のことしか分からない。甲骨文ですでに数字の”6”に用いられた。詳細は論語語釈「六」を参照。


(甲骨文1・2)
「五」の初出は甲骨文。甲骨文の字形には五本線のものと、線の交差のものとがある。前者は単純に「5」を示し、後者はおそらく片手の指いっぱいを示したと思われる。音読みは呉音でも漢音でも「ゴ」。甲骨文の時代から数字の「5」を意味した。西周以降に、人名や官職名の例が見られる。詳細は論語語釈「五」を参照。


(甲骨文)
「人」の初出は甲骨文。原義は人の横姿。「ニン」は呉音。甲骨文・金文では、人一般を意味するほかに、”奴隷”を意味しうる。対して「大」「夫」などの人間の正面形には、下級の意味を含む用例は見られない。詳細は論語語釈「人」を参照。
童子(トウシ)
論語の本章では”未成年者”。「ドウジ」は慣用音で、訓み下しは「わらべ」。春秋時代の漢語では、「子」は”こども”ではなく”貴人”の意で、「童子」は”貴公子”を意味するが、本章は漢代の偽作が確定するため”未成年者”と解して良い。


(甲骨文)
「童」の初出は甲骨文。字形は「辛」+”目を見開いた人”で、盲目化された奴隷の姿。原義は”奴隷”。甲骨文の用例は文意が明瞭でない。春秋末期までに、異民族への蔑称、”少しでも”・”子供”の意に用いた。詳細は論語語釈「童」を参照。
六七人(リクシツジン)
論語の本章では”六七人ほど”。「ロクシチニン」は呉音。読み下しは「むななたり」。
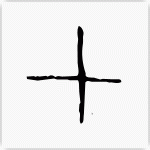

(甲骨文)
「七」の初出は甲骨文。「シチ」は呉音。字形は「切」の原字と同じで、たてよこに入れた切れ目。これがなぜ数字の”7”を意味するようになったかは、音を借りた仮借と解する以外に方法が無い。原義は数字の”なな”。「漢語多功能字庫」によると、甲骨文から戦国の竹簡まで一貫して、数字の”なな”の意で用いられている。詳細は論語語釈「七」を参照。
浴*(ヨク)

倗缶(金)・春秋末期
論語の本章では”水浴びする”。初出は甲春秋末期の金文。字形は「人」+音符「谷」。下に「冫」らしき点を伴うものがあり、春秋末期の例はいずれも「浴缶」とあるから、水浴びのための道具だったろう。戦国の竹簡では”たに”の用例がある。詳細は論語語釈「浴」を参照。
沂(キ)

(金文大篆)
論語の本章では、魯国の川、沂水のこと。地図では右下、都城の曲阜からは随分遠いので、泊まりがけの旅行になるだろう。
論語では本章のみに登場。漢音は「ギ」。初出は後漢の説文解字。固有名詞のため、論語の時代に存在しないと断じ得ない。カールグレン上古音は不明(平)。王力上古音はŋǐəi。「キ」は慣用音。『学研漢和大字典』によると会意兼形声文字で、「水+(音符)斤(キン)(近づく、せまる)」で、岸が水ぎわにせまった川。また、水ぎわのがけ、という。詳細は論語語釈「沂」を参照。
風(ホウ)


(甲骨文)
論語の本章では空気の速い流れである”かぜ”。初出は甲骨文。字形は鳥が風を切って飛ぶさま。「フウ」は呉音。甲骨文から”かぜ”の意に用いた。詳細は論語語釈「風」を参照。
舞雩*(ブウ)
論語の本章では”雨乞いをするための舞台”。


(甲骨文)
「舞」の初出は甲骨文。字形は「無」と同じ。手に飾りを持って舞う姿。原義は”舞(う)”。金文では原義に用いた。詳細は論語語釈「舞」を参照。


(甲骨文)
「𩁹」の初出は甲骨文。甲骨文の字形は「雨」+「干」”さすまた”。さすまた状の祭具を手に取って雨乞いする様。字形によっては「干」→「示」”祭壇”になっているものもある。甲骨文については文字列の元データが公開されていないが、漢語多功能字庫によると人名の例があるという。西周になると、「于」”~に”とも解せる例があり、また”いわく”と解されている例がある。「語」との音通と言えそうで言えそうにない。春秋末期には”雨乞い”と解せる例がある。詳細は論語語釈「雩」を参照。
詠*(エイ)→咏*(エイ)


論語の本章では”歌う”。この語義は春秋時代では確認できない。論語では本章のみに登場。
初出は西周早期の金文。定州竹簡論語の「咏」は異体字。字形は「行」+「人」+「𠙵」。街道の交差点に立ちものを言うこと。春秋末期までの用例は、人名、または”(鐘の)音を出す”。詳細は論語語釈「詠」を参照。
歸(キ)
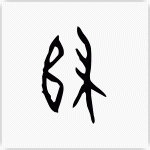

(甲骨文)
論語の本章では”帰る”→”葬儀を行うべき家族”。新字体は「帰」。甲骨文の字形は「𠂤」”軍隊”+「帚」”ほうき→主婦権の象徴”で、軍隊が王妃に出迎えられて帰還すること。詳細は論語語釈「帰」を参照。
夫子(フウシ)
論語の本章では”孔子先生”。”父の如き人”の意味での敬称。


(甲骨文)
「夫」の初出は甲骨文。論語では「夫子」として多出。「夫」に指示詞の用例が春秋時代以前に無いことから、”あの人”ではなく”父の如き人”の意で、多くは孔子を意味する。「フウ」は慣用音。字形はかんざしを挿した成人男性の姿で、原義は”成人男性”。「大夫」は領主を意味し、「夫人」は君主の夫人を意味する。固有名詞を除き”成人男性”以外の語義を獲得したのは西周末期の金文からで、「敷」”あまねく”・”連ねる”と読める文字列がある。以上以外の語義は、春秋時代以前には確認できない。詳細は論語語釈「夫」を参照。
喟然(キゼン)
論語の本章では、”ためいきをつくように”。「喟」は”ため息”。「然」は”~であるさま”。論語子罕篇11にある、後世に偽作された目と耳を覆いたくなる顔淵のおべんちゃら「顏淵喟然歎曰」から取ってきたのはほぼ確実。
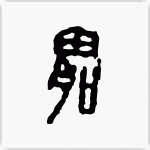

(晋系戦国文字)
「喟」の初出は晋系戦国文字。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。字形は「𠙵」”くち”+音符「胃」。上古音に同音は存在しない。戦国の竹簡では、「葨」「𦳢」「渭」が「喟」と釈文されている。異体字に「嘳」があるという。初出は「喟」と同じとされる。詳細は論語語釈「喟」を参照。


(金文)
「然」が”~であるさま”である語義は春秋時代以前では確認できない。初出は春秋早期の金文。「ネン」は呉音。初出の字形は「黄」+「火」+「隹」で、黄色い炎でヤキトリを焼くさま。現伝の字形は「月」”にく”+「犬」+「灬」”ほのお”で、犬肉を焼くさま。原義は”焼く”。”~であるさま”の語義は戦国末期まで時代が下る。詳細は論語語釈「然」を参照。
歎(タン)


(篆書)
論語の本章では”感動してたたえる”。論語子罕篇11の定州竹簡論語では事実上の異体字「嘆」と書くが、本章では何と書いてあったか欠損して分からない。初出は戦国の竹簡で、ただし字形は「難」または「戁」。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。「歎」の字形は「𦰩」”火あぶり”+「欠」”口を大きく開けた人”で、悲惨なさまに口を開けて歎くさま。「嘆」は「𦰩」+「𠙵」”くち”で、意味するところは同じ。戦国の竹簡で”なげく”の意に用いた。詳細は論語語釈「歎」を参照。
吾(ゴ)


(甲骨文)
論語の本章では”わたし”。初出は甲骨文。字形は「五」+「口」で、原義は『学研漢和大字典』によると「語の原字」というがはっきりしない。一人称代名詞に使うのは音を借りた仮借だとされる。詳細は論語語釈「吾」を参照。
春秋時代までは中国語にも格変化があり、一人称では「吾」を主格と所有格に用い、「我」を所有格と目的格に用いた。しかし論語でその文法が崩れ、「我」と「吾」が区別されなくなっている章があるのは、後世の創作が多数含まれているため。
與(ヨ)


(金文)
論語の本章では”~に”。この語義は春秋時代では確認出来ない。新字体は「与」。初出は春秋中期の金文。金文の字形は「牙」”象牙”+「又」”手”四つで、二人の両手で象牙を受け渡す様。人が手に手を取ってともに行動するさま。従って原義は”ともに”・”…と”。詳細は論語語釈「与」を参照。
論語:付記
前回同様、本章は長いので分割して記す。この章、つづく。
検証
論語の本章は、文字史から春秋時代以前に遡れず、語法からも同様。前漢儒による偽作と考えるのが理にかなう。
解説
早くは和辻哲郎から指摘されていたことだが、本章は現実にはあり得ないけしきで、子路・冉有といった一門の大立て者と、他ならぬ師匠の孔子を前にして、一人だけ身勝手に琴弾きにふけっている曽子のおやじ曽皙を、三者を超えて偉いように描いている。
その曽皙について儒者ですらも、必ずしも「孔子先生の高弟・曽子先生のお父上」として敬っていたわけではない。本章が成立する漢代には、とんでもないサド親父としての評価が定まっている。
曾子耘瓜,誤斬其根。曾晢怒,建大杖以擊其背,曾子仆地而不知人久之。有頃乃蘇,欣然而起,進於曾晢曰:「嚮也參得罪於大人,大人用力教參,得無疾乎?」退而就房,援琴而歌,欲令曾晳而聞之,知其體康也。孔子聞之而怒,告門弟子曰:「參來,勿內。」曾參自以為無罪,使人請於孔子。子曰:「汝不聞乎?昔瞽瞍有子曰舜,舜之事瞽瞍,欲使之,未嘗不在於側;索而殺之,未嘗可得。小棰則待過,大杖則逃走,故瞽瞍不犯不父之罪,而舜不失烝烝之孝。今參事父,委身以待暴怒,殪而不避,既身死而陷父於不義,其不孝孰大焉!汝非天子之民也,殺天子之民,其罪奚若?」曾參聞之,曰:「參罪大矣!」遂造孔子而謝過。


曽子が瓜畑の世話をしている最中、うっかり蔓を切ってしまった。芋づる式に瓜がダメになったと知って曽皙が真っ赤になって怒り、クワを振り上げて曽子の背中を執拗にぶちのめした。その場に倒れた曽子はしばらく気を失ったままだったが、やがて息を吹き返すと嬉しそうに立ち上がり、家に飛んで帰って曽皙に言った。
「先ほどは大変申し訳ないことを致しました。クワを振るって戒めを下されましたが、おけがはございませんでしたか?」そのまま自室に引き籠もって、チンチャカ琴をかき鳴らしてわあわあと歌った。曽皙に歌を聴かせて、大したことない、と思わせるためである。


それを伝え聞いた孔子は、真っ赤になって怒った。「あの馬鹿者が! 皆の者! 曽子めが来ても、ワシの部屋に入れるな!」自分は全然悪くない、むしろ立派なことをしたと思っている曽子が、弟子仲間に無理を言って取り次いで貰うと、孔子は説教を始めた。

「あのな、お前も知っての通り、いにしえの舜王の親父はろくでなしだった。即位前の舜王は、親父が用を言い付けると言うことを聞いたが、親父が自分を殺そうとしたときは姿を隠した。親父が小クワを振り回している間はくたびれるまで待ち、大クワを振り回し始めたら飛んで逃げた。おかげで親父も虐待の犯罪者にならずに済み、舜王も孝行者だという評判を保った。
そこへ行くとお前は何だ。父親の発狂をただぼんやりと待ち、殴られるに任せた。もし死にでもしたら、父親を殺人犯にするところだったんだぞ。親不孝も甚だしい。それにお前だって、天子様の民ではないか。天子様の民を殺した罪とは、そう軽いものではないぞ。」
曽子はしょぼくれて「済みませんでした」とあやまった。(『孔子家語』六本10。ほぼ同じ話を前漢末期の劉向『説苑』にも記す)
では漢代より前の曽皙の評価はどうだったか。そもそも曽皙の存在を言い始めたのは、孔子没後一世紀に生まれた孟子で、それも決して肯定的に描いていない。
(萬章問)「敢問何如斯可謂狂矣?」
曰:「如琴張、曾皙、牧皮者,孔子之所謂狂矣。」
「何以謂之狂也?」
曰:「其志嘐嘐然,曰『古之人,古之人』。夷考其行而不掩焉者也。」
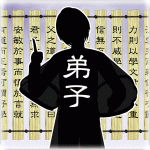

(弟子の)万章「もの狂いとはどのような人でしょう。」
孟子「琴張や曽皙や牧皮のような人が、孔子先生の言うもの狂いだね。」

万章「どうしてもの狂いなんですか?」
孟子「願望ばかり大きくて、まるでニワトリがけたたましく鳴くように、二言目には”昔の人なら! 昔の人なら!”と目の前の出来事にケチをつける。軽率に何でも出来ると思い上がっていて、そのくせ実行が伴わない。いつまでたっても、何もやり遂げることがない。」(『孟子』尽心下篇)
そもそも「曽皙」の「皙」の字の初出が後漢の『説文解字』だから(論語語釈「皙」)、この話が本当に孟子によるものかどうかも怪しいのだが、ここではひとまず措く。固有名詞だから同音近音のいかなる漢字も、当時の置換候補になり得るからだ。ともあれ孟子は次のようにも語った。
曾子養曾皙,必有酒肉。將徹,必請所與。問有餘,必曰『有』。曾皙死,曾元養曾子,必有酒肉。將徹,不請所與。問有餘,曰『亡矣』。將以復進也。此所謂養口體者也。若曾子,則可謂養志也。事親若曾子者,可也。
曽子が曽皙の介護をするに当たっては、食事に必ず酒と肉をそえた(=ご馳走を作った)。食器を下げる時にも、必ず「どれがお気に召しましたか」と聞き、「まだあるか」と聞かれたら、必ず「あります」と答えられるように(事前に用意)した。曽皙が死ぬと、今度は曽子が長男の曽元の介護を受ける番になったが、曽元はやはり酒と肉を食事に添えた。だが食後に気に入りを聞く事も無く、「まだあるか」と聞かれても「もうありません」としか答えなかった。毎度の食事がこのさまで、これはただ空き腹を養っただけに過ぎない。曽子の奉仕なら、心まで満たしたと評価できる。親孝行というものは、曽子の域まで達して、やっと合格点なのだ。(『孟子』離婁上19)
曾皙嗜羊棗,而曾子不忍食羊棗。
公孫丑問曰:「膾炙與羊棗孰美?」
孟子曰:「膾炙哉!」
公孫丑曰:「然則曾子何為食膾炙而不食羊棗?」
曰:「膾炙所同也,羊棗所獨也。諱名不諱姓,姓所同也,名所獨也。」
曽皙は棗で煮込んだ羊のうま煮が好きだったが、曽子はそのうま煮が精神的に食べられなかった。
(弟子の)公孫丑「肉の膾炙(カイシャ。刺身で食えるほど新鮮な肉のあぶり焼き、つまりバーベキュー)と羊のうま煮では、どっちが美味いですかね?」
孟子「そりゃ膾炙だ。」
公孫丑「じゃなんで曽子は、膾炙は食ってもうま煮を食わなかったんですかね?」
孟子「膾炙はみんなでワイワイ食うものだが、うま煮は一人でコソコソ食うものだからだ。人のいみ名を名指しで呼ぶと失礼になるが、姓で呼べば失礼にならんだろう? 同姓の人は大勢いるから、そんなに名指しされたような気分にならんが、いみ名は個人だけのものだから、”お前”と指さしたように嫌がられる。」(『孟子』盡心下82)
2例目の方は何が言いたいかちょっとよく分からないが、親孝行の話ではなく、「美味しいご飯はみんなで食べよう」の精神に反する、独り食いを平気でやらかすのはいかんという説教だろう。曽子と聞けばすぐ親孝行だと決めてかかるのは、ナントカの一つ覚えというものだ。
さて戦国時代までの曽皙に関する話は、あと一例しかない。
曾子曰:「君子行於道路,其有父者可知也,其有師者可知也。夫無父而無師者,餘若夫何哉!」此言事師之猶事父也。曾點使曾參,過期而不至,人皆見曾點曰:「無乃畏邪?」曾點曰:「彼雖畏,我存,夫安敢畏?」孔子畏於匡,顏淵後,孔子曰:「吾以汝為死矣。」顏淵曰:「子在,回何敢死?」顏回之於孔子也,猶曾參之事父也。古之賢者,與其尊師若此,故師盡智竭道以教。
曽子が言ったそうだ。「君子は道を行くにも、父のある者にはそれらしく、師のある者にはそれらしい態度を見て取れる。父も師も無い者は(無茶苦茶で)、他人には手の付けようが無い」と。
これは師匠に対して父親のように奉公しろという説教である。曽点が曽子を呼びつけたところ、ぜんぜんやってこなかった事があった。それを知った連中が、曽点に会うたび「親をバカにしていませんか」と言う。曽点はすました顔で「あれはきちんとわしを敬っておるよ。わしの目の黒いうちは、らしい振りをしないだけだ。」
孔子が匡のまちで悪党と間違えられて牢に放り込まれ、その時顔淵は付き合わなかった(論語子罕篇5)。(牢から出てきてから)孔子は顔淵に「お前はもう死んでしまったかと思った」と言ったが、顔淵は「先生が生きている間は、わざわざ死ぬようなことはしません」と答えた。(忠義ぶって自分も牢に放り込まれる演出はしなかった。)
顔淵が孔子に仕えた態度は、曽子の父親に対する態度と同じである。むかしの賢者が師匠に仕える法は、みなこのようであって、だから師匠は思慮の限り知識の限りを尽くして教えたわけだ。(『呂氏春秋』勸學3)
ここでの曽皙は息子の曾參(曽参。曽子)とともに、あわれ曾點(曽点)といみ名を呼び捨てにされている。あるいは前漢儒が儒教のあれこれに辻褄を合わせる前まで、曽皙は何があざ名で何がいみ名かわからなかったからかもしれない。もともと名もなき農民だったのだから無理は無い。
つまり曽皙は漢儒がそう決めつけるまで、とんでもないサド親父だとは思われていなかった節がある。曽子当人は子夏を怒鳴り上げてたかったり、孔門の重鎮である有若を白痴呼ばわりしたり、他人に厳しいサド傾向があるから、おやじのサドを受け継いだという想像には正当性がある。
(曽子が子を亡くしたばかりの子夏に言った。)「そもそも子を失い、視力を失ったのがお前の罪だ。」(『小載礼記』檀弓上41)
(有若を拝めと言われた)曽子「いやですね。大河でジャブジャブ洗った上に、秋の陽にカンカンと晒した布のように、有若の頭の中は真っ白だ。こんな馬鹿を拝むなんてとんでもない。」(『孟子』滕文公上4)
ただ論語の本章が、そもそも前漢儒の偽作であり、「遠慮しないで抱負を言いなさい」と誘い込んだ孔子が、子路の回答を聞いてせせら笑うというサド話でもある(論語先進篇25)。身体的にも精神的にも社会的にも強者だった孔子が、そんなサドをする動機がそもそもないのだが。
だが前漢儒者業界は、隙あらば他人の首をリアルにちょん切て取って代わろうとたくらむサド社会であり、その「常識」たるや村八分をする閉じた寒村の「常識」=因習と同じだったから(論語公冶長篇24余話「人でなしの主君とろくでなしの家臣」)、曽皙サド説は前漢儒のでっち上げと考えるのにもまた筋が通る。訳者としてはいずれとも断定できない。
論語の本章今回部分、古注は次の通り。
古注『論語集解義疏』
㸃爾何如鼓瑟希註孔安國曰思所以對故其音希也鏗爾舍瑟而作對曰異乎三子者之撰註孔安國曰置瑟起對也撰具也為政之具也鏗爾者投瑟之聲也子曰何傷乎亦各言其志也註孔安國曰各言己志於義無傷之曰暮春者春服既成得冠者五六人童子六七人浴乎沂風乎舞雩詠而歸註苞氏曰暮春者季春三月也春服既成者衣單袷之時也我欲得冠者五六人童子六七人浴於沂水之上風涼於舞雩之下歌詠先王之道歸夫子之門也夫子喟然歎曰吾與㸃也註周生烈曰善點之獨知時也
本文「㸃爾何如鼓瑟希」。
注釈。孔安国「質問に答えなければならないと思ったので、琴を途切れ途切れに弾いていたのである。」
本文「鏗爾舍瑟而作對曰異乎三子者之撰」。
注釈。孔安国「琴を置いて立ち上がって孔子に答えたのである。撰とは”ご立派な答え”の意である。政策として立派だと言ったのである。鏗爾とは琴を放り投げる音である。」
本文「子曰何傷乎亦各言其志也」。
注釈。孔安国「それぞれ正義の志を述べたのだから、”ご立派”などとおちょくってはいかんよと諭したのである。」
本文「曰暮春者春服既成得冠者五六人童子六七人浴乎沂風乎舞雩詠而歸」。
注釈。包咸「暮春とは(立春を正月とする)春三月ごろのことである。春服既成とは、衣類の裏を抜いて単衣にすることである。”私は大人五六人、子供六七人ほどともに、沂水の涼風を浴びて、雨乞い台の下でいにしえの聖王の道を歌に歌い、それから先生の所へ帰りたい”と言ったのである。」
本文「夫子喟然歎曰吾與㸃也」。
注釈。周生烈「曽点だけが季節ばなしをしたのを誉めたのである。」
「次は私の番だな」と分かっているんだったら、琴など弾いてないでおとなしく話を聞いておれ、と訳者が孔子なら曽皙をしばき上げているところだ。ただし実在が怪しい孔安国の言う、曽皙が「お三方はまことに立派」とおちょくった、それに対して孔子が「からかってはいかんよ」とたしなめたという話は面白い。本章を偽作した前漢儒は、存外そのつもりで書いたのかも知れないからだ。
新注は次の通り。
新注『論語集注』
「點!爾何如?」鼓瑟希,鏗爾,舍瑟而作。對曰:「異乎三子者之撰。」子曰:「何傷乎?亦各言其志也。」曰:「莫春者,春服既成。冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,風乎舞雩,詠而歸。」夫子喟然歎曰;「吾與點也!」鏗,苦耕反。舍,上聲。撰,士免反。莫、冠,並去聲。沂,魚依反。雩音于。四子侍坐,以齒為序,則點當次對。以方鼓瑟,故孔子先問求、赤而後及點也。希,間歇也。作,起也。撰,具也。春服,單袷之衣。浴,盥濯也,今上巳祓除是也。沂,水名,在魯城南,地志以為有溫泉焉,理或然也。風,乘涼也。舞雩,祭天禱雨之處,有壇墠樹木也。詠,歌也。曾點之學,蓋有以見夫人欲盡處,天理流行,隨處充滿,無少欠闕。故其動靜之際,從容如此。而其言志,則又不過即其所居之位,樂其日用之常,初無舍己為人之意。而其胸次悠然,直與天地萬物上下同流,各得其所之妙,隱然自見於言外。視三子之規規於事為之末者,其氣象不侔矣,故夫子歎息而深許之。而門人記其本末獨加詳焉,蓋亦有以識此矣。
本文「點!爾何如?鼓瑟希,鏗爾,舍瑟而作。對曰:異乎三子者之撰」子曰:何傷乎?亦各言其志也。曰:莫春者,春服既成。冠者五六人,童子六七人,浴乎沂,風乎舞雩,詠而歸。夫子喟然歎曰:吾與點也!」
鏗は苦-耕の反切で読む。舍は上がり調子に読む。撰は士-免の反切で読む。莫、冠は、どちらも尻下がりに読む。沂は魚-依の反切で読む。雩の音は于である。四弟子が孔子の側に座るには、年齢で席次を決めた。だから曽点は二番目にはずだった。だがチンチャカ琴を弾いていたので、孔子は先に冉求と公西赤に問い、曽点の番が回ってきたのである。希とは途切れがちに、の意である。作とは、立ち上がることである。撰とは、備わっている、十分であるの意である。春服とは、単衣のことである。浴とは、水浴びである。現在では三月三日の節句にみそぎをしているあれである。沂は川の名である。魯の都城の南を流れ、地理書では温泉があると書いてある。だから温泉に行ったと考えるのが正しいかも知れない。風とは涼むことである。舞雩とは雨乞いの場所で、聖域として結界、依り代の樹木が生えている。詠とは歌うことである。曽点の学問はたぶん、我欲を捨て、天のことわりに従い、どこでも不都合を起こさず、不十分なところが無いものだったのだろう。だから動くも止まるも自由自在で、我を張らないのはこの通りだった。そこへ抱負を答えたのだから、必ず現状に不満を抱かず、日常を楽しむことを言い、初めから自分を捨てて人に役に立つなどとは言わなかった。その思いは緩やかであり、同時に天地万物と動きを共に詩、それぞれがあり得べき所に収まる絶妙な様を見て取っているのを、言葉の外にほのめかした。先の三弟子の答えは鹿爪らしいちまちまで、そしてどうやら本気でやってのける気が無い。だから孔子先生はため息をついて曽点の答えを深く良いものと認めたのである。そして門人がこの様子を記録したのだが、三弟子と曽点の優劣について、曽点の答えだけを詳しく記しているのだが、たぶん曽点の答えが優れていると知ってそうしたのかも知れない。
宋儒はオカルトで世間をたぶらかして喰っていた連中だから、「天地のことわり」うんぬんは本章の偽作者である漢儒には知ったことではなかったのはもちろんである。論語雍也篇3余話「宋儒のオカルトと高慢ちき」を参照。
余話
(思案中)






コメント