論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子曰參乎吾道一以貫之曾子曰唯子出門人問曰何謂也曾子曰夫子之道忠恕而巳矣
校訂
東洋文庫蔵清家本
子曰參乎吾道一以貫之哉曾子曰唯/子出門人問曰何謂也曾子曰夫子之道忠恕而已矣
※「已」字:京大本同、宮内庁本「巳」。
後漢熹平石経
(子)…白唯子出門人問白何謂也曽子白夫子之道忠恕而巳…
定州竹簡論語
……何謂也?曾子曰:「夫子之道,忠恕而已矣。」72
標点文
子曰、「參乎。吾道一以貫之哉。」曾子曰、「唯。」子出、門人問曰、「何謂也。」曾子曰、「夫子之道、忠恕而已矣。」
復元白文(論語時代での表記)






























 忠恕
忠恕


※貫→毌。論語の本章は「忠」「恕」の字が論語の時代に存在しない。「乎」「門」「問」「何」の用法に疑問がある。本章は前漢以降の儒者による創作である。
書き下し
子曰く、參乎、吾が道は一にして、以て之を貫ける哉。曾子曰く、唯り。子出づ。門人問うて曰く、何の謂ぞ也。曾子曰く、夫子之道は忠と恕に而て已む矣。
論語:現代日本語訳
逐語訳


先生が言った。「参よ、私の道は一つで、それでずっと道を貫いているのだ」。曽子が言った。「はい」。先生は部屋を出た。門人が問うて言った。「何を言ったのか」。曽子が言った。「先生の道は、真心と思いやりだけだ」。
意訳


孔子「曽子よ! 私はずっと一つのことを貫いてきたのだ。」
曽子「はい。仰る通りです。」
孔子が席を立った。
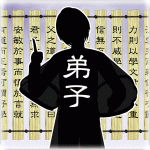

他の塾生「どういう意味です?」
曽子「有り難くわが言葉を拝聴するが良い。先生の道は、忠義と思いやりなのであるぞよ。」
従来訳
先師がいわれた。
「参よ、私の道はただ一つの原理で貫かれているのだ。」
曾先生が答えられた。――
「さようでございます。」
先師はそういって室を出て行かれた。すると、ほかの門人たちが曾先生にたずねた。――
「今のは何のことでしょう。」
曾先生は答えていわれた。――
「先生の道は忠恕の一語につきるのです。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子說:「曾參啊!我的思想是用一個基本思想貫徹始終的。」曾子說:「是。」孔子走後,其他學生問:「什麽意思?」曾子說:「老師的思想,就是忠恕。」
孔子が言った。「曽子よ! 私の思想は、一つの根本思想で貫かれているのだ。」曽子が言った。「はい。」孔子が去った後、他の塾生が問うた。「どういう意味か。」曽子が言った。「先生の思想は、つまり忠実と思いやりだ。」
論語:語釈
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。


(甲骨文)
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
漢石経では「曰」字を「白」字と記す。古義を共有しないから転注ではなく、音が遠いから仮借でもない。前漢の定州竹簡論語では「曰」と記すのを後漢に「白」と記すのは、春秋の金文や楚系戦国文字などの「曰」字の古形に、「白」字に近い形のものがあるからで、後漢の世で古風を装うにはありうることだ。この用法は「敬白」のように現代にも定着しているが、「白」を”言う”の意で用いるのは、後漢の『釈名』から見られる。論語語釈「白」も参照。
參(シン)


(金文)
孔子の弟子とされてきた、曽子の名。新字体は「参」。漢音(遣隋使・遣唐使が聞き帰った音)は通常「サン」だが、曽子の名は「シン」と読むならいになっている。孔子は名指しで”あのウスノロ”と罵倒している(論語先進篇17)。「參」は春秋末期では明確に数字の”3”として用いられており、「曾參」(曽参)とは単に”曽家の三男”を意味するのではないか。詳細は論語語釈「参」を参照。
曽子は孔子の直弟子ではなく、仮に実在したとしても、孔子家の家事使用人に過ぎない。詳細は論語の人物:曽参子輿を参照。
乎(コ)


(甲骨文)
論語の本章では、”…よ”。呼びかけの意を示す。初出は甲骨文。甲骨文の字形は持ち手を取り付けた呼び鐘の象形で、原義は”呼ぶ”こと。甲骨文では”命じる”・”呼ぶ”を意味し、金文も同様で、「呼」の原字となった。句末の助辞として用いられたのは、戦国時代以降になる。ただし「烏乎」で”ああ”の意は、西周早期の金文に見え、句末でも詠嘆の意ならば論語の時代に存在した可能性がある。詳細は論語語釈「乎」を参照。
吾(ゴ)


(甲骨文)
論語の本章では”わたしの”。初出は甲骨文。字形は「五」+「口」で、原義は『学研漢和大字典』によると「語の原字」というがはっきりしない。一人称代名詞に使うのは音を借りた仮借だとされる。詳細は論語語釈「吾」を参照。
春秋時代までは中国語にも格変化があり、一人称では「吾」を主格と所有格に用い、「我」を所有格と目的格に用いた。しかし論語でその文法が崩れ、「我」と「吾」が区別されなくなっている章があるのは、後世の創作が多数含まれているため。
道(トウ)
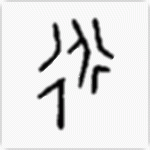

「道」(甲骨文・金文)
論語の本章では”道”→”人生”。動詞で用いる場合は”みち”から発展して”導く=治める・従う”の意が戦国時代からある。”言う”の意味もあるが俗語。初出は甲骨文。字形に「首」が含まれるようになったのは金文からで、甲骨文の字形は十字路に立った人の姿。「ドウ」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。詳細は論語語釈「道」を参照。
一(イツ)


(甲骨文)
論語の本章では、”一つ事”。「イチ」は呉音。初出は甲骨文。重文「壹」の初出は戦国文字。字形は横棒一本で、数字の”いち”を表した指事文字。詳細は論語語釈「一」を参照。
以(イ)


(甲骨文)
論語の本章では”それで”。初出は甲骨文。人が手に道具を持った象形。原義は”手に持つ”。論語の時代までに、”率いる”・”用いる”・”携える”の語義があり、また接続詞に用いた。さらに”用いる”と読めばほとんどの前置詞”…で”は、春秋時代の不在を回避できる。詳細は論語語釈「以」を参照。
貫(カン)


(金文)
論語の本章では”貫く”。初出は西周早期の金文。同音は官とそれを部品とする漢字群など多数。字形はタカラガイを二つヒモで貫き通したさまで、原義は”貫く”。金文では原義で用いられた。部品の毌にも”つらぬく”の意がある。詳細は論語語釈「貫」を参照。
哉(サイ)
唐石経の系統を引く現伝論語にはこの字は欠けているが、清家本には記され、定州竹簡論語ではこの部分の簡が欠損している。ただし「哉」の用例は定州竹簡論語にもあり、このためこの字を補って校訂した。
論語の伝承について詳細は「論語の成立過程まとめ」を参照。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)


(金文)
論語の本章では”…だなあ”。詠歎の意を示す。初出は西周末期の金文。ただし字形は「𠙵」”くち”を欠く「𢦏」で、「戈」”カマ状のほこ”+「十」”傷”。”きずつく”・”そこなう”の語釈が『大漢和辞典』にある。現行字体の初出は春秋末期の金文。「𠙵」が加わったことから、おそらく音を借りた仮借として語気を示すのに用いられた。金文では詠歎に、また”給与”の意に用いられた。戦国の竹簡では、”始まる”の意に用いられた。詳細は論語語釈「哉」を参照。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章では”これ”・”~の”。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”…の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。
曾子(ソウシ)
新字体は「曽子」。孔子の弟子とされてきた曽参子輿の敬称。「子」とは貴族や知識人に対する敬称で、春秋戦国時代、孔子のように開祖級の学者は知識人を○子と呼び、その弟子は子夏のように子○と呼ばれた。つまり「曽子」とは、孔子と同列に置いた敬称。辞書的には論語語釈「曽」を参照。
唯(イ)


(甲骨文)
論語の本章では”はい”。その通り、との返答。初出は甲骨文。「ユイ」は呉音。字形は「𠙵」”口”+「隹」”とり”だが、早くから「隹」は”とり”の意では用いられず、発言者の感情を表す語気詞”はい”を意味する肯定の言葉に用いられ、「唯」が独立する結果になった。古い字体である「隹」を含めると、春秋末期までに、”そもそも”・”丁度その時”・”ひたすら”・”ただ~だけ”の語義が確認できる。詳細は論語語釈「唯」を参照。
出(シュツ/スイ)


(甲骨文)
論語の本章では”(孔子が講義室から)出る”。初出は甲骨文。「シュツ」の漢音は”出る”・”出す”を、「スイ」の音はもっぱら”出す”を意味する。呉音は同じく「スチ/スイ」。字形は「止」”あし”+「凵」”あな”で、穴から出るさま。原義は”出る”。論語の時代までに、”出る”・”出す”、人名の語義が確認できる。詳細は論語語釈「出」を参照。
門(ボン)


(甲骨文)
論語の本章では”学派”。ここでは孔子一門のこと。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。「モン」は呉音。字形はもんを描いた象形。甲骨文では原義で、金文では加えて”門を破る”(庚壺・春秋末期)の意に、戦国の竹簡では地名に用いた。詳細は論語語釈「門」を参照。
人(ジン)


(甲骨文)
論語の本章では”…の者”。「門人」で”孔子の弟子”。初出は甲骨文。原義は人の横姿。「ニン」は呉音。甲骨文・金文では、人一般を意味するほかに、”奴隷”を意味しうる。対して「大」「夫」などの人間の正面形には、下級の意味を含む用例は見られない。詳細は論語語釈「人」を参照。
問(ブン)


(甲骨文)
論語の本章では”問う”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。「モン」は呉音。字形は「門」+「口」。甲骨文での語義は不明。西周から春秋に用例が無く、一旦滅んだ漢語である可能性がある。戦国の金文では人名に用いられ、”問う”の語義は戦国最末期の竹簡から。それ以前の戦国時代、「昏」または「𦖞」で”問う”を記した。詳細は論語語釈「問」を参照。
何(カ)


(甲骨文)
論語の本章では”なに”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は「人」+”天秤棒と荷物”または”農具のスキ”で、原義は”になう”。甲骨文から人名に用いられたが、”なに”のような疑問辞での用法は、戦国時代の竹簡まで時代が下る。詳細は論語語釈「何」を参照。
謂(イ)


(金文)
論語の本章では”意味”。本来はただ”いう”のではなく、”…だと認定する”の意。現行書体の初出は春秋後期の石鼓文。部品で同義の「胃」の初出は春秋早期の金文。金文では氏族名に、また音を借りて”言う”を意味した。戦国の竹簡になると、あきらかに”~は~であると言う”の用例が見られる。詳細は論語語釈「謂」を参照。
也(ヤ)


(金文)
論語の本章では、「や」と読んで疑問の意”…か”に用いている。初出は春秋時代の金文。原義は諸説あってはっきりしない。「や」と読み主語を強調する用法は、春秋中期から例があるが、「也」を句末で断定などに用いるのは、戦国時代末期以降の用法で、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「也」を参照。
夫子(フウシ)


(甲骨文)
論語の本章では”孔子先生”。従来「夫子」は「かの人」と訓読され、「夫」は指示詞とされてきた。しかし論語の時代、「夫」に指示詞の語義は無い。同音「父」は甲骨文より存在し、血統・姓氏上の”ちちおや”のみならず、父親と同年代の男性を意味した。従って論語における「夫子」がもし当時の言葉なら、”父の如き人”の意味での敬称。詳細は論語語釈「夫」を参照。
「子」は貴族や知識人に対する敬称。論語語釈「子」を参照。
忠(チュウ)

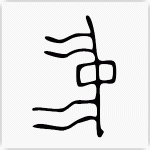
「忠」(金文)/「中」(甲骨文)
論語の本章では”忠実”。初出は戦国末期の金文。ほかに戦国時代の竹簡が見られる。字形は「中」+「心」で、「中」に”旗印”の語義があり、一説に原義は上級者の命令に従うこと=”忠実”。ただし『墨子』・『孟子』など、戦国時代以降の文献で、”自分を偽らない”と解すべき例が複数あり、それらが後世の改竄なのか、当時の語義なのかは判然としない。「忠」が戦国時代になって現れた理由は、諸侯国の戦争が激烈になり、領民に「忠義」をすり込まないと生き残れなくなったため。詳細は論語語釈「忠」を参照。
恕(ショ)


(戦国末期金文)
論語の本章では”思いやり”。初出は戦国末期の金文。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。「ジョ」は慣用音。同音に”思いやる”の語は無い。戦国の金文・竹簡では、みな「怒」の意で用いる。論語の本章では”怒る”ではありえないから、つまり本章の創作者は前漢の儒者という事になる。詳細は論語語釈「恕」を参照。より詳細には、論語における「恕」を参照。
戦国時代まで、「恕」は”思いやり”ではなく”お互い様”の意。現伝の「恕」の解釈を発明したのは前漢の儒者で、もちろん孔子や曽子とは関係が無い。論語衛霊公篇24の付記を参照。
巳(シ)→已(イ)
論語の本章では”すでに”。
現存最古の論語本である定州竹簡論語は「已」と記し、唐石経は「巳」と記し、東洋文庫蔵・京大蔵清家本は「已」と記す。宮内庁蔵清家本は「巳」と記す。清家本は唐石経より前の古注系論語を伝承しており、唐石経を訂正しうるが、より古い定州本に従い「已」に校訂した。
論語の古本では、このほか「己」字も「巳」字・「已」字と混用される。つまり唐代頃までは「巳」”へび”と「已」”すでに”と「己」”おのれ”は相互に異体字として通用した。


(甲骨文)
「已」の初出は甲骨文。字形と原義は不詳。字形はおそらく農具のスキで、原義は同音の「以」と同じく”手に取る”だったかもしれない。論語の時代までに”終わる”の語義が確認出来、ここから、”~てしまう”など断定・完了の意を容易に導ける。詳細は論語語釈「已」を参照。


(甲骨文)
「巳」の初出は甲骨文。字形はヘビの象形。「ミ」は呉音。甲骨文では干支の六番目に用いられ、西周・春秋の金文では加えて、「已」”すでに”・”ああ”・「己」”自分”・「怡」”楽しませる”・「祀」”まつる”の意に用いた。詳細は論語語釈「巳」を参照。
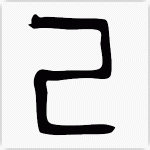

(甲骨文)
「己」字の初出は甲骨文。「コ」は呉音。字形はものを束ねる縄の象形だが、甲骨文の時代から十干の六番目として用いられた。従って原義は不明。”自分”の意での用例は春秋末期の金文に確認できる。詳細は論語語釈「己」を参照。
而已矣(ジイイ)

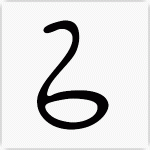

(金文)
論語の本章では、”~だけである”。「而」は接続辞、「已」は”やむ・おわる”、「矣」は断定または詠嘆の言葉。”~であって終わるのである”。二文字「而已」でも三文字揃っても「のみ」と読み下すのが伝統的だが、訳者はもう少しまじめに原文を読もうとした。
なお”のみ”と言いたいならただ一言「耳」と言えば済むのだが、「而已矣」と曽子が言葉を重ねて言ったのは、もったいぶった言い方をしたことを示す。無能がばれて明治政府から追い出された大隈重信が、演説で「あるんであるんである」と言ったのと似ている。
論語に限れば、前漢の定州竹簡論語が「矣」「而已」など一字か二字で済ませているところを、後漢を経た古注『論語集解義疏』では「而已矣」になっている箇所がある。論語解説「後漢というふざけた帝国」を参照。ただし本章に限れば、定州竹簡論語も「而已矣」と記している。
曹銀晶「談《論語》中的”也已矣”連用現象」(北京大学)によると、類語の「也已矣」は前漢宣帝期の定州論語にそんな表現は無いか、「矣」「也」「也已」と記されたという。要するに、漢帝国から南北朝にかけての儒者が、もったいを付けて幼稚なことを書いたのだ。
辞書的には論語語釈「而」・論語語釈「已」・論語語釈「矣」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章は、春秋戦国の誰一人引用せず、前漢初期の『韓詩外伝』巻三37に、「故君子之道,忠恕而已矣」とあるのが事実上の初出。ただし発言者を誰だとは特定していない。再出は定州竹簡論語で、前漢の半ばまでには、本章が論語の一篇に加えられたことになる。

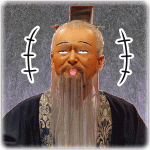
だが『韓詩外伝』も定州竹簡論語も、本章前半の孔子と曽子の対話を記していない。前半の「一以貫之」は論語衛霊公篇3で子貢を相手に「予一以貫之」と言い、この子貢との対話を『史記』孔子世家が再録している。文字史的にこちらが元ネタで、本章はその換骨奪胎版。
そして「一以貫之」は、前漢末期に王莽の取り巻きが、まだ少年の平帝に王莽を讃える上奏文を提出した中で用いられている。
此皆上世之所鮮,禹稷之所難,而公包其終始,一以貫之,可謂備矣!

以上申し上げました政治上の実績は、古来にもまれな素晴らしいもので、禹王や周の開祖でも真似の出来なかったことでございます。ところが王莽どのはこれら全てを完璧にやってのけましたし、仕官以来その完璧を貫いております。これほど出来る人物もおりますまい。(『漢書』王莽伝上35)
 +
+ =
=
先秦両漢の「一以貫之」はこれで全部で、定州竹簡論語より時代が下る王莽が、本章後半の創作者ではあり得ないが、なにやら王莽臭い文章ではある。本章の後半「忠恕」部分に孔子と子貢の対話をくっつけて、まるで遺伝子組み換え作物のようなものをこしらえた可能性はある。
解説
論語の本章では、曽子は孔子の筆頭弟子のような扱いを受けているが、この伝説が定州竹簡論語にあるからには、曽子の神格化は前漢前半には始まっていたのだろう。だが戦国時代の孟子や荀子は、曽子を弟子の一人として扱いはしても、筆頭としてあがめてはいない。
詳細は孟子は曽子をどう見たか・荀子は曽子をどう見たかを参照。
曽子が『孝経』の作者と見なされるなど、儒家の道統の上で孔子に次ぐ二代目と扱われるようになったのは、はるか後世の宋代のことで、宋儒は論語をはじめ儒教経典を、その道統に都合のよいよう確信犯的に書き換えた可能性がある。詳細は儒家の道統と有若の実像を参照。

明代の絵本『孔子聖蹟図』の一枚。ついたての真ん前が孔子、向かって左側で、他の弟子と違った偉そうな服を着ているのが曽子。
最後に儒者の言い分を見ておこう。古注では前漢武帝期の儒者と言われる孔安国が注を付けているが、この男は高祖劉邦の名を避諱(はばかって使わず、別の字に置き換えること)しないなど、実在そのものが疑わしい。
古注は「注」=本文への注釈と、「疏」=注釈の付け足しで成り立っているが、本章の「疏」には古注の原型を作った何晏の名が見えず、代わりに同時期(三国魏)の王弼の名が見えている。すなわち前半後半を伴った本章の完成は、典拠的には後漢滅亡後という事になる。
古注『論語義疏』
註孔安國曰直曉不問故荅曰唯也…疏子曰至已矣 云參乎者呼曾子名欲語之參曾子名也云吾道一以貫之哉者所語曾子之言也道者孔子之道也貫猶統也譬如以繩穿物有貫統也孔子語曾子曰吾教化之道唯用一道以貫統天下萬理也故王弼曰貫猶統也夫事有歸理有㑹故得其歸事雖殷大可以一名舉總其㑹理雖博可以至約窮也譬猶以君御民執一統衆之道也云胃子曰唯者唯猶今應爾也曾子曉孔子言故直應爾而已不諮問也云子出者當是孔子往曾子處得曾子荅竟後而孔子出戶去云門人問曰何謂也者門人曾子弟子也不解孔子之言故問於曾子也云曾子曰夫子之道忠恕而已矣者曾子荅弟子釋於孔子之道也忠謂盡中心也恕謂忖我以度於人也言孔子之道更無他法故用忠恕之心以已測物則萬物之理皆可窮驗也故王弼曰忠者情之盡也恕者反情以同物者也未有反諸其身而不得物之情未有能全其恕而不盡理之極也能盡理極則無物不統極不可二故謂之一也推身統物窮類適盡一言而可終身行者其唯恕也
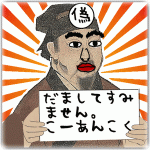

注釈。孔安国「回りくどい問いなので、”はい”とだけ答えたのである。」
付け足し。先生は真髄を騙りそれが記された。
「參乎」というのは曽子の名を呼んで、これと語りたかったのである。參とは曽子の名である。「吾道一以貫之哉」とは、曽子に語った言葉である。道とは孔子の道である。貫とはずっと続けてきたということである。丁度ヒモでものを繋げたような事を言う。
孔子が曽子に語ったこととは、「我が教えはたった一つの原則で天下のあらゆる事柄を見通すものである」ということだ。
だから王弼が言った。「貫とはまとめ上げるに近い。如何なる現象も原理原則に従うから作用できる。だからその原理は膨大なあらゆる現象をたった一つの原理にまとめたもので、どんな出来事でもその範疇で理解することが出来る。例えるなら、君主がただ一人で万民を統治するようなものである。」
胃子「唯とは、”今あなたの仰ったとおりです”という意味だ。曽子は孔子の言葉の隅々まで理解していたので、すぐさま”その通りです”と返事をし、問い返す必要が無かった。子出とは、孔子が曽子の目の前で問うたのに対し、曽子がすぐさま返事をしたので、満足して立ち去ったということだ。門人問曰何謂也とは、曽子の弟子が孔子の言葉の意味が分からず、曽子に問うたという事だ。曾子曰夫子之道忠恕而已矣とは、曽子が弟子に答えて、孔子の教説を解説してやったという事だ。忠とは真心を尽くすことだ。恕とは他人の立場で思いやるという事だ。」
本章の心は、孔子の道は他でもないことを言った。だから忠恕の心で森羅万象を見つめれば、理解できないことが無いのを示した。
だから王弼は言った。「忠とは心を尽くすことだ。恕とは相手を自分と同一視することだ。同一視が出来なければ、それが何でどうなっているかが分からない。同一視をまっとうできなければ、原理原則は理解できない。原理が理解できればこの世に分からないことなど無い。だからたった一つの道と言ったのだ。その原理は一言で言い尽くせる。そして生涯守り続けるべき者が、恕の心なのだ。」
おそらく前漢儒がでっち上げただろう本文に、一生懸命理屈を付けようとして、ますます黒魔術みたいにしている。これは古注の儒者もむしろ被害者で、儒者は儀礼の類を偽作する達人ではあったものの、ラノベ作家としては芸が無かったことの尻拭いをさせられている。
詳細は論語郷党篇8余話「音を立てるな」を参照。
新注『論語集注』
參,所金反。唯,上聲。參乎者,呼曾子之名而告之。貫,通也。唯者,應之速而無疑者也。聖人之心,渾然一理,而泛應曲當,用各不同。曾子於其用處,蓋已隨事精察而力行之,但未知其體之一爾。夫子知其真積力久,將有所得,是以呼而告之。曾子果能默契其指,即應之速而無疑也。
盡己之謂忠,推己之謂恕。而已矣者,竭盡而無餘之辭也。夫子之一理渾然而泛應曲當,譬則天地之至誠無息,而萬物各得其所也。自此之外,固無餘法,而亦無待於推矣。曾子有見於此而難言之,故借學者盡己、推己之目以著明之,欲人之易曉也。蓋至誠無息者,道之體也,萬殊之所以一本也;萬物各得其所者,道之用也,一本之所以萬殊也。以此觀之,一以貫之之實可見矣。或曰:「中心為忠,如心為恕。」於義亦通。程子曰:「以己及物,仁也;推己及物,恕也,違道不遠是也。忠恕一以貫之:忠者天道,恕者人道;忠者無妄,恕者所以行乎忠也;忠者體,恕者用,大本達道也。此與違道不遠異者,動以天爾。」又曰:「『維天之命,於穆不已』,忠也;『乾道變化,各正性命』,恕也。」又曰:「聖人教人各因其才,吾道一以貫之,惟曾子為能達此,孔子所以告之也。曾子告門人曰:『夫子之道,忠恕而已矣』,亦猶夫子之告曾子也。中庸所謂『忠恕違道不遠』,斯乃下學上達之義。」


參は所-金の反切の音である。唯は上がり調子に読む。參乎とは、曽子の名を呼んだのである。貫とは通すことである。唯とは、すぐさま返事して疑問が無いことを言う。聖人之心は一つの原理を分かちがたくまとめており、どんなことにも応用出来るが、その用い方はそのたび異なる。曽子はその応用について、たぶん熱心に極めていたが、ただし原則のなんたるかが分からなかった。先生は曽子の熱心を見て、教えてやろうと考えて、呼んで問うたのだ。果たして曽子は先生の暗示をすぐさま悟り、即座に返事して疑問を解いたのだ。
自分を捧げ尽くすのを忠と言い、相手を自分と同一視するのを恕という。而已矣とは、言い尽くしてそれ以外には何も無い、ということだ。先生の示す原理は全てを包括し全てに応用出来る。例えるなら天地は窮極の真心を持ち意志がないから、万物がその場を与えられているようなものである。これ以外に、真理は存在しないし、余計な詮索の必要も無い。曽子はこの曰く言いがたい真理を知ろうとしたから、自分の全てを尽くして学び、全てを自分と同一視することで真理を理解し、人に説明してやろうと思った。
思うに窮極の真心を持ち欲を持たないことが、真理の本体である。万物はこのたった一つによって生かされている。万物がそのように生かされていることが、真理の作用した結果である。そのように考えれば、たった一つの真理が万物を貫き満たしているさまを見て取れる。
ある人が言った。「真心を忠と言い、心のままを恕と言う。」そう解してもよい。
程頤「自分と同一視して”してやる”のは、仁である。自分と同一視して”思いやる”のは、恕である。やっていることは違うようだが、実はほとんど同じである。忠恕はただ一つの真理として万物を貫いている。忠を行うのは天の道を行くことであり、恕を行うのは人の道を行くことである。忠なる者には妄想が無い。恕なる者が実行するのが忠なのである。忠は本体であり、恕はその作用である。偉大な原則であり真理に達している。この真理とやり方は違えども遠くないものが、どうかすると天をも左右する。」
程頤はこうも言った。「ただ天の命だけが、おだやかで止まない、という。これが忠である。天の変化が、万物の運命を正しくする、という。これが恕である。」
こうも言った。「聖人は人を見て法を説く。”吾道一以貫之”とだけ言えば分かったのは、曽子だけだった。だから孔子はそう言った。そして曽子は弟子に、”先生の道は忠恕だけだ”と言った。それもまた先生が、曽子に暗示したことである。『中庸』が言う”忠と恕はやり方が違うが遠くない”とは、分からぬ者がわかった者に教わって分かることわりを言ったのだ。」
程子=程頤がワケわかめな事を言っているのは、儒教に黒魔術を持ち込んだ張本人だからで、無理に分かる必要は無いし、分かる価値があることも言っていない。後世の西田キタロー同様、ひたすら難解なことを言って、世間にハッタリを掛けていただけなのだから。
詳細は論語雍也篇3余話「宋儒のオカルトと高慢ちき」を参照。
それでも儒者だって人間で、金のために偽作をこしらえたには違いない。材料の無いところから無理にでもコジツケやウンチクを創作するのは、それはそれで苦労したらしい。出世のために頑張っても、うまく行かない儒者を『笑府』が次のように例えている。
一士屢科不利。其妻素患難產。謂夫曰。這一節。與生產一般艱難。士曰。你卻是有在肚裡。
ある儒者、何度科挙(高級官僚採用試験)を受けても落ちてしまう。その妻は、生まれつき難産の体質だった。
妻「試験って、お産と同じぐらいには難しいものなのですね。」
儒者「それでもお前の場合は、腹の中にあるものを出すだけで済むからいいや。」(『笑府』巻二・産喩)
余話
ネズミ男


なお西田キタローはわけワカメなことばかり言いふらした挙げ句、だんだんと世間師稼業がうまく行かなくなったらしく、東条英機にゴマをすって取り入ろうとした。だが東条はそのあまりにあからさまなやり口に呆れ返り、放置して付き合おうとはしなかった。
怒ったキタローは東条の悪口を書き、ただし憲兵を恐れて仲間だけに配ったらしい。キタローの説が戦前にもてはやされたのは、黒船以来の対横文字劣等感がある日本人に、一時的かゆみ止めとして作用したからで、今なおその真似をして、難読無意味な論文は文系業界に多い。

何も書いてありはしないのだ。閲覧者諸賢はどうか恐れず、笑い飛ばして頂きたい。





コメント