論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子貢曰夫子之文章可得而聞也夫子之言性與天道不可得而聞也
校訂
諸本
- 武内本:史記世家引、也已に作り、漢書睦宏伝引已矣に作り、外戚伝注引也已矣に作る。
東洋文庫蔵清家本
子貢曰夫子之文章可得而聞也/夫子之言性與天道不可得而聞也已矣
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
(なし)
※定州竹簡論語には他章句末に「也已矣」の用例無く「也已」または「也」のみ見られる。
標点文
子貢曰、「夫子之文章、可得而聞也。夫子之言性與天道、不可得而聞也已。」
復元白文(論語時代での表記)




























※貢→(甲骨文)。論語の本章は「也」の用法に疑問がある。
書き下し
子貢曰く、夫子之文章は得而聞く可き也、夫子之性與天つ道とを言ふは、得而聞く可から不る也已。
論語:現代日本語訳
逐語訳

子貢が言った。「先生の文学と歴史の話は聞いてよく分かることが出来た。先生の生物学と天文学の話は聞いてよく分かることが出来ないまま終わって仕舞った。」
意訳

子貢「先生の文系の話は良く分かったが、理系の話はよく分からなかった。」
従来訳
子貢がいった。――
「先生のご思想、ご人格の華はなというべき詩書礼楽のお話や、日常生活の実践に関するお話は、いつでもうかがえるが、その根本をなす人間の本質とか、宇宙の原理とかいう哲学的なお話は、容易にはうかがえない。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
子貢說:「老師的文章,可以聽得到;老師有關本性和天道的理論,不是光靠聽就能理解的。」
子貢が言った。「先生の文章は、聞いて分かった。先生の本性や天道の理論は、聞いただけでは理解できなかった。」
論語:語釈
子貢

孔子の弟子。姓は端木、いみ名は賜、あざ名は子貢。孔門十哲の一人で、宰予子我と共に「言語」の才を挙げられている。孔門の中で政界ではもっとも栄達し、経営の才にも優れておそらく一門の財政を支えた。春秋末期の外交界でも活躍し、『史記』によれば呉の覇権を破って越に勝利させたのは子貢の計略に依った。孔子逝去の折には他の弟子の倍、六年喪に服し、孔子の墓のそばで生前のように仕えた。詳細は論語の人物:端木賜子貢参照。


(甲骨文)
「子」の初出は甲骨文。字形は赤ん坊の象形。春秋時代では、貴族や知識人への敬称に用いた。季康子や孔子のように、大貴族や開祖級の知識人は「○子」と呼び、一般貴族や孔子の弟子などは「○子」と呼んだ。詳細は論語語釈「子」を参照。


(甲骨文)
「貢」の初出は甲骨文。その後一旦出土が絶え、再出は前漢まで時代が下る。従って、殷周革命で一旦滅びた漢語である可能性がある。ただし固有名詞「子貢」として用いる場合、同音近音のあらゆる漢字が置換候補になり得るし、端木賜子貢の実在を疑えるわけでもない。甲骨文での語義は”貢ぐ”。字形は取っ手の付いた物体+〔二〕だが、何を意味しているか分からない。詳細は論語語釈「貢」を参照。
曰(エツ)


(甲骨文)
論語で最も多用される、”言う”を意味する言葉。初出は甲骨文。原義は「𠙵」=「口」から声が出て来るさま。詳細は論語語釈「曰」を参照。
夫子(フウシ)


(甲骨文)
論語の本章では”孔子先生”。従来「夫子」は「かの人」と訓読され、「夫」は指示詞とされてきた。しかし論語の時代、「夫」に指示詞の語義は無い。同音「父」は甲骨文より存在し、血統・姓氏上の”ちちおや”のみならず、父親と同年代の男性を意味した。従って論語における「夫子」がもし当時の言葉なら、”父の如き人”の意味での敬称。詳細は論語語釈「夫」を参照。
「子」は貴族や知識人に対する敬称。論語語釈「子」を参照。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章では「の」と読んで”~の”。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”。足を止めたところ。原義は”これ”。”これ”という指示代名詞に用いるのは、音を借りた仮借文字だが、甲骨文から用例がある。”…の”の語義は、春秋早期の金文に用例がある。詳細は論語語釈「之」を参照。
文(ブン)


(甲骨文)
論語の本章では”彫り付けたもの”→”文字”→”文学”。初出は甲骨文。「モン」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。原義は”入れ墨”で、甲骨文や金文では地名・人名の他、”美しい”の例があるが、”文章”の用例は戦国時代の竹簡から。詳細は論語語釈「文」を参照。
章(ショウ)


(殷代金文)
論語の本章では”記されたもの”→”記録”→”史学”。初出は殷代末期の金文。字形は〔䇂〕(漢音ケン)”筆刀”+亀甲で、亀甲に文字を刻むさま。原義は”文章”。金文では”玉”・”玉器”の意に用いた。詳細は論語語釈「章」を参照。
可(カ)


(甲骨文)
論語の本章では”~できる”。初出は甲骨文。字形は「口」+「屈曲したかぎ型」で、原義は”やっとものを言う”こと。甲骨文から”~できる”を表した。日本語の「よろし」にあたるが、可能”~できる”・勧誘”…のがよい”・当然”…すべきだ”・認定”…に値する”の語義もある。詳細は論語語釈「可」を参照。
得(トク)


(甲骨文)
論語の本章では”手に入れる”。初出は甲骨文。甲骨文に、すでに「彳」”みち”が加わった字形がある。字形は「貝」”タカラガイ”+「又」”手”で、原義は宝物を得ること。詳細は論語語釈「得」を参照。
而(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”~かつ~”。初出は甲骨文。原義は”あごひげ”とされるが用例が確認できない。甲骨文から”~と”を意味し、金文になると、二人称や”そして”の意に用いた。英語のandに当たるが、「A而B」は、AとBが分かちがたく一体となっている事を意味し、単なる時間の前後や類似を意味しない。詳細は論語語釈「而」を参照。
可得而(えて…べし)
漢文では”できるようになる”や”してよい(か)”を表すが、論語ではこの言い廻しは本章だけで、孔子とすれ違うように春秋末から戦国を生きた墨子や、孔子没後一世紀に生まれた孟子からよく見られるようになる。少なくとも孔子生前の漢語としては、もったいぶった表現であり、後世「可」→「可得而」に書き換えられた可能性がある。
聞(ブン)
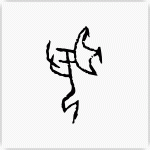
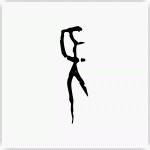
(甲骨文1・2)
論語の本章では”(先生の教えを)聞く”。初出は甲骨文。「モン」は呉音。甲骨文の字形は「耳」+「人」で、字形によっては座って冠をかぶった人が、耳に手を当てているものもある。原義は”聞く”。「耳」+「人」と見える字形も甲骨文にはある。詳細は論語語釈「聞」を参照。
也(ヤ)


(金文)
論語の本章では、「なり」と読んで断定の意。第四句では「かな」と読んで詠歎の意に解してもかまわないが、断定の語義は春秋時代では確認できない。初出は事実上春秋時代の金文。字形は口から強く語気を放つさまで、原義は”…こそは”。春秋末期までに句中で主格の強調、句末で詠歎、疑問や反語に用いたが、断定の意が明瞭に確認できるのは、戦国時代末期の金文からで、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「也」を参照。
言(ゲン)


(甲骨文)
論語の本章では”発言”。初出は甲骨文。字形は諸説あってはっきりしない。「口」+「辛」”ハリ・ナイフ”の組み合わせに見えるが、それがなぜ”ことば”へとつながるかは分からない。原義は”言葉・話”。甲骨文で原義と祭礼名の、金文で”宴会”(伯矩鼎・西周早期)の意があるという。詳細は論語語釈「言」を参照。
性(セイ)


(金文)
論語の本章では”生物学”。初出は西周中期の金文。ただし「生」と書き分けられていない。りっしんべんが付くようになったのは、後漢の『説文解字』から。「ショウ」は呉音。「生」とは若干音が異なる。同音は「省」「姓」「騂」。字形は「生」”地面から植物が生い育つさま”。原義は”生き物”で、のち”生き物の性質”を表すためりっしんべんが付いた。春秋末期までにりっしんべんの付いた字形は見られず、「性」と語釈された例も一例のみで、それもその読みには無理がある。「生」=”生物”と解するべき。詳細は論語語釈「性」を参照。


伝統的な論語の解釈では、「性」を儒学の一大眼目である「性命論」(天から授けられた、人の持ちまえの性質とは何か、という議論)として捉え、孔子はそれを子貢には言わなかった、とする。しかし性命論がやかましくなったのは戦国時代の孟子と荀子によるもの。孔子の生前に遡ってこの語義をあてがうことは出来ない。
定州竹簡論語・論語陽貨篇2では「性」を「生」と記しており、本章は定州竹簡論語に存在しないが、仮に論語の本章を史実とするなら、後漢儒がが性命論に都合のよいよう書き換えた可能性がある。
與(ヨ)


(金文)
論語の本章では、”~と”。新字体は「与」。新字体初出は春秋中期の金文。金文の字形は「牙」”象牙”+「又」”手”四つで、二人の両手で象牙を受け渡す様。人が手に手を取ってともに行動するさま。従って原義は”ともに”・”~と”。詳細は論語語釈「与」を参照。
天(テン)

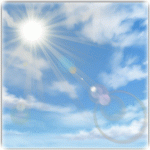
(甲骨文)
論語の本章では”天体”。初出は甲骨文。字形は人の正面形「大」の頭部を強調した姿で、原義は”脳天”。高いことから派生して”てん”を意味するようになった。甲骨文では”あたま”、地名・人名に用い、金文では”天の神”を意味し、また「天室」”天の祭祀場”の用例がある。詳細は論語語釈「天」を参照。
なお殷代まで「申」と書かれた”天神”を、西周になったとたんに「神」と書き始めたのは、殷王朝を滅ぼして国盗りをした周王朝が、「天命」に従ったのだと言い張るためで、文字を複雑化させたのはもったいを付けるため。「天子」の言葉が中国語に現れるのも西周早期で、殷の君主は自分から”天の子”などと図々しいことは言わなかった。詳細は論語述而篇34余話「周王朝の図々しさ」を参照。
道(トウ)


(甲骨文)
論語の本章では”運行”。初出は甲骨文。「ドウ」は呉音。動詞で用いる場合は”みち”から発展して”導く=治める・従う”の意が戦国時代からある。”言う”の意味もあるが俗語。字形に「首」が含まれるようになったのは金文からで、甲骨文の字形は十字路に立った人の姿。原義は”みち”。”道徳”の語義は戦国時代にならないと現れない。詳細は論語語釈「道」を参照。
天道(テントウ)
論語の本章では”天の運行”→”天文学”。正確なこよみの作成に不可欠で、天文学がいい加減では、古代では例えば饑饉を招き、現代社会も時計が狂えば例えば物流が成り立たない。古代から現在に至るまで、人間社会の盛衰を左右する、極めて重要な学問だった。

渾天儀。中国独自の天体観測機器。
不(フウ)


(甲骨文)
漢文で最も多用される否定辞。初出は甲骨文。原義は花のがく。否定辞に用いるのは音を借りた派生義。詳細は論語語釈「不」を参照。現代中国語では主に「没」(méi)が使われる。
也→也已(なるのみ)
唐石経は「也」とのみ記し、清家本は「也已矣」と記す。「也已矣」は「也」を強調した表現。
清家本は年代こそ唐石経より新しいが、唐朝廷の都合で書き換えられる前の論語の文字列を伝承しており、唐石経を訂正しうる。ただし論語の本章には全文を欠くものの、現存最古の論語本である定州竹簡論語の章末には「也」または「也已」の用例のみあり、「也已矣」は見られない。従って「也」→「也已」へと校訂した。
論語の伝承について詳細は「論語の成立過程まとめ」を参照。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)
清家本が伝えるのは古注『論語集解義疏』系統の文字列だが、古注はやたらと意味なき言葉をつけ加える癖がある。「也」→「也已矣」もその一つで、あえて訳せば、「あるんであるんである」という、晩年になって頭がぼけた大隈重信のような言い廻しとなる。
論語:付記
検証
論語の本章は、春秋戦国の誰一人引用せず、前漢中期の『史記』の、弟子伝ではなく孔子世家に、子貢の言として記されるのが初出。また前漢中期の終わりごろに埋蔵された定州竹簡論語から漏れている。従って前漢末期以降になって、論語に取り込まれた可能性がある。
だが文字的には無理なく論語の時代に遡れる。「生」を「性」と解する時代錯誤に付き合わなければ、本章はごく当たり前の一弟子の回想と解しうる。
解説
論語の本章を、孟子以降の「性命論」(人間は本来善か悪か)として解する本があるが、全く賛成出来ない。上記の通り、春秋末期以前にりっしんべんを伴った「性」の字は存在せず、「生」を「性」と釈文した例も一例しかなく、そしてその釈文はかなり強引だからだ。
孟子が生まれたのは孔子没後一世紀で、荀子はらにその60年後になる。孔子が性命論を説くことがあり得ない。また古代では天文学や生物学は極めて重要で、農作の結果を左右しその如何で国が栄えも滅びもしたから、性命論のような宗教論議をしている余裕は無かった。
孔子塾とは平民出身の塾生が、君子=貴族にふさわしい技能と教養を身につけて身分を格上げする場所であり、貴族の教養とは読み書きと算術、歴史の知識、そして詩を含む音楽だった。歴史を共有する者こそ同じ文明に属する者であり、史学の知識は中華人のあかしでもあった。
算術を必須としたのは、役人として計量と記帳に必要があるからであり、また将校として戦場での部隊編成や作戦立案に不可欠だったからだ。こうした孔子塾の必須科目を六芸と言うが、のこりは戦車の操縦と弓術であり、戦士としての技能だった(論語における「君子」)。
すると論語の本章で子貢が言う生物学や天文学は、いわゆる選択科目ということになる。孔子自身は若い頃、牧場の管理人として家畜を肥え太らせた実績があるから(『史記』孔子世家)、現代で言えば農業技師として働いた経験があることになる。
また博物の段階を出ていないものの、異様なけものを「麟」だと見抜いたり(孔子世家)、越で出土した巨骨や、季氏の屋敷の井戸から出てきた化石のなんたるかについて、それが現代科学の批判に耐えるかはともかく、問う者にうんちくをたれて感心されている(孔子世家1/2)。
孔子時代の天文学については、論語が甲骨文や金文を除けばもっとも古い文献であることから、よくわからない。しかし論語に次いで古いと思われる『春秋』などでは、同時代人が注意深く天文を観察したことが伺えるし、1年が約365+1/4日であるとすでに分かっていた。
しかしそうした科学技術の担い手は、君子=貴族ではなく職人集団だったようで、ひょっとすると職能奴隷階級の技術だったかも。従って君子の教養とは見なされず、孔子塾の必須科目=六芸にも、「数」は入っているが「天道」「性」は入っていない。
孔子自身は「身分が低かったから多芸になった」(論語子罕篇6)と述解しているように、「天道」=天文学、「性」=生物学にも詳しかっただろう。天文学については『左伝』哀公十二年(BC483)の条に記事がある。
冬十二月、暦では寒い季節のはずなのに、夏に出るイナゴの被害が起こった。筆頭家老の季康子が孔子にわけを問うた。
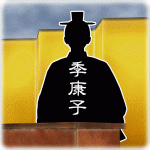

孔子「火星が地平線に隠れてから、イナゴの害は収まるものです。今火星はまだ西の空に上がっています。これは天文官が暦を作り間違えたのです。」
また孔子は月の運行から天気を予報し、弟子の子の生誕を予言した。それについて没後、顔が似ているという理由で後継者に一端据えられた有若は、孔子が予言できた理由を弟弟子に問われて答えられず、ボンクラだとして降ろされた伝説がある(論語の人物:有若子有)。
なお古注は「性」をもちろん性命論で捉えている。
古注『論語集解義疏』
註章明也文彩形質著見可得以耳目自修也…註性者人之所受以生者也天道者元亨日新之道也深微故不可得而聞也注釈。
注釈。何晏「章とは明らかなことである。文章の修辞や文体は見ればはっきりと分かる。それで目や耳を鍛えるのである。…性とは人が生を受けた理由のことである。そもそも生まれ、そして寿命が日々続いていく根本原因のことである。これははなはだ微妙で奥深い事柄なので、なので”得て聞くべからざる”と言った。」
オカルトが大好きな新注の宋儒も変わらない。
新注『論語集注』
文章,德之見乎外者,威儀文辭皆是也。性者,人所受之天理;天道者,天理自然之本體,其實一理也。言夫子之文章,日見乎外,固學者所共聞;至於性與天道,則夫子罕言之,而學者有不得聞者。蓋聖門教不躐等,子貢至是始得聞之,而歎其美也。程子曰:「此子貢聞夫子之至論而歎美之言也。」
文章とは書き手の人徳が表に現れたものである。立ち居振る舞いや言葉の修辞はどれもその例である。性とは、人が天から受けた根本法則である。天道とは、天の法則をあるがままに運営する本体であり、それは全く一つの根本法則に行きつく。
夫子之文章と本文にあるのは、毎日孔子の所作として観察できること、弟子として毎日聞く話である。性と天道については、先生はめったに言わなかった(論語子罕篇1。偽作)。だから弟子はめったに聞けなかったのである。
たぶん先生の聖なる教えは弟子の出来の程度以上を語らなかった。子貢は初めて性と天道の教えを聞いて、その素晴らしさを賛美したのだ。
程頤「この章は、子貢が先生の奥義を聞いて賛美したのである。」
オカルト以外に何も言っていないとお分かりだろうか。論語雍也篇3余話「宋儒の高慢とオカルト」も参照されたい。
余話
論語時代のサファリパーク
子貢が本章で数理に関わる感慨を述べたのは、彼自身興味があったからだろう。商売や外交といった現実的な才に、弟子の中で最高の業績を残しているからには、いわゆる理数系に興味を持って当然だから。珍しい産物が出たと聞けば、車を飛ばして買い付けに出かけたかも。
珍しい産物と言えば『左伝』の記述によれば、黄河流域の晋国で「龍」が出たと書いてある(昭公二十九年=BC513)。おそらくはワニだろうが、今日でも揚子江にはヨウスコウワニが住んでいる。それだけ当時の華北は温かかったわけ。

また論語の時代はサイの皮を武具に用いており、華南にはゾウもいた可能性がある。ゾウはこんにちでも雲南当たりで群れが見られるという。また孔子と縁の深いけものに、「仁獣」である「麟」がいる。漢語の上では麒麟の雌だが、いったいどのような獣だったかわからない。
麒麟が首の長いジラフでないことはもちろんだが、『封神演義』で太公望が乗り回している四不象が中国で絶滅する寸前に英国へ輸出されて現存するように、今では絶えてしまった実在の獣である可能性がある。だが早くから龍馬と混同され、鱗の生えた馬のような獣とされた。

『三才図会』鳳・龍馬 東京大学東洋文化研究所蔵
それも『笑府』はからかっている。
孔子見死麟。哭之不置。弟子謀所以慰之者。乃編錢掛牛體。告孔子曰。麟已活矣。孔子觀之。曰非也。分明一隻牛。只多這幾箇錢耳。

孔子が麟の死んだ姿を見て嘆き、全然泣き止まない。弟子が孔子を慰めようとして、銭を編んで牛に掛け、「麟が生き返りました」と孔子に言った。
それを見た孔子「こんなの麟じゃない。牛じゃないか。ケチケチせずにもう少し銭を足せば、麟らしくなるのに。」(『笑府』巻一・麟)
中国の古記録に嘘ハッタリは付き物だが、全てをニセだと断じるわけにはいかない。麒麟だっていたかも知れず、人間の見た目による種の分類は当てにならない。首の長いキリンは人間には一種に見えるが、遺伝子を調べると掛け合わせることの出来ない数種類に分かれるという。


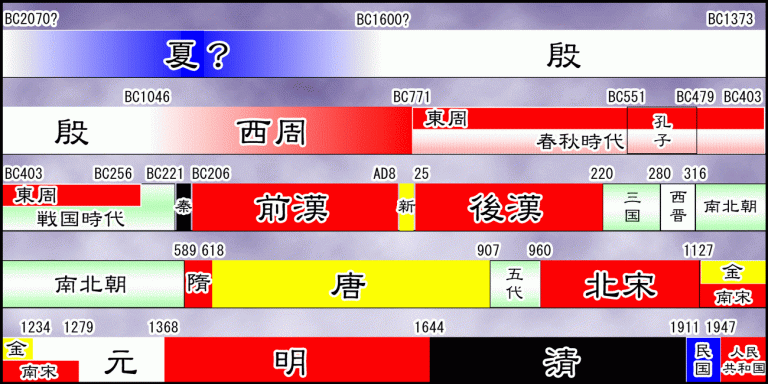
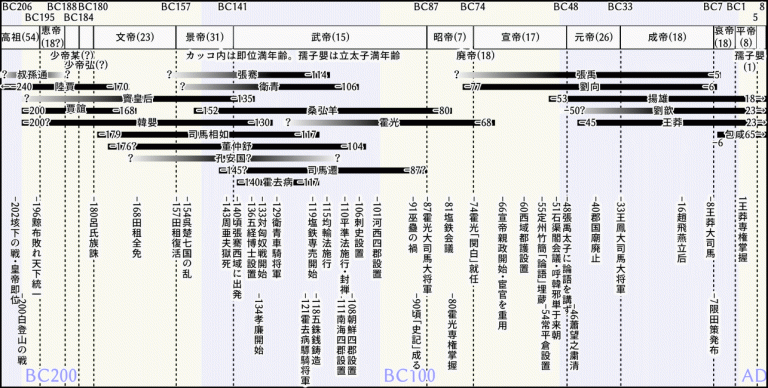



コメント