論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子曰道不行乗桴浮于海從我者其由與子路聞之喜子曰由也好勇過我無所取材
- 「海」字:〔𠂉〕→〔亠〕
校訂
諸本
- 武内本:漢書地理志顔注引也歟に作る。
東洋文庫蔵清家本
子曰道不行乗桴浮於海從我者其由也與/子路聞之喜/子曰由也好勇過我無所取材
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
子曰:「道不行,乘泡a浮於海。從我者,其由b與。」子路□80之喜。子曰:「由也,好勇過我,無所取材。」81
- 泡、今本作「桴」、泡誤。古桴、枹同通、枹・泡形近。
- 於、阮本作「于」、皇本作「於」。
標点文
子曰、「道不行、乘泡浮於海、從我者、其由與。」子路聞之喜。子曰、「由也好勇過我、無所取材。」
復元白文(論語時代での表記)


































※泡(桴)→付・材→才。論語の本章は、「從」「與」「過」の用法に疑問がある。
書き下し
子曰く、道行か不、桴に乗つて海於浮ばむ。我に從ふ者は其れ由與。子路之を聞いて喜ぶ。子曰く、由也勇を好むこと我に過ぐるも、材を取る所無しと。
論語:現代日本語訳
逐語訳


先生が言った。「理想の政治が行われない。いかだに乗って海に浮かぼう。私に従う者は由(子路)だろう」。子路がそれを伝え聞いて喜んだ。先生が言った。「由は勇気を好む事私以上だが、材料を取る場所が無い。」
意訳

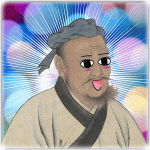
孔子「あーあ。ひどい世の中だ。いかだに乗って外国へ行ってしまおう。でも付いてくるのは子路だけかな?」子路はこのつぶやきを伝え聞いて喜んだそうだ。そこで言った。
「子路は私以上の武芸者で頼もしいが、肝心のいかだの材料はどうしようか。」
 Photo via https://pixabay.com/ja/
Photo via https://pixabay.com/ja/
従来訳
先師がいわれた。――
「私の説く治国の道も、到底行われそうにないし、そろそろ桴にでも乗って海外に出ようと思うが、いよいよそうなった場合、私について来てくれるのは、由かな。」
子路はそれをきいて大喜びであった。すると先師がまたいわれた。――
「ところで、由は、勇気を愛する点では私以上だが、分別が足りないので、いささか心細いね。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子說:「理想無法實現了,我準備乘筏漂到海上。會跟我走的,衹有子路吧?」子路聽說後很高興。孔子說:「子路啊,他比我勇敢,但缺乏才能。」
孔子が言った。「理想は実現しそうにない。私はいかだを用意して海上を漂うとしよう。私と共に行ってくれるのは、ただ子路だけかな?」子路は聞き終えてたいそう喜んだ。孔子が言った。「子路はのう、私に比べて勇敢だが、ただし才能に乏しい。」
論語:語釈
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。


(甲骨文)
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
道(トウ)
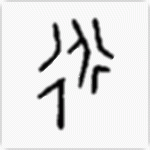

「道」(甲骨文・金文)
論語の本章では”原則”→”孔子の求める理想の政道”。動詞で用いる場合は”みち”から発展して”導く=治める・従う”の意が戦国時代からある。”言う”の意味もあるが俗語。初出は甲骨文。字形に「首」が含まれるようになったのは金文からで、甲骨文の字形は十字路に立った人の姿。「ドウ」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。詳細は論語語釈「道」を参照。
不(フウ)


(甲骨文)
漢文で最も多用される否定辞。初出は甲骨文。「フ」は呉音、「ブ」は慣用音。原義は花のがく。否定辞に用いるのは音を借りた派生義だが、甲骨文から否定辞”…ない”の意に用いた。詳細は論語語釈「不」を参照。
行(コウ)


(甲骨文)
論語の本章では”行く”。初出は甲骨文。十字路を描いたもので、真ん中に「人」を加えると「道」の字になる。甲骨文や春秋時代の金文までは、”みち”・”ゆく”の語義で、”おこなう”の語義が見られるのは戦国末期から。詳細は論語語釈「行」を参照。
乘(ショウ)
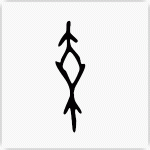

(甲骨文)
論語の本章では”乗る”。初出は甲骨文。新字体は「乗」。「ジョウ」は呉音。甲骨文の字形は人が木に登ったさまで、原義は”のぼる”。甲骨文では原義に加えて人名に、金文では”乗る”、馬車の数量詞、数字の”四”に用いられた。詳細は論語語釈「乗」を参照。
桴(フウ)→泡(ホウ)


(戦国金文)
論語の本章では”木製のいかだ”。論語では本章のみに登場。『大漢和辞典』の第一義は”棟木”。竹製のいかだは筏と書く。初出は戦国時代末期の金文。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補は「付」。「フウ」の音で太鼓の”ばち”・”横木”、「フ」の音で”いかだ”を意味する。同音に孚(卵をかえす)とそれを部品とする漢字群、卜を部品とする漢字群。字形は「木」+「孚」”子を捕らえた様”で、「孚」は音符で意味が無い。詳細は論語語釈「桴」を参照。


「泡」(篆書)
定州竹簡論語の「泡」の初出は後漢の『説文解字』。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。字形は「氵」+「包」”胎児”で、胎児のように丸くて自ら浮き上がってくるあわ。原義は”水の沸き立つさま”。『説文解字』は「包」は音符で語義に関わりがなく、全体で古代の川の名とするが、前漢末期の『方言』で”盛り上がる”の意として使われている。”いかだ”の語義は他の資料に確認できない。定州竹簡論語の注釈が言うように、誤字と思われる。詳細は論語語釈「泡」を参照。
浮(フウ)


(金文)
論語の本章では”浮かぶ”→”漕ぎ出す”。初出は春秋時代の金文。「フ」は慣用音。呉音は「ブ」。字形は「氵」+「孚」”子供を捕まえたさま”で、「孚」はおそらく音符で意味が無い。原義は”浮かぶ”。金文では氏族名に用いた。詳細は論語語釈「浮」を参照。
於(ヨ)


(金文)
論語の本章では”~に”。初出は西周早期の金文。ただし字体は「烏」。「ヨ」は”~において”の漢音(遣隋使・遣唐使が聞き帰った音)、呉音は「オ」。「オ」は”ああ”の漢音、呉音は「ウ」。現行字体の初出は春秋中期の金文。西周時代では”ああ”という感嘆詞、または”~において”の意に用いた。詳細は論語語釈「於」を参照。
海(カイ)


(金文)
論語の本章では”うみ”。初出は西周早期の金文。新字体は「海」。中国・台湾・香港では新字体がコード上の正字として扱われている。字形は「氵」+「每」”暗い”。原義は深く暗い海。金文では原義に用いた。詳細は論語語釈「海」を参照。
從(ショウ)


(甲骨文)
論語の本章では、”つき従う”。初出は甲骨文。新字体は「従」。「ジュウ」は呉音。字形は「彳」”みち”+「从」”大勢の人”で、人が通るべき筋道。原義は筋道に従うこと。甲骨文での解釈は不詳だが、金文では”従ってゆく”、「縦」と記して”好きなようにさせる”の用例があるが、”聞き従う”は戦国時代の「中山王鼎」まで時代が下る。詳細は論語語釈「従」を参照。
我(ガ)


(甲骨文)
論語の本章では”わたし(に)”。初出は甲骨文。字形はノコギリ型のかねが付いた長柄武器。甲骨文では占い師の名、一人称複数に用いた。金文では一人称単数に用いられた。戦国の竹簡でも一人称単数に用いられ、また「義」”ただしい”の用例がある。詳細は論語語釈「我」を参照。
者(シャ)


(金文)
論語の本章では”…する者は”。旧字体は〔耂〕と〔日〕の間に〔丶〕一画を伴う。新字体は「者」。ただし唐石経・清家本ともに新字体と同じく「者」と記す。現存最古の論語本である定州竹簡論語も「者」と釈文(これこれの字であると断定すること)している。初出は殷代末期の金文。金文の字形は「木」”植物”+「水」+「口」で、”この植物に水をやれ”と言うことだろうか。原義は不明。初出では称号に用いている。春秋時代までに「諸」と同様”さまざまな”、”~する者”・”~は”の意に用いた。漢文では人に限らず事物にも用いる。詳細は論語語釈「者」を参照。
其(キ)


(甲骨文)
論語の本章では”それは”という代名詞。「我に従う者」の言い換え。初出は甲骨文。原義は農具の箕。ちりとりに用いる。金文になってから、その下に台の形を加えた。のち音を借りて、”それ”の意をあらわすようになった。人称代名詞に用いた例は、殷代末期から、指示代名詞に用いた例は、戦国中期からになる。詳細は論語語釈「其」を参照。
由(ユウ)


(甲骨文)
論語の本章では、史料に記録が残る孔子の最初の弟子。本名(いみ名)は仲由、あざなは子路。通説で季路とも言うのは孔子より千年後の儒者の出任せで、信用するに足りない(論語先進篇11語釈)。詳細は論語の人物:仲由子路を参照。
なお「由」の原義は”ともし火の油”。詳細は論語語釈「由」を参照。だが子路の本名の「由」の場合は”経路”を意味し、ゆえにあざ名は呼応して子「路」という。ただし漢字の用法的には怪しく、「由」が”経路”を意味した用例は、戦国時代以降でないと確認できない。
與(ヨ)


(金文)
論語の本章では、”…か”。この語義は春秋時代では確認できない。新字体は「与」。論語の本章では、”~と”。新字体初出は春秋中期の金文。金文の字形は「牙」”象牙”+「又」”手”四つで、二人の両手で象牙を受け渡す様。人が手に手を取ってともに行動するさま。従って原義は”ともに”・”~と”。詳細は論語語釈「与」を参照。
子路(シロ)
論語の本章では史料に記録が残る孔子の最初の弟子、仲由子路のこと。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、子路のように学派の弟子や一般貴族は「子○」と呼び、孔子のような学派の開祖や大貴族は「○子」と読んだ。「子」は古くは殷の王族を意味した。詳細は論語語釈「子」を参照。


「路」(金文)
「路」の初出は西周中期の金文。字形は「足」+「各」”夊と𠙵”=人のやって来るさま。全体で人が行き来するみち。原義は”みち”。「各」は音符と意符を兼ねている。金文では「露」”さらす”を意味した。詳細は論語語釈「路」を参照。
聞(ブン)→□
定州竹簡論語では、「子路」と「之喜」の間に一字分あってその字形が判読できない。従って何が書かれていたかは不明。この部分に相当する簡80号・81号は上下が欠けること無く揃っており、かつ80号は本章頭の「子」が先頭で、判読不能の「□」が末尾にあった。横書きにして記せば以下の通り。
子曰道不行乘泡浮於海從我者其由與子路□簡80号
之喜子曰由也好勇過我無所取材簡81号
現在の論語の本章に関して、中国伝承論語の祖である唐石経、日本伝承論語の祖である清家本は、この□部分を「聞」と伝えており、紙本で最古の論語である宮内庁蔵南宋版『論語注疏』でも「聞」となっているが、掲載手続きが面倒なのでここには載せない。

唐開成石経
「聞」は論語の本章では”聞く”。初出は甲骨文。「モン」は呉音。甲骨文の字形は「耳」+「人」で、字形によっては座って冠をかぶった人が、耳に手を当てているものもある。原義は”聞く”。詳細は論語語釈「聞」を参照。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章では”これ”。自分を指す。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”…の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。
喜(キ)
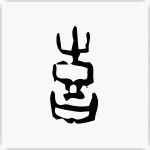

(甲骨文)
論語の本章では”よろこぶ”。初出は甲骨文。初出は甲骨文。字形は「壴」”つづみ”+「𠙵」”くち”で、太鼓を叩きながら歌を歌うさま。原義は”神楽”。甲骨文では原義のほか人名・国名に、”よろこぶ”の意に用い、金文では人名と楽曲名のほかは、”祭祀”、原義に用いた。詳細は論語語釈「喜」を参照。
也(ヤ)


(金文)
論語の本章では、「や」と読んで主格の強調に用いている。初出は事実上春秋時代の金文。字形は口から強く語気を放つさまで、原義は”…こそは”。春秋末期までに句中で主格の強調、句末で詠歎、疑問や反語に用いたが、断定の意が明瞭に確認できるのは、戦国時代末期の金文からで、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「也」を参照。
好(コウ)


(甲骨文)
論語の本章では”好む”。初出は甲骨文。字形は「子」+「母」で、原義は母親が子供を可愛がるさま。春秋時代以前に、すでに”よい”・”好む”・”親しむ”・”先祖への奉仕”の語義があった。詳細は論語語釈「好」を参照。
勇(ヨウ)


(金文)
論語の本章では、”勇気”。現伝字形の初出は春秋末期あるいは戦国早期の金文。部品で同音同訓同調の「甬」の初出は西周中期の金文。「ユウ・ユ」は呉音。字形は「甬」”鐘”+「力」で、チンカンと鐘を鳴るのを聞いて勇み立つさま。詳細は論語語釈「勇」を参照。
過(カ)
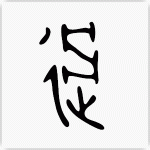

(金文)
論語の本章では”過ぎる”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は西周早期の金文。字形は「彳」”みち”+「止」”あし”+「冎」”ほね”で、字形の意味や原義は不明。春秋末期までの用例は全て人名や氏族名で、動詞や形容詞の用法は戦国時代以降に確認できる。詳細は論語語釈「過」を参照。
無(ブ)


(甲骨文)
論語の本章では”存在しない”。日本語では「ない」は形容詞か助動詞だが、漢語では動詞。英語の”deny”に相当する。初出は甲骨文。「ム」は呉音。甲骨文の字形は、ほうきのような飾りを両手に持って舞う姿で、「舞」の原字。その飾を「某」と呼び、「某」の語義が”…でない”だったので、「無」は”ない”を意味するようになった。論語の時代までに、”雨乞い”・”ない”の語義が確認されている。戦国時代以降は、”ない”は多く”毋”と書かれた。詳細は論語語釈「無」を参照。
所(ソ)


(金文)
論語の本章では”…すべき場所”。初出は春秋末期の金文。「ショ」は呉音。字形は「戸」+「斤」”おの”。「斤」は家父長権の象徴で、原義は”一家(の居所)”。論語の時代までの金文では”ところ”の意がある。詳細は論語語釈「所」を参照。
取(シュ)


(甲骨文)
論語の本章では”取り入れる”。初出は甲骨文。字形は「耳」+「又」”手”で、耳を掴んで捕らえるさま。原義は”捕獲する”。甲骨文では原義、”嫁取りする”の意に、金文では”採取する”の意(晉姜鼎・春秋中期)に、また地名・人名に用いられた。詳細は論語語釈「取」を参照。
材(サイ)


(楚系戦国文字)
論語の本章では”材木”。論語では本章のみに登場。初出は戦国文字。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補は「才」。「ザイ」は呉音。同音に才とそれを部品とする漢字群。うち「才」につき『大漢和辞典』は『集韻』を引いて、「通じて材に作る」という。ただし春秋時代以前の「才」にその語義は確認できないが、原義は”棒杭”。詳細は論語語釈「材」を参照。
無所取材
論語の本章では、”材木を取る場所がない”。仮に論語の本章が偽作の場合、”才能を取るべき場所が無い”→”取り柄が無い”。
また別の解釈として、「無所」「取材」と二句に分け、「所無くして材を取る」と読み、”どこでも(いかだの)材木を調達できる”とも解せるが、理屈は単純な方が正しいという、オッカムのカミソリに従うことにした。
論語:付記
検証
論語の本章は春秋戦国の誰一人引用せず、後半の「由也…取材」が前漢中期の『史記』弟子伝に再録されており、事実上の初出。いかだに乗って外国へ行ってしまう、という言い廻しの初出は、『史記』よりやや時代が前の、前漢中期の『淮南子』から。
寒不能生寒,熱不能生熱;不寒不熱,能生寒熱。故有形出於無形,未有天地能生天地者也,至深微廣大矣!雨之集無能霑,待其止而能有濡;矢之發無能貫,待其止而能有穿。唯止能止眾止。因高而為台,就下而為池,各就其勢,不敢更為。聖人用物,若用朱絲約芻狗,若為土龍以求雨。芻狗待之而求福,土龍待之而得食。魯人身善制冠,妻善織履,往徙於越而大困窮,以其所修而遊不用之鄉。譬若樹荷山上,而畜火井中。操釣上山,揭斧入淵,欲得所求,難也。方車而蹠越,乘桴而入胡,欲無窮,不可得也。楚王有白蝯,王自射之,則搏矢而熙;使養由基射之,始調弓矯矢,未發而蝯擁柱號矣,有先中中者也。

寒さに耐えられないから寒いのであり、暑さに耐えられないから暑いのだ。寒がりも暑がりもしなければ、暑いも寒いも関係ない。そもそも寒暑という無形があるからこそ、この有形の天地が存在するのだ。有形の天地が天地を産んだと言う話は、いまだかつて聞いたことが無い。寒暑のなんと奥深く精密なことよ。
雨が降りすぎては潤すことが出来ない。止んで適当に乾いたところで潤うという。矢が飛んだままでは貫通しない。止まってそこで貫通するのだ。ただ止まることだけが、止まることが出来るのだ。だから土が積もって台地になり、えぐれて池になるのは、理の当然でそうなるので、変えようとしても変えられない。
聖人は万物を活用するが、藁で作ったおもちゃの犬や、土で作ったおもちゃの竜で雨乞いしたとて、おもちゃが天の恵みを求めるわけではない。魯国の者は鹿爪らしく冠をかぶり、その妻は巧みに靴を縫うが、南方の越国に出掛けたら、頭も足も蒸れて大いに困る。冠や靴が無用な土地に行ったのだから。
たとえるなら材木を産地の山に運び上げ、井戸の水中で種火を保とうというようなものだ。釣り竿をかついで山に登り、斧を担いで川に下って、魚や材木を求めても、それは無理というものである。車を連ねて南方の越に逃げ、筏に乗って外国へ行こうとしても、どこまで行ってもきりがなく、安らぎの場所など得られない。
楚王は白いテナガザルを飼っていたが、からかわれてサルを射たものの、サルは矢を払いのけてキーキー笑った。そこで名射手の養由基を呼んで射させることにしたが、養由基が弓を取り出して準備したとたん、まだ射ないのにサルは柱を抱いて泣き出した。これが射る前に当たるというものだ。(『淮南子』説山訓13)
「魯国人は鹿爪らしく…」はおそらく戦国初期の呉起の故事から。また『荘子』逍遥遊篇にも同じ話があり、そののちの韓非も同じ故事を説いている。
魯人身善織屨,妻善織縞,而欲徒於越,或謂之曰:「子必窮矣。」魯人曰:「何也?」曰:「屨為履之也,而越人跣行;縞為冠之也,而越人被髮。以子之所長,游於不用之國,欲使無窮,其可得乎?」

魯の者に靴造りの上手がおり、その妻はあやぎぬ織りが得意だった。南方の越で商売をしようと思ったところ、近所の人がとめた。「きっと貧乏なさるに違いありません。」
靴造り「どうしてです?」
近所の者「靴は足に履くものですが、越人は素足で過ごします。あや絹は冠にしてかぶりますが、越人はざんばら髪で過ごします。あなたの得意技は、あの国では無用の長物です。売れるわけが無い。貧乏したくなくても、するに決まっているではありませんか。」(『韓非子』説林上28)
論語の本章は、上記の通り後世の引用が見られないが、文字史的には論語の時代まで遡れるので、とりあえず史実として扱う。
解説
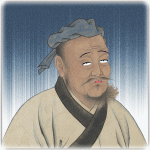
三国志の張飛同様、儒者も多くの漢学教授も、子路は少し頭が足りないように書きたがる。そこで従来訳のような解釈になるのだが、根拠はどこにもない。この点珍しく吉川本は、「いったいどこで、そうした大きないかだをつくる材料をとって来るというのかね」と訳している。
だが帝国儒教というお芝居には、わかりやすい乱暴者が必要だったらしい。
しかし史実の子路は、武芸よりもむしろ政治の達者だったようだ。
(衛国には蒲邑という、一揆を繰り返すめんどくさい住人が住むまちがあった。やり手の殿様である衛の霊公が、亡命してきた孔子一行から子路を見込んで、)子路が蒲の領主になった。しばらくして孔子の滞在先に出向いて挨拶した。
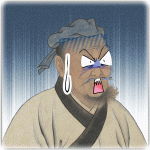
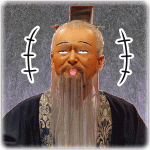
子路「一つお教えを賜りたく。」
孔子「蒲の統治のことじゃな? 町人はどんな者どもかね。」
子路「まちに武装したヤクザ者が、大勢で大手を振ってうろついていて、手が付けられません。」(『孔子家語』致思19)
『史記』弟子伝に「蒲大夫」とあり、代官(宰)ではなく領主で、春秋時代の邑の領主は「卿」と呼ばれた、国公に次ぐ上級貴族になる。霊公は半ば厄介払いから、蒲を子路にくれてやったのだが、子路はみごとに治めきったらしい。武芸もヤクザ者を黙らせるのに役立ったろう。
古注の儒者も、必ずしも論語の本章を、子路乱暴者説で読んでいない。
古注『論語義疏』
註馬融曰桴編竹木也大者曰筏小者曰桴也…註孔安國曰喜與已俱行也…註鄭玄曰子路信夫子欲行故言好勇過我也無所取材者言無所取桴材也以子路不解微言故戲之耳一曰子路聞孔子欲乘桴浮海便喜不復顧望故孔子歎其勇曰過我無所復取哉言唯取於己也古字材哉同耳疏子曰至取材 云道不行乗桴浮於海者桴者編竹木也大曰筏小曰桴孔子聖道不行於世故或欲居九夷或欲乘桴泛海故云道不行乘桴浮於海也云從我者其由也與者由子路名也言從我浮海者當時子路也故云其由與云子路聞之喜者子路聞孔子唯將與已俱行所以喜也云子曰由也好勇過我者然孔子本意托秉桴激時俗而子路信之將行既不達微㫖故孔子不復更言其實且先云由好勇過我以戲之也所以云過我者我始有乘桴之言而子路便實欲乘此是勇過我也云無所取材者又言汝勇乃過勝於我然我無所覓取為桴之材也

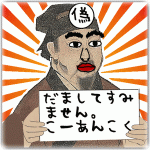
注釈。馬融「桴は編んだ竹や木である。大きなものは筏といい、小さなものは桴という。」
注釈。孔安国「一緒に行けると聞いて喜んだのである。」


注釈。鄭玄「子路は先生を信じて行こうとした。だから先生は”武勇がある”と誉めた。無所取材とは、いかだの材料を取る所が無いということだ。遠回しにものを言ったのを子路が真に受けたので、からかったのだ。一説によると、子路は孔子がいかだで海に出ると聞いて、いそいそとその準備を始めたので、孔子は呆れて”余計な勇気が余っている。取り柄が無い”と歎いた。単に”取る”とだけ言って、”取材”とは言っていない。古くは”材”と”哉”は同じだったからだ。」
付け足し。先生は材を取ることを言い、それが記された。道不行乗桴浮於海とあり、桴とは編んだ竹や木である。大きなのを筏といい、小さなのを桴という。孔子の聖なる道は世間に流行らなかったので、”九夷”の蛮族のところへ行こうとして、あるいはいかだに乗って海に出ようとした。だから「道不行乘桴浮於海」と言った。從我者其由也與とあり、由は子路の名である。從我浮海とは、つまり子路を指す。だから「其由與」と言った。子路聞之喜とは、子路が孔子の話を聞いて、自分だけお供になれると思って喜んだのだ。子曰由也好勇過我とは、そうは言っても孔子の本意は俗世間でいかだのように浮かぶことにあったから、子路が言葉を真に受けて出かけようとし、孔子の遠回りな言い方に気が付かないのに呆れて、違う言葉を重ねて、”しゅごい武勇でちゅねー”と子路をおだてて済ませたのだ。過我とは、孔子が始めに”いかだに乗る”といったのを子路が真に受けたのを言ったのだ。無所取材とは武勇に優れすぎると言い、優れていない自分には竹取りの翁を演じるなどご免だと言ったのだ。
だが新注になると子路おバカ説がハンダ付けになってしまう。
新注『論語集注』
桴,音孚。從、好,並去聲。與,平聲。材,與裁同,古字借用。桴,筏也。程子曰:「浮海之歎,傷天下之無賢君也。子路勇於義,故謂其能從己,皆假設之言耳。子路以為實然,而喜夫子之與己,故夫子美其勇,而譏其不能裁度事理,以適於義也。」


桴の音は孚である。從と好は、どちらも尻下がりに読む。與は平らな調子で読む。材は裁と同義で、昔は音を借りて裁の意に用いた。桴とは竹のいかだである。
程頤「海に出てしまおうと歎いたのは、天下に名君がいないので諦めたからである。子路は義理が絡むと勇ましい男だったから、ついてきてくれるだろう、と言った。だがこの話はたとえ話に過ぎなかったのに、子路が真に受けて、孔子の言葉に喜んだ。つまり先生は子路の義理がたさを誉めはしたが、もののことわりが分からない(不能裁度事理)のをからかって、子路を道理へと導こうとした。」
つまり宋儒は「無所取材」→「無所取裁」、「取り裁く所無し」と読み、”道理を見分ける能が無い”と解した。確かに文字史上は「材」「裁」の通用例が金文にもあるのでそう言えなくはないが、素直に”材木”と解する方が単純で、これもオッカムのカミソリに従った方がいい。
なお古注では本章を前章の続きとして扱っているように「中国哲学書電子化計画」が記すが、底本の四庫全書本や懐徳堂本では分割しており、データ入力かコーディングの間違いと思われる。

中国哲学書電子化計画『論語集解義疏』
余話
ひげ親父
明末の笑い話集『笑府』を編んだ馮夢竜は、偽善や独善をからかうだけに、子路をそこまで乱暴者として描いていない。『笑府』に子路は二例あるが、その一つを紹介する。
顏子。々路與伯魚三人。私議曰。夫子惟鬍。故開口不脫乎字。顏子曰。他對我說回也其庶乎。子路曰。他對我說。由。誨女知之乎。伯魚曰。他對我說。女為周南君南矣乎。孔子在屏後聞之。出責伯魚曰。回是箇短命的。由是箇不得好[死]的。也罷了。你是我的兒子。也來嘲我。
筆頭弟子の顔淵と、一番弟子の子路と、孔子の一人息子の伯魚が、三人寄って雑談した。「先生はおヒゲ(鬍)が長いから、口を開くたびに”乎”っておっしゃるんだね。」
顔淵「私には、”回よ、完璧に近い乎”とおっしゃったよ。」
子路「オレには、”由よ、お前に知るということを教えてやろう乎”と仰せだったぞ。」
伯魚「ボクには、”お前は周南召南のうたを覚えたか乎”と言ったよ。」
ついたての後ろでこの話を聞いていた孔子が出てきて、伯魚を叱った。「顔淵は若死にしちまうし*1、子路はろくな死に方をしない*2。二人の真似をするんじゃない。お前はワシの子ではないか。親をからかうとは何たることだ。」(『笑府』巻十・鬍子答嘲)



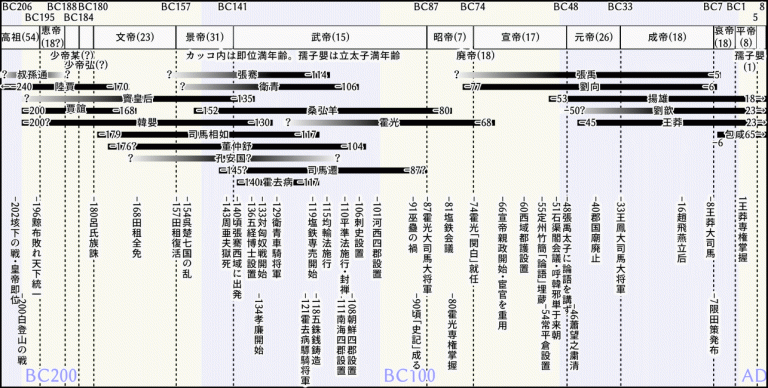


コメント