論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子使漆彫開仕對曰吾斯之未能信子說
- 「說」字:〔兌〕→〔兊〕。
校訂
諸本
- 論語集釋:漢書人表作「漆雕啓」,王應麟漢志考證曰:「史記列傳:『漆彫開字子開。』史記避景帝諱也。論語注以開爲名。」
東洋文庫蔵清家本
子使漆彫開仕對曰吾斯之未能信/子説
- 「彫」字:〔彡〕→〔丿人〕。
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
(なし)
標点文
子使漆彫啟仕。對曰、「吾斯之未能信。」子說。
復元白文(論語時代での表記)
















※彫(雕)→周・仕→事・說→兌。論語の本章は、「未」「信」の用法に疑問がある。
書き下し
子漆彫啟を使て仕へしめむとす。對へて曰く、吾が斯を之未だ信ずるに能はざるとすと。子說ぶ。
論語:現代日本語訳
逐語訳
先生は漆彫啟を仕官させようとした。答えて言った。「私は自分の境地は、まったくまだ信じることが出来ないのです」。先生は喜んだ。
意訳

漆彫啟に仕官を勧めたら、まだ自信がないと断った。あやつめ、出来る!
従来訳
先師が漆雕開に仕官をすすめられた。すると、漆雕開はこたえた。――
「私には、まだ役目を果すだけの自信がありません。」先師はその答えを心から喜ばれた。下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子要漆雕開當官。漆雕開說:「我還沒自信。」孔子聽後很高興。
孔子が漆雕開を官職に就かせようとした。漆雕開が言った。「私はまだ自信がありません。」孔子は聞き終えてたいそう喜んだ。
論語:語釈
子(シ)


(甲骨文)
論語の本章では「子謂」では”(孔子)先生”、「其子」「兄之子」では”娘”。初出は甲骨文。字形は赤ん坊の象形。春秋時代では、貴族や知識人への敬称に用いた。季康子や孔子のように、大貴族や開祖級の知識人は「○子」と呼び、一般貴族や孔子の弟子などは「○子」と呼んだ。詳細は論語語釈「子」を参照。
使(シ)


(甲骨文)
論語の本章では”~させる”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「事」と同じで、「口」+「筆」+「手」、口に出した事を書き記すこと、つまり事務。春秋時代までは「吏」と書かれ、”使者(に出す・出る)”の語義が加わった。のち他動詞に転じて、つかう、使役するの意に専用されるようになった。詳細は論語語釈「使」を参照。
漆雕開(シツチョウカイ)→漆彫啟(シツチョウケイ)
BC540ー?。孔子の弟子。姓は漆彫(雕)、名は啓。漢景帝の名が同じく啓なので、後世名を開と言い換えた。『孔子家語』によると、孔子より11年少。『漢書』芸文志によると、漆雕開の弟子が記した『漆雕子』という書物があったという。また『韓非子』によると、儒家八派のひとつに漆雕氏の儒があったという。
唐開成石経、現存最古の古注本である清家本は「彫」と記す。日本伝承の古注本は「彫」のまま伝えた。一方元禄五年(1692)刊の早大蔵新注は「雕」と記す。中国伝承では、宮内庁蔵宋版論語注疏、四庫全書会要本新注も「雕」と記す。従っておそらく宋儒による改変。なお宋の皇帝のいみ名に「彫」は見られない。
論語の伝承について詳細は「論語の成立過程まとめ」を参照。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)


「漆」(金文)
「漆」の初出は春秋早期の金文。初出の字形は「雨」”樹木の刻み目+両手”+「桼」”樹液”。樹木に刻み目を入れて樹液をすくい取るさま。原義は”うるし”。詳細は論語語釈「漆」を参照。
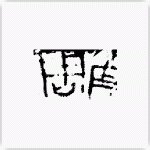

「雕」(戦国金文)
「雕」の初出は戦国末期の金文、字形は音符「周」+「隹」”とり”で、原義は鳥の”ワシ”。”ほる”の語義は音通。
古注の「彫」は異体字。彫の字も初出は戦国文字で、やはり論語の時代に存在しない。春秋時代の置換候補は、部品の周の字。”ほる”意を持つ漢字で、チョウと音読みするものに、琱があり、春秋時代の金文に存在する上、初文は周とされるから、周に”ほる”意があると解することは可能。詳細は論語語釈「雕」を参照。


「開」(秦系戦国文字)
「開」の初出は秦系戦国文字。字形は「門」+「廾」”両手”で、両手で門をあけるさま。原義は”開ける”。戦国の金文では人名に用いた。同音同訓「闓」の初出は後漢の『説文解字』。日本語音で同音同訓の「䦱」の初出は『説文解字』。同訓近音の「啓」の初出は甲骨文で、音通する置換字候補となる。詳細は論語語釈「開」を参照。


「啟」(甲骨文)
漢儒によって避諱される前の「啟」の新字体は「啓」。初出は甲骨文。中国・台湾・香港では「啟」がコード上の正字として扱われているが、唐石経・清家本ともに「啓」と記す。『学研漢和大字典』は「啟」字を載せず、「啓」の異体字として「諬」を載せ、「小学堂」は「啟」を「啓」の異体字とはしていないが、「諬」は異体字の一つとして所収。字形は「屮」”手”+「戸」”片開きの門”+「𠙵」”くち”で、門を開いておとなうさま。原義は”ひらく”。甲骨文では”報告する”・”天が晴れる”の意に、金文では”気付く”の意に用いた。戦国の金文では”領土を拡大する”、氏族名・地名・人名に用いた。詳細は論語語釈「啓」を参照。
仕(シ)
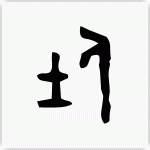

(戦国金文)
論語の本章では”出仕させる”。初出は戦国早期の金文。字形は「士」+「人」で、原義は”役人”。戦国の金文で地名や人名に用いた。同音異調の「事」が論語時代の置換候補となる。詳細は論語語釈「仕」を参照。
對(タイ)


(甲骨文)
論語の本章では”回答する”。初出は甲骨文。新字体は「対」。「ツイ」は唐音。字形は「丵」”草むら”+「又」”手”で、草むらに手を入れて開墾するさま。原義は”開墾”。甲骨文では、祭礼の名と地名に用いられ、金文では加えて、音を借りた仮借として”対応する”・”応答する”の語義が出来た。詳細は論語語釈「対」を参照。
曰(エツ)


(甲骨文)
論語で最も多用される、”言う”を意味する言葉。初出は甲骨文。原義は「𠙵」=「口」から声が出て来るさま。詳細は論語語釈「曰」を参照。
吾(ゴ)


(甲骨文)
論語の本章では”わたし”。初出は甲骨文。字形は「五」+「口」で、原義は『学研漢和大字典』によると「語の原字」というがはっきりしない。一人称代名詞に使うのは音を借りた仮借だとされる。詳細は論語語釈「吾」を参照。
春秋時代までは中国語にも格変化があり、一人称では「吾」を主格と所有格に用い、「我」を所有格と目的格に用いた。しかし論語でその文法が崩れ、「我」と「吾」が区別されなくなっている章があるのは、後世の創作が多数含まれているため。
斯(シ)


(金文)
論語の本章では、”境地”。孔子に教わった学問習得の、さまざまな見地からの達成程度を指す。学んだ学問全体。初出は西周末期の金文。字形は「其」”籠に盛った供え物を祭壇に載せたさま”+「斤」”おの”で、文化的に厳かにしつらえられた神聖空間のさま。意味内容の無い語調を整える助字ではなく、ある状態や程度にある場面を指す。例えば論語子罕篇5にいう「斯文」とは、ちまちました個別の文化的成果物ではなく、風俗習慣を含めた中華文明全体を言う。詳細は論語語釈「斯」を参照。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章では「これ」と訓読し、”まさに~”。強調の意。
『学研漢和大字典』「之」条
- 「~之…」は、「~をこれ…す」とよみ、「~を…する」と訳す。倒置・強調の意を示す。
字の初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”…の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。
吾斯之未能信
論語の本章では、”私は先生にさまざまなことを教わりましたが、そのどれ一つも、まだ自信を持つことが出来ません”。
- 吾:”私の”。
- 斯:”教わった学問の全体”。孔子塾で教えたのは一芸ではなく「六芸」と言って貴族の技能教養全般で、そうしたさまざまな教科全部ひっくるめて、習得の達成程度を指す。短く言うなら”学問の境地”。
- 之:強意。教わった個別の事柄、そのどれ一つですら、という謙遜の意を示す。
- 未:”まだ…でない”。
- 能:”出来る”。
- 信:”信じる”。自信を持つこと。
未(ビ)


(甲骨文)
論語の本章では”今までない”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。「ミ」は呉音。字形は枝の繁った樹木で、原義は”繁る”。ただしこの語義は漢文にほとんど見られず、もっぱら音を借りて否定辞として用いられ、「いまだ…ず」と読む再読文字。ただしその語義が現れるのは戦国時代まで時代が下る。詳細は論語語釈「未」を参照。
能(ドウ)


(甲骨文)
論語の本章では”~できる”。初出は甲骨文。「ノウ」は呉音。原義は鳥や羊を煮込んだ栄養満点のシチューを囲んだ親睦会で、金文の段階で”親睦”を意味し、また”可能”を意味した。詳細は論語語釈「能」を参照。


「能~」は「よく~す」と訓読するのが漢文業界の座敷わらしだが、”上手に~できる”の意と誤解するので賛成しない。読めない漢文を読めるとウソをついてきた、大昔に死んだおじゃる公家の出任せに付き合うのはもうやめよう。
信(シン)
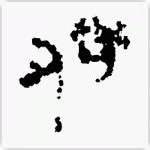

(金文)
論語の本章では、”信じる”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は西周末期の金文。字形は「人」+「口」で、原義は”人の言葉”だったと思われる。西周末期までは人名に用い、春秋時代の出土が無い。”信じる”・”信頼(を得る)”など「信用」系統の語義は、戦国の竹簡からで、同音の漢字にも、論語の時代までの「信」にも確認出来ない。詳細は論語語釈「信」を参照。
說(エツ)


(楚系戦国文字)
論語の本章では”喜ぶ”。新字体は「説」。初出は楚系戦国文字。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補は部品の「兌」で、原義は”笑う”。詳細は論語語釈「説」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章は、定州竹簡論語に無く、春秋戦国の誰一人引用も再録もせず、前漢中期の『史記』弟子伝にそのまま引用してあるのが事実上の初出。しかし文字史的には全ての文字が論語の時代まで遡れるので、とりあえず史実として扱う。
解説
上記の校訂の通り、漆雕開が実在の人物なら漆彫啓と記すべきだが、論語業界では漆雕開とアロンアルファで接着したほど漢儒以降の呼び名が定着しているので、以下、無理に剝がさず漆雕開と記す。
孔子の弟子は仕官が目的で入塾したが、孔子は一部の弟子に自分の補助者となるのを望んだ。漆雕開もその一人だろうが、論語では本章にしか名が出ない。孔子とすれ違うように春秋末から戦国を生きた墨子は、「罪を犯して体のどこかを切る刑に処された」と言う。
「舜」の字が墨子より約一世紀後の初出であることを承知で引用する。なお以下引用する『墨子』では、漆雕開を「桼雕」と記している。
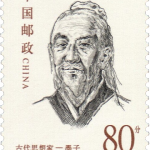
墨子曰く、孔子が弟子を集めて、こういう要らん説教をしたらしい。
孔子「聖人聖人とワシは世間に言うたが、実は全部でっち上げだ。いにしえの聖王舜は、バカ親父の顔を見る時に限り、米つきバッタのようにペコペコした。王がそんなバカに頭を下げれば、舐められて国が滅びかねなかった。周公旦も人でなしだった。家族を放置して、留守にしっぱなしのまま趣味の政治いじりに励んだ。」
こういう発言を聞くと、孔子の腹は真っ黒で、仕出かした政治的陰謀はその表れだ。孔子の弟子どもはみな、そろって孔子の真似をした。子貢と子路は、衛国で小悪党の孔悝を焚き付けて反乱を起こさせ、陽貨は斉国で謀反を起こし、佛肸は中牟に立てこもって独立を企んだ。漆雕開は何を仕出かしたか知らないが、ともかく捕まって肢体切りの刑にあった。こうした孔子一党の悪行は、数え上げたら切りがない。
そもそも弟子入りとは、師匠よりあとに生まれたことを自覚して、師匠の言葉通りに努め、行い通りに真似るものだ。未熟者だし、智恵も師匠より劣っているからだ。だから今や、孔子が腹黒と分かった以上、その弟子を名乗る今の儒者どもも、大いに疑ってかかるべきである。(『墨子』非儒篇下12)
これに対し、前後の漢帝国ごろに作られたと言われる『孔叢子』は反論している。
詰之曰:如此言,衛之亂,子貢、季路為之耶?斯不待言而了矣。陽虎欲見孔子,孔子不見,何弟子之有?弗肹以中牟畔,召孔子,則有之矣。為孔子弟子,未之聞也。且漆雕開形殘,非行己之致,何傷於德哉?
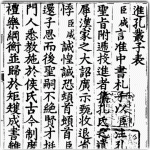
墨子の言い分はおかしい。衛国の騒乱で、子貢や子路がいったいどんな悪事を働いたというのか。一々論じる価値も無い。陽貨=陽虎は孔子に会おうとして、孔子は避けたではないか。どうして陽虎が弟子であるものか。弗肹が中牟に立てこもって反乱を起こし、孔子を呼んだのはその通りだろう。だが孔子の弟子だったという話は聞いたことがない。それにもし漆雕開が刑に処されたとしても、自分の行いが悪くてそうなったのではない。その人徳は何ら傷つかないではないか(『孔叢子』詰墨12)
いずれひいきの引き倒しの反論だから、真に受けるには当たらないが、陽虎については言う通りで、論語陽貨篇1に記した通り、陽貨と陽虎は別人だった可能性がある。それ以外は漢儒より、より近い年代の人物として孔子を知っていた墨子の言い分に、より説得力がある。
漆雕開もまた顔淵や公冶長のように、孔子一門の諜報員ではないか(孔門十哲の謎)、と勘ぐりたくなるが、上記したように戦国最末期の『韓非子』には当時の儒家の一派閥として「漆雕氏」を挙げており、漆雕開は学者や教師の道を歩んだと考える方が妥当だろう。
世之顯學,儒、墨也。儒之所至,孔丘也。墨之所至,墨翟也。自孔子之死也,有子張之儒,有子思之儒,有顏氏之儒,有孟氏之儒,有漆雕氏之儒,有仲良氏之儒,有孫氏之儒,有樂正氏之儒。自墨子之死也,有相里氏之墨,有相夫氏之墨,有鄧陵氏之墨。故孔、墨之後,儒分為八,墨離為三,取舍相反、不同,而皆自謂真孔、墨,孔、墨不可復生,將誰使定世之學乎?孔子、墨子俱道堯、舜,而取舍不同,皆自謂真堯、舜,堯、舜不復生,將誰使定儒、墨之誠乎?殷、周七百餘歲,虞、夏二千餘歲,而不能定儒、墨之真,今乃欲審堯、舜之道於三千歲之前,意者其不可必乎!無參驗而必之者、愚也,弗能必而據之者、誣也。故明據先王,必定堯、舜者,非愚則誣也。愚誣之學,雜反之行,明主弗受也。
現在の世で流行している学問と言えば、儒家と墨家です。儒家は孔丘に始まりました。墨家は墨翟に始まりました。孔子の没後、子張派、子思派、顔氏派、孟子派、漆雕派、仲良派、孫派、樂正派に分裂しています。墨子の没後、相里派、相夫派、鄧陵派に分裂しています。だから孔子や墨子が世を去ったのち、儒家は八つに分かれ、墨家は三つに分かれたわけです。
その主張は互いに食い違いがあり、同じではありませんが、みな自派こそが真の孔子や墨子の教えを伝えていると言っています。孔子や墨子を生き返らせることが出来ないのに、いったい誰が本物の教えだと言えるでしょうか。
孔子と墨子はともに堯や舜を讃えていますが、その主張は互いに食い違って同じではありません。ですがどちらも自分たちが真の堯や舜の教えを引き継いでいると言います。堯や舜を生き返らせることが出来ないのに、いったい誰が儒家と墨家のどちらが正しいと言えるでしょうか。
殷と周で七百年あまり、堯舜と夏王朝で二千年あまりと言われますが、今の儒家も墨家も、その史実を明らかに出来る者はいません。堯舜など三千年も前の人物です。今の人間が、いったいどうやってその史実を知れるというのでしょう。
知っていると言い張る者はかならずニセモノです。証拠もないのに口から出任せを言う者をバカ者と言います。出来ない事を出来ると言い張る者をペテン師と言います。だから明らかに先王の道に従い、堯舜の道をブレなく理解している者は、バカ者でもペテン師でもありません。
バカ者とペテン師の説く学説は、本物の教えに勝手な個人的感想を混ぜ込み、互いに矛盾があります。賢明なる大王殿下には、どうかそうした者どもの意見をお採り挙げになりませんよう。(『韓非子』顕学1)
この韓非の言い分に信憑性があるのは、想定した読み手であるのちの始皇帝が、ウソには本気で怒る性格だったからで、当時の儒家に漆雕派を含む八派があったのは事実と見てよい。すると「顔氏派」もあるから、顔淵もまた学者や教師の道を歩んだように見えそうだ。
だがそうではなかろう。上掲リンク先に記した通り、顔淵は孔子の母と同族であり、国際傭兵団の大親分・顔濁鄒と同族だった。孔子が後ろ暗い国際陰謀に手を染めたことは墨子が証言しているから、孔門に諜報部門があったのは十分あり得、その元締めは顔淵にしか務まらない。
話を漆雕開に戻すと、弟子の中では孔子より9歳年少の子路に次いで、11歳差と年長格にある。おそらく最年長は弟子と言うより後援者だった冉耕伯牛だったろうが、主要弟子の顔淵が30歳下、冉有が29歳下、子貢が31歳下(いずれも『史記』弟子伝による)であるのより年上。
顔淵前後の弟子が入門した時期も、まだ孔子が魯の政界デビューを果たす前だったから、必ずしも仕官目当てで入ったわけではないが、顔淵や子路は孔子と生来の縁故があった。彼らより年長の漆雕開にはそうした情報が無く、純粋に孔子の学識を見込んで入門した可能性がある。
孔子も塾が繁盛すると、興味本位の入門希望者に門前払いを食わせたりしているが(論語八佾篇3・論語陽貨篇20)、まだ中堅役人の兼業で教えていた頃はそうでもなかっただろう。社会の底辺に生まれながら、人並み優れた学識を身につけたことを、世間に認められたのだから。
また孔子塾も、孔子が宰相になった実績が付くと、大いに繁盛したはずで、一説には弟子の数は三千という。そうなると助教や師範代が必要になるのはもっともで、漆雕開は助教として後進の指導に当たったのだろう。本当に足が悪かったとしても、座学の講師なら無理が無い。
孔子も自分の学識に惚れ込んで入門した漆雕開が助教を務めてくれるのを、喜んだに違いない。
余話
先祖代々のスパイ
漆雕開が学者として後世に派閥を残したのはいいとして、韓非の言う『顔氏』派とは何者か。まさか諜報術を伝える派閥ではあるまい。孔子没後、儒家は革命政党であることを止めたし、事実上滅亡と言ってよいほど衰微した、と孔子没後一世紀に生まれた孟子が証言している。
衰微した学派に諜報の能も必要も無い。

学者を名乗る連中は、デタラメを言い合っては「はい論破!」とか幼稚なことを言っていたから、楊朱と墨翟の学説に天下を占領された。天下の学説と言えば、楊朱の学派でなければ墨家だった。(『孟子』滕文公下14)
顔淵の著作は現伝せず、ただし『漢書』芸文志にそれらしいのが載る。だがそのリストの前後を董仲舒の著作で挟まれており、これも董仲舒の偽作が疑わしい。前漢以降、孔子に次ぐ権威となった顔淵の著作が、一冊残らず綺麗さっぱり消え失せるのも、偽作だからだろう。
董仲舒についてより詳しくは、論語公冶長篇24余話を参照。
すると戦国の世で顔氏派を名乗った者たちは、一体何を伝授していたのだろう。孔子の教説の中で、いわゆる文系科目に含まれるものは、荀子が証言した子夏派がつたえただろうし、礼法は子游派が伝えただろう。算術は墨家が伝えたが、武術は伝えた派閥の記録が無い。
『春秋左氏伝』には、「戦を前に将校たちが車座になって、”顔高どのの弓は六鈞(46kg)もの強さだと”と言って、弓を回していじくっていた」(『春秋左氏伝』定公八年2)という記述があり、顔淵も弓が得意だった、だから顔氏派が武術を伝えたと言いたいところだが無理がある。
やっぱり諜報術でも伝えたんだろうか。
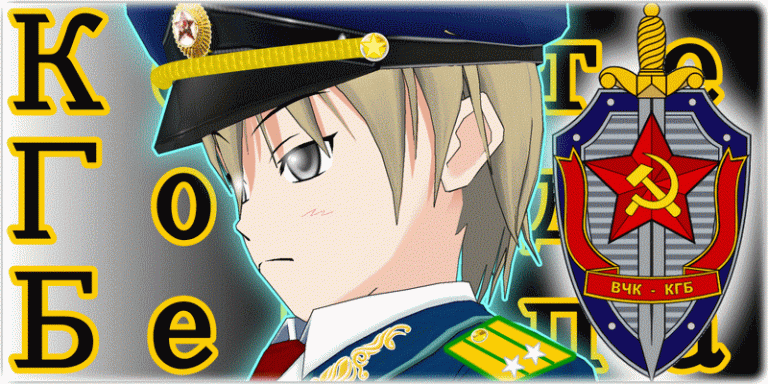






コメント