論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子貢曰管仲非仁者與桓公殺公子糾不能死又相之子曰管仲相桓公霸諸侯一匡天下民到于今受其賜微管仲吾其被髪左衽矣豈若匹夫匹婦之爲諒也自經於溝瀆而莫之知也
※「髪」字はへん〔镸〕でつくり〔彡犮〕
校訂
諸本
- 武内本:被髮、漢書終軍伝編髪に作る、注云編読て辮となすと、蓋し被編辮同音相通ず、辮髪左衽は夷狄の俗。衽釋文袵に作る。若の字唐石経旁添。
東洋文庫蔵清家本
子貢曰管仲非仁者與桓公殺公子糾不能死又相之子曰管仲相桓公霸諸侯一匡天下/民到于今受其賜/𭗒管仲吾其被髪左衽矣/豈若匹夫匹婦之爲諒也自經於溝瀆而莫之知也
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
子![]() 曰:「管中非仁者與?桓公殺公子糾,不能死,有a[相]381……壹b□天下,到c于今382……
曰:「管中非仁者與?桓公殺公子糾,不能死,有a[相]381……壹b□天下,到c于今382……
- 今本”有”作“又”字。
- 今本”壹”作”一”字。
- 今本”到”字前有”民”字。
標点文
子貢曰、「管中非仁者與。桓公殺公子糾、不能死、有相之。」子曰、「管仲相桓公、霸諸侯、壹匡天下、到于今受其賜。微管仲、吾其被髮左衽矣。豈若匹夫匹婦之爲諒也、自經於溝瀆、而莫之知也。」
復元白文(論語時代での表記)













































 被
被
 衽
衽 豈
豈





 諒
諒



 瀆
瀆 




※貢→(甲骨文)・管→官・仁→(甲骨文)・桓→亘・糾→丩・壹→一。論語の本章は赤字が論語の時代に存在しない。「與」「霸」「匡」「微」「髮」「婦」「經」の用法に疑問がある。本章は漢帝国の儒者による創作である。
書き下し
子貢曰く、管仲は仁者に非ざる與。桓公公子糾を殺すも、死ぬ能はず、之を相ける有り。子曰く、管仲桓公を相けて、諸侯に霸たらしめ、天が下を壹たび匡し、今于到るまで其の賜を受く。管仲微りさば、吾其れ髮を被らし衽を左にし矣む。豈に匹夫匹婦之諒を爲す也、自ら溝瀆於經れ而、之を知る莫きに若かん也。
論語:現代日本語訳
逐語訳


子貢が言った。「管仲は上記無差別の愛がある者ではないのですか。桓公が公子糾を殺しても、死ねませんでしたし、その上桓公を助け(て宰相になり)ました。」
先生が言った。「管仲は桓公を助けて、諸侯の覇者にし、天下を一度は正しくし、今になるまでその恩恵を受けている。管仲がいなかったら、私は髪をざんばらにして、左前の服を着ていただろう。どうしてつまらぬ男女が操を立てて、自分から溝で首をくくって土左衛門になっても、そのことを誰も知る者が無いのと同じだろうか。」
意訳


子貢「管仲は薄情者じゃないですか? 桓公が主君の公子糾を殺しても後を追わず、その上かたきの桓公を補佐して宰相になりました。」
孔子「管仲は桓公を補佐して諸侯の覇者に押し上げ、天下の乱れを一度は正した。我ら中華の者は今になっても、そのおかげを被っている。管仲が居なかったら、私は今ごろザンバラ髪に、左前のみっともない服を着るハメになっていただろう。管仲はそういうすごい人じゃぞ? 少々悪どいところがあってもどこが悪い。そのあたりの愚夫愚婦が、つまらぬ忠義立てをして我から首をくくり、ドブ川に身投げしても、誰も知る人はいませんでした、というのとは違うのだ。」
従来訳
子貢がいった。――
「管仲は仁者とはいえますまい。桓公が公子糾を殺した時、糾に殉じて死ぬことが出来ず、しかも、桓公に仕えてその政を輔佐したのではありませんか。」
先師がこたえられた。
「管仲が桓公を輔佐して諸侯聯盟の覇者たらしめ、天下を統一安定したればこそ、人民は今日にいたるまでその恩恵に浴しているのだ。もし管仲がいなかったとしたら、われわれも今頃は夷狄の風俗に従って髪をふりみだし、着物を左前に着ていることだろう。管仲ほどの人が、小さな義理人情にこだわり、どぶの中で首をくくって名もなく死んで行くような、匹夫匹婦のまねごとをすると思ったら、それは見当ちがいではないかね。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
子貢說:「管仲不是仁人吧?齊桓公殺公子糾時,管仲不能為公子糾殉死,反做了齊桓公的宰相。」孔子說:「管仲做齊桓公的宰相,稱霸諸侯,一匡天下,人民現在還都享受到他的恩惠。沒有管仲,恐怕我們還要受愚昧人的侵擾。豈能拘泥於匹夫匹婦的小睗小信?自縊於溝瀆而不為人知呢。」
子貢が言った。「管仲は仁者じゃないですね?斉の桓公が公子糾を殺したとき、管仲は公子のために殉死出来ませんでした。かえって桓公の宰相になりました。」孔子が言った。「管仲は桓公の宰相になって、諸侯の旗頭と讃えさせた。一度天下をまとめると、人民は今もみなその恩恵を受けている。もし管仲がいなかったら、我々は蛮族に侵入されただろうと恐れる。つまらない男女のような小さな信義にこだわれるか?自分で首を吊ったり身投げしたりして、誰も識る者はいないのだぞ?」
論語:語釈
子 貢 曰、「管 仲 非 仁 者 與。桓 公 殺 公 子 糾、不 能 死、有(又) 相 之。」子 曰、「管 仲 相 桓 公、霸 諸 侯、壹(一) 匡 天 下、(民) 到 于 今 受 其 賜。 微 管 仲、吾 其 被 髮 左 衽 矣 豈 若 匹 夫 匹 婦 之 爲 諒 也、自 經 於 溝 瀆、而 莫 之 知 也。」
子貢(シコウ)

BC520ごろ-BC446ごろ 。孔子の弟子。姓は端木、名は賜。衛国出身。論語では弁舌の才を孟子に評価された、孔門十哲の一人(孔門十哲の謎)。孔子より31歳年少。春秋時代末期から戦国時代にかけて、外交官、内政官、大商人として活躍した。
『史記』によれば子貢は魯や斉の宰相を歴任したともされる。さらに「貨殖列伝」にその名を連ねるほど商才に恵まれ、孔子門下で最も富んだ。子禽だけでなく、斉の景公や魯の大夫たちからも、孔子以上の才があると評されたが、子貢はそのたびに否定している。
孔子没後、弟子たちを取りまとめ葬儀を担った。唐の時代に黎侯に封じられた。孔子一門の財政を担っていたと思われる。また孔子没後、礼法の倍の6年間墓のそばで喪に服した。斉における孔子一門のとりまとめ役になったと言われる。詳細は論語の人物:端木賜子貢参照。


「子」(甲骨文)
「子」は貴族や知識人に対する敬称。初出は甲骨文。字形は赤ん坊の象形で、古くは殷王族を意味した。春秋時代では、貴族や知識人への敬称に用いた。孔子のように学派の開祖や、大貴族は、「○子」と呼び、学派の弟子や、一般貴族は、「子○」と呼んだ。詳細は論語語釈「子」を参照。


(甲骨文)
子貢の「貢」は、文字通り”みつぐ”ことであり、本姓名の端木賜と呼応したあざ名と思われる。所出は甲骨文。『史記』貨殖列伝では「子贛」と記し、「贛」”賜う”の初出は楚系戦国文字だが、殷墟第三期の甲骨文に「章丮」とあり、「贛」の意だとされている。詳細は論語語釈「貢」を参照。
『論語集釋』によれば、漢石経では全て「子贛」と記すという。定州竹簡論語でも、多く「![]() 」と記す。本章はその部分が欠損しているが、おそらくその一例。
」と記す。本章はその部分が欠損しているが、おそらくその一例。
曰(エツ)


(甲骨文)
「曰」は論語で最も多用される、”言う”を意味する言葉。初出は甲骨文。原義は「𠙵」=「口」から声が出て来るさま。詳細は論語語釈「曰」を参照。
管仲(カンチュウ)→管中(カンチュウ)
論語では、かつての斉国の名宰相。?ーBC645。姓は管、名は夷吾、字は仲。中国春秋時代における斉の政治家で、桓公に仕え、覇者に押し上げた。


「管」(前漢隷書)
「管」の初出は前漢の隷書。部品の「官」は同音、初出は甲骨文。字形は「竹」+「官」で、原義は『説文解字』の言う、”笛”だと理解するしか法が無い。論語では斉の名宰相管仲の姓氏として用いるが、当時存在しない字であり、どのように書かれていたかは憶測するしかない。おそらく「官」だったろう。詳細は論語語釈「管」を参照。


「仲」(甲骨文)
「仲」の初出は甲骨文。ただし字形は「中」。現行字体の初出は戦国文字。「丨」の上下に吹き流しのある「中」と異なり、多くは吹き流しを欠く。字形は「○」に「丨」で真ん中を貫いたさま。原義は”真ん中”。「漢語多功能字庫」は「甲金文」というおおざっぱな括りで、「仲」=兄弟の真ん中、次男を意味したという。論語語釈「中」も参照。詳細は論語語釈「仲」を参照。
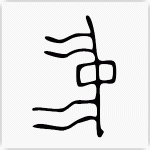

「中」(甲骨文)
定州竹簡論語の「中」の初出は甲骨文。甲骨文の字形には、上下の吹き流しのみになっているものもある。字形は軍司令部の位置を示す軍旗で、原義は”中央”。甲骨文では原義で、また子の生まれ順「伯仲叔季」の第二番目を意味した。金文でも同様だが、族名や地名人名などの固有名詞にも用いられた。また”終わり”を意味した。詳細は論語語釈「中」を参照。
非(ヒ)


(甲骨文)
論語の本章では”~でない”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は互いに背を向けた二人の「人」で、原義は”…でない”。「人」の上に「一」が書き足されているのは、「北」との混同を避けるためと思われる。甲骨文では否定辞に、金文では”過失”、春秋の玉石文では「彼」”あの”、戦国時代の金文では”非難する”、戦国の竹簡では否定辞に用いられた。詳細は論語語釈「非」を参照。
仁者(ジンシャ)


論語の本章では、”常時無差別の愛を持った、あわれみ深い者”。この解釈は孔子没後一世紀に現れた孟子が主張した「仁義」”常時無差別の愛”に基づくもので、「仁は論語で説かれた最高の德」という主張は、時代錯誤の間違い。孔子の生前、「仁」とは単に”貴族らしさ”でしかなかった。詳細は論語における「仁」を参照。

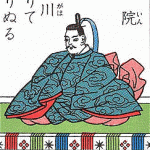
(甲骨文)
「仁」の初出は甲骨文。字形は「亻」”ひと”+「二」”敷物”で、原義は敷物に座った”貴人”。詳細は論語語釈「仁」を参照。


(金文)
「者」の初出は殷代末期の金文。金文の字形は「木」”植物”+「水」+「口」で、”この植物に水をやれ”と言うことだろうか。原義は不明。初出では称号に用いている。春秋時代までに「諸」と同様”さまざまな”、”…は”の意に用いた。漢文では人に限らず事物にも用いる。詳細は論語語釈「者」を参照。
與(ヨ)


(金文)
論語の本章では”~か”という疑問辞。この語義は春秋時代では確認できない。新字体は「与」。初出は春秋中期の金文。金文の字形は「牙」”象牙”+「又」”手”四つで、二人の両手で象牙を受け渡す様。人が手に手を取ってともに行動するさま。従って原義は”ともに”・”~と”。詳細は論語語釈「与」を参照。
桓公(カンコウ)
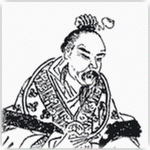
春秋時代、姜氏斉国第16代国君。位BC685-BC643。春秋時代最初の覇者とされる。詳細はwikipedia参照。
孔子が桓公のことをどう思っていたか、実はよく分からない。論語の中で孔子が桓公について言及した章は、前々章論語憲問篇16と、前章論語憲問篇17と、本章だけだが、人物評をしたのは前々章だけで、しかも後世の偽作で孔子の意見ではない。


(金文)
「桓」の初出は西周末期の金文で、ただし字形は「𧻚」。現伝字体の初出は前漢の隷書。字形は「木」+「亘」で、「亘」は甲骨文で占い師の名に用いたほかは、戦国時代の竹簡まで出土が無い。”うずまき”とも、”明らかな太陽”とも解せる。一種の装飾的署名だと思う。「桓」は何かを明らかに示すための標識。同音多数。西周末期の金文に、”あきらかで勢いの良い”の意で用いた。詳細は論語語釈「桓」を参照。
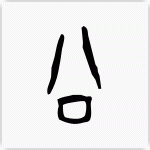

「公」(甲骨文)
「公」の初出は甲骨文。字形は〔八〕”ひげ”+「口」で、口髭を生やした先祖の男性。甲骨文では”先祖の君主”の意に、金文では原義、貴族への敬称、古人への敬称、父や夫への敬称に用いられ、戦国の竹簡では男性への敬称、諸侯への呼称に用いられた。詳細は論語語釈「公」を参照。
殺(サイ)


(甲骨文)
論語の本章では”殺す”。新字体は「殺」。一説に初出は甲骨文。その字形は「戈」”カマ状のほこ”+斬首した髪。西周中期まではこの字形で、西周末期より髪に「人」形を加えた「𣏂」の形に、「殳」”撃つ”を加えた形に記された。漢音では”ころす”の意では「サツ」と読み、”削ぐ”の意では「サイ」と読む。甲骨文から”ころす”の意に用いたが、”削ぐ”の意は戦国末期まで確認できない。詳細は論語語釈「殺」を参照。
公子糾(コウシキュウ)
論語の本章では、斉の桓公の実兄。
『春秋左氏伝』『史記』が伝える所によると、桓公のまたの実兄・襄公が斉国公の地位にあったが、異常性欲者で実妹の文姜と通じた。文姜は魯の桓公(位BC711-BC694)に嫁いだが、その後も襄公と密通を続けた。斉を訪れた魯の桓公が事実を知ると、襄公は桓公を謀殺した。
あまりのこととて公子糾は魯国に逃げ、公子小白(のちの斉桓公)は莒国へ逃げた。さらに公族の公孫無知が襄公を殺して斉国公になった。しかし無知もすぐ暗殺されたので、糾と小白の跡目争いになったが、小白が勝利して斉の桓公となった。敗れた糾は魯国に逃げ戻ったが殺された。
管仲は公子糾に仕えており、跡目争いの時には手ずから弓をとって公子小白を射貫いたが、実は矢はベルトのバックルに当たっただけで小白は無事だった。死んだふりして生き延び、桓公となった小白は、側近の鮑叔のすすめで管仲を許し、宰相に据えた。
以上は、孔子が生まれる130年ほど昔の話である。


相馬経2下・前漢/「丩」湯鼎・春秋
「糾」の初出は前漢の隷書。字形は〔糸〕+〔丩〕(カ音不明)。「丩」の語義は”まつわる・まとう”と『大漢和辞典』は言い、初出は甲骨文。同音に「虯」”みづち”・「赳」”つよい・はたらき”。甲骨文での「丩」の語義は欠損が多くて明らかではない。西周では器名に用いられ語義不明。戦国の竹簡では「丩」は「糾」と釈文され、”ただす”と解せる。論語での用例は人名の「公子糾」のみなので、同音近音のあらゆる字が置換候補となる。公子糾が当時どのように記されたかは分からない。詳細は論語語釈「糾」を参照。
不(フウ)


(甲骨文)
論語の本章では”~でない”。漢文で最も多用される否定辞。「フ」は呉音、「ブ」は慣用音。初出は甲骨文。原義は花のがく。否定辞に用いるのは音を借りた派生義。詳細は論語語釈「不」を参照。現代中国語では主に「没」(méi)が使われる。
能(ドウ)


(甲骨文)
論語の本章では”~できる”。字の初出は甲骨文。「ノウ」は呉音。原義は鳥や羊を煮込んだ栄養満点のシチューを囲んだ親睦会で、金文の段階で”親睦”を意味し、また”可能”を意味した。詳細は論語語釈「能」を参照。


「能~」は「よく~す」と訓読するのが漢文業界の座敷わらしだが、”上手に~できる”の意と誤解するので賛成しない。読めない漢文を読めるとウソをついてきた、大昔に死んだおじゃる公家の出任せに付き合うのはもうやめよう。
死(シ)
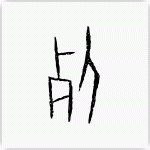

(甲骨文)
論語の本章では”死ぬ”。初出は甲骨文。字形は「𣦵」”祭壇上の祈祷文”+「人」で、人の死を弔うさま。原義は”死”。甲骨文では、原義に用いられ、金文では加えて、”消える”・”月齢の名”、”つかさどる”の意に用いられた。戦国の竹簡では、”死体”の用例がある。詳細は論語語釈「死」を参照。
又(ユウ)→有(ユウ)
論語の本章では”(ということ)があった”。唐石経、清家本は「又」gi̯ŭɡ(去)と記し、定州竹簡論語は「有」gi̯ŭɡ(上)と記す。カールグレン上古音では同音異調で、どちらも”存在する”の語義を持つ。時系列から定州本に従い校訂した。論語の伝承について詳細は「論語の成立過程まとめ」を参照。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)


(甲骨文)
「又」の初出は甲骨文。字形は右手の象形。甲骨文では祭祀名に用い、”みぎ”、”有る”を意味した。金文では”またさらに”・”補佐する”を意味した。詳細は論語語釈「又」を参照。


(甲骨文)
「有」の初出は甲骨文。ただし字形は「月」を欠く「㞢」または「又」。字形はいずれも”手”の象形。金文以降、「月」”にく”を手に取った形に描かれた。原義は”手にする”。原義は腕で”抱える”さま。甲骨文から”ある”・”手に入れる”の語義を、春秋末期までの金文に”存在する”・”所有する”の語義を確認できる。詳細は論語語釈「有」を参照。
相(ショウ)


(甲骨文)
論語の本章では”補佐して宰相になる”。初出は甲骨文。「ソウ」は呉音。字形は「木」+「目」。木をじっと見るさま。原義は”見る”。甲骨文では地名に用い、春秋時代までの金文では原義に、戦国の金文では”補佐する”、”宰相”、”失う”の意に用いられた。戦国の竹簡では、”相互に”、”補助する”、”遂行する”の意に用いられた。詳細は論語語釈「相」を参照。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章、「有相之」「莫之知」では”これ”。前者は斉の桓公を、後者は庶民の身投げを指す。「匹夫匹婦之」では”~の”。
字の初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”~の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
霸*(ハ)


(甲骨文)
論語の本章では”諸侯の旗頭にする”。この語義は春秋時代では確認出来ない。論語では本章のみに登場。初出は甲骨文。甲骨文の字形は〔革〕+〔月〕。新月の前後に見える月の縁取りをいう。金文以降は〔雨〕かんむりが加わる。漢音「ハ」で”はたがしら”を、「ハク」で”新月のさま”を指す。同じく”諸侯の旗頭”を意味する「伯」と上古音が近い。甲骨文から”新月の頃”を意味し、以降春秋末期までこの語義で、いわゆる「覇者」の用例は戦国の竹簡以降となる。詳細は論語語釈「霸」を参照。
諸侯(ショコウ)
論語の本章では”大名”。周王の直臣で、かつそれぞれの領国を治める封建君主。


(秦系戦国文字)
「諸」は論語の時代では、まだ「者」と分化していない。「者」の初出は西周末期の金文。現行字体の初出は秦系戦国文字。金文の字形は「者」だけで”さまざまな”の意がある。詳細は論語語釈「諸」を参照。
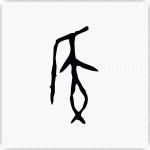

(甲骨文)
「侯」の初出は甲骨文。字形は「厂」”陣幕”+「矢」。陣幕を張った射場に立てる矢のまと。甲骨文では”まとを射る”と解せそうな例のほか、多く”諸侯”と解せる例がある。西周・春秋の金文でも”諸侯”の意に用いた。詳細は論語語釈「侯」を参照。
一(イツ)→壹(イツ)


(甲骨文)
論語の本章では”一たび”。「一」の漢音は「イツ」、「イチ」は呉音。初出は甲骨文。定州竹簡論語が記す重文「壹」の初出は戦国文字。字形は横棒一本で、数字の”いち”を表した指事文字。詳細は論語語釈「一」を参照。
匡(キョウ)
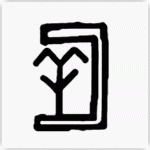

(甲骨文)
論語の本章では”正す”。この語義は論語の時代に確認出来ない。ただし字形から、”躾ける”の語義は容易に想像できる。初出は甲骨文。字形は「匚」”塀”+「羊」または「牛」。家畜を大事に囲っておくさま。春秋末期までに、地名のほか”四角い青銅器”の意に用いた。詳細は論語語釈「匡」を参照。
天下(テンカ)
論語の本章では”地上”。具体的には”中華世界”。

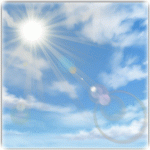
(甲骨文)
「天」の初出は甲骨文。字形は人の正面形「大」の頭部を強調した姿で、原義は”脳天”。高いことから派生して”てん”を意味するようになった。甲骨文では”あたま”、地名・人名に用い、金文では”天の神”を意味し、また「天室」”天の祭祀場”の用例がある。詳細は論語語釈「天」を参照。
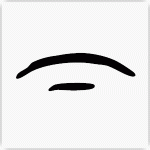

(甲骨文)
「下」の初出は甲骨文。「ゲ」は呉音。字形は「一」”基準線”+「﹅」で、下に在ることを示す指事文字。原義は”した”。によると、甲骨文では原義で、春秋までの金文では地名に、戦国の金文では官職名に(卅五年鼎)用いた。詳細は論語語釈「下」を参照。
到*(トウ)


(金文)
論語の本章では”もたらす”→”いたる”。初出は西周中期の金文。字形は「至」”矢が届く”+「人」。人が到着するさま。つくり「人」が誤って「刂」に確立するのは漢より以降で、それまでは〔至人〕の字形だった。また、漢以降に「致」が分化した。西周の金文から人名に、また”もたらす”の意に用いた。戦国最末期から、”…の時が至る”、”…まで”の意に用いた。詳細は論語語釈「到」を参照。
于(ウ)
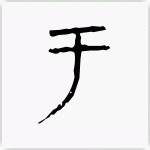

(甲骨文)
論語の本章では”~に”。初出は甲骨文。字形の由来と原義は不明。甲骨文から春秋末期まで、”~に”の意に用いた。詳細は論語語釈「于」を参照。
今(キン)


(甲骨文)
論語の本章では”いま”。初出は甲骨文。「コン」は呉音。字形は「亼」”集める”+「一」で、一箇所に人を集めるさまだが、それがなぜ”いま”を意味するのかは分からない。「一」を欠く字形もあり、英語で人を集めてものを言う際の第一声が”now”なのと何か関係があるかも知れない。甲骨文では”今日”を意味し、金文でも同様、また”いま”を意味した。詳細は論語語釈「今」を参照。
受(シュウ)
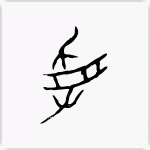

(甲骨文)
論語の本章では”受け取る”。初出は甲骨文。初出の字形は上下対になった「又」”手”の間に「舟」。「舟」の意味するところは不明だが、何かを受け渡しするさま。甲骨文の「舟」は”ふね”ではなく国名。”ふね”と釈文される「舟」の甲骨文は存在するが明らかに字形が違い、ほとんど現行の「舟」字に近い。論語の時代、「授」と書き分けられていない。「ジュ」は慣用音、呉音は「ズ」。春秋末期までに、”受け取る”・”渡す”の意に用いた。詳細は論語語釈「受」を参照。
其(キ)


(甲骨文)
論語の本章では”その”。管仲の行為を指す。「此」が近い事物を指すのに対し、「其」はやや遠い事物を指す。字の初出は甲骨文。甲骨文の字形は「𠀠」”かご”。それと指させる事物の意。金文から下に「二」”折敷”または「丌」”机”・”祭壇”を加えた。人称代名詞に用いた例は、殷代末期から、指示代名詞に用いた例は、戦国中期からになる。詠嘆の意は西周の金文から見られ、派生して反語や疑問に解するのにも無理が無い。詳細は論語語釈「其」を参照。
賜(シ)


「賜」(金文)
論語の本章では”恩恵”。現行字体の初出は西周末期の金文。字形は「貝」+「鳥」で、「貝」は宝物、「鳥」は「易」の変形。「易」は甲骨文から、”あたえる”を意味した。戦国早期の金文では人名に用い、越王家の姓氏名だったという。孔子の弟子、端木賜子貢のいみ名(本名)でもある。人物については論語の人物:端木賜子貢を参照。字の詳細は論語語釈「易」を参照。
微(ビ)


「微」(甲骨文)
論語の本章では”もし~が無かったら”。この語義は春秋時代では確認できない。
『学研漢和大字典』「微」条
- 「~なかりせば」「~なくんば」とよみ、「~がなかったとしたら」と訳す。順接の仮定条件の意を示す。「微趙君、幾為丞相所売=趙君微(な)かりせば、幾ど丞相の売る所と為らんとす」〈趙君(趙高)がいなかったならば、危うく宰相にしてやられるところであった〉〔史記・李斯〕
初出は甲骨文。字形は「長」”髪の長い人”+「丨」”くし”+「又」”手”で、長い髪を整えるさま。原義は”美しい”。漫然とのっぺり美しいのではなく、髪のように繊細にうつくしいさま。甲骨文では地名・国名・人名に用い、金文では加えて原義で用いた。戦国の竹簡では”小さい”、漢代の帛書では”細かい”を意味した。詳細は論語語釈「微」を参照。
吾(ゴ)


(甲骨文)
論語の本章では”わたし”。初出は甲骨文。字形は「五」+「口」で、原義は『学研漢和大字典』によると「語の原字」というがはっきりしない。一人称代名詞に使うのは音を借りた仮借だとされる。詳細は論語語釈「吾」を参照。
春秋時代までは中国語にも格変化があり、一人称では「吾」を主格と所有格に用い、「我」を所有格と目的格に用いた。しかし論語でその文法が崩れ、「我」と「吾」が区別されなくなっている章があるのは、後世の創作が多数含まれているため。
被髮(ヒハツ)
論語の本章では”ざんばら髪”。ここでの「被」は”「披」と同じく”開く”→”広がってバラバラになる”の意。従って「被髪」とは中華文明から見て異族の風習である、まげを結わない髪型。髪をまとめず、まとめてもさかやき部分を剃ってしまう(弁髪やちょんまげ)。論語時代の中華文明圏では、貴族の男性はまげを結い、冠をかんざしで止めてかぶるもので、女性は冠こそかぶらないものの、かんざしで髪を結い上げた。庶民も男性は頭巾をかぶり、髪を露出させるのは労働の時などに限られたと思われる。


「被」(楚系戦国文字)
「被」の初出は戦国文字。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。論語では本章のみに登場。字形は〔衣〕+〔革〕。かわごろもを着るさま。同音に「皮」、「疲」、「罷」、「鞁」”うまのかざり”。戦国文字から、”着る”・”かぶる”・”~される”の意に用いた。詳細は論語語釈「被」を参照。


召卣・西周早期
「髮」の初出は西周早期の金文。論語では本章のみに登場。新字体は「髪」。”かみのけ”の語義は論語の時代に確認出来ない。初出の字形は〔犬〕+〔首〕。チベット犬のようにたてがみのある犬の会意文字。異体字に「𩠙」。西周から春秋にかけては、”ふさふさと多い”の意に用いた。詳細は論語語釈「髪」を参照。

カスティリオーネ「蒼猊図」
左衽(サジン)
論語の本章では、左側の襟を内側に入れ込んで着ること。いわゆる「左前」。後世、中華文明から見て野蛮人の風俗と解されたが、春秋時代に異族が左衽していた、あるいは中国人が右衽していたという、史料的・考古学的証拠を訳者は知らない。
「左衽」の文献上の初出は『史記』趙世家・武霊王十九年で、武霊王が胡服の利点をある王族に説くくだりに見られる。「夫翦發文身,錯臂左衽,甌越之民也。」”そもそも髪を剃って体に入れ墨し、腕に彫り物をして左前の服を着るのは、南方は越族の風習だ。”
従って孔子生前の中華文明圏で、右前を正当とし左前を野蛮と見たかどうかはわからない。『書経』や大小の『礼記』のたぐいに、襟についての記述はあるが、いつ書かれたかはわからないし、そもそも「衽」の字が論語の時代に存在しない以上、後世の偽作と断じるしか無い。


(甲骨文)
「左」の初出は甲骨文。字形は左手の象形。原義は”左”。甲骨文では原義に、金文では加えて”補佐する”の意で用いた。論語語釈「左」を参照。


「衽」(秦系戦国文字)
「衽」の初出は戦国文字。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。字形は〔衣〕+音符〔壬〕。同音は「壬」とそれを部品とする漢字群多数。戦国時代の用例に、”えり”と解せる例がある。詳細は論語語釈「衽」を参照。
なお後世には異民族にも右前が広がったらしく、いわゆるチャイナドレスはモンゴル人や満州人の衣服の変形だが、右前である。

右利きの人が右前の服を着れば右腕が動かしやすく、懐にも手を入れやすい。人類はおおむね右利きが多いと言うから、左前の利点は弓の弦が引っかかりにくいことぐらい。ここから先は想像だが、管仲も孔子も現在の山東省の人だから、異民族に左前の衣服が多かったのでは?
山東省の異民族を東夷と言い、夷は弓に巧みなことの象形と言われるから。対して後のモンゴル人も弓に巧みだったが、現伝するチンギスハーンの肖像画は右前。『蒙古襲来絵詞』に描かれた蒙古兵も右前に見える。もっとも、攻め込んだ軍勢のほとんどは高麗人だったという。

矣(イ)


(金文)
論語の本章では、”~てしまっただろう”。初出は殷代末期の金文。字形は「𠙵」”人の頭”+「大」”人の歩く姿”。背を向けて立ち去ってゆく人の姿。原義はおそらく”…し終えた”。ここから完了・断定を意味しうる。詳細は論語語釈「矣」を参照。
豈(キ)


(秦系戦国文字)
論語の本章では”どうして…だろうか”。反語の意。初出は戦国最末期の「睡虎地秦簡」。論語時代の置換候補は存在しない。字形はおそらく「豆」”たかつき”+”蓋”+”手”。原義は不明。「漢語多功能字庫」によると「鼓」の初文「壴」”太鼓”と同形というが、上古音がまるで違う。『説文解字』は「凱歌」の「凱」の初文と言うが、「豈」は初出から”どうして…であろう”の意で用いられており、後漢儒の空耳アワーに過ぎない。近音同訓に「幾」があるが、春秋末期までに”どうして…だろうか”の用例が確認できない。詳細は論語語釈「豈」を参照。
若(ジャク)


(甲骨文)
論語の本章では”~のような”。初出は甲骨文。字形はかぶり物または長い髪を伴ったしもべが上を仰ぎ受けるさまで、原義は”従う”。同じ現象を上から目線で言えば”許す”の意となる。甲骨文からその他”~のようだ”の意があるが、”若い”の語釈がいつからかは不詳。詳細は論語語釈「若」を参照。
豈若(あに~しかん)
「豈若」の管到(語が支配する範囲)がものすごく長く、それゆえにものすごく分かりにくい表現。おそらくは意図的に壊された漢語と言える。
豈若匹夫匹婦之爲諒也、自經於溝瀆、而莫之知也。
豈に匹夫匹婦之諒を爲す也、自ら溝瀆於經れ而、之知る莫きに若かん也。
「豈若」は孟子も好んで用いたが、ここまで長い「ウナギの寝床」は、先秦両漢では後漢の王符『潜夫論』ぐらいしか見当たらない。
故堯參鄉黨以得舜,文王參己以得呂尚。豈若殷辛、秦政,既得賢人,反決滯於讎,誅殺正直,而進任姦臣之黨哉?
だから堯は田舎を探し回って後継者に舜を得、文王は土手を歩き回って太公望を得た。どうして紂王や始皇帝が人材を集めたにもかかわらず、天下に溜まったうらみを返されるはめになり、本当の事を言う者を殺し、あくどい連中ばかり昇進させたのと同じと言えようか?(『潜夫論』潜歎)
匹夫匹婦(ヒップヒップ)
論語の本章では”地位身分教養財産のない男女”。動物を一匹二匹と数えるように、漢文では人間を見下す時は動物にたとえる。これは南方の異民族を「蛮」と呼んで「虫」が入り、北方の異民族を「狄」と呼んでけものへん「犭」(=犬)が入っている例と同じ。
われわれ日本人は中華思想の分類では東夷に入り、「人」が入っているだけまだましだが、海と親しんで生活するのを「魚鼈にまみれる」と言い、魚やスッポンの仲間と見なされた。中華思想の夢想性の高さがおわかり頂けるだろうか。事実はどうでもいいのである。


(金文)
「匹」の初出は西周早期の金文。字形は大鎌+虫で、大鎌で斬られてしまうような小さな虫の意。春秋末期までに、家畜の単位のほか、”補佐する”の意に用いた。詳細は論語語釈「匹」を参照。


(甲骨文)
「夫」の初出は甲骨文。論語では「夫子」として多出。「夫」に指示詞の用例が春秋時代以前に無いことから、”あの人”ではなく”父の如き人”の意で、多くは孔子を意味する。「フウ」は慣用音。字形はかんざしを挿した成人男性の姿で、原義は”成人男性”。「大夫」は領主を意味し、「夫人」は君主の夫人を意味する。固有名詞を除き”成人男性”以外の語義を獲得したのは西周末期の金文からで、「敷」”あまねく”・”連ねる”と読める文字列がある。以上以外の語義は、春秋時代以前には確認できない。詳細は論語語釈「夫」を参照。
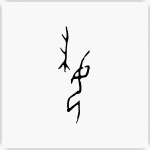

「婦」の初出は甲骨文。字形は「帚」”ほうき”+「女」。ほうきは主婦権の象徴。殷代の女性の地位は高く、王妃は政治・軍事に関わった。論語語釈「帰」も参照。「フ」は慣用音。呉音は「ブ」。甲骨文から”夫人”の意に用い、殷代末期~西周早期の金文では、「姑」とは別の概念だったと分かる。ただし春秋末期までの用例に、女性一般を意味するものは見つかっていない。詳細は論語語釈「婦」を参照。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章、「匹婦之爲諒」では”~の”。「莫之知」では”このこと”。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”~の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。
爲(イ)
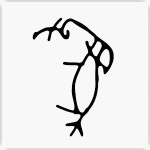

(甲骨文)
論語の本章では”する”。新字体は「為」。字形は象を調教するさま。甲骨文の段階で、”ある”や人名を、金文の段階で”作る”・”する”・”…になる”を意味した。詳細は論語語釈「為」を参照。
諒*(リョウ)


(前漢隷書)
初出は事実上前漢の隷書。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。字形は〔言〕+〔京〕”たかどの”。高く掲げることの出来る明らかな言葉。同音は「涼」、「亮」”あきらか”、「掠」、「倞」”つよい・あきらか”。戦国最末期に「掠」と釈文され、”むちうつ”と解せる例があるが、「諒」の原字とは断じがたい。「諒」があきらかに”あきらか”の意で用いられたのは、前漢初期の『韓詩外伝』まで時代が下る。詳細は論語語釈「諒」を参照。
也(ヤ)


(金文)
論語の本章では、「爲諒也」で「や」と読んで主格の強調、”~までしても”の意に用いている。文末「莫之知也」では「豈若」と呼応して詠嘆の意、”~というのか”。初出は事実上春秋時代の金文。字形は口から強く語気を放つさまで、原義は”…こそは”。春秋末期までに句中で主格の強調、句末で詠歎、疑問や反語に用いたが、断定の意が明瞭に確認できるのは、戦国時代末期の金文からで、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「也」を参照。
自(シ)
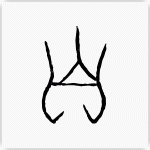
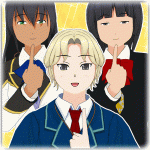
(甲骨文)
論語の本章では”自分で”。初出は甲骨文。「ジ」は呉音。原義は人間の”鼻”。春秋時代までに、”鼻”・”みずから”・”~から”・”~により”の意があった。戦国の竹簡では、「自然」の「自」に用いられるようになった。詳細は論語語釈「自」を参照。
經*(ケイ)


虢季子白盤・西周末期
論語の本章では”首をくくる”。この語義は論語の時代では確認出来ない。論語では本章のみに登場。現行字形の初出は事実上西周末期の金文。字形は〔糸〕+〔巠〕”はたに縦糸をかけたさま”。糸や紐でしめ、つなぎとめること。「キョウ」は呉音。西周・春秋の金文では”つなぎ止める”・”まとめあげる”・”見習う”の意に、戦国の竹簡では”たていと”・”常識”の意に用いた。”くびれる”語義の初出は後漢の『説文解字』で、論語の時代に存在しない。詳細は論語語釈「経」を参照。
原義は縦糸だが、『春秋公羊伝』昭公十三年などで”縊れ死ぬ”の意でも用いられた。漢代以降の書き換えを疑わせる。
於(ヨ)


(金文)
論語の本章では”~に”。”~で”と解しても良い。初出は西周早期の金文。ただし字体は「烏」。「ヨ」は”~において”の漢音(遣隋使・遣唐使が聞き帰った音)、呉音は「オ」。「オ」は”ああ”の漢音、呉音は「ウ」。現行字体の初出は春秋中期の金文。西周時代では”ああ”という感嘆詞、または”~において”の意に用いた。詳細は論語語釈「於」を参照。
溝瀆*(コウトク)


(秦系戦国文字)
論語の本章では”水路”。おそらく「瀆」”排水路”に対して”用水路”を意味する。初出は秦系戦国文字。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。字形は「氵」+「冓」”一対の毛槍”。毛槍を二本立てて測量して開削した水路の意。同音に「冓」を部品とする漢字群など。戦国の竹簡から”みぞ”の意に用いた。詳細は論語語釈「溝」を参照。


(戦国金文)
「瀆」の初出は戦国中期の竹簡。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。論語では本章のみに登場。のちに”けがす”の意に用いられたことから、おそらく”排水路”を意味する。字形は〔氵〕+音符〔賣〕。同音は「賣」(売)を部品とした漢字群多数。戦国の竹簡では、おそらく”みぞ”の意に用いた。詳細は論語語釈「瀆」を参照。
而(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”そして”。初出は甲骨文。原義は”あごひげ”とされるが用例が確認できない。甲骨文から”~と”を意味し、金文になると、二人称や”そして”の意に用いた。英語のandに当たるが、「A而B」は、AとBが分かちがたく一体となっている事を意味し、単なる時間の前後や類似を意味しない。詳細は論語語釈「而」を参照。
莫(バク)
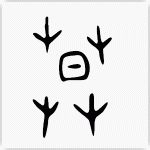

(甲骨文)
論語の本章では”~ない”。初出は甲骨文。漢音「ボ」で”暮れる”、「バク」で”無い”・”かくす”を示す。字形は「茻」”くさはら”+「日」で、平原に日が沈むさま。原義は”暮れる”。甲骨文では原義のほか地名に、金文では人名、”墓”・”ない”の意に、戦国の金文では原義のほか”ない”の意に、官職名に用いた。詳細は論語語釈「莫」を参照。
知(チ)


(甲骨文)
論語の本章では”知る”。現行書体の初出は秦系戦国文字。孔子在世当時の金文では「知」・「智」は区別せず書かれた。甲骨文で「知」・「智」に比定されている字形には複数の種類があり、原義は明瞭でない。ただし春秋時代までには、すでに”知る”を意味した。”知者”・”管掌する”の用例は、戦国時時代から。詳細は論語語釈「知」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章が前章論語憲問篇17「子路曰く、管仲公子糾を殺し~。」の焼き直しであるのは誰の目にも明らかで、前章が文字史的に論語の時代に遡れるのに対し、本章は漢代にならないと現れない漢字や語法がてんこ盛りで、漢儒の偽作と断定してよい。漢代中期の定州竹簡論語には含まれるから、おそらくは董仲舒一派の手による偽作だろう。
論語の本章の引用は、たとえば「被髮左衽」は後漢末期の徐幹『中論』が初出で、前漢代には見られない。
夫君子仁以博愛,義以除惡,信以立情,禮以自節,聰以自察,明以觀色,謀以行權,智以辨物,豈可無一哉?謂夫多少之間耳。且管仲背君事讎,奢而失禮,使桓公有九合諸侯、一匡天下之功,仲尼稱之曰:『微管仲,吾其被髮左衽矣。』召忽伏節死難,人臣之美義也;仲尼比為匹夫匹婦之為諒矣。
そもそも君子は、無差別の愛で人々に恵みを垂れ、正義の心で悪を退治し、信頼で社会の雰囲気をすがすがしくし、礼儀作法で行動にけじめを付け、頭の良さでものごとを見抜き、知識で事物の何たるかを判別し、深く考えて価値判断に釣り合いを取り、智恵であらゆるものを分類する。このうちどれ一つも、ぜんぜん無いわけではないだろう。程度の多い少ないを言えるに過ぎない。
たとえば管仲は主君を裏切ってかたきの桓公に仕え、おごり高ぶって礼法から外れたが、九度も諸侯を呼び集めるなど桓公を覇者へ押し上げ、一度は天下をまとめ上げた功績があった。だから孔子は讃えて言った。「管仲がいなかったら、私はいやはや、ざんばら髪に左前の服を着るハメになっていた」と。対して召忽は忠節を守って死んだが、臣下としてまことに天晴れな振る舞いだった。ところが孔子はこの死を、愚夫愚婦のつまらない義理立てにたとえた。(『中論』智行篇)
解説
論語の本章の成立とほぼ同時期、襟の左右を『史記』は言った。手を貸すことを「加担」と言うが、漢文業者は函館本線森駅名物イカめしく「左袒」という。
「為呂氏右袒,為劉氏左袒。」軍中皆左袒為劉氏。
(漢の高祖劉邦が死ぬと、皇后の呂后は自分以外の劉邦の夫人をむごたらしく殺し、同族を高位高官に据えた。劉邦の遺臣は呂后が死ぬのを待って行動に出た。その一人、陸相兼参謀総長の周勃が近衛隊の司令官だった呂禄をだまして司令官の印をまきあげ、駐屯地に押し入って、将兵に演説した。)「呂氏に付く者は右肩を脱げ。劉氏に付く者は左肩を脱げ。」将兵はみな左肩を脱いで劉氏の側に付いた。(『史記』呂太后本紀)
論語の本章が言うように、中国人が右衽していたなら、右肩を脱ごうとすれば「べらんめえ」は言わなくていいがもろ肌脱ぎ、左肩からまず脱ぎ上半身丸出しにならねばならない。「武装解除しろ」と言われたのと同じで、なるほど将兵も左袒したがるはずだ。
あるいは中国の儒者や物書きに、通時代的につきまとう人格の卑劣、武人への蔑視が本章となって現れたのかも知れないが、漢代の文民がどういう格好をしていたか、さかのぼっても後漢の画像石が右衽しているのを知れるのみ。まして論語の時代、中国人の襟の左右は分からない。
論語の本章、新古の注は次の通り。
古注『論語集解義疏』
子貢曰管仲非仁者與桓公殺公子糾不能死又相之子曰管仲相桓公霸諸侯一匡天下註馬融曰匡正也天子微弱桓公率諸侯以尊周室一正天下也民到于今受其賜註受其賜者謂不被髮左衽之惠也微管仲吾其被髮左衽矣註馬融曰微無也無管仲則君不君臣不臣皆為夷狄也豈若匹夫匹婦之為諒也自經於溝瀆而莫之知也註王肅曰經經死於溝瀆之中也管仲召忽之於公子糾君臣之義未正成故死之未足深嘉不死未足多非死事既難亦在於過厚故仲尼但美管仲之功亦不言召忽不當死也
本文「子貢曰管仲非仁者與桓公殺公子糾不能死又相之子曰管仲相桓公霸諸侯一匡天下」。
注釈。馬融「匡とは正すことである。周の天子が勢力を失い、桓公が諸侯を率いて王室を貴びひとたびは天下を正したのである。」
本文「民到于今受其賜」。
注釈。「”そのたまものを受く”とは、ざんばら髪や左前の服を着るはめにならなかったことをいう。」
本文「微管仲吾其被髮左衽矣」。
注釈。馬融「微とは無かったら、の意である。管仲は主君を主君とも思わず、臣下らしくないふるまいをしたが、こういうのは蛮族と同じである。」
本文「豈若匹夫匹婦之為諒也自經於溝瀆而莫之知也」。
注釈。王粛「經とは首をくくってドブ川に身投げすることである。管仲は主君の公子糾を裏切り、召忽は忠義を守って自殺したが、当時はまだ、君臣の倫理が確立されていなかった。だから孔子は”死んだのは立派だったが、無駄死にだった。死なずに何もしなかったならそいつは悪党だ”と言った。死ぬのは困難だが、死んでみせるのはやり過ぎでもある。だから孔子は管仲の功績を讃え、召忽は死ぬべきではなかったとは言わなかった。」
新注『論語集注』
子貢曰:「管仲非仁者與?桓公殺公子糾,不能死,又相之。」與,平聲。相,去聲。○子貢意不死猶可,相之則已甚矣子曰:「管仲相桓公,霸諸侯,一匡天下,民到于今受其賜。微管仲,吾其被髮左衽矣。被,皮寄反。衽,而審反。霸,與伯同,長也。匡,正也。尊周室,攘夷狄,皆所以正天下也。微,無也。衽,衣衿也。被髮左衽,夷狄之俗也。豈若匹夫匹婦之為諒也,自經於溝瀆而莫之知也。」諒,小信也。經,縊也。莫之知,人不知也。後漢書引此文,莫字上有人字。程子曰:「桓公,兄也。子糾,弟也。仲私於所事,輔之以爭國,非義也。桓公殺之雖過,而糾之死實當。仲始與之同謀,遂與之同死,可也;知輔之爭為不義,將自免以圖後功亦可也。故聖人不責其死而稱其功。若使桓弟而糾兄,管仲所輔者正,桓奪其國而殺之,則管仲之與桓,不可同世之讎也。若計其後功而與其事桓,聖人之言,無乃害義之甚,啟萬世反覆不忠之亂乎?如唐之王珪魏徵,不死建成之難,而從太宗,可謂害於義矣。後雖有功,何足贖哉?」愚謂管仲有功而無罪,故聖人獨稱其功;王魏先有罪而後有功,則不以相掩可也。
本文「子貢曰:管仲非仁者與?桓公殺公子糾,不能死,又相之。」
與は平らな調子で読む。相は尻下がりに読む。
子貢は、管仲が死なないで居たのはまだいいが、宰相にまでなったのがやり過ぎと言ったのである。
本文「子曰:管仲相桓公,霸諸侯,一匡天下,民到于今受其賜。微管仲,吾其被髮左衽矣。」
被は皮-寄の反切で読む。衽は而-審の反切で読む。霸は伯と同義で、かしらをいう。匡は正すことである。周王室を貴び、蛮族を追い払うのは、どれも天下を正す行為である。微とは無かったら、の意である。衽は衣類の襟である。被髮左衽は、蛮族の習慣である。
本文「豈若匹夫匹婦之為諒也,自經於溝瀆而莫之知也。」
諒は、つまらない義理立てのことである。經とは首をくくることである。莫之知とは、他人が知らないという事である。後漢書はこの部分を引用し、莫字の上に人字を加えている。
程頤「桓公は兄で子糾はその弟だった。管仲めが責務を自分勝手に解釈し、宰相となって跡目争いで公子糾を裏切ったのは、正義ではない。桓公が公子糾を殺したのも間違いだが、その死は当然でもあった。管仲めは公子糾と跡目争いの陰謀に加わったのだから、失敗したなら死んでしまえばよかったのだ。公子糾に跡目をつがせて宰相になろうというのがそもそも不義で、そう言われるのがイヤなら自分で無関係を決め込んで事が静まるのを待てば良かったのだ。だから聖人は死ななかったのを言葉に出して責めず、功績だけを讃えたのだ。桓公は弟で公子糾は兄なのだから、兄を補佐した管仲は正しいのだが、桓公が跡目を奪って兄を殺したのだから、管仲が桓公に手を貸したのは、兄弟ゲンカとは関係が無い。もし後々のことを考えて最初から桓公に仕えていたなら、聖人の言葉はむしろ正義を汚すもので、万世の後まで謀反人の肩を持つことになるのではないか? 唐帝国の建国の功臣だった王珪や魏徵は、はじめ唐の敵方に付いたが、のち太宗(李世民)に従って功臣となったのは、正義を汚す行いだった。あとになって功績を挙げたからと言って、それが言い訳になるだろうか。」
愚かなわたし(朱子)が考えるに、管仲には功績は有っても罪は無い。だから聖人は功績だけを言挙げして讃えたのだ。王珪や魏徵はまず罪があって後に功績を立てたが、それで足し引きゼロにはならないのだ。」
程頤は精神医学上の病人で、出仕前から人の悪口ばかり言うので皇帝以下から嫌われた。本章での言い分もそう割り引かねばならない。また朱子の言い分は、群雄割拠の中で唐の敵方に付いた王珪や魏徵が、一旦破れて書類上の罪人になったからいけないといい、管仲についてはなんで無罪なのか書いていない。
宋儒の頭がでたらめなのは論語雍也篇3余話「宋儒のオカルトと高慢ちき」に記した通り。
参考動画
余話
古拙と言うよりただの下手
中国の造形美術は、兵馬俑に見られるように秦帝国の時代にすでに、おどろくべき写実性と造形技術を持っていたが、漢になると子供の粘土人形のような稚拙な造形しか見られなくなる。訳者は中国美術史には素人だが、下掲のような漢の画像石を見ると、技術的な退化があったと想像する。

「武氏墓群石刻」後漢
この画像石は論語の本章にもやや関わりがある。その故事は次の通り。
曹沫者,魯人也,以勇力事魯莊公。莊公好力。曹沫為魯將,與齊戰,三敗北。魯莊公懼,乃獻遂邑之地以和。猶復以為將。齊桓公許與魯會于柯而盟。桓公與莊公既盟於壇上,曹沫執匕首劫齊桓公,桓公左右莫敢動,而問曰:「子將何欲?」曹沫曰:「齊彊魯弱,而大國侵魯亦甚矣。今魯城壞即壓齊境,君其圖之。」桓公乃許盡歸魯之侵地。既已言,曹沫投其匕首,下壇,北面就群臣之位,顏色不變,辭令如故。桓公怒,欲倍其約。管仲曰:「不可。夫貪小利以自快,棄信於諸侯,失天下之援,不如與之。」於是桓公乃遂割魯侵地,曹沫三戰所亡地盡復予魯。
曹沫は魯の人である。武勇を見出されて荘公に仕えた。荘公は腕力の強い者を好んでいたからである。曹沫は魯の将軍として斉と戦ったが、三度負けてしまった。荘公は恐れをなして、そのまま占領されたまちをいくつか割譲して講話したいと思った。
曹沫はそのまま将軍の任に止まった。斉の桓公は柯の地で魯と会談し講和条約を結ぶのを許した。桓公と荘公が舞台の上で調印しようとした時、曹沫が短刀を持って桓公の首に突きつけたので、桓公のお付きの者は誰も動けなくなった。
桓公が「貴殿は何が望みじゃ?」と聞くので、曹沫は「斉は強く魯は弱い。それをいいことに我が魯を襲った。今魯のまちを受け取って城壁を壊せば、つまりは自分で斉の国境を崩す事になる。殿はよくお考えあれ」と言った。桓公はすぐさま占領した魯の土地を返すよう家臣に命じた。
その言葉が終わると、曹沫は短刀を投げ捨てて舞台を降り、北向きになって臣下の礼を取った。しかし顔つきは元のまま大胆不敵で、受け答えも偉そうに聞こえた。桓公は怒って、今したばかりの返還の約束を取り消そうとした。
そこで管仲が言った。「いけません。少々の利益に目が眩んで、諸侯への信頼を失えば、天下の世論が味方してくれなくなります。占領地は返した方がいいでしょう。」こうして桓公は正式に魯へ占領地を返還し、曹沫は三度負けて失った領地を取り戻した。(『史記』刺客列伝)
甲骨文には見られるが金文には見られず、戦国や漢以降になって再び現れる漢字はいくらもある。つまり殷周革命によって一旦失われた漢語とみるべきで、そこで文化・技術的断絶があったことを思わないではいられない。人類の技術は、時代が進めば進むというものでもないわけだ。
ローマ水道を中世ヨーロッパ人が復元出来なかったように、造形技術も退化するときがある。ジャパニメーションは今では数少ない国際競争力のある輸出品になってしまったが、そうなりつつあった今世紀初頭、著しく退化した造形が流行ったことがある。大人の事情により具体例は言えない。
さて秦は生活習慣といい製鉄技術といい、東洋人と言うより多分に西方遊牧民的、あるいは印欧語族的においがする。においがするだけで「秦人は西洋人だった」というわけではないが、必ずしもコーカソイドばかりでなかったスキタイの製鉄技術と、時代的に驚くほど似ていると聞く。
兵馬俑も、ギリシア・ローマの彫像を思わせるが、ただ「似ている」と言えるに過ぎない。




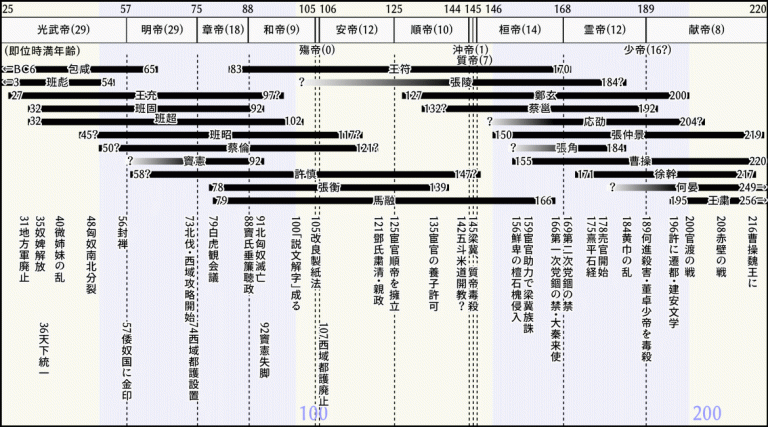



コメント