論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子曰默而識之學而不厭誨人不倦何有於我哉
校訂
東洋文庫蔵清家本
子曰默而識之學而不厭誨人不倦何有於我哉
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
……」[黑而職a,學b不厭,誨人不]卷c,何有於我哉?」139
- 黑而職、今本作「默而識之」。『釋文』云、「默、俗作嘿」。默也通黑、見『爾雅』釈器。職、識二字経典中互作。
- 今本「學」字下有「而」字。
- 巻、今本作「倦」。巻借為倦。
標点文
子曰、「黑而職、學不厭、誨人不卷、何有於我哉。」
復元白文(論語時代での表記)



















※論語の本章は、「默」「倦」が論語の時代に存在せず、「黑」に”だまる”の意は論語の時代に存在しない。「卷」に”うみつかれる”の意は論語の時代に存在しない。「之」の用法に疑問がある。本章は戦国末期以降の創作の可能性がある。
書き下し
子曰く、黑し而職し、學びて厭は不、人を誨へて卷ま不る、何ぞ我於有らむ哉。
論語:現代日本語訳
逐語訳

先生が言った。「黙って記し、学んで嫌がらず、人を教えて飽きない。私に何があるだろうか。」
意訳

文句を付けず過去の文化をよく書き残し、学んで嫌がらず、人を教えて飽きない。こんな事は私にとって、何でもない。
従来訳
先師がいわれた。――
「沈默のうちに心に銘記する、あくことなく学ぶ、そして倦むことなく人を導く。それだけは私に出来る。そして私に出来るのは、ただそれだけだ。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子說:「將知識默記在心,學習時,不感到滿足;教人時,不感到疲倦,對我來說沒什麽問題。」
孔子が言った。「知識を黙って心に記し、学んでも、満足しない。人に教えるとき、疲れを感じない。私にとっては、何の問題でも無い。」
論語:語釈
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。


(甲骨文)
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
默(ボク)→黑(コク)
唐石経と清家本は「默」と記し、現存最古の論語本である定州竹簡論語は「黑」と記す。時系列に従い「黑」へと校訂した。ただし定州本の当時、すでに「默」字は有ったと思われ、「默」字として「黑」字を記したのか、ただの誤字かは分からない。
論語の伝承について詳細は「論語の成立過程まとめ」を参照。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)


(前漢隷書)
論語の本章では”黙って”。「モク」は呉音。新字体は「黙」。初出は前漢の隷書『蒼頡篇』。『蒼頡篇』は秦から前漢にかけて通用した字書であり、武帝期にメルヘンオタクであった司馬相如が類書の『凡将篇』を編んでいることから、宣帝期の定州本の時代にはすでに「默」字が存在したと考えるのが理に合う。また現在「蒼頡篇・西漢」と小学堂で分類されている文字は、前漢武帝期の筆写とされる「北京大学蔵西漢竹書」が出典と思われ、より時代が下る宣帝期に「默」字が存在したのは確実と考える。
しかし「默」字は論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。字形は「黑」(黒)+「犬」。前漢ごろ、「黑」に”だまる”の語義が出来てから、犬を加えて、普段ワンワンと吠える犬が黙っているさま。詳細は論語語釈「黙」を参照。
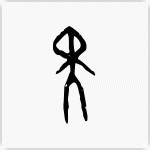

(甲骨文)
定州竹簡論語の「黑」の新字体は「黒」。甲骨文の字形は頭の大きな人。春秋の金文になると点が付けられるようになり、戦国文字になると点が二つになった。この字形は「堇」「𦰩」”火あぶりされるみこ”に極めて近く、おそらく原義は生け贄が黒焦げになったさま。春秋末期までに、”黒い”・”月食”・人名に用いた。”だまる”の語義は確認できない。詳細は論語語釈「黒」を参照。
定州竹簡論語に「黑」とあり、甲骨文まで遡れることから、論語の本章を史実と解したいところだが、”だまる”の語義がない以上、今後「黑」→”黙る”の出土があるまで、本章は創作と断じるしか無い。
而(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”…すると同時に”。初出は甲骨文。原義は”あごひげ”とされるが用例が確認できない。甲骨文から”~と”を意味し、金文になると、二人称や”そして”の意に用いた。英語のandに当たるが、「A而B」は、AとBが分かちがたく一体となっている事を意味し、単なる時間の前後や類似を意味しない。詳細は論語語釈「而」を参照。
識(シ)→職(ショク)


(金文)
論語の本章では、”記す”。初出は西周早期の金文。初出の字形は「戠」で、「戈」+”棒杭”。「戠」の語義は兵器の名とも、土盛りとも、”あつまる”の意ともされるが、初出は”知る”の意と解せる。漢音(遣隋使・遣唐使が聞き帰った音)は、”しる”では「ショク」、”しるす”では「シ」。初出の金文では”知る”と解せ、春秋末期までの用例はこれ一件しか無い。また戦国末期までの出土に、”記す”と明確に解読できる例は無い。詳細は論語語釈「識」を参照。
本章はおそらく前漢ごろの創作だが、後漢末まで文献に”記す”の用例が見つからない。
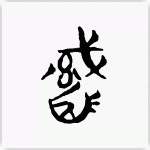

(玉書)
定州竹簡論語の「職」の初出は春秋末期の玉書。字形は「耳」+「戠」”犠牲獣をともなう祭祀”。原義はおそらく”血をすすり合って誓う”。春秋末期の金文で”職”と解せ、春秋末期までの用例は以上で全て。戦国時代には人名の用例が加わり、戦国最末期の竹簡に”記す”の用例がある。詳細は論語語釈「職」を参照。
定州竹簡論語の筆者は、”記す”のつもりで記していると思われる。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章では”まさに”。この語義は春秋時代では確認できない。定州竹簡論語では欠いている。直前の動詞を強調する働きをし、意味内容を持っていない。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”~の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。
學(カク)


(甲骨文)
論語の本章では”学ぶ”。「ガク」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。初出は甲骨文。新字体は「学」。原義は”学ぶ”。座学と実技を問わない。上部は「爻」”算木”を両手で操る姿。「爻」は計算にも占いにも用いられる。甲骨文は下部の「子」を欠き、金文より加わる。詳細は論語語釈「学」を参照。
不(フウ)


(甲骨文)
漢文で最も多用される否定辞。初出は甲骨文。「フ」は呉音、「ブ」は慣用音。原義は花のがく。否定辞に用いるのは音を借りた派生義だが、甲骨文から否定辞”…ない”の意に用いた。詳細は論語語釈「不」を参照。
厭(エン/オウ)


(金文)
論語の本章では(もう十分だから)”飽きる”。初出は西周早期の金文。漢音「エン」で”あきる”、「オウ」で”押さえる”の意を示す。字形は「𠙵」”くち→あたま”+「月」”からだ”+「犬」で、脂の強い犬肉に人が飽き足りるさま。原義は”あきる”。金文では”満ち足りる”の意に用いた。異体字の「猒」を含めて、”厭う”の意は確認できないが、”満ち足りる”の派生義としては妥当と判断する。詳細は論語語釈「厭」を参照。
誨(カイ)


(金文)
論語の本章では”教える”。初出は甲骨文とされるが、「每」(毎)の字形であり、「每」に”おしえる”の語義は甲骨文で確認できない。現行字体の初出は西周中期の金文。字形は「言」+「每」で、「每」は髪飾りを付けた女の姿。ただし漢字の部品としては”暗い”を意味し、「某」と同義だった。春秋末期までの金文では人名のほか、”たくらむ”・”教える”の語義がある。詳細は論語語釈「誨」を参照。
人(ジン)


(甲骨文)
論語の本章では”他人”。初出は甲骨文。原義は人の横姿。「ニン」は呉音。甲骨文・金文では、人一般を意味するほかに、”奴隷”を意味しうる。対して「大」「夫」などの人間の正面形には、下級の意味を含む用例は見られない。詳細は論語語釈「人」を参照。
倦(ケン)→卷(ケン)


論語の本章では(くたびれて)”飽きる”。初出は楚系戦国文字。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。字形は「人」+「卷」。「卷」の原義ははっきりせず、おそらく音符。原義は”あきる”。同音に「権」・「卷」(巻)など多数。戦国の竹簡に”あきる”の用例があり、また「劵」を「倦」と釈文する例がある。詳細は論語語釈「倦」を参照。
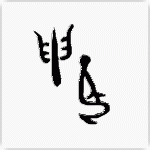

(金文)
定州竹簡論語「卷」(巻)の初出は殷代末期の金文。両手+棒状のもの+背中を向けた人で、人に見えないように何かを”抱え込む・隠す”と解するのが理にかなうと思う。ただし殷周の用例は全て族徽(家紋)か人名で、何を意味しているのかわからない。戦国最末期の竹簡で、”引き返す”と解せる例がある。詳細は論語語釈「巻」を参照。
「倦」は論語の時代に存在せず、論語時代の置換候補も無く、「卷」には春秋末期までに”うみつかれる”の用例が無い。従って論語時代の表記は復元出来ないとするのが理にかなう。
何(カ)


「何」(甲骨文)
「何」は論語の本章では”なに”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は「人」+”天秤棒と荷物”または”農具のスキ”で、原義は”になう”。甲骨文から人名に用いられたが、”なに”のような疑問辞での用法は、戦国時代の竹簡まで時代が下る。詳細は論語語釈「何」を参照。
有(ユウ)


(甲骨文)
論語の本章では”ある”。初出は甲骨文。ただし字形は「月」を欠く「㞢」または「又」。字形はいずれも”手”の象形。原義は両腕で抱え持つこと。詳細は論語語釈「有」を参照。
於(ヨ)


(金文)
論語の本章では”~に”。初出は西周早期の金文。ただし字体は「烏」。「ヨ」は”…において”の漢音(遣隋使・遣唐使が聞き帰った音)、呉音は「オ」。「オ」は”ああ”の漢音、呉音は「ウ」。現行字体の初出は春秋中期の金文。西周時代では”ああ”という感嘆詞、または”~において”の意に用いた。詳細は論語語釈「於」を参照。
我(ガ)


(甲骨文)
論語の本章では”わたし”。初出は甲骨文。字形はノコギリ型のかねが付いた長柄武器。甲骨文では占い師の名、一人称複数に用いた。金文では一人称単数に用いられた。戦国の竹簡でも一人称単数に用いられ、また「義」”ただしい”の用例がある。詳細は論語語釈「我」を参照。
哉(サイ)


(金文)
論語の本章では”…かね”。詠歎の籠もった反語の意を示す。初出は西周末期の金文。ただし字形は「𠙵」”くち”を欠く「𢦏」で、「戈」”カマ状のほこ”+「十」”傷”。”きずつく”・”そこなう”の語釈が『大漢和辞典』にある。現行字体の初出は春秋末期の金文。「𠙵」が加わったことから、おそらく音を借りた仮借として語気を示すのに用いられた。金文では詠歎に、また”給与”の意に用いられた。戦国の竹簡では、”始まる”の意に用いられた。詳細は論語語釈「哉」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章は上記の通り、「默」「倦」が論語の時代に存在せず、定州竹簡論語の「黑」「卷」が論語時代の置換候補たりえない。今後の発掘によっては結論が変わるだろうが、現在では戦国時代もかなり末になってに創作されたと考えるのが理にかなう。
「默而識之」は先秦両漢に引用無し、「學而不厭、誨人不倦、何有於我哉」は若干違う文字列で戦国最末期の『呂氏春秋』にある。
孔子曰:「吾何足以稱哉?勿已者,則好學而不厭,好教而不倦,其惟此邪。」
孔子曰く、「私に何の理由があって賞賛されるのか? そんなものはすでに捨て去った。学びを好んで飽きず、教えるのを好んでくたびれず、ただそれだけのことだ。」(『呂氏春秋』尊師5)
ただ文字列としては偽作と断じるしか無いが、偽作の動機が見いだせず、あるいは史実の孔子がこのようなことを言った可能性はある。
解説
孔子が「黙ってよく書き記し、学んで嫌がらず、人を教えて飽きない」のはその通りで、前章の「述べて作らず」と合わせ、孔子の言葉の信憑性を裏付ける決まり文句になっている。しかしだからといって、孔子が作り事をしないわけではない。こんな例もある。
晋国の筆頭家老に趙盾(チョウジュン、チョウトンとも)という人がいて、幼くして国君になった霊公の守り役だった。成長した霊公は手の着けられないバカ殿になり、諌めた趙盾を殺そうとした。人望のあった趙盾はさまざまな人の助けを借りて逃亡したが、国境を越える手前で霊公が暗殺された。急いで都城に戻った趙順を、史官の董狐(トウコ)が書いて、でかでかと朝廷に貼り出した。いわく、「趙盾が主君の霊公を殺した。」
趙盾「なんだこれは。でたらめじゃないか。書き直しなさい。」
董狐「いいえ。あなたは宰相で、暗殺の時、国境を越えていませんでした。都城に戻っても、下手人を処刑していません。これはあなたの責任です。だからあなたが殺したも同然です。」
趙盾「やれやれ。何と言うことだ。”心を込めた行いが、かえって身のあだになる”とは私のことだ。」

孔子「いにしえの董狐は見上げた史官だ。法を守って隠さず書いた。趙盾も立派だが、法には従わなければならない。国境を越えなかったのが残念だ。」(『春秋左氏伝』宣公二年2)
『春秋左氏伝』の筆者がいきさつを記さなかったら、趙盾は主君を殺した悪人として伝わったことになる。孔子の言う「述べて作らず」はこのでんで、史実と受け取っていいかは注意が必要。また孔子にとっての法とは、成文法ではなく運用者の勝手にできるものだった。
詳細は論語における「法」を参照。
余話
どいつもこいつも元〒囗刂ス卜
春秋の君子が「黙って記す」わけにはいかないことをたびたび記した。政論に負けてしまうし、外交交渉をしくじり、戦場で兵を叱咤激励出来ないからだ。詳細は論語衛霊公篇11余話「口利かん」を参照。
対して書斎に籠もってちくちくと物書きをするのは、戦国時代以降の儒者や、帝政期の官僚儒者の姿である。
上掲『呂氏春秋』が、「学而不厭」以降しか孔子の言葉として乗せていないのは、「黙而識之」を実際に孔子が言った可能性がないことを示す。『呂氏春秋』の成立は、秦帝国創立直前で、始皇帝はウソに本気で怒ったから、「黙而識之」を論語に押し込んだのは漢儒だろう。
皇帝にとって、目の前で頭を下げている家臣どもが腹の中で何を企んでいるか、興味を持たざるを得ない。家臣が結託して排除に掛かったら、自分の身が危ないからである。例えば後漢の皇帝の多くは、父は子に帝位を継がせられず、皇帝は幼くして即位し、成人すると殺された。
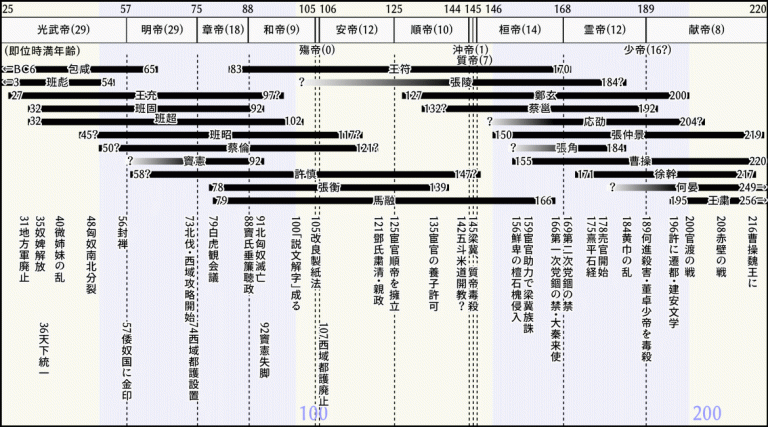
後漢年表 クリックで拡大
対して皇帝に頭を下げる儒者官僚は、本当の事を口に出すわけにはいかない。極端な例は前漢武帝で、気に食わないことを聞くと家臣を家族ごと、割と気軽に皆殺しにした(論語雍也篇11余話)。黙っていないと身が危ない。黙っていられると身が危ない皇帝と対を為した。
中国屈指のまじめ皇帝である清の雍正帝は、家臣の口を開こうと説教した。
同心補佐。盡誠極言。勿使朕躬有過。此朕所厚望於爾等也。…且使人主之好惡而果有未公。則何不面折廷諍。而爲是陽奉陰違。以遂其植黨營私之計也。
心を一つにして朕を補佐し、誠実をつくしウソの無い言葉でズケズケ申せ。朕に間違いを起こさせるな。これこそが、朕が諸君にとりわけ希望することである。
…もし君主の好悪に、確かに公平でない点があるのなら、どうして面と向かって批判し、公の場で当否を争わないのか。それはつまり、表では従う振りをして、裏では舌を出すというもので、そうやって自分の党派を立て、私利私欲のたくらみを実現させようとするのである。(清雍正帝『御製朋党論』)
これは中国に限ったことではない。明治維新後閣僚になった連中は、どいつもこいつも元〒囗刂ス卜で、西郷隆盛のような教唆犯もいれば、伊藤博文のような実行犯もいる。黒田清隆の夫人斬殺事件を、無かったことにしてしまった明治政府である。天皇は緊張を強いられた。
明治帝政も初期には、天皇が至尊の存在だという認識が一般にまで浸透しておらず、天皇は神主の親分程度に思われていた。従って天皇を守るはずの御親兵が、待遇の不満から反乱を起こし、気軽に天皇に銃を向けた。二二六の「兇暴ノ将校ラ」は明治ですでに出ていたのだ。
女官の記録によれば、天皇は日本刀の業物の収集に狂奔し、毎日一時間は刀をいじって過ごしたという。日本帝国が明治の間は割と効率的に運用されたのは、明治帝の緊張と無関係ではない。積極的に君主たろうとした大正帝は病気で果たせず、昭和帝には緊張感が見られない。
また明治帝は世界史上珍しいことに、自ら絶対君主権を手放して立憲帝政に移った。家臣がそう望んだからそうなったのでもあるが、ただし軍事権は握って離さなかった。これは日本史上に珍しいことで、天皇が国軍を直接把握しその頭領となったのは、上古を除けば戦前だけだ。
対して昭和帝は知能は高かったし、粗暴を嫌う紳士ではあったが、保身のみを考え君主の器ではなかった。たよりないひょろひょろと軍人から見られていたために、二二六事件が起こったわけだし、それ以外の軍人の横暴も、大元帥なのに舐められていたのが心理的背景にある。

対して明治では、おじゃる公家も緊張していた。西園寺公望が晩年に住んだ、焼津坐漁荘の窓格子の竹には、襲撃に備えて鉄筋が入っている。


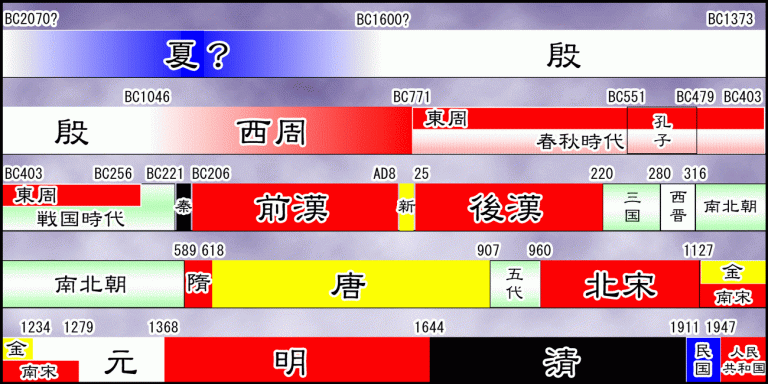


コメント