論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子語魯大師樂曰樂其可知也始作翕如也從之純如也皦如也繹如也以成
- 「純」字:最後の一画を欠く。唐憲宗李純の避諱。
校訂
諸本
東洋文庫蔵清家本
子語魯大師樂曰樂其可知已始作翕如也/從之純如也/皦如也/繹如也以成
後漢熹平石経
(なし)
定州竹簡論語
……如也,允如[也a,以]60……
- 允如也、今本作「繹如也」。
標点文
子語魯大師樂曰、「樂其可知已。始作、翕如也。從之、純如也、皦如也、允如也。以成。」
復元白文(論語時代での表記)














 翕
翕





 皦
皦






※論語の本章は、赤字が論語の時代に存在しない。「語」「大師」「其」「也」「如」「始」「純」「繹」「允」「成」(解によっては「從」も)の用法に疑問がある。本章は後世の儒者による創作である。
書き下し
子、魯の大師に樂を語りて曰く、樂は其れ知る可き已。始め作すとき翕すが如き也、之を從つとき純むが如き也、皦かな如き也、允むが如き也、以て成る。
論語:現代日本語訳
逐語訳

先生が魯国の楽長に言った。「音楽の要点はそもそも知ることが出来てしまいます。演奏の始めは各楽器を合わせる如く、合ったら各楽器の音を交えざるが如く、交えざるようになったら激しく、激しくなったら音を調和させて、それでまとまります。」
意訳

協奏曲の要点。各楽器を静かに鳴らし、音が合ったら各自力強く、激しく、響き合わせ、スッと終えること。
従来訳
先師が魯の楽長に音楽について語られた。――
「およそ音楽の世界は一如の世界だ。そこにはいささかの対立もない。先ず一人一人の楽手の心と手と楽器が一如になり、楽手と楽手とが一如になり、更に楽手と聴衆とが一如になって、翕如として一つの機をねらう。これが未発の音楽だ。この翕如たる一如の世界が、機熟しておのずから振動をはじめると、純如として濁りのない音波が人々の耳を打つ。その音はただ一つである。ただ一つではあるが、その中には金音もあり、石音もあり、それぞれに独自の音色を保って、決しておたがいに殺しあうことがない。皦如として独自を守りつつ、しかもただ一つの音の流れに没入するのだ。こうして時がたつにつれ、高低、強弱、緩急、さまざまの変化を見せるのであるが、その間、厘毫のすきもなく、繹如としてつづいて行く。そこに時間的な一如の世界があり、永遠と一瞬との一致が見出される。まことの音楽というものは、こうして始まり、こうして終るものだ。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子同魯國樂官談音樂,說:「音樂是可知的:開頭是合奏;隨後是純正、清晰、綿長的音調,這樣就完成了。」
孔子が魯国の音楽官と同席して音楽を語った。いわく、「音楽は知ることが出来る。始まりは音を合わせる。そのあとで各楽器特有の音を出す。すると澄み切った長い音調となる。このようにして完成する。」
論語:語釈
子(シ)


(甲骨文)
論語の本章では”(孔子)先生”。初出は甲骨文。字形は赤ん坊の象形。春秋時代では、貴族や知識人への敬称に用いた。季康子や孔子のように、大貴族や開祖級の知識人は「○子」と呼び、一般貴族や孔子の弟子などは「○子」と呼んだ。詳細は論語語釈「子」を参照。
語(ギョ)


(金文)
論語の本章では”語る”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は春秋末期の金文。「ゴ」は呉音。字形は「言」+「吾」で、初出の字形では「吾」は「五」二つ。春秋末期以前の用例は1つしかなく、「娯」”楽しむ”と解せられている。詳細は論語語釈「語」を参照。
論語の本章では、孔子が一方的に説教を垂れているだけだが、『漢書』などを参照すると、論語の本章を偽作した漢人の間では、”互いに言葉のやりとりをする”というニュアンスで理解されていたらしく、本章の舞台設定は、孔子と楽長との語り合いの中で、孔子が言った、ということになる。
魯(ロ)


(甲骨文)
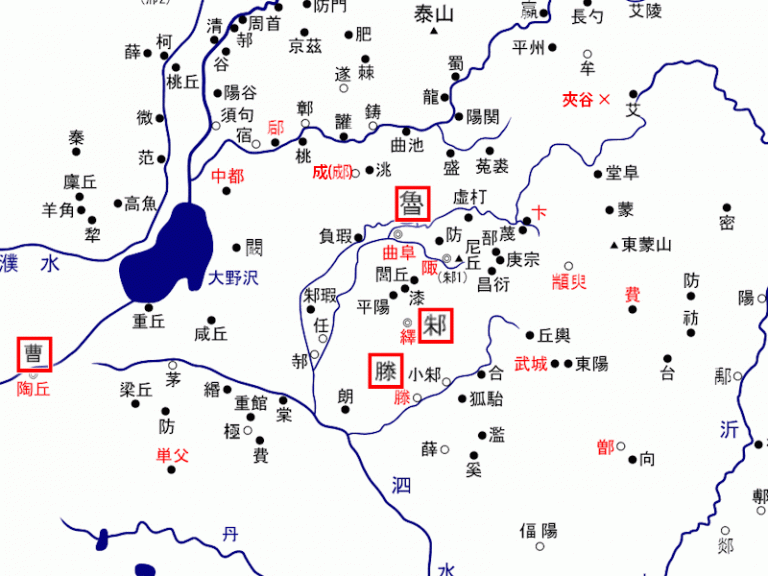
MAP via http://shibakyumei.web.fc2.com/
孔子の生まれた春秋諸侯国の一国。周初の摂政・周公旦を開祖とし、周公旦の子・伯禽が初代国公。現在の中国山東省南部(山東半島の付け根)にあった。北の端には聖山である泰山があり、西の端には大野沢という湖があった。東は大国・斉、南には邾・滕といった小国があった。首邑は曲阜(現曲阜)。wikipediaを参照。また辞書的には論語語釈「魯」を参照。
大師(タイシ)
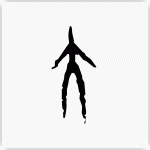
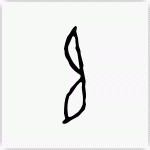
(甲骨文)
論語の本章では、”宮廷楽団長”。「ダイシ」は呉音。甲骨文・金文の用例に従えば、”大いなる軍隊”の意だが、漢帝国成立後に儒者が「周代の理想の制度」なるものをでっち上げるに至って、「春官の属。楽工の長で、大師・小師に分かつ」と『大漢和辞典』はいう。これも基づき武内本は「楽官の名」という。論語の本章が漢帝国以降の創作であることを示す言葉。
論語の時代、音楽は盲人が掌った。魯の宮廷楽団長もおそらく盲人だったろうことが、論語衛霊公篇42から推測できる。辞書的には論語語釈「大」・論語語釈「師」を参照。
樂(ガク/ラク)


(甲骨文)
論語の本章では”音楽”。初出は甲骨文。新字体は「楽」。原義は手鈴の姿で、”音楽”の意の方が先行する。漢音(遣隋使・遣唐使が聞き帰った音)「ガク」で”奏でる”を、「ラク」で”たのしい”・”たのしむ”を意味する。春秋時代までに両者の語義を確認できる。詳細は論語語釈「楽」を参照。
曰(エツ)


(甲骨文)
論語で最も多用される、”言う”を意味する言葉。初出は甲骨文。原義は「𠙵」=「口」から声が出て来るさま。詳細は論語語釈「曰」を参照。
其(キ)


(甲骨文)
論語の本章では「それ」とよみ、”そもそも”という詠歎を示す。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「𠀠」”かご”。かごに盛った、それと指させる事物の意。金文から下に「二」”折敷”または「丌」”机”・”祭壇”を加えた。人称代名詞に用いた例は、殷代末期から、指示代名詞に用いた例は、戦国中期からになる。詳細は論語語釈「其」を参照。
可(カ)


(甲骨文)
論語の本章では”…出来る”。積極的に認める意味ではない。初出は甲骨文。字形は「口」+「屈曲したかぎ型」で、原義は”やっとものを言う”こと。甲骨文から”~できる”を表した。日本語の「よろし」にあたるが、可能”~できる”・勧誘”…のがよい”・当然”…すべきだ”・認定”…に値する”の語義もある。詳細は論語語釈「可」を参照。
知(チ)


(甲骨文)
論語の本章では”知る”。現行書体の初出は春秋早期の金文。春秋時代までは「智」と区別せず書かれた。甲骨文で「知」・「智」に比定されている字形には複数の種類があり、原義は”誓う”。春秋末期までに、”知る”を意味した。”知者”・”管掌する”の用例は、戦国時時代から。詳細は論語語釈「知」を参照。
也(ヤ)→已(イ)
現存最古の論語本である定州竹簡論語は「樂其可知□」部分を欠き、唐石経は「樂其可知也」と記し、清家本は「樂其可知已」と記す。唐石経は晩唐になって刻まれたが、唐朝の都合によりそれまでの文字列を書き換えた点が少なくない。日本には唐より前の隋代にはすでに論語が伝わり、古い文字列を伝承していた。
清家本は時系列としては、唐石経はおろか宋代の論語注疏や新注より新しいのだが、唐石経より前の、論語の古い文字列を伝えていると言える。従って清家本に従い「樂其可知也」→「樂其可知已」に校訂した。
論語の伝承について詳細は「論語の成立過程まとめ」を参照。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)


(金文)
「也」は論語の本章では、「其可知也已」では「なり」と読んで断定の意を示す。この語義は春秋時代では確認できない。「如」のうしろでは「たり」と読んで断定の意を示す。初出は事実上春秋時代の金文。字形は口から強く語気を放つさまで、原義は”…こそは”。春秋末期までに句中で主格の強調、句末で詠歎、疑問や反語に用いたが、断定の意が明瞭に確認できるのは、戦国時代末期の金文からで、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「也」を参照。


(甲骨文)
「已」は論語の本章では”…てしまう”の派生義として”…である”。断定の意。
『学研漢和大字典』「已」条
「~のみ」とよみ、文末におかれ、(1)「~なのである」と訳す。断定の意を示す。「苟無恒心、放辟邪侈、無不為已=苟(いや)しくも恒心無(な)ければ、放辟邪侈(はうへきじゃし)、為さざる無きのみ」〈いったんこの道徳心を持たなくなると、したいほうだい、(悪いことで)しないことはなくなります〉〔孟子・梁上〕
字の初出は甲骨文。字形と原義は不詳。字形はおそらく農具のスキで、原義は同音の「以」と同じく”手に取る”だったかもしれない。論語の時代までに”終わる”の語義が確認出来、ここから、”~てしまう”など断定・完了の意を容易に導ける。詳細は論語語釈「已」を参照。
始(シ)
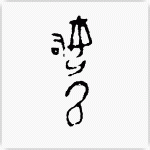

(金文)
論語の本章では”はじめ”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は殷代末期の金文。ただし字形は「![]() 」。字形は「司」+「女」+〔㠯〕”農具のスキ”。現伝字形の初出は西周末期の金文。ただし部品が左右で入れ替わっている。女性がスキをとって働くさま。原義は不詳。金文で姓氏名に用いられた。詳細は論語語釈「始」を参照。
」。字形は「司」+「女」+〔㠯〕”農具のスキ”。現伝字形の初出は西周末期の金文。ただし部品が左右で入れ替わっている。女性がスキをとって働くさま。原義は不詳。金文で姓氏名に用いられた。詳細は論語語釈「始」を参照。
作(サク)


(甲骨文)
論語の本章では”音を出す”。初出は甲骨文。金文まではへんを欠いた「乍」と記される。字形は死神が持っているような大ガマ。原義は草木を刈り取るさま。”開墾”を意味し、春秋時代までに”作る”・”定める”・”…を用いて”・”…とする”の意があったが、”突然”・”しばらく”の意は、戦国の竹簡まで時代が下る。詳細は論語語釈「作」を参照。
翕如(キュウジョ)

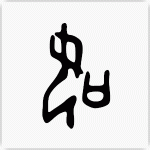
「翕」(篆書)/「如」(甲骨文)
論語の本章では”あわせるように”。「翕」は論語では本章のみに登場。初出は後漢の『説文解字』。字形は「合」+「羽」で、鳥が羽ばたきを合わせるさま。漢代になって作られた新しい言葉で、論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。詳細は論語語釈「翕」を参照。
「如」は論語の本章では”…のように”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。年代確実な金文は未発掘。字形は「女」+「口」。甲骨文の字形には、上下や左右に「口」+「女」と記すものもあって一定しない。原義は”ゆく”。詳細は論語語釈「如」を参照。
從(ショウ)


(甲骨文)
論語の本章では、”好きなように奏でる”。ただし本章は漢代以降の偽作が確定しているので、”従う”と訳すのにも理がある。ただしこの語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。新字体は「従」。「ジュウ」は呉音。字形は「彳」”みち”+「从」”大勢の人”で、人が通るべき筋道。原義は筋道に従うこと。甲骨文での解釈は不詳だが、金文では”従ってゆく”、「縦」と記して”好きなようにさせる”の用例があるが、”聞き従う”は戦国時代の「中山王鼎」まで時代が下る。詳細は論語語釈「従」を参照。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章では”これ”。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”~の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。
純如(シュンジョ)


「純」(甲骨文)
論語の本章では”純粋なように”。この語義は春秋時代では確認できない。「純」の初出は甲骨文。論語の春秋時代までは「屯」と書き分けられていなかった。現行字体の初出は戦国時代の金文。「ジュン」は呉音。「屯」の字形の由来は”カイコ”。原義は”きぬ(いと)”。甲骨文では”一対の”・”あいだじゅう”を意味した。金文では”厚い”・”大きい”、”衣類のふち”を意味した。戦国の竹簡では、”すべて”を意味した。つまり”混ざらない”の語義は、戦国時代以降になる。詳細は論語語釈「純」を参照。
皦如(キョウジョ)

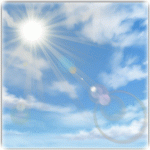
「皦」(古文)
論語の本章では”輝くように”。「皦」は論語では本章のみに登場。初出は後漢の『説文解字』。字形は「白」+「敫」”日光の輝き”で、白く明るく輝くさま。漢代になって出来た新しい言葉で、論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。詳細は論語語釈「皦」を参照。
繹如(エキジョ)→允如(インジョ)


「繹」(玉石文)
論語の本章では”引き延ばすように”。この語義は春秋時代では確認できない。「繹」の初出は春秋末期の玉石文。カールグレン上古音はdi̯ak(入)。同音に睪(うかがい見る)を部品とする漢字群。『大漢和辞典』には睪に”引く”の語釈を載せる。ただし睪の初出は戦国早期の金文で、論語の時代に存在したとは言いがたい。字形は「糸」+「睪」で、糸巻きから糸を引き出すさま。原義は”糸を引き抜く”。詳細は論語語釈「繹」を参照。


「允」(甲骨文)
定州竹簡論語の「允」は、論語の本章では”調和が取れて公平なさま”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は座席に座った上位者が首を縦に振るさまで、原義は”許す”。甲骨文では”実際に”、金文では”信用”、”用いる”の意に用いた。詳細は論語語釈「允」を参照。
以(イ)


(甲骨文)
論語の本章では”それで”。初出は甲骨文。人が手に道具を持った象形。原義は”手に持つ”。論語の時代までに、名詞(人名)、動詞”用いる”、接続詞”そして”の語義があったが、前置詞”~で”に用いる例は確認できない。ただしほとんどの前置詞の例は、”用いる”と動詞に解せば春秋時代の不在を回避できる。詳細は論語語釈「以」を参照。
成(セイ)


(甲骨文)
論語の本章では”完成する”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は「戊」”まさかり”+「丨」”血のしたたり”で、処刑や犠牲をし終えたさま。甲骨文の字形には「丨」が「囗」”くに”になっているものがあり、もっぱら殷の開祖大乙の名として使われていることから、”征服”を意味しているようである。いずれにせよ原義は”…し終える”。甲骨文では地名・人名、”犠牲を屠る”に用い、金文では地名・人名、”盛る”(弔家父簠・春秋早期)に、戦国の金文では”完成”の意に用いた。詳細は論語語釈「成」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章は、音楽について御託を並べた漢帝国の儒者による創作。前漢中期に司馬遷が『史記』孔子世家に再録するまで、春秋戦国の誰一人引用していない。その後はただ「翕如」だけが、後漢末から三国にかけての張仲景による医学書『傷寒論』に記されるのみ。
陽明病,欲食,小便反不利,大便自調,其人骨節疼,翕翕如有熱狀,奄然發狂,濈然汗出而解者,此水不勝穀氣,與汗共併,脈緊則愈。


陽明病(症状が明らかな病気)の患者が、食べたがるのに、小便の出が悪く、大便だけはするする出て、節々がうずくように痛み、痛みと同調するように熱が出て、病魔が内に籠もったような感覚があって苦しみ、ダラダラと汗が流れるのにすっきりしない者は、これは水分が不足して消化が十分でないのであり、無駄に汗を流して水分を失っているのだから、脈拍が早くなれば治る。(『傷寒論』弁陽明脈証并治)
張仲景の死去は219年とされており、王朝の系譜から言えば後漢が滅ぶのはその翌年だが、後漢は霊帝の死去と共に事実上滅亡しており、それ以降は後漢とは言え、実は三国時代。霊帝を継いだ少帝は即位と同時に殺され、最後の献帝は曹操の慈悲で皇帝であり続けたに過ぎない。
解説
論語の各所に記されているように、孔子は音楽をよくし、塾の必須科目にも入れていた。しかし当時の音楽がどのようなものだったかは、楽譜が残っていないためにわからない。儒教経典の中でも音楽を取り扱った『楽経』は、早くに失われ現存しない。
いずれ後世の創作だから、始めから無かったのだ、と考えることも出来る。
論語の本章はほぼ擬態音で表現されているために、その意味もはっきりしない。従来の論語本もまた同じで、宮崎本に至っては、わかるかこんなの、とばかりこう訳している。

最初の出だしは翕如、それを受けて純如、今度は急転して皦如、おしまいに繹如としてそれで終わりですね。(『論語の新研究』)
そこで訳者としては、こんな事であろうかと思う動画を提示するに留める。
また『説苑』脩文篇の記述は参考になるように見えるが、いずれも後世の創作。
余話
弁証論治
内科的には事実上『傷寒論』から始まる中国伝統医学(いわゆる漢方)は、病態を「陰陽」「表裏」「虚実」の3つのベクトルで分類しようとする。それらの意味は医家によって解釈が異なるが、訳者は「気の上げ下げ」「病態の見た目の程度」「潜伏か顕現か」だと思っている。
冬にガンガン暖房を吹かしても寒くてかなわないのは、「裏」に寒気が閉じこもって抜けないからで、たいていは蜂蜜と生姜を利かせた甘酒を摂ることで緩和する。蜂蜜は気の滞りを和らげ、生姜は裏を温め、酒粕は基礎体力に力を付けて虚実ともに抵抗する力を与える。
夏にガンガン冷房を吹かしても暑くてかなわないのに風邪を引く場合があるのは、「表」の熱だけ取り去ろうと過剰に冷やすからで、やり過ぎると一挙に裏の熱まで奪い、本来体を営み衛るべき体温まで失うことになる。だからといって氷菓で「裏」を冷やしすぎると腹を下す。
中医学が熱について実践的な処方を編み出せたのは、ずいぶん時代が下って清代の温病論からになる。それ以前はとにかく「温めろ」というのが主流で、冷房技術の無い時代では当然とも言えるが、体温を維持できるだけの食糧が、頻繁に饑饉で滞った反映でもある。
清代は歴代王朝に比べて豊かだったとも言える。その結果、例えば風邪のたぐいの治療では、現在でも科学的医療に迫るほどの効果があったりする。だからと言って不実な薬屋のたぐいが言うことを真に受けてはならないが、漢文が読める余慶として、嘘が見抜けたりもする。
3つのベクトルで理論的に処方を決めていく手続きを「弁証論治」と呼ぶが、漢文が読める医師が少ないこともあって、病院で処方される漢方薬には首をかしげることが少なくない。かといって文系おたくをこじらせた訳者如きが、お医者の先生に楯突くのはオカルト同然になる。
例えば代替医療でルイボス茶を熱心に勧める例がある。普段のお茶として訳者は好んでルイボスを飲むし、それが現地人の間で医薬として使われていたことは知っているが、では何でアフリカの現地で厄介な疫病が繰り返し起こるのか、を考えれば薬にする気にはならない。
数Ⅰ的論理学に比べ、現代での漢文読解力の実用性は、せいぜいこの程度に過ぎない。



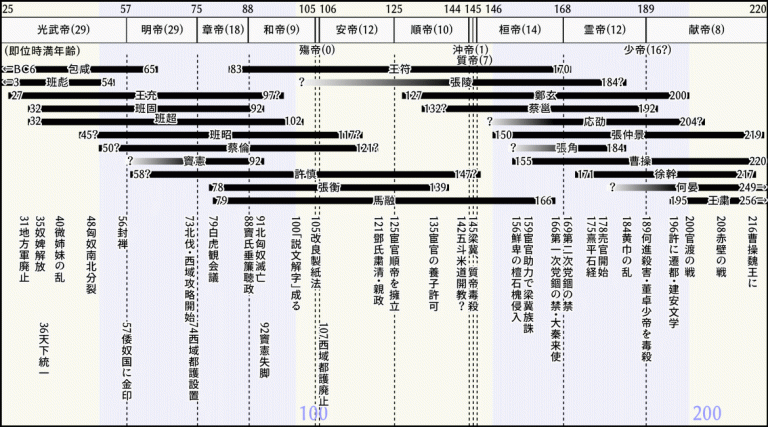


コメント