論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子貢曰貧而無諂富而無驕何如子曰可也未若貧而樂富而好禮者也子貢曰詩云如切如磋如琢如磨其斯之謂與子曰賜也始可與言詩巳矣吿諸往而知來者
校訂
東洋文庫蔵清家本
子貢曰貧而無謟富而無驕何如子曰可也/未若貧而樂道富而好禮者也/子貢曰詩云如切如磋如琢如磨其斯之謂與/子曰賜也始可與言詩已矣吿諸往而知來者也
後漢熹平石経
…而無諂富而無驕…吿諸往而知来…
定州竹簡論語
……樂a,富而好禮者也。子![]() b曰:「《詩》云:『如切如磋,如琢如磨』,1……
b曰:「《詩》云:『如切如磋,如琢如磨』,1……
- 皇侃『論語義疏』(以下簡称「皇本」)、高麗本、日本足利本、『史記』仲尼弟子列伝、孔安国注、邢疏、「樂」下皆有「道」字、阮元『十三経注疏』本(以下簡称「阮本」)「樂」下無「道」字。
 、今本多作「貢」、漢石経作「贛」。以下同。『説文』云、「貢、献功也。」「贛、賜也。」段注云、「端木賜字子贛、凡作子貢者、亦皆後人所改。
、今本多作「貢」、漢石経作「贛」。以下同。『説文』云、「貢、献功也。」「贛、賜也。」段注云、「端木賜字子贛、凡作子貢者、亦皆後人所改。 、貢皆贛之省。」
、貢皆贛之省。」
標点文
子貢曰、「貧而無諂、富而無驕、何如。」子曰、「可也、未若貧而樂、富而好禮者也」。子貢曰、「詩云如切如磋、如琢如磨、其斯之謂與。」子曰、「賜也、始可與言詩已矣。吿諸往而知來者也。」
復元白文(論語時代での表記)


 貧
貧
 諂
諂 










 貧
貧












 切
切

 琢
琢 磨
磨 























※貢→(甲骨文)・驕→喬・詩→辭・磋→差。本章は赤字が論語の時代に存在しない。「何」「如」「也」「未」の用法に疑問がある。論語の本章は、戦国時代以降、おそらくは後漢末から三国にかけての儒者による創作である。
書き下し
子貢曰く、貧しくし而諂う無く、富み而驕る無きは、何ぞ如かん。子曰く、可しき也も、未だ貧しくし而樂むに若かざり、富み而禮を好む者也。子貢曰く、詩に云く、切るが如く磋るが如く、琢むが如く磨くが如しとは、其斯之謂與。子曰く、賜也、始めて興に詩を言ふ可き已矣。諸往けるを吿げ而來たるを知る者也。
論語:現代日本語訳
逐語訳


子貢が言った。「貧しくてへつらわない。富んでおごらない。こういうのはどうでしょう。」
先生が言った。「悪くない。しかし貧しくて楽しむ者には及ばず、富んで礼法を好む者に過ぎない。」
子貢が言った。「『詩経』にあります。切るようにこするように磨くように研ぐように、と。それはこういう境地を言うのですか。」
先生が言った。「賜よ。共に詩を語ることが出来るようになったな。お前はいろいろと過去の事情を話せば、(それで)未来を知る(=推論できる)者だな。」
意訳


子貢「世の中には顔回のような、貧乏でもプライドの高い者がいます。でも私のように威張らない金持ちの方が、立派じゃないですかね。」
孔子「威張らぬ金持ちも悪くない、が、顔回のように貧乏を楽しむ貧乏人には及ばない。浮ついた金でウチのような礼法教室に通ってくる、お前みたいな小金持ちに過ぎないね。」
子貢「はぁ。顔回は♪原石は~、よ~く磨くと玉になる~。みたいに自分を磨いたんですかね。」
孔子「よしよし。お前も歌ごころが分かるようになったな。あの古い歌の通りに磨くと、お前もそのうち、顔回みたいな立派な人間になれるぞよ。」
従来訳
子貢が先師にたずねた。――
「貧乏でも人にへつらわない、富んでも人に驕らない、というほどでしたら、立派な人物だと思いますが、いかがでしょう。」
先師がこたえられた。――
「先ず一とおりの人物だといえるだろう。だが、貧富を超越し、へつらうまいとか驕るまいとかいうかまえ心からすっかり脱却して、貧乏してもその貧乏の中で心ゆたかに道を楽しみ、富んでもごく自然に礼を愛するというような人には及ばないね。」
すると子貢がいった。――
「なるほど人間の修養には、上には上があるものですね。詩経に、切るごとく、
磋るごとく、
琢つごとく、
磨くがごとく、
たゆみなく、
道にはげまん。とありますが、そういうことをいったものでございましょうか。」
先師は、よろこんでいわれた。――
「賜よ、お前はいいところに気がついた。それでこそ共に詩を談ずる資格があるのだ。君は一つのことがわかると、すぐつぎのことがわかる人物だね。」
現代中国での解釈例
子貢說:「貧窮卻不阿諛奉承,富貴卻不狂妄自大,怎樣?」孔子說:「可以。不如窮得有志氣,富得有涵養的人。」子貢說:「修養的完善,如同玉器的加工:切了再磋,琢了再磨,對吧?」孔子說:「子貢啊,現在可以與你談詩了。說到過去,你就知道未來。」
子貢が言った。「貧乏なのに却っておもねらずご機嫌を取らず、富貴なのに却って自分が偉いと妄想しない。〔こういうのは〕どうでしょうか。」孔子が言った。「悪くは無い。〔だが〕追い詰められて志を保ち、富んで教養のある人には及ばない。」子貢が言った。「修養の完成とは、玉の加工と同じように、切っては磨き、彫っては研ぐ。正しいですか?」孔子が言った。「子貢よ。今、お前と共に詩を語れるようになった。過去について説明すると、お前はすぐに未来を理解する。」
論語:語釈
子貢(シコウ)→子 (シコウ)
(シコウ)

孔子の弟子。政才・商才にもっともすぐれ、孔子没後は東方の大国・斉の宰相になったとされる。論語の人物:端木賜子貢を参照。
「子」は知識人・貴族への敬称。初出は甲骨文。貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指すが、そうでない例外もある。字形は生まれたばかりの赤ん坊の象形。詳細は論語語釈「子」を参照。
「![]() 」は「貢」の異体字。「貢」は金文は未発掘だが、甲骨文から存在する。詳細は論語語釈「貢」を参照。
」は「貢」の異体字。「貢」は金文は未発掘だが、甲骨文から存在する。詳細は論語語釈「貢」を参照。
問(ブン)


(甲骨文)
論語の本章では”問う”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。「モン」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。字形は「門」+「口」。原義=甲骨文での語義は不明。西周から春秋に用例が無く、一旦滅んだ漢語である可能性がある。戦国の金文では人名に用いられ、”問う”の語義は戦国最末期の竹簡から。それ以前の戦国時代、「昏」または「𦖞」で”問う”を記した。詳細は論語語釈「問」を参照。
この字は唐石経の系統を引く現伝論語には無いが、現伝の古注『論語義疏』にはあるものの、現存最古の古注本である宮内庁蔵清家本には無い。また定州竹簡論語では欠損部分で、字の存在を否定しない。
曰(エツ)


(甲骨文)
論語で最も多用される、”言う”を意味する言葉。初出は甲骨文。原義は「𠙵」=「口」から声が出て来るさま。詳細は論語語釈「曰」を参照。なお「曰」を「のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
貧(ヒン)


(楚系戦国文字)
論語の本章では”貧しい”。初出は楚系戦国文字。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補も無い。字形は「分」+「貝」で、初出での原義は確認しがたい。「ビン」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。詳細は論語語釈「貧」を参照。
而(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”それでなお”。初出は甲骨文。原義は”あごひげ”とされるが用例が確認できない。甲骨文から”~と”を意味し、金文になると、二人称や”そして”の意に用いた。英語のandに当たるが、「A而B」は、AとBが分かちがたく一体となっている事を意味し、単なる時間の前後や類似を意味しない。詳細は論語語釈「而」を参照。
無(ブ)


(甲骨文)
論語の本章では”~しない”。初出は甲骨文。「ム」は呉音。甲骨文の字形は、ほうきのような飾りを両手に持って舞う姿で、「舞」の原字。その飾を「某」と呼び、「某」の語義が”…でない”だったので、「無」は”ない”を意味するようになった。論語の時代までに、”雨乞い”・”ない”の語義が確認されている。戦国時代以降は、”ない”は多く”毋”と書かれた。詳細は論語語釈「無」を参照。
諂(テン)


(隷書)/「臽」(金文)
論語の本章では、こびへつらいのうち、”相手を落とし穴にはめるようなへつらい”。初出は前漢の隷書。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補も無い。同音は存在しない。字形は「言」+「臽」”落とし入れる”で、言葉で人を落とし入れること。詳細は論語語釈「諂」を参照。
貧而無諂

”貧乏だがヘコヘコしない”。古注によれば、子貢は暗に顔淵(顔回)を指している。ところが孔子にとって顔淵は、ただプライドが高いだけの貧乏人ではなく、貧乏そのものを楽しめる、とんでもなく上出来の人物だった。ゆえに「貧而樂」(貧しくして楽しむ)と言った。
ただしこの雍也篇の章は後世の創作で、顔淵神格化を推し進めたのは、おそらく前漢の董仲舒。論語先進篇3付記を参照。また董仲舒についてより詳しくは、論語公冶長篇24余話を参照。
富(フウ)

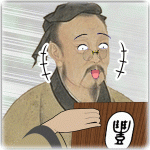
(甲骨文)
論語の本章では”富む”。初出は甲骨文。「フ」は呉音。字形は「冖」+「酉」”酒壺”で、屋根の下に酒をたくわえたさま。「厚」と同じく「酉」は潤沢の象徴で(→論語語釈「厚」)、原義は”ゆたか”。詳細は論語語釈「富」を参照。
驕(キョウ)


(秦系戦国文字)
論語の本章では”おごり高ぶる”。現行書体の初出は秦系戦国文字で、論語の時代に存在しない。ただし論語の時代には部品で同音の「喬」と書き分けられていなかった。字形は「馬」+「喬」”たかい”。馬が跳ね上がったさま。詳細は論語語釈「驕」を参照。
富而無驕
論語の本章では、”金持ちだが威張らない”。
古注によれば、子貢は暗に自分を指している。子貢が孔子や塾生たちの経済支援をしつつも驕らない人だったことは、孔子没後反対派閥が後継となったにもかかわらず、「子」という敬称を取り払われず、十哲からも外されなかったことから想像できる。
しかし孔子はそんな子貢を、「カルチャーとかに通ってくる小金持ち(富而好禮者=富みて礼を好む者)のたぐいだ」とやりこめたわけ。
何(カ)


(甲骨文)
論語の本章では”なに”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は「人」+”天秤棒と荷物”または”農具のスキ”で、原義は”になう”。甲骨文から人名に用いられたが、”なに”のような疑問辞での用法は、戦国時代の竹簡まで時代が下る。詳細は論語語釈「何」を参照。
如(ジョ)


(甲骨文)
論語の本章では”…のような(もの)”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は「口」+「女」。甲骨文の字形には、上下や左右に部品の配置が異なるものもあって一定しない。原義は”ゆく”。詳細は論語語釈「如」を参照。
何如(なんぞしかん)


論語の本章では”どうでしょう”。「何」が「如」”つき従う”か=”どう(なる)でしょう”の意。対して「如何」は「何」に「如」”つき従う(べき)”か=”どうしましょう”の意。


「いかん」と訓読するのが漢文業界の座敷わらしだが、「如何」も「いかん」と読むので混乱するだけ。とうにくたばった、読めない漢文を読めると世間を欺してきた、おじゃる公家やくそ坊主の真似をするのはもうやめよう。通説が「いかん」と読み下す一連の句形については、漢文読解メモ「いかん」を参照。
可(カ)


(甲骨文)
論語の本章では”悪くない”。積極的に認める意味ではない。初出は甲骨文。字形は「口」+「屈曲したかぎ型」で、原義は”やっとものを言う”こと。甲骨文から”~できる”を表した。日本語の「よろし」にあたるが、可能”~できる”・勧誘”…のがよい”・当然”…すべきだ”・認定”…に値する”の語義もある。詳細は論語語釈「可」を参照。
也(ヤ)


(金文)
論語の本章では、「や」と読んで下の句とつなげる働きと、「なり」と読んで断定の意に用いている。後者の語義は春秋時代では確認できない。初出は春秋時代の金文。原義は諸説あってはっきりしない。「や」と読み主語を強調する用法は、春秋中期から例があるが、「也」を句末で断定に用いるのは、戦国時代末期以降の用法で、論語の時代には存在しない。詳細は論語語釈「也」を参照。
文末の「也」は唐石経の系統を引く現伝論語には見られないが、最古の古注本である宮内庁本は記し、先行する漢石経・定州竹簡論語はこの部分が欠損している。物証が無いのは「無かった」証拠にはならないので、宮内庁本に従い校訂した。
未(ビ)


(甲骨文)
論語の本章では”今までにいない”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。「ミ」は呉音。字形は枝の繁った樹木で、原義は”繁る”。ただしこの語義は漢文にほとんど見られず、もっぱら音を借りて否定辞として用いられ、「いまだ…ず」と読む再読文字。ただしその語義が現れるのは戦国時代まで時代が下る。詳細は論語語釈「未」を参照。
若(ジャク)


(甲骨文)
論語の本章では”同程度になる”。初出は甲骨文。字形はかぶり物または長い髪を伴ったしもべが上を仰ぎ受けるさまで、原義は”従う”。同じ現象を上から目線で言えば”許す”の意となる。甲骨文からその他”~のようだ”の意があるが、”若い”の語釈がいつからかは不詳。詳細は論語語釈「若」を参照。
樂(ラク)


(甲骨文)
論語の本章では”楽しむ”。初出は甲骨文。新字体は「楽」。原義は手鈴の姿で、”音楽”の意の方が先行する。漢音(遣隋使・遣唐使が聞き帰った音)「ガク」で”奏でる”を、「ラク」で”たのしい”・”たのしむ”を意味する。春秋時代までに両者の語義を確認できる。詳細は論語語釈「楽」を参照。
道(トウ)

国会図書館蔵『唐開成石經』拓本
唐石経は傍記し、清家本は格内に記す。先行する漢石経はこの部分を欠き、現存最古の定州本は記さない。よってないものとして扱った。唐石経の傍記は後になってからの追加で、清家本は「唐帝国公認の論語」に従って書いたと考えるのが筋が通る。論語の伝承について詳細は「論語の成立過程まとめ」を参照。
原始論語?…→定州竹簡論語→白虎通義→ ┌(中国)─唐石経─論語注疏─論語集注─(古注滅ぶ)→ →漢石経─古注─経典釈文─┤ ↓↓↓↓↓↓↓さまざまな影響↓↓↓↓↓↓↓ ・慶大本 └(日本)─清家本─正平本─文明本─足利本─根本本→ →(中国)─(古注逆輸入)─論語正義─────→(現在) →(日本)─────────────懐徳堂本→(現在)
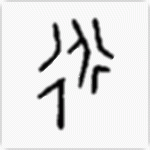

(甲骨文)
「道」は論語の本章では”人生”。初出は甲骨文。「ドウ」は呉音。字形は「行」”十字路”+「人」で、原義は人の通る”道”。「首」の形が含まれるのは金文から。春秋時代までの語義は”道”または官職名?で、”みちびく”・”道徳”の語義は戦国時代にならないと見られない。詳細は論語語釈「道」を参照。
孔子の生前では、”原則・やり方”という一般的意味があるだけで、道徳的な意味はなかった。そういうめんどうくさいもったい付けをしたのは、孔子没後約一世紀の孟子からになる。
好(コウ)


(甲骨文)
論語の本章では”好む”。初出は甲骨文。字形は「子」+「母」で、原義は母親が子供を可愛がるさま。春秋時代以前に、すでに”よい”・”好む”・”親しむ”・”先祖への奉仕”の語義があった。詳細は論語語釈「好」を参照。
禮(レイ)


(甲骨文)
論語の本章では”礼儀作法”。新字体は「礼」。しめすへんのある現行字体の初出は秦系戦国文字。無い「豊」の字の初出は甲骨文。両者は同音。現行字形は「示」+「豊」で、「示」は先祖の霊を示す位牌。「豊」はたかつきに豊かに供え物を盛ったさま。具体的には「豆」”たかつき”+「牛」+「丰」”穀物”二つで、つまり牛丼大盛りである。詳細は論語語釈「礼」を参照。
者(シャ)


(金文)
論語の本章では”そういう者”。旧字体は〔耂〕と〔日〕の間に〔丶〕一画を伴う。新字体は「者」。ただし唐石経・清家本ともに新字体と同じく「者」と記す。現存最古の論語本である定州竹簡論語も「者」と釈文(これこれの字であると断定すること)している。初出は殷代末期の金文。金文の字形は「木」”植物”+「水」+「口」で、”この植物に水をやれ”と言うことだろうか。原義は不明。初出では称号に用いている。春秋時代までに「諸」と同様”さまざまな”、”~する者”・”~は”の意に用いた。漢文では人に限らず事物にも用いる。詳細は論語語釈「者」を参照。
未若貧而樂、富而好禮者也
論語本章、この部分の訓読には二種類ある。
未若貧而樂、富而好禮者也。
「未だ貧しくして楽しみ、富みて礼を好む者に若かざる也。」
”貧しくても楽しみ、かつ富んだら礼を好む者、には及ばない。”
未若貧而樂、富而好禮者也。
「未だ貧しくして楽しむに若かざり、富みて礼を好む者也。」
”貧しくても楽しむ者に及ばない。富んだら礼を好む者だ。”
古注を参照すると、論語の本章は、子貢が自分と顔淵とを比較したものという。しかし上下どちらの読みでそう判断したのかははっきりしない。ただ、もし顔淵との比較とするなら、貧しくても楽しむ顔淵と、富んで礼を好む子貢との対比になると読むには、下しかない。

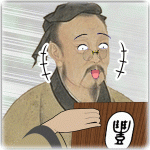
新注は上を支持しているようだ。「子貢はかつて貧しく、金儲けに励んで富んだのだろう」と朱子の個人的感想を言っている。しかしそうするなら、「貧しくても楽しみ、富んだら礼を好む者に」子貢はすでになっているわけで、「及ばない」わけではないから理屈が通らない。
それともあれだろうか、新古の儒者はそろって、子貢は富んだが礼を好まない愚か者だとでも言いたいのだろうか。「人は過去の人物を言いたい放題言う。だから君子はそういうゴミ溜めには近寄らないものだ」(論語子張篇20)と子貢が言った通りの結果になった?
漢文は対句を重んじる言語。五文字五文字で釣り合いを取った読みの方に理がある。いずれにせよ従来の読み下しは、句読は間違っていないが返り点を付け間違っている。これはまるまる中国の儒者のせいではなく、朱子とそれを有り難がった日本の儒者と漢学者の怠慢。
従来訳がどんな読み下しをして、上記のような現代語訳に至ったかは不明なので、筆者の下村湖人先生が教育を受けた戦前の、論語の権威で東京帝国大学教授・宇野哲人の本を参照する。

「未だ貧しうして楽しみ、富んで礼を好む者に若かざるなり。」
しかし、まだ貧富を超越してはいない。貧乏しても貧乏を忘れて泰然自得して楽しんでおり、富んでも富を忘れて善に拠り理に循って礼を好む者には及ばない。(『論語新釈』)
孔子が言ってもいない超越だの泰然だの善に拠りだのは、新古の注の受け売りだが、上の読みをしている。しかし顔淵は一生貧乏だったから、「富んで礼を好む」者ではない。子貢と顔淵の対比話はどこへ? つまり儒者の受け売りをするにもいいとこ取りをしたということだ。
しかしだからこそ、余計なごてごてを付けざるを得ないハメになった。読者は余計にわけが分からない。おそらくは、江戸儒者あたりの返り点が間違っていたのと、新古注の儒者の個人的感想の間にある断絶を無理に混ぜて、どうにか繕ってみました、ということだろう。
詩(シ)


(楚系戦国文字)
論語の本章では”『詩経』”。初出は戦国文字。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補は近音の「辞」。字形は「言」+「寺」”役所”のものや、「之」”ゆく”+「口」などさまざまある。原義が字形によって異なり、明瞭でない。詳細は論語語釈「詩」を参照。
云(ウン)


(甲骨文)
論語の本章では”いう”。何かの文書や、誰それがそう言った、の場合に用いる。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は「一」+”うずまき”で、かなとこ雲(積乱雲)の象形。甲骨文では原義の”雲”に用いた。金文では語義のない助辞としての用例がある。”いう”の語義はいつ現れたか分からないが、分化した「雲」の字形が現れるのが楚系戦国文字からであることから、戦国時代とみるのが妥当だが、殷末の金文に”言う”と解せなくもない用例がある。詳細は論語語釈「云」を参照。
切(セツ)
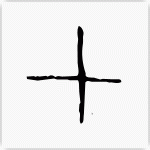

(甲骨文)
論語の本章では”宝石を研磨する”。現行字体の初出は前漢の隷書。それ以前は「七」と書き分けられなかった。「七」の初出は甲骨文。ただし春秋末期までに”切る”と解せる「七」は無く、論語時代の置換候補は存在しない。同音は無し。字形は「七」たてよこに刻んだ切り目+「刀」。原義は”切る”。詳細は論語語釈「切」を参照。
磋(サ)


「差」(金文)
論語の本章では”宝石を研磨する”。初出は前漢の定州竹簡論語。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補は近音で部品の「差」。字形は「石」+「差」”こする”。詳細は論語語釈「磋」を参照。
琢(タク)


(篆書)
論語の本章では”宝石を研磨する”。初出は前漢の定州竹簡論語。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。同音に春秋時代以前に存在した文字は無い。字形は「玉」+「豖」。「豖」(チク/チョク・トク:上古音不明)は”行き悩む様”で、”きる・みがく”の語釈は『大漢和辞典』に無い。詳細は論語語釈「琢」を参照。
磨(バ)


(楚系戦国文字)
論語の本章では”宝石を研磨する”。「マ」は呉音。初出は楚系戦国文字または後漢の『説文解字』だが、字体が■(上下に𣏟+石)または「䃺」。現伝字体の初出は漢代の篆書。同音はいずれも春秋時代以前に存在しない。詳細は論語語釈「磨」を参照。
切磋琢磨
『詩経』の「伝」(注釈)によれば、それぞれ、骨、象牙、玉、石の加工。武内本はこれをコピペして「切磋琢磨とは骨象玉石を磨くこと。転じて学問修養により人品を向上せしむる意」と記す。

子貢が引用した詩は、現伝の『詩経』によると次の通り。
瞻彼淇奧、綠竹猗猗。
淇の川の奥を見やれば、みずみずしい竹がうるわしい。
有匪君子、如切如磋、如琢如磨。
教養ある君子というものは、切るように研ぐように、彫るように磨くように
瑟兮僩兮、赫兮咺兮。
おごそかで威厳があり、見栄えがして凛々しい。
有匪君子、終不可諼兮。
ゆえに教養ある君子は、ついぞ誰にも損ない得ない。(『詩経』衛風・淇奧)
つまり文字史からこの詩そのもの成立のが前漢以降ということになり、現伝の『詩経』は論語と同様、後世のマゼモンがたっぷり練り込まれたパチモンということになる。
其(キ)


(甲骨文)
論語の本章では”その”という指示詞。「切磋琢磨」を指す。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「𠀠」”かご”。かごに盛った、それと指させる事物の意。金文から下に「二」”折敷”または「丌」”机”・”祭壇”を加えた。人称代名詞に用いた例は、殷代末期から、指示代名詞に用いた例は、戦国中期からになる。詳細は論語語釈「其」を参照。
斯(シ)


(金文)
論語の本章では「きは」と読み、”そういう境地”の意。孔子が言った、”貧しくても人生を楽しみ、礼を好む”状態を指す。古詩「切磋琢磨」の精神とは、孔子の言った「未若貧而樂、富而好禮」という心理状態を指しているのですね、と子貢がうまいこと言って念を押しているのである。
字の初出は西周末期の金文。字形は「其」”籠に盛った供え物を祭壇に載せたさま”+「斤」”おの”で、文化的に厳かにしつらえられた神聖空間のさま。意味内容の無い語調を整える助字ではなく、ある状態や程度にある場面を指す。例えば論語子罕篇5にいう「斯文」とは、ちまちました個別の文化的成果物ではなく、風俗習慣を含めた中華文明全体を言う。詳細は論語語釈「斯」を参照。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章では”~の”。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”~の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。
謂(イ)


(金文)
論語の本章では”…ということの表現”。現行書体の初出は春秋後期の石鼓文。部品で同義の「胃」の初出は春秋早期の金文。『学研漢和大字典』によると、胃は、「まるい胃袋の中に食べたものが点々と入っているさま+肉」で、まるい胃袋のこと。謂は、「言+〔音符〕胃」の会意兼形声文字で、何かをめぐって、ものをいうこと、という。詳細は論語語釈「謂」を参照。
與(ヨ)


(金文)
論語の本章では、”…か”・”…と(もに)”。新字体は「与」。論語の本章では、”~と”。新字体初出は春秋中期の金文。金文の字形は「牙」”象牙”+「又」”手”四つで、二人の両手で象牙を受け渡す様。人が手に手を取ってともに行動するさま。従って原義は”ともに”・”~と”。詳細は論語語釈「与」を参照。
其斯之謂與(そのきはのいいか)
論語の本章では、”そういう境地の表現ですか”。「其」は『学研漢和大字典』に「此(この)に対して、やや遠いところを指す」とあり、引用詩の前の、「貧而樂、富而好禮」を指す。「斯」とは「貧而樂、富而好禮」の”境地”・”精神”。「詩が言う切磋琢磨とは、貧しくして…の精神を指すのですね」と子貢がやや孔子におもねった、あるいは甘えた表現。
子曰「…未若貧而樂、富而好禮者也」。 └───────↓ 子曰、「詩云如切如磋、如琢如磨、其斯之謂與。」
そう言われた孔子は、あられもなく「でかした! うんうん、お前も詩が分かるようになってきたか! その上、ちょっとものを言えば将来のことまで見通す逸材だ!」と子貢を褒め讃えたわけ。
年若の閲覧者諸賢。よーく聞き候らえ。年長者、とりわけ孔子のような教え魔は、自分の説教を真に受けて、「それはこういうことなんですね」と若者に感心されると、コドモのように喜ぶチョロい生物ですぞ。そのあたりをつ突いて甘い汁を吸うのが、若者の特権というものでござる。

それに、この句を「それこれのいいか」とナントカの一つ覚えのように訓読し、意味を問い詰めると誤魔化しにかかる不届きな漢文業者は、旧帝大の漢学教授にもおりますぞ。そういうやからは諸賢を食おうとしている肉食のサルですから、決して真に受けてはなりませんぞ。
- 論語雍也篇27余話「そうだ漢学教授しよう」
賜(シ)
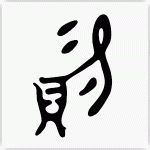
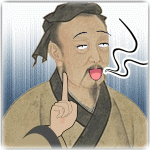
(金文)
論語の本章では、端木賜子貢の本名。姓は端木。
「賜」の初出は西周早期の金文だが、字形は「易」。現行字体の初出は西周末期の金文。字形は「貝」+「鳥」で、「貝」は宝物、「鳥」は「易」の変形。「易」は甲骨文から、”あたえる”を意味した。詳細は論語語釈「易」を参照。「賜」は戦国早期の金文では人名に用い(越王者旨於賜鐘)、越王家の姓氏名だったという。詳細は論語語釈「賜」を参照。
呉越の抗争に絡んで、呉国は一時孔子一門の住まう魯国を半ば占領したことがある(『春秋左氏伝』哀公八年)。その解決のため孔子は子貢を呉越に派遣して抗争を煽ったのだが、呉からはけんもほろろに断られ、越からは下へも置かないもてなしと賛同を得た。その背景に存外、衛の出身と言われる子貢の氏族と、越王家とのつながりがあるかも知れない。
始(シ)
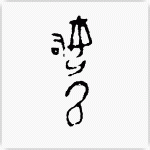

(金文)
論語の本章では”はじめて”。初出は殷代末期の金文。ただし字形は「![]() 」。字形は「司」+「女」+〔㠯〕”農具のスキ”。現伝字形の初出は西周末期の金文。ただし部品が左右で入れ替わっている。女性がスキをとって働くさま。原義は不詳。金文で姓氏名に用いられたが、”はじめ(る)”の語義は春秋時代では確認できない。詳細は論語語釈「始」を参照。
」。字形は「司」+「女」+〔㠯〕”農具のスキ”。現伝字形の初出は西周末期の金文。ただし部品が左右で入れ替わっている。女性がスキをとって働くさま。原義は不詳。金文で姓氏名に用いられたが、”はじめ(る)”の語義は春秋時代では確認できない。詳細は論語語釈「始」を参照。
言(ゲン)


(甲骨文)
論語の本章では”かたる”。初出は甲骨文。字形は諸説あってはっきりしない。「口」+「辛」”ハリ・ナイフ”の組み合わせに見えるが、それがなぜ”ことば”へとつながるかは分からない。原義は”言葉・話”。甲骨文で原義と祭礼名の、金文で”宴会”(伯矩鼎・西周早期)の意があるという。詳細は論語語釈「言」を参照。
已


(甲骨文)
論語の本章では”…てしまう”。初出は甲骨文。字形と原義は不詳。字形はおそらく農具のスキで、原義は同音の「以」と同じく”手に取る”だったかもしれない。論語の時代までに”終わる”の語義が確認出来、ここから、”~てしまう”など断定・完了の意を容易に導ける。詳細は論語語釈「已」を参照。
唐石経は「巳」と書く。「巳」”へび”「已」”すでに”「己」”おのれ”は、異体字としてそれぞれ通用した。
矣(イ)


(金文)
論語の本章では、”(きっと)~である”。初出は殷代末期の金文。字形は「𠙵」”人の頭”+「大」”人の歩く姿”。背を向けて立ち去ってゆく人の姿。原義はおそらく”…し終えた”。ここから完了・断定を意味しうる。詳細は論語語釈「矣」を参照。
吿(コク/コウ)


(甲骨文)
論語の本章では”告げる・説明する”。新字体は「告」。初出は甲骨文。「コク」の読みで”つげる”、「コウ」の読みで”君主のおさとし”。字形は「辛」”ハリまたは小刀”+「口」。甲骨文には「辛」が「屮」”草”や「牛」になっているものもある。字解や原義は、「口」に関わるほかは不詳。甲骨文で祭礼の名、”告げる”、金文では”告発する”(五祀衛鼎・西周)の用例があった。詳細は論語語釈「告」を参照。
諸(ショ)


(秦系戦国文字)
論語の本章では”いろいろ”。論語の時代では、まだ「者」と「諸」は分化していない。「者」の初出は西周末期の金文。ごんべんのある現行字体の初出は秦系戦国文字。「之於」(シヲ)と音が通じるので一字で代用した言葉と言い出したのは清儒で、安易に論語に適用すべきではない。
金文の字形は「者」だけで”さまざまな”の意がある。「者」も春秋時代までにその用例がある。詳細は論語語釈「諸」を参照。
往(オウ)


(甲骨文)
論語の本章では”過去”。この語義は原義の”ゆく”の派生義、”行き過ぎたもの”。初出は甲骨文。ただし字形は「㞷」。現行字体の初出は春秋末期の金文。字形は「止」”ゆく”+「王」で、原義は”ゆく”とされる。おそらく上古音で「往」「王」が同音のため、区別のために「止」を付けたとみられる。甲骨文の字形にはけものへんを伴う「狂」の字形があり、「狂」は近音。「狂」は甲骨文では”近づく”の意で用いられた。詳細は論語語釈「往」を参照。
知(チ)


(甲骨文)
論語の本章では”知る”。現行書体の初出は春秋早期の金文。春秋時代までは「智」と区別せず書かれた。甲骨文で「知」・「智」に比定されている字形には複数の種類があり、原義は”誓う”。春秋末期までに、”知る”を意味した。”知者”・”管掌する”の用例は、戦国時時代から。詳細は論語語釈「知」を参照。
來(ライ)
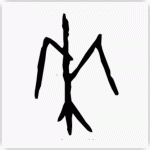

(甲骨文)
論語の本章では”未来”。この語義は”来る”の派生義で、”来たるべきもの”。初出は甲骨文。新字体は「来」。原義は穂がたれて実った”小麦”。西方から伝わった作物だという事で、甲骨文の時代から、小麦を意味すると同時に”来る”も意味した。詳細は論語語釈「来」を参照。
吿諸往而知來者也
直訳すると”過去を告げれば、未来を知る者である”。
唐突の感があって文脈を繋ぎにくく、従来訳のように苦しい訳をせざるを得ないようだ。ここでは過去=子貢が引用した『詩経』の古いうたにある修行、未来=子貢が目指すべき、『詩経』がうたい、また顔回が実践したあるべき君子の姿、と解した。
論語:付記
検証
論語の本章は、前半は『史記』に再録されるまで誰も引用していない。
引用した詩の部分は、戦国末期の荀子が引用しているので、それまでには作られたのだろう。それ以降の部分は、先秦両漢の誰一人引用していない。「貧」のような、「貝」を含んだ漢字は財産と関わりがあるとされるが、論語の時代でもそう言えるかには疑問がある。
以上から本章は、戦国時代の創作と思われる。
解説
中国は一度の例外を除いて、海洋国家だったことがないし、貝は取って食うものだった。

明・鄭和艦隊の「宝船」© Kosov vladimir 09071967
論語の本章では、「貧」の置換候補として「勻」を挙げうるが、実は両者は声調こそ同じ平声だが、個別のカールグレン上古音に共通するのはi̯とnだけで、共通率は40%でしかない。こういう判断は50%を超えないと、「共通している」と談じるのが訳者当人すら図々しく思う。
| 貧 | bʰ | i̯ | ə | n | |
| 勻 | ɡ | i̯ | w | ĕ | n |
ナニ訳者は不逞の輩さ、と開き直る根性は無いから、少し言い訳を書いておこう。
この「貧」に「貝」が入っていることから、漢字の「貝」をタカラガイと解し、古代では貨幣の役割を果たしたと通説は言う。だが訳者は中国貨幣史を専門としないものの、管見の限り孔子の生前、貨幣が存在した話を聞かない。専門家の説明も、極めて歯切れがよろしくない。
「春秋戦国時代」と両時代をひとまとめにして論じても、貨幣史としては立派に通用するのだろうが、論語を読む者には困るのである。孔子の時代、すでに金属のコインがあったオリエントやギリシア、古代インド十六大国と比べて、中国の貨幣経済は心細い。
これは旧大陸の古代文明の中で、他の文明は海によって繋がれて、盛んに他文明圏と交渉を持ったのに対し、古代中華文明は他文明に対して日本人以上の引き籠もりで、沿岸航海はしただろうが、他の文明圏まで出掛けていって商売をした、という話が全く聞こえてこない。
中国のカミサマはギリシアの同業のように、アルゴー船で乗り出したりしないのである。
ただ分かっているのは、西周早期の青銅器「利簋」に、「易又吏利金」とあり(→銘文)、王の側近だった利という人物に、「金」(春秋時代までは青銅、銅とスズの合金を意味する)を与えた、とある。地殻中に銅は質量で約0.005%しかなく、スズは約0.00022%しかない。
鉄が約4%あると言えば、その貴重さが分かるだろうか。だが仮に青銅が貴重であり、通貨「のように」用いられたとしても、それを「貨幣」と言ってよいかどうか。重量や品位を保証するなにがしかの規格と権威が無ければ、貨幣と呼ぶのをためらうしかない。
『史記』によれば、孔子も俸給を穀物で受け取った。おそらく現物支給ではなく、なにがしかの証文のようなものを与えられたと思うが、紙もない時代、木や竹の証文が当時あったとして、現在では全て腐り果ててしまい、ただの一例も出土例を聞かない。
次に論語の本章は、論語学而篇のうち、唯一定州竹簡論語が現存している章で、定州竹簡論語は、現代の発掘前にすでに盗掘による焼損に遭い、発掘後は研究所に紅衛兵が暴れ込んで、滅茶苦茶に壊してしまった。学而篇は論語の第一巻だから、一番破損しやすかったのだろう。
仕舞うにも箱などの一番手前に置いただろうから、墓泥棒が薪代わりに焼いてしまうにも、手に取りやすかったと思われる。結果として学而篇は、定州竹簡論語の簡1号のみが残った。1枚のみと言う数の少なさの偶然が、紅衛兵の愚かしい所業から免れさせたと思われる。
現物の写真などは公開されていないので、横書きにして図示すれば次の通り。
…部分は、欠損を含む解読不能部分で、何か字が書いてあったのか、もはや知ることが出来ない。簡1枚には19-21字が記されていたと言うから、残った19字だけでも1枚を構成しうるが、「…」の記入は簡を綴る部分の欠損を意味し、前後いずれかに字があったことになる。
元の簡の模様については、わずかに版本の表紙に描かれた画像のみ。反時計回りで示す。

恐らく論語雍也篇、「子曰雍也可使南面也…」の部分と思われる。
論語の本章、新古の注は次の通り。
古注『論語集解義疏』
子貢問曰貧而無諂富而無驕何如子曰可也註孔安國曰未足多也未若貧而樂道富而好禮者也註鄭𤣥曰樂謂志於道不以貧賤為憂苦也子貢曰詩云如切如磋如琢如磨其斯之謂與也註孔安國曰能貧而樂道富而好禮者能自切磋琢磨者也子曰賜也始可與言詩已矣告諸往而知來者也註孔安國曰諸之也子貢知引時以成孔子義善取類故然之往告之以貧而樂道來荅以切磋琢磨者也
本文「子貢問曰貧而無諂富而無驕何如子曰可也」。
注釈。孔安国「まだそれでは十分とは言えない、と言ったのである。」
本文「未若貧而樂道富而好禮者也」。
注釈。鄭玄「楽とは儒学に志して、貧乏を気にしないのを言う。」
本文「子貢曰詩云如切如磋如琢如磨其斯之謂與也」。
注釈。孔安国「貧乏でも儒学を学ぶのを好み富んでも礼儀作法を好む者は、自分で自分を高められるのである。」
本文「子曰賜也始可與言詩已矣告諸往而知來者也」。
注釈。孔安国「諸とは”これ”の意である。子貢は詩を引用して孔子の説いた意義を表現した。よく意味をくみ取った引用をしたので、孔子は子貢を肯定した。孔子はすでに”貧しくても楽しむ”ことを説いたのだが、子貢は”切磋琢磨”で説教を理解したことを示した。
新注『論語集注』
子貢曰:「貧而無諂,富而無驕,何如?」子曰:「可也。未若貧而樂,富而好禮者也。」樂,音洛。好,去聲。諂,卑屈也。驕,矜肆也。常人溺於貧富之中,而不知所以自守,故必有二者之病。無諂無驕,則知自守矣,而未能超乎貧富之外也。凡曰可者,僅可而有所未盡之辭也。樂則心廣體胖而忘其貧,好禮則安處善,樂循理,亦不自知其富矣。子貢貨殖,蓋先貧後富,而嘗用力於自守者,故以此為問。而夫子答之如此,蓋許其所已能,而勉其所未至也。子貢曰:「詩云:『如切如磋,如琢如磨。』其斯之謂與?」磋,七多反。與,平聲。詩衛風淇澳之篇,言治骨角者,既切之而復磋之;治玉石者,既琢之而復磨之;治之已精,而益求其精也。子貢自以無諂無驕為至矣,聞夫子之言,又知義理之無窮,雖有得焉,而未可遽自足也,故引是詩以明之。子曰:「賜也,始可與言詩已矣!告諸往而知來者。」往者,其所已言者。來者,其所未言者。愚按:此章問答,其淺深高下,固不待辨說而明矣。然不切則磋無所施,不琢則磨無所措。故學者雖不可安於小成,而不求造道之極致;亦不可騖於虛遠,而不察切己之實病也。
本文「子貢曰:貧而無諂,富而無驕,何如?子曰:可也。未若貧而樂,富而好禮者也。」
楽の音は洛である。好の字は尻下がりに読む。諂とは卑屈になることである。驕とはおごり高ぶることである。
常人は富に溺れてしまい、自分を守る術を知らない。だから貧乏しても富んでも二種の憂いがある。卑屈にも傲慢にもならない、これが自分を守る事である。だが貧富そのものを超越したとは言えない。ただ、まずはよろしいと言えるのは、せいぜい貧富に踊らされて極端なことを言わないことである。
本当の楽とは、心も体もおおらかに広々として、貧乏が気にならないことだ。礼を好むとは、善事を行うことだけで満足することで、ものの道理がその通りであることを楽しみ、自分がどんなにすごいことを知っているか自覚しないことである。
子貢は金儲けに精を出し、たぶんそれ以前は貧乏で、ようよう金持ちになったのだろう。だから以前は意識的に自分を守る必要があったから、このような問いをした。そして孔子先生がこのように答えたのは、子貢のいくぶんかの成長を評価しつつも、まだ努力して身につけるべき境地があったからだろう。
本文「子貢曰:詩云:『如切如磋,如琢如磨。』其斯之謂與?」
磋の字は、七-多の反切で読む。與は平らな調子で読む。『詩経』衛風の淇澳之篇の引用である。骨や角を加工して、既に磨き上げたのを磋という。玉や石を加工して、すでに磨き上げたのを磨という。美しい部分だけを削り出して、さらに美しく磨くことである。子貢は自分を金持ちでも威張らないと評価していたが、先生の説教を聞いて、究極の境地とそのことわりが極まりないのを知り、学ぶことは出来るだろうが、まだその境地は遠いだろうと考えた。だから詩を引用して思ったところを表した。
本文「子曰:賜也,始可與言詩已矣!告諸往而知來者。」
往とは、すでに語ったことを指す。来とは、まだ言っていないことを指す。愚かな私・朱子が考えるに、本章の問答は、話の程度については説明の必要は無いほど明らかだ。だが切らなければ摺ることは出来ず、余計な部分を欠き落とさねば磨くことは出来ない。だから儒学を学ぶ者は僅かばかりの理解で満足してはならないが、奥義を超えて勝手なことを言ってはならない。さらに意味の無い空理空論を追い求め、却って自分をダメにすることがあってはならない。
余話
天気晴朗ナレドモ波高シ
明治中期、日本を脅かした清国の北洋水師(艦隊)は、その名の通りもとは北洋・南洋の二個艦隊の一つだった。既に清朝の地方政治はボス政治になっており、シナ海沿岸を南北に分け、それぞれに大臣を置いて海防と外交と通商を担当させた。

北洋水師旗艦・戦艦「定遠」
南洋水師が清仏戦争で壊滅すると、清国海軍は事実上北洋水師だけとなったが、ドイツ製の戦艦二隻を揃え、日本周辺をうろつき回って日本人を怯えさせ、長崎に寄港した際には水兵が乱暴を働いたりした。これに激高した日本世論が、食うものも食わずに軍艦を買いそろえた。
この事件については某中国のサイトに、時代考証がデタラメの上に中国人の方が被害者であるかのようなちん画が載っているが、後先考えずに乱暴を働けば、何人だろうと怒り出す道理が中国政府には通じない。役人個人さえ儲かれば、自国が滅んでも関係ないからだ。
ここが帝政など権威的官僚支配を行う国の弱点と言うべきで、日本も昭和の前半には、軍人だけでない文武の役人がこぞって内外で乱暴を働き、壊滅的な敗戦を招いた。だからあまりよそ様のことを悪く言えないのだが、現代の中国の横暴は、同様の理屈で理解してしまえる。
対して明治中期の日本は三笠などの戦艦はまだ国産出来ず、輸入品は「貧しくして」買えず、戦艦並みの主砲を無理やり小船に取り付けて防護巡洋艦と称した。これが三景艦と呼ばれる松島型で、実戦では主砲は役立たずに終わったが北洋水師をほぼ全滅させた。
西太后が北洋大臣の李鴻章から金を召し上げて、その結果戦艦の主砲に弾が三発しか用意されていなかったとも言われる。これは現在にも通じる中国のやり口で、大人しく振る舞っていると居丈高に乱暴を働くが、相手が本気で怒るとびっくりして負けてしまうのである。
抜刀納刀を稽古したことがない者には、刀の恐ろしさが分からない。抜けても収めるときに、指を落として終わる。埋まった土砂崩れから浮き逃げた後、初めて人は水と土の恐ろしさを知る。火の恐ろしさすら、慌てふためき辛くも命が助かってやっと、訳者は思い知った。

(→youtube)
これはロシアも同様で、ニコライ二世は日本を馬鹿にしながら戦争が起きるとは思っていなかったとも言われる。だから開戦が決まるとロシア海軍の当局者は困惑し、バルチック艦隊を率いたロジェストウェンスキーは、”勝てる見込みがない”と正直な手紙を妻に送っている。
ロシア帝国とその海軍が、開戦前に日本をなめていたことは、バルチック艦隊の名前からも分かる。旅順でロシアの太平洋艦隊(![]() B
B ![]()
![]() )が壊滅し、増援のバルチック艦隊は「第二太平洋艦隊」(とネボガトフの第三艦隊)が正式名称と日本で思われている。
)が壊滅し、増援のバルチック艦隊は「第二太平洋艦隊」(とネボガトフの第三艦隊)が正式名称と日本で思われている。
だが厳密には正しくない。「第二太平洋艦隊」の原語は![]()
![]()
![]() 。
。
語順通りに直訳すれば”第二太平洋戦隊”。最新鋭のボロジノ型戦艦を4隻も連ねた大部隊を、ロシア帝国は「艦隊」ではなく一級下がった「戦隊」と見ていた。日本の第一・第二「連合艦隊」に対して、「戦隊」一つをあてがえば十分、と思っていたのである。
だから東郷平八郎が大将だったのに、ロジェストウェンスキーは中将でしかなかった。ロシアだけの事情ではない。おごれる平家は久しくない。アメリカ太平洋艦隊を襲うのに、昭和の帝国海軍は南雲忠一「中将」を司令官とし、山本五十六は本国で愛人と砂糖饅頭を食っていた。
ロシア艦隊の敗北原因を、遠征の困難に求めるのは当然だが、各艦の能力も低かった。戦艦の数は日本艦隊の倍だと司馬遼太郎は書いたが、ロシア戦艦の半ばは波の静かなバルト海専用の浮き砲台に近く、それが日本近海の荒波に翻弄され、何とか沈まないでいたのが実情だった。
以下の動画は訳者も何度かお世話になった大好きな「かめ丸」の例。
引退してしまった彼女だが、深夜に竹橋を出港する「かめ丸」の、メシのうまかったこと。
司馬の小説を動画にしたNHKの芸が細かいと思ったのは、米西戦争観戦中の各国海軍士官の制服を、多分それぞれの本国で作らせたことで、ロシア士官の白い詰め襟は、どう見ても他国より仕立てが悪かった。そしてロシア帝国は敗北し、三国干渉で得た旅順と大連を失った。
だがロシア人の遼東半島に対する執念は深かったらしく、二次大戦で日本が負けると、満洲に押し込んだついでに旅順と大連に居座った。三国干渉直後の状態に戻せというのである。もちろん中国人は怒ったが、しつこく交渉して1950年、やっとソ連軍に帰って貰った。
だがその後も、![]()
![]() “不凍港”の遼東半島を諦める気は無いようである。
“不凍港”の遼東半島を諦める気は無いようである。

ソ連海軍の長距離航海徽章に3a ![]()
![]() とあるのは”長い航海により”と訳されるが、ロシア人が聞けば容易に3a
とあるのは”長い航海により”と訳されるが、ロシア人が聞けば容易に3a ![]()
![]() ”大連から外へ進撃”を連想するはず。このモットーは現在のロシア連邦海軍太平洋艦隊でも変更がないらしい(wikipediaロシア語版)。
”大連から外へ進撃”を連想するはず。このモットーは現在のロシア連邦海軍太平洋艦隊でも変更がないらしい(wikipediaロシア語版)。
ロシア語版wikipediaの大連条には、「1945年にソ連軍が解放した」と書いた後で、”1950年に無償でソ連政府から中国に寄贈した”と書いてある。原語は大人の事情によりここに記せないが、要するに呉れてやったと言っているわけ。
閲覧者諸賢にお察し頂きたいが、中露関係は今でもこんなものだ。


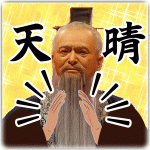



コメント