論語:原文・書き下し
原文(唐開成石経)
子曰君子不重則不威學則不固主忠信無友不如己者過則勿憚改
※後半は論語子罕篇25と重複。
校訂
諸本
東洋文庫蔵清家本
子曰君子不重則不威學則不固/主忠信無友不如己者過則勿憚改
※前章から区分無しで続けて記されている。「友」字は〔友丶〕、「魏寇憑墓志」刻。
後漢熹平石経
…君子不重則不威學則…
定州竹簡論語
(なし)
※後半が重複している論語子罕篇25も、簡が存在しない。
標点文
子曰、「君子不重則不威。學則不固。主忠信、無友不如己者。過則勿憚改。」
復元白文(論語時代での表記)













 忠
忠








 憚
憚
書き下し
子曰く、君子重から不らば則ち威なら不。學ばば則ち固なら不。忠と信を主り、己に如か不る者を友ふ無かれ。過たば則ち改むるを憚る勿れ。
論語:現代日本語訳
逐語訳

先生が言った。「教養ある人格者は荘重でないと威厳が無い。学ぶから頭が固くならない。自分と他人を偽らないようにせよ。自分より劣りの者を友にするな。間違えたら改めるのを誤魔化すな。」
意訳

塾生活心得五箇条。
- いつも偉そうにしてろ。
- 頭を固くするな。
- 他人に奉仕して信頼を得ろ。
- 馬鹿と付き合うな。
- 間違いを素直に認めろ。
従来訳
先師がいわれた。――
「道に志す人は、常に言語動作を慎重にしなければならない。でないと、外見が軽っぽく見えるだけでなく、学ぶこともしっかり身につかない。むろん、忠実と信義とを第一義として一切の言動を貫くべきだ。安易に自分より知徳の劣った人と交っていい気になるのは禁物である。人間だから過失はあるだろうが、大事なのは、その過失を即座に勇敢に改めることだ。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
孔子說:「君子不穩重就不會有威嚴,經常學習就不會固執,一切要以忠信為本,不要結交不如自己的朋友,有錯誤不要怕改正。」
孔子が言った。「君子は重々しくないと全く威厳を持てない。常に学び続けると全く頭が固くならない。全てはまごころと信頼で行うのを基本とせねばならない。自分より劣りの友人と付き合ってはならない。間違えたら改めるのを恐れてはならない。」
論語:語釈
子曰(シエツ)(し、いわく)

論語の本章では”孔子先生が言った”。「子」は貴族や知識人に対する敬称で、論語では多くの場合孔子を指す。「子」は赤ん坊の象形、「曰」は口から息が出て来るさま。「子」も「曰」も、共に初出は甲骨文。辞書的には論語語釈「子」・論語語釈「曰」を参照。
この二文字を、「し、のたまわく」と読み下す例がある。「言う」→「のたまう」の敬語化だが、漢語の「曰」に敬語の要素は無い。古来、論語業者が世間からお金をむしるためのハッタリで、現在の論語読者が従うべき理由はないだろう。
君子(クンシ)
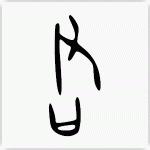

(甲骨文)
論語の本章では「よきひと」と訓読して”教養と身分のある者”。孔子存命中は単に「もののふ」”貴族”を意味するだけだったが、孔子没後一世紀に生まれた孟子が語義を書き換えた。詳細は論語における「君子」を参照。論語学而篇1とは語釈が異なるが、日本語の「ひと」がhumanと他人と異性とさらにその他を意味するように、古典の語釈はそのたびごとに慎重に行わなければならない。
「君子」は共に初出は甲骨文。「君」の原義は人と神を取り持つ神官。「子」は生まれたての赤ん坊で、とりわけ王子を指す。論語語釈「君」・論語語釈「子」を参照。
不(フウ)


(甲骨文)
漢文で最も多用される否定辞。初出は甲骨文。原義は花のがく。否定辞に用いるのは音を借りた派生義。詳細は論語語釈「不」を参照。現代中国語では主に「没」(méi)が使われる。
『学研漢和大字典』によると「弗(フツ)(払いのけ拒否する)とも通じる」とあり、『大漢和辞典』の第二義に「なかれ。禁止の辞」とある。
重(チョウ)
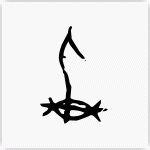
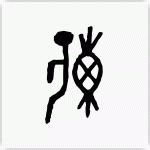
(甲骨文・金文)
論語の本章では”重々しい”。初出は甲骨文。「ジュウ」は呉音(遣隋使より前に日本に伝わった音)。字形は「人」+「東」”ふくろ”で、金文の字形では、ふくろを背負う姿になっているものがある。原義は不詳。明確に”重い”・”重さ”の意が確認できるのは、戦国時代以降になる。詳細は論語語釈「重」を参照。
則(ソク)


(甲骨文)
論語の本章では、「A則B」で”AはBである”。初出は甲骨文。字形は「鼎」”三本脚の青銅器”と「人」の組み合わせで、大きな青銅器の銘文に人が恐れ入るさま。原義は”法律”。論語の時代=金文の時代までに、”法”・”則る”・”刻む”の意と、「すなわち」と読む接続詞の用法が見える。詳細は論語語釈「則」を参照。
「すなわち」と訓む一連の漢字については、漢文読解メモ「すなわち」を参照。
威(イ)


(金文)
論語の本章では”おごそかな”。初出は西周中期の金文。字形は「戈」+「女」で、西周中期の金文の時代に、「威儀」と記され、すでに”いかめしくする”の語義があった。詳細は論語語釈「威」を参照。
學(カク)


(甲骨文)
論語の本章では”学ぶ”。「ガク」は呉音。初出は甲骨文。新字体は「学」。原義は”学ぶ”。座学と実技を問わない。上部は「爻」”算木”を両手で操る姿。「爻」は計算にも占いにも用いられる。甲骨文は下部の「子」を欠き、金文より加わる。詳細は論語語釈「学」を参照。
固(コ)


(金文)
論語の本章では”頑固になる”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は春秋時代の金文。字形は「囗」+「十」+「曰」だが、由来と意味するところは不明。部品で同音の「古」が、「固」の原字とされるが、春秋末期までに”かたい”の用例がない。詳細は論語語釈「固」を参照。
主(シュ)


(甲骨文)
論語の本章では”まもる”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。字形は位牌の形で、原義は”位牌”。金文の時代では氏名や氏族名に用いられるようになったが、自然界の”ぬし”や、”あるじとする”の語義は戦国初期になるまで確認できない。詳細は論語語釈「主」を参照。
本章では動詞として読むしかないが、”あるじとする”の派生義”まもる”と解した。『大漢和辞典』に語釈があり、出典は三国時代の辞典『広雅』。
忠(チュウ)

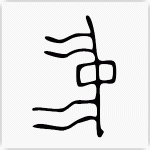
「忠」(金文)/「中」(甲骨文)
論語の本章では”忠実”。初出は戦国末期の金文。ほかに戦国時代の竹簡が見られる。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補もない。字形は「中」+「心」で、「中」に”旗印”の語義があり、一説に原義は上級者の命令に従うこと=”忠実”。ただし『墨子』・『孟子』など、戦国時代以降の文献で、”自分を偽らない”と解すべき例が複数あり、それらが後世の改竄なのか、当時の語義なのかは判然としない。「忠」が戦国時代になって現れた理由は、諸侯国の戦争が激烈になり、領民に「忠義」をすり込まないと生き残れなくなったため。詳細は論語語釈「忠」を参照。
信(シン)
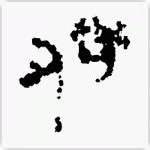

(金文)
論語の本章では、”他人を欺かないこと”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は西周末期の金文。字形は「人」+「口」で、原義は”人の言葉”だったと思われる。西周末期までは人名に用い、春秋時代の出土が無い。”信じる”・”信頼(を得る)”など「信用」系統の語義は、戦国の竹簡からで、同音の漢字にも、論語の時代までの「信」にも確認出来ない。詳細は論語語釈「信」を参照。
無(ブ)→毋(ブ)


(甲骨文)
論語の本章では”するな”。初出は甲骨文。「ム」は呉音。甲骨文の字形は、ほうきのような飾りを両手に持って舞う姿で、「舞」の原字。その飾を「某」と呼び、「某」の語義が”…でない”だったので、「無」は”ない”を意味するようになった。論語の時代までに、”雨乞い”・”ない”の語義が確認されている。戦国時代以降は、”ない”は多く”毋”と書かれた。詳細は論語語釈「無」を参照。


(金文)
『経典釋文』の「毋」の、現行書体の初出は戦国文字で、無と同音。春秋時代以前は「母」と書き分けられておらず、「母」の初出は甲骨文。「毋」と「母」の古代音は、頭のmが共通しているだけで似ても似付かないが、「母」məɡ(上)には、”暗い”の語義が甲骨文からあった。詳細は論語語釈「毋」を参照。
古注では「無」と記しており、こちらがより古形と言える。

鵜飼文庫『論語義疏』
友(ユウ)
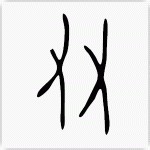

(甲骨文)
論語の本章では”友人”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は複数人が腕を突き出したさまで、原義はおそらく”共同する”。論語の時代までに、”友人”・”友好”の用例がある。詳細は論語語釈「友」を参照。
如(ジョ)
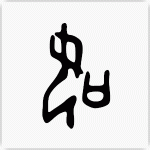

(甲骨文)
論語の本章では”~のようである”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「女」+「𠙵」”くち”で、”ゆく”の意と解されている。春秋末期までの金文には、「女」で「如」を示した例しか無く、語義も”ゆく”と解されている。詳細は論語語釈「如」を参照。
者(シャ)


(金文)
論語の本章では”そういう者”。旧字体は〔耂〕と〔日〕の間に〔丶〕一画を伴う。新字体は「者」。ただし唐石経・清家本ともに新字体と同じく「者」と記す。現存最古の論語本である定州竹簡論語も「者」と釈文(これこれの字であると断定すること)している。初出は殷代末期の金文。金文の字形は「木」”植物”+「水」+「口」で、”この植物に水をやれ”と言うことだろうか。原義は不明。初出では称号に用いている。春秋時代までに「諸」と同様”さまざまな”、”~する者”・”~は”の意に用いた。漢文では人に限らず事物にも用いる。詳細は論語語釈「者」を参照。
過(カ)
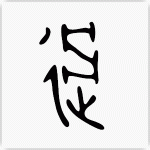

(金文)
論語の本章では”あやまちをおかす”。この語義は春秋時代では確認できない。初出は西周早期の金文。字形は「彳」”みち”+「止」”あし”+「冎」”ほね”で、字形の意味や原義は不明。春秋末期までの用例は全て人名や氏族名で、動詞や形容詞の用法は戦国時代以降に確認できる。詳細は論語語釈「過」を参照。
勿(ブツ)


(甲骨文)
論語の本章では”~するな”。初出は甲骨文。金文の字形は「三」+「刀」で、もの切り分けるさまと解せるが、その用例を確認できない。甲骨文から”無い”を意味し、西周の金文から”するな”の語義が確認できる。詳細は論語語釈「勿」を参照。
憚(タン)


(金文・篆書)
論語の本章では”いやがり、苦しむこと”。『大漢和辞典』の第一義は”はばかる”。論語では本章と、重出の子罕篇25にしか見られない。初出は戦国末期の金文。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補も無い。字形は單(単)+「心」。「単」の原義は”武器”とも”うちわ”とも言い、諸説あって明瞭でない。詳細は論語語釈「憚」を参照。
改
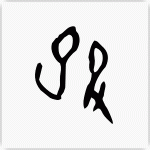

(甲骨文)
論語の本章では”あらためる”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は「巳」”へび”+「攴」”叩く”。蛇を叩くさまだが、甲骨文から”改める”の意だと解釈されており、なぜそのような語釈になったのか明らかでない。詳細は論語語釈「改」を参照。
論語:付記
検証
論語の本章は、戦国時代前半の『孟子』に「古之君子、過則改之。今之君子、過則順之。」とある以外、誰も引用していない。古注にはあるから、後漢時代にあっただろうが、定州竹簡論語に無く、重複している論語子罕篇25も、簡が存在しない。
古注『論語集解義疏』
子曰君子不重則不威學則不固註孔安國曰固蔽也一曰言人不敢重既無威學不能堅固識其義理也主忠信無友不如已者過則勿憚改註鄭𤣥曰主親也憚難也
本文。「子曰君子不重則不威學則不固」。注釈。孔安国「固とは隠し覆うことである。一説には、人格に重々しさが無いように務めれば、威厳が無く学問が堅固になれないが、ものの道理は分かる、という。
本文。「主忠信無友不如已者過則勿憚改」。
注釈。鄭玄「主とは親しむことである。憚は難しいと思うことである。」
前漢ごろ成立の『孔子家語』に引用があるが、いつ書き加えられたか不明。
孔子之舊曰原壤,其母死,夫子將助之以木槨。子路曰:「由也昔者聞諸夫子,無友不如己者,過則勿憚改。夫子憚矣。姑已,若何?」

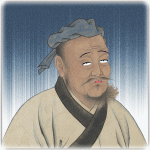
孔子の旧友に原壌という者がおり、その母親が亡くなった。先生は外棺を作るのを手伝いに行こうとした。すると子路が言った。
「先生は以前おっしゃいましたね、自分より程度の低い者と付き合うな。間違ったら改めるのをためらうな、と。ところが先生はダラダラと、あの下らない原壌と付き合ったまま改めようとしない。行くのをやめたらどうですか。」(『孔子家語』屈節解4)
原壌は、論語憲問篇46に名が見える。
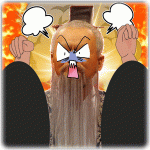
幼なじみの原壤の奴が「うちに来い」と言うので行ってやったら、あやつめ、あぐらをかいて出迎えよった。頭に来たので説教してやった。「ガキの頃からワル坊主で、大きくなってもろくな事をしてこなかった。今ジジイになっても図々しく生きていやがる。お前みたいなのを、穀潰しと言うんだ!」スネを二三回引っ叩いてやった。
おそらく本章は、それまでのことわざを綴って、漢儒が創作したと思われる。
解説
論語の本章について、孔子がこんな事を言うとは思えない。「態度を作れ」は「巧言令色」(論語学而篇3)と矛盾し、「付き合うな」は「有朋遠方来」(論語学而篇1)と矛盾する。孔子が年齢も身分も出身国も違う弟子をまとめるのに、差別を奨励しては学級崩壊が起こる。

まして孔子一門は単なる本の虫の集まりではなく革命政党でもあり、戦時の出陣に備え武芸も必須科目に入っているから、一度仲間割れが起これば血の雨が降る。それに孔子存命中、一門の結束がゆるんだ記録は見あたらない。分派が出来たのは、孔子没後のことだ。
孔子が塾内の雰囲気をよく保つために、いかに心を砕いたかは、例えば下記論語先進篇14にも見える。劣りを理由にからかいたがるのは若者の常だが、孔子は事の発端が自分であっても、塾内にいじめの兆しを見ると、すぐさま火消しにかかる教師として描かれた。

子路「♪ジャジャジャーン!」
孔子「子路や、お前の琴にはうんざりするな。いっそよそで弾いてくれんか。ウチで弾かれると恥になる。」
弟弟子「子路さんってボンクラだよねー。」「ねー。」
孔子「こりゃお前達。子路は基礎は出来ておるんだ。奥義を知らないだけだぞ。」
ただし残念ながら、この論語先進篇の記述は史実ではない。だが顔淵を上席の弟子として遇した理由の一つは、顔淵が入門してから、塾内の雰囲気を和ませたことにある(「われ回をえてより後、門人ますます親しむ」『史記』仲尼弟子列伝)。これはいかに弟子同士の悪感情を取り除くかに、孔子が腐心したかの表れでもある。
藤堂博士はこうした孔子塾のけしきを、次のように述べている。
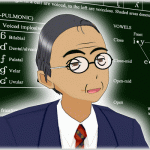
孔子は〔論語子罕篇12〕のように、召使いとか臣下とかいう古い身分制度を、頭から否定して、人と人との対等の人間関係をめざした。「弟子」とは、今までになかった対人関係である。先輩と後輩とが、弟の如く、子の如く向かい合う関係である。学園とはそういうものだ。「朋あり、遠方より来たる、また楽しからずや。」とあるように、両者はつまり朋友の関係にほかならない。(『漢文入門』論語のこころ)
余話
本当の差別
処世訓としては”馬鹿と関わるな”は正しいだろうが、そもそも人が集まれば個別の能力に優劣が出るのは当たり前で、いちいち見下していては集団生活が成り立たない。それは孔子も心得ていて、心得ていなかったのは後世の威張り返った儒者だ。二つの証拠を挙げよう。
孔子將行,雨而無蓋。門人曰:「商也有之。」孔子曰:「商之為人也,甚恡於財。吾聞與人交,推其長者,違其短者,故能久也。」

孔子が出掛けようとすると、雨が降り出したが傘が無い。門人が「子夏の傘を借りては」と言うと、孔子は言った。「子夏は物惜しみする性格だ。やめておこう。ほれ、世間でも言うだろう、人と付き合うには長所だけに目をとめ、短所には目をつぶるものだ、だから付き合いが長続きする、と。」(『孔子家語』致思15)
有鬻乾柿者。一士見之。連取食二杖。又欲舉手。鬻柿者慍曰。相公各要尊重。士復取一杖。且行且頋曰。你不知。此物甚能清肺。

乾し柿売りが店を開いていると儒者がやって来て、勝手に二つを取って食い、食い終わってまだ取ろうとする。柿売りが怒って、「旦那、恥を知りなさい」と言うと、儒者はまた一つ取って食いながら、すたすたと行ってしまう。振り返って言うことには、「お前ごときには分かるまいが、これはとても肺を清める(頭が良くなる)ものなのだ。」(『笑府』巻十二・柿)
『家語』の王粛偽作説は清儒の偽証。『笑府』が書かれたのは明代(1368-1644)の末で、論語の本章の成立がそこまで下がるわけはないが、孔子が”劣りとも付き合っていた”こと、後世の儒者が無意識に、学のない者を差別している事が見て取れる。
これは現代の学歴差別にも見られる事で、自分の学歴を鼻に掛けて、無意識に人を憤慨させる愚かな者は珍しくない。勝手にひがむ者もいるにはいるが、ひがみ者が意識的にひがむのに対し、差別する者は自分が相手を人間扱いしていないことに、全く気が付かない。

これが本当の差別だ。こうした差別を儒教に持ち込んだのは戦国時代の荀子だが、孔子にはそのような無意味なことをしている余裕は無かった。その志望が差別の撤廃だったからだ。春秋時代の身分差別を乗り越えて、弟子を貴族に押し上げる。それが孔子塾だった。





コメント
漢文については全くの素人の者です。「無友不如己者」の部分を、単純に「友の己に如かざる者無し」と解釈する可能性を思いついたのですが、どう思われますか。つまり、「学友の中に自分よりも劣っている者はいない(という心構えで謙虚に学友から学べ)」という意味です。無茶な解釈でしょうか。
解の一つとしてあり得ます。ただ文脈から考えますと、前句とつなげて「忠信を主(まも)らば、友の己に如か不る者無し」(自他共にウソをつかなければ、自分と対等でない学友はいない)、だから間違いはすぐに改めなさい、と読むのがよいと考えます。