論語:原文・白文・書き下し
原文・白文
(前回より続く)
問於桀溺、桀溺曰、「子爲誰。」曰、「爲仲由。」曰、「是魯孔丘*之徒與。」對曰、「然。」曰、「滔滔*者、天下皆是也、而誰以易之。且而與其從辟人之士*、豈若從辟世之士哉。」耰*而不輟。
(次回に続く)
校訂
武内本
釋文孔丘孔子に作る。滔滔、史記世家及び鄭本悠悠に作る。蓋し古論は悠悠、魯論は滔滔に作る。悠悠は周流の貌、滔滔も同じ意。唐石経士下也の字あり。釋文及び漢石経耰を櫌に作る。
後漢熹平石経
…若從避丗之士㦲櫌而不輟
- 「從」字:〔丶丿䒑乙〕
定州竹簡論語
……[輟]。子路以告。子撫然曰:」鳥獸不可與同群,吾559
復元白文(論語時代での表記)























































 耰
耰
 輟
輟
※桀→(秦系戦国文字)・豈→其。論語の本章は赤字が論語の時代に存在しない。「之」「以」「易」の用法に疑問がある。少なくとも本章の文末の付け足しは、漢帝国の儒者による付け足しである。
書き下し
桀溺於問ふ。桀溺曰く、子は誰と爲す。曰く、仲由と爲す。曰く、是れ魯の孔丘之徒與。對へて曰く、然り。曰く、滔滔たる者、天下皆是也、而して誰か以て之を易へむ。且つ而其の人を辟する之士に從はむ與り、豈世を辟くる之士に從ふに若かむ哉と。櫌し而輟めず。
論語:現代日本語訳
逐語訳
(子路が)桀溺に問うた。桀溺が言った。「あなたは誰だというのか。」(子路が)言った。「仲由です。」(桀溺が)言った。「これは魯の孔丘の弟子か。」(子路が)答えて言った。「そうです。」(桀溺が)言った。「とうとうと流れ行く。天下は全てそうだ。それなのに誰がその流れを変えるか。その上あなたが人の悪を言い立てる人に従うことが、どうして世を遠ざける人に従うことに及ぶのか。」土をかぶせて(仕事を)やめなかった。
意訳
子路が桀溺に渡し場を聞いた。
桀溺「ご貴殿はどなたでござる?」
子路「仲由でござる。」
桀溺「あの魯の孔丘の弟子でござるか?」
子路「いかにも。」
桀溺「洪水のように、トウトウと押し流されるのが世の常でござる。一体誰がその流れを止めることが出来ようか。ご貴殿も”世も末じゃ”とばかり言っておる師匠につくより、拙者どものような隠者の仲間入りをした方がいいのではござらぬかな?」
そう言って撒いた種に土をかける手を休めなかった。

従来訳
そこで子路は今度は桀溺にたずねた。すると桀溺がいった。
「お前さんはいったい誰かね。」
子路――
「仲由と申すものです。」
桀溺――
「ほう。すると、魯の孔丘のお弟子じゃな。」
子路――
「そうです。」
桀溺――
「今の世の中は、どうせ泥水の洪水見たようなものじゃ。お前さんの師匠は、いったい誰を力にこの時勢を変えようとなさるのかな。お前さんもお前さんじゃ。そんな人にいつまでもついてまわって、どうなさるおつもりじゃ。この人間もいけない、あの人間もいけないと、人間の選り好みばかりしている人についてまわるよりか、いっそ、さっぱりと世の中に見切りをつけて、のんきな渡世をしている人のまねをして見たら、どうだね。」
桀溺はそういって、まいた種にせっせと土をかぶせ、それっきり見向きもしなかった。下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
子路再問桀溺。桀溺說:「你是誰?「我是仲由。「是魯國孔丘的學生嗎?「是。「壞人壞事象洪水一樣泛濫,誰和你們去改變?你與其跟隨避人的人,哪裏比得上跟隨我們這些避世的人呢?」他邊說邊不停地播種。
子路は桀溺に問い直した。桀溺が言った。「君は誰だ。」「私は仲由だ。」「それは魯国の孔丘の弟子か?」「そうだ。」「人をダメにし、計画をダメにするのは洪水と同じで、溢れた水に押し流されると同じ、誰が君らと共に変えようとするか。君はあの人を避けているような人に従うより、かえって我らのような世を避けるような人に従う方が得をするのではないかな?」彼は言いながら、地に種を撒くのを止めなかった。
論語:語釈
問 於 桀 溺、桀 溺 曰、「子 爲 誰。」曰、「爲 仲 由。」曰、「是 魯 孔 丘 之 徒 與。」對 曰、「然。」曰、「滔 滔 者、天 下 皆 是 也、而 誰 以 易 之。且 而 與 其 從 辟 人 之 士 (也)、豈 若 從 辟 世 之 士 櫌(耰) 而 不 輟。
桀溺(ケツデキ)
論語の本章では人名。詳細は前回の語釈を参照。
子(シ)

(甲骨文)
論語の本章ではあなた”。初出は甲骨文。「子」はもと王の息子を意味し、論語の時代では貴族や教師に対する尊称。桀溺は子路に敬意を払っているのである。辞書的には論語語釈「子」を参照。
仲由


論語の本章では、孔子の弟子、子路の実名。敬称で呼びかけた桀溺に対して、子路はへりくだって自分を名乗っているのである。論語の人物・仲由子路も参照。
孔丘


(金文)
論語の本章では、孔子の姓と実名。子路に対しては敬称で呼びかけたが、その師である孔子に対してはぞんざいに呼んだことになる。現代日本語的に言うなら、”孔子の野郎”。辞書的には論語語釈「孔」・論語語釈「丘」を参照。
之(シ)


(甲骨文)
論語の本章では”…の”・”これ”。初出は甲骨文。字形は”足”+「一」”地面”で、あしを止めたところ。原義はつま先でつ突くような、”まさにこれ”。殷代末期から”ゆく”の語義を持った可能性があり、春秋末期までに”~の”の語義を獲得した。詳細は論語語釈「之」を参照。
滔滔

(古文)
藤堂本によると”ゆらゆらと波立つさま”。
「滔」は論語では本章のみに登場。初出は西周末期の金文。同じく藤堂博士の手による『学研漢和大字典』によると舀(ヨウ)は「爪(手)+臼(うす)」の会意文字で、うすの中を手でこね回すこと。搗(トウ)と同じ。滔は「水+(音符)舀」で、水がいちめんにこねかえすようにいきりたつこと、という。詳細は論語語釈「滔」を参照。
易

(金文)
論語の本章では(世の中の流れを)”変える”。初出は甲骨文。『学研漢和大字典』によると「やもり+彡印(もよう)」の会意文字で、蜥蜴(セキエキ)の蜴の原字。もと、たいらにへばりつくやもりの特色に名づけたことば。また、伝逓の逓(次々に、横に伝わる)にあて、AからBにと、横に、次々とかわっていくのを易という、という。詳細は論語語釈「易」を参照。
伝統的には「おさめる」と読む場合があり、流れを平らかに治める意とするが、いたずらに漢字の語義を増やすことには賛成できない。
而(ジ)


(甲骨文)
論語の本章では”それなのに”・”あなた”・”…しながら”。初出は甲骨文。原義は”あごひげ”とされるが用例が確認できない。甲骨文から”~と”を意味し、金文になると、二人称や”そして”の意に用いた。英語のandに当たるが、「A而B」は、AとBが分かちがたく一体となっている事を意味し、単なる時間の前後や類似を意味しない。詳細は論語語釈「而」を参照。
以(イ)


(甲骨文)
論語の本章では”それで”。初出は甲骨文。人が手に道具を持った象形。原義は”手に持つ”。論語の時代までに、名詞(人名)、動詞”用いる”、接続詞”そして”の語義があったが、前置詞”~で”に用いる例は確認できない。ただしほとんどの前置詞の例は、”用いる”と動詞に解せば春秋時代の不在を回避できる。詳細は論語語釈「以」を参照。
易(エキ/イ)
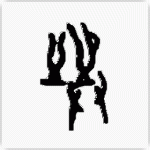
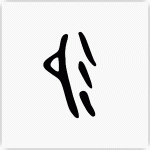
(甲骨文1・2)
論語の本章では、”改める”。初出は甲骨文。甲骨文の字形は、「匜」”水差し”に両手を添え、「皿」=別の容器に注ぐ形で、略体は「盤」”皿”を傾けて液体を注ぐ形。「益」と語源を同じくし、原義は”移し替える”・”増やす”。古代中国では「対飲」と言って、臣下に褒美を取らせるときには、酒を注いで飲ませることがあり、「易」は”賜う”の意となった。戦国時代の竹簡以降に字形が乱れ、トカゲの形に描かれるようになり、現在に至っている。論語の時代までに確認できるのは”賜う”の意だけで、”替える”・”…しやすい”の語義は戦国時代から。漢音は”変える”の場合「エキ」、”…しやすい”の場合「イ」。詳細は論語語釈「易」を参照。
而誰以易之
ここでの「而」は(時世時節は洪水が全てを押し流すような者である、)”それなのに”。
辟
論語の本章では「辟人」で”人を罰する”、「辟世」で”世間から隠れる”。初出は甲骨文。『学研漢和大字典』によると「人+辛(刑罰を加える刃物)+口」の会意文字で、人の処刑を命じ、平伏させる君主をあらわす。また、人体を刃物で引き裂く刑罰をあらわすとも解せられる、という。詳細は論語語釈「辟」を参照。
伝統的には(人を・世を)”避ける”と文中で解を統一していたが、政治いじりやお説教が大好きな孔子が、人を避けたことはないので理屈が通じない。「辟」の原義が”処刑”であり、派生義として”避ける”意があることを、知識人の桀溺はよく知っていたし、「子」と敬称で呼んだ相手の子路が知識人であるからこそ、掛け言葉のように言ってみせたのである。
而與其從辟人之士
ここでの「與」(与)は、「より」と読んで比較を意味する助辞。詳細は論語語釈「与」を参照。
豈
論語の本章では”どうして”。初出は戦国文字で、論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補は「其」。詳細は論語語釈「豈」を参照。
耰(ユウ)→櫌(ユウ)

(古文)
論語の本章では、撒いた種の上に土をかぶせること。「耰」「櫌」ともに論語では本章のみに登場。
「耰」の初出は不明。論語の時代に存在が確認出来ない。同音多数で、論語時代の置換候補は見つからない。
『学研漢和大字典』によると形声文字で、「耒(すき)+(音符)憂」。この字は「耒+(音符)夒(ノウ)(さるがひっかくように表面をならす)」が原字で、擾(ジョウ)(かきまわす)と同系のことばであろう。のち、音符を憂ととり違えてユウと読むようになったもの、という。
漢石経では「櫌」と書くが、正字、または異体字と扱ってよさそうである。詳細は論語語釈「耰」を参照。
輟(テツ)

(古文)
論語の本章では”やめる”こと。初出は説文解字。論語の時代に存在しない。論語時代の置換候補も無い。『学研漢和大字典』によると会意兼形声文字で、「車+(音符)叕(テツ)(次々とつながるつながりが中断する)」。車のつらなる回転が、ふと中断すること、という。詳細は論語語釈「輟」を参照。
論語:付記
文末の「耰而不輟」を除けば、論語の本章のこの部分も、前回同様の史実と見てよさそうである。桀溺も長沮と同様、かつて貴族だったか、または貴族を目指して勉学と稽古に励んだ事のある人物と見てよく、長沮と違い始めから孔子を「孔丘」と呼び捨てにしている。
だが目の前の子路に対しては、「子爲誰」(ご貴殿はどなたでござるか)と貴族にふさわしい言葉遣いで話した。「ワシはそなへんの百姓ではないぞ」という気負いがある。隠者らしくないが、世をすねた者とはそういうものだろう。隠者の修行に段階がいろいろとあるわけだ。
また上記の通り、「辟」の字を掛詞で使っており、自分の教養をあらわにした。おそらくは漢帝国の儒者が書き加えたであろう「耰而不輟」は、そういう意味ではふさわしく、桀溺はまだ隠者として悟りきっていないのを自覚して、言って「しまった」と恥じたのだ。
前回の長沮と同じく、桀溺も隠者としてはまだ駆け出しだろう。聞こえるようなイヤミを言ったり、先の長沮と子路との対話を隣で聞いていながら、「あの孔丘の弟子か」と分かりきったことを聞いている。つまり子路にあれこれ言わせよう、聞かせようとの欲望がある。
人に求めないから、隠者なのだ。孔子は鋭く二人の不出来を見抜いただろう。





コメント