論語:原文・白文・書き下し
原文・白文
周公謂魯公曰、「君子不施*其親、不使大臣怨乎不以。故舊無大故、則不棄*也、無*求備於一人。」
校訂
武内本
釋文施を弛に作る。弛は棄忘也、廢也。唐石経棄を弃に作り、毋を無に作る。
後漢熹平石経
周公謂魯公白君子不施其親…大臣怨…
- 「不」字:〔一八个〕。
- 「其」字:上半分中心に〔丨〕一画あり。
- 「臣」字:〔巨丨〕。
定州竹簡論語
……公謂魯公曰:「君子不施a……使大臣怨乎不572……舊無大故,則弗舍b也。毋c求備於一人!」573
- 不施『釈文』云”’不弛’、本今*作’施’”、漢石經作”施”。
- 舎、今本作”棄”。
- 毋、今本作”無”。
*「本今」→「今本」の誤?
→周公謂魯公曰、「君子不施其親、不使大臣怨乎不以。故舊無大故、則弗舍也、毋求備於一人。」
復元白文(論語時代での表記)



































※施→(甲骨文)・怨→夗。論語の本章は、「則」の用法に疑問がある。
書き下し
周公魯公に謂ひて曰く、君子は其の親に施さ不らば、大じき臣を使て以ゐられ不る乎怨ましめ不。故に舊は大じき故無からば、則ち舍て弗れ也。備はるを一人於求むる毋かれ。
論語:現代日本語訳
逐語訳
周公が魯公に言った。「貴族は身内に与えないなら、重臣に用いられない怨みを持たせない。だからなじみの者は大きな理由が無ければ、必ず捨ててはならないぞ。(万能が)備わっていることを一人に求めてはならない。」
意訳
周公が、領地に赴く魯公に言った。
「身内にひいきをするな。それなら重臣に”ケチな殿様じゃ”と恨まれずに済む。だからお前を恨んでもいない古くからの家臣を、大した理由無しに追い払うな。家臣も人の子だ、何でも出来るわけではないからな。」
従来訳
周公が魯公にいわれた。――
「君主たるものは親族を見捨てるものではない。大臣をして信任のうすきをかこたせてはならぬ。古くからの臣下は、重大な理由がなければ棄てないがいい。一人の人に何もかも備わるのを求めてはならぬ。」下村湖人『現代訳論語』
現代中国での解釈例
周公對魯公說:「君子不疏遠親屬,不使大臣抱怨不受重用。如果老臣舊友沒犯大錯,就不要拋棄他們。不要對人求全則備。」
周公が魯公に言った。「君子は親族と疎遠にならず、大臣に重用されない恨みを抱かせない。もし老臣や旧友に重大な間違いが無ければ、絶対に彼らを追い払ってはならない。他人に全てが揃っているのを求めてはならない。」
論語:語釈
周公

血統上の魯国の始祖、周公旦のこと。論語では、周王朝の一族で開国の功臣で、摂政も務めたとされる人物。その子・伯禽が魯公に任じられて魯国が始まった。
魯公
諸侯としての魯国の開祖、伯禽のこと。伯禽の代から魯に居付いて諸侯となる。
君子

孔子から一世紀後の孟子が、自分の商売の都合から”教養ある人格者”その他その時の都合で多様な語義をでっち上げるまで、「君子」とは単純に参政権のある”貴族”を意味した。ただし貴族と言っても領主ばかりではなく、周代では城郭都市内に住む商工民にも参政権と従軍義務があり、「君子」の範疇に入る。詳細は論語における「君子」を参照。
施

(古文)
論語の本章では、「ほどこす」と読んで”呉れてやる”。古来”押しやる・遠ざける”と解するが、例によって儒者のデタラメで根拠が無い。
曰君子不施其親註孔安國曰施易也不以他人親易其親也
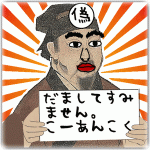
本文「曰君子不施其親」
孔安国「施とは取り替えることである。他人を任命せず、身内は身内で交替させるという意味である。」(『論語集解義疏』)
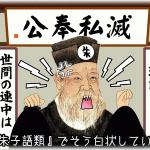
朱子「施の字は陸氏の『経典釈文』では弛むの字になっている。福氏の本でもそうなっている。魯公とは周公の子、伯禽である。弛とは、捨てる事だ。」(『論語集注』)
『経典釈文』は隋から初唐の陸徳明が書いた、主に音の面から儒教経典に付けた注で、見るべき点はあってもそのテキストが正しい証拠はどこにも無い。「福本」とはどの本か分からない程度に訳者は不勉強だが、いずれ儒者のでっち上げ本だろうから調べる気力が途中で尽きた。
「施」の初出は甲骨文。『学研漢和大字典』によると也は長いへびを描いた象形文字で、長くのびる意を含む。施は「はた+〔音符〕也」の会意兼形声文字で、吹き流しが長くのびること、という。春秋末期までに、”のばす”・”およぼす”の意がある。詳細は論語語釈「施」を参照。
不施
論語の本章では”呉れてやらない”。版本により「施」”ほどこす”と「弛」”ゆるむ・いい加減に扱う”の異同がある。時系列で並べると次の通り。
つまり南北朝末期から唐の半ばまでは、「不弛」と書かれ、”君子は身内びいきをしろ”と解されていたことになる。それが晩唐になって、”身内びいきするな”に戻った。おそらくは『論語義疏』との矛盾を解決したと思われる。
なお『論語義疏』が編まれたのは南北朝時代だが、ブツとしては日本の足利本がおそらく最古で、非公開。その足利本のほか当時参照できる諸本によって校訂したのが、大正時代の武内博士による懐徳堂本。それをさらに21世紀になって中国の漢学者が新たな出土資料を集めて校訂したのが北京中華書局本。
だから時系列としては最後に回るのだが、南朝・梁で皇侃が編纂したときは、おそらく漢石経にならい「施」になっていたと思われる。
怨
論語の本章では”うらむ”。この文字の初出は戦国文字で、論語の時代に存在しないが、同音の夗が論語時代の置換候補になる。詳細は論語語釈「怨」を参照。
以(イ)


(甲骨文)
論語の本章では”用いる”。初出は甲骨文。人が手に道具を持った象形。原義は”手に持つ”。論語の時代までに、名詞(人名)、動詞”用いる”、接続詞”そして”の語義があったが、前置詞”~で”に用いる例は確認できない。ただしほとんどの前置詞の例は、”用いる”と動詞に解せば春秋時代の不在を回避できる。詳細は論語語釈「以」を参照。
怨乎不以
ここでの「乎」は助詞として用いられ、「~に」「~を」「~より」と読んで、起点・対象・比較・受身の意を示す。「以」は動詞の”用いる”の意として用いられている。論語語釈「乎」・論語語釈「以」を参照。
故舊(旧)


(金文)
論語の本章では”古いなじみの者”と古来解する。だが論語の時代は一文字一語が原則で、熟語はないと考えるべき。したがって、「故」=”だから”、「旧」=”古いなじみ”と呼んだ方が理にかなう。
大故


(金文)
論語の本章のここでは”大きな理由”。「故」について『学研漢和大字典』には事件や事故など、おこってくるよくない事がら。さしさわり、というが、その意に転じた理由は不明。

「故」の初出は西周早期の金文。『学研漢和大字典』によると古は、かたくなった頭骨、またはかたいかぶとを描いた象形文字。故は「攴(動詞の記号)+〔音符〕古」会意兼形声文字で、かたまって固定した事実になること、という。論語語釈「故」を参照。
則(ソク)


(甲骨文)
論語の本章では、”…の場合は”。初出は甲骨文。字形は「鼎」”三本脚の青銅器”と「人」の組み合わせで、大きな青銅器の銘文に人が恐れ入るさま。原義は”法律”。論語の時代=金文の時代までに、”法”・”則る”・”刻む”の意と、「すなわち」と読む接続詞の用法が見える。詳細は論語語釈「則」を参照。
無求備於一人
論語の本章では、「多芸」などを補って”一人に万能が備わっているのを求めない”と古来解する。だがそれは句読を切り違えたからその必要があるのであり、”古い家臣を大きな理由なく放逐してはならない”という前の句の続きとして考えれば、”人は万能ではないのだから”という理由を言った節と素直に解せる。
論語:付記
論語の本章は上記の検討通り、文字史的に春秋時代の文と考えてよく、唯一「也」の字を句末で用いている点は、戦国時代以降の語法になる。しかし句末の語気を示す言葉は筆写のうちにいくらでも変わったり増減したりするので、これだけで捏造と断じることは出来ない。
ただし古注のでたらめな注釈は受け入れがたい。後漢の儒者は揃って馬鹿ばかりだった。書き換えをやらせた霊帝は、ろくでなしが多い後漢の皇帝の中でも、極めつけの暗君だった。君臣揃って、身内びいきを周公サマに公認してほしかったのだ。
その事情は、論語解説「後漢というふざけた帝国」を参照。
本章を武内義雄『論語之研究』では、前章同様、篇末の付け足しと断じている。その理由は、武内博士も中国儒者のデタラメを真に受けて、古来の誤読を改めようとしなかったから。そうなったわけは、日本での漢学教育が、師匠のオウム返しを歴代続けていたからだ。
だからフビライ=ハンから国書が届いたとき、五山の坊主は読めと言われて困ったはずで、おそらくは博多あたりの貿易商から、こっそり「実はこう書いてあります」と教えて貰ったのだろう。東大寺が所蔵する写しに付けられた訓点を見ると、そう疑いたくなってくる。
 (クリックで拡大)
(クリックで拡大)
そして既存の論語本でも、「君子不施其親、不使大臣怨乎不以」を”身内を大事にするから、重臣が不満を持たない”と解する例があるが、「んなわきゃねえだろ」と誰もが思うだろう。これは中国社会の宿痾というべき身内びいきに、大義名分を与えるためのこじつけ。
身内びいきするから不満が起こるのである。動物学で類人猿を使った実験によると、サルはお貰いの絶対額より、他ザルとの差別の方に激しく怒るそうで、人間も類人猿の一つであるからには当然だ。だがそんなことも分からない連中が、デタラメな解釈を垂れ流してきた。
これもオウム返しと猿真似でよしとしていたことの副産物で、自分で考えようとしない。だがそういう本を当てにせず自文で読解すると、これが存外楽しいのである。それなりの修業は要るが、偉そうな連中の恥ずかしい裏面を覗いて罵倒するのは、金のかからない娯楽でもある。
ためしにそういう論語センセイに、「身内びいきするとどうして家臣の不満が止まるのですか?」と聞いてみるとよい。猿のさらなる猿真似で、適当な言いくるめをするのがせいぜいのはずだ。そういう末猿を言葉丁寧におちょくってみるのは、天誅の一種でもあろう。
最後に中国のサル話を、重複を恐れず記しておく。

朝三暮四
勞神明為一,而不知其同也,謂之朝三。何謂朝三?曰狙公賦芧,曰:「朝三而莫四。」眾狙皆怒。曰:「然則朝四而莫三。」眾狙皆悅。名實未虧,而喜怒為用,亦因是也。是以聖人和之以是非,而休乎天鈞,是之謂兩行。

神経をすり減らして、やっと「AとBに区別が無い」と知るのは、元々同じだと知らなかったゆえの徒労に過ぎない。これを「朝三」という。どうしてそう言うか?
サル好きのおやじが沢山サルを飼っていて、ある日「ドングリを朝に三つ、夕方に四つやろう」とサルどもに告げた。これまでより減らされたサルどもは皆キーキーと怒った。そこで「では朝に四つ、夕方に三つにしよう」と言うと、サルどもは皆喜んだ。
どちらも合計は同じなのに、怒ったり喜んだりするのは、やはりもともと同じであることを知らないからだ。だから聖人は皆を納得させるのに、こういうペテンは使わない。天の恵みも同じで、もともとえこひいきが無い。これを「うまく回っている」と言うのだ。(『荘子』斉物論6。『列子』黄帝19にも同様の話があるが、その現代語訳は論語顔淵篇2付記に掲載)





コメント