原文
道可道,非常道。名可名,非常名。無名天地之始;有名萬物之母。故常無欲,以觀其妙;常有欲,以觀其徼。此兩者,同出而異名,同謂之玄。玄之又玄,衆妙之門。
復元白文



























 妙
妙 






















 妙
妙

※物→(甲骨文)/欲→谷。本章は「妙」の字が金文以前に存在しない。戦国中末期の竹簡(「郭店楚簡」老子甲8)からしか無い。しかも「妙」を外すと本章は成立しない。老子道徳経の本章は、戦国時代以降の道士による創作である。
書き下し
道(みち)の道(みち)とす可(べ)きは、常(つね)の道(みち)に非(あら)ず。名(な)の名(な)とす可(べ)きは、常(つね)の名(な)に非(あら)ず。名(な)無(な)きは天(あめ)地(つち)の始(はじ)めにして、名(な)有(あ)るは萬(よろづ)物(もの)の母(はは)なり。故(ゆえ)に常(つね)は欲(もとめ)無(な)かれば、以(もっ)て其(そ)の妙(たへ)を観(み)る。常(つね)に欲(もとめ)有(あ)らば、以(もっ)て其(そ)の徼(てらひ)を観(み)ん。此(こ)の兩(ふた)つなる者(もの)は、同(おな)じきより出(い)でて名(な)を異(こと)にす。同(おな)じく之(これ)を玄(くろ)と謂(い)う。玄(くろ)の又(また)玄(くろ)は、衆(もろ)妙(たへ)の門(うから)なり。
現代日本語訳
逐語訳
道で道であると定義できる道は、不変の道ではない。名称の名づけられる名称は、不変の名称ではない。名称が無いものが天地の始めで、名称があるものが万物の母である。だから不変の法則に欲が無ければ、その作用によるその微妙な働きを並べて見る。不変の法則に欲があれば、その作用による激しい行動を並べて見る。この両者は、同じ所より出て名が違う。同じく両者を黒という。黒と黒との集合は、微妙な作用が集まった一族である。
意訳

目に見える宇宙の法則は、常に変化して止まない。変化して止まないものに名を付けても、すぐにその名にふさわしくなくなってしまう。だがこの名づけようも無い変化して止まない何かが、宇宙を生み出した根源の力であり、変化が緩やかになってやっと名づけられるようになった状態の何かが、物質世界を生み出したのだ。
目に見える宇宙の法則のさらにその奥にある、変わらない根本法則には、通常は何かをしようとする欲望が無い。だからその働きで、穏やかにありとあらゆるものを生み出すのが見える。だがもし一時的な傾向を持って、何かをしようとするなら、その激しい変化を見て取れるだろう。穏やかな通常の営み、激しい一時的な営み、これらは共に根本法則が生み出したものでありながら、その著しい違いのために、別の名を持っているのだ。
しかし両者を混ぜたら、必ず真っ黒になる。ありとあらゆるものを混ぜたら、必ずそれは真っ黒になるが、それでもなお、宇宙の根本法則が生み出した、全てを包み込む一族であるには違いない。
付記
解説
古来難解とされる老子道徳経だが、本章に限ればさほど難しいことを言っているわけではない。難解と言われたのは、訳を付けた公家や儒者や漢学教授が不真面目で、読み下しに手抜きをして音読みで済ませたのと、現代宇宙論の一つにも興味を持たなかったからだ。
「無名天地之始、有名萬物之母」などは、文字を眺めていても何のことか分からないが、「宇宙の晴れ上がり」を知っていれば一発で類推できる。漢学教授に、『老子』の訳本を出すぐらいなら宇宙論の基礎ぐらい知っとけ、と求めるのは無茶だが、次のような不真面目は困る。
故(ゆえ)に常(つね)に無(む)は以(もっ)て其(そ)の妙(みょう)を観(み)んと欲(ほっ)し、常(つね)に有(う)は以(もっ)て其(そ)の徼(きょう)を観(み)んと欲(ほっ)す。(某教授『老子』)
ここはまず文法を誤り句読を切り間違えているのだが、その前にこういう、読み下したようで漢字一字一字を解釈せず、音読みで済ませている巫山戯(ふざけ)た読み下しを、訳者は「ジョーバンキシ読み」と呼ぶことにしている。常盤貴子氏のことだと分かるだろうか。「ミョウ」って何だ。「キョウ」って何だ。それを調べるのが、読み下しと翻訳というものである。
故常無欲、以觀其妙。常有欲、以觀其徼。
中国語は古代も現代もSVO型の言語だから、まず「常」は主語で、「無」「有」は述語動詞で、「欲」は客語≒目的語だ。つまり「常は欲無し」。従ってよほど中国語が不自由な書き手でない限り、「常に無は…欲し」などという読みにはなりようが無い。
もし他の解釈をするなら、「常」を修飾語と解して、「常の無は欲す、以てその妙を見る」=”恒常的に形無きものが働いて、その結果ありとあらゆるものを作り出すのを見て取れる”になるだろう。漢文解釈に別解はあっていいが、不真面目は許されない。読者と世間の迷惑だ。
この某教授は超有力大学のかなり高名な男だが、べつの自著でこういうふざけ方をしている。
譯読というのは、漢文の各〻の字義に対する日本語の譯語をあてて讀むことで、これを訓讀という。もっとも中國の單語のすべてに譯語をつくることができず、中國の發音をそのまま使った單語もある(それらは今日まで日本語の中でそのまま使われているものも少なくない。いわゆる「字音語」または「漢語」)。してみると、漢文の讀み方としては、譯讀の單語と音讀の單語とがいりまじっていることになるが、言語の構造からいえば、日本語として了解できるようになっているから、訓讀が主で音讀が從だということになる。それでこのように譯讀された漢文を訓讀漢文という。
「ツネニムハモッテソノミョーヲミントホッシ」と書かれて「日本語として了解できる」わけがない。「ハッキタイダ」で”やまたのおろち”と理解せい、と要求するに等しい。自分の不勉強と手抜きと読者への没義道に開き直り、「ジョーバンキシ」で結構だ、というわけだが、この文は漢文の読解教則本に記されたもので、名門出版社から出たかなり厚めの本でもある。法外とは言えないが安価でもない。あわれな読者はこんなものを買わされた挙げ句、漢文の読み方が何も身に付かないままで終わり、あるいは途中で投げ出して諦めることになる。
すでに新字体が発表された7年後の初版でもあり、新仮名遣いをしておきながら、漢字だけ旧字にするというのに現れた、漢文業者の世間に対するもったいつけ、思い上がりは、精神の腐り果てた人間にしか見られないことだと思う。一般に漢学教授とは、こういうろくでもない連中だ。詳細は論語雍也篇27余話「そうだ漢学教授しよう」を参照。
もし諸賢が漢文を読めるようになりたいなら、拙稿「漢文が読めるようになる方法」が何かのきっかけになるとよいのだが。
老子の実在
老子道徳経の本章は、書体から戦国中末期以降の創作であることは確定だが、老子という歴史人物について、訳者は疑いを持っていない。伝説では老子道徳経は、若き日の孔子に礼法などの教えを授けた教師の記した書で、老子は周王室の文書館に勤務していた。
孔子を送り出した後、世が乱れたので辞職して西に向かい、国境の関所役人に乞われて、老子道徳経を書いて授けた後、西の彼方へ去ったという。

おそらく孔子に教えた老子は実在しただろう。だが資料にはその後、人間にはあり得ない長寿の人物として、老子の事跡が記述される。それらもおそらく実在し、つまり老子という名は落語家同様、代々受け継がれる学派の総帥の名跡だったのだ。

それを証す史料は無いが、太古の研究とはそういうものである。また上掲の現代語訳は訳者なりの解釈であって、本当に原文にそう書いているという保証が出来ない。元々多義語である漢字に加え、原文では言葉の定義をしてから書いてはいないからだ。

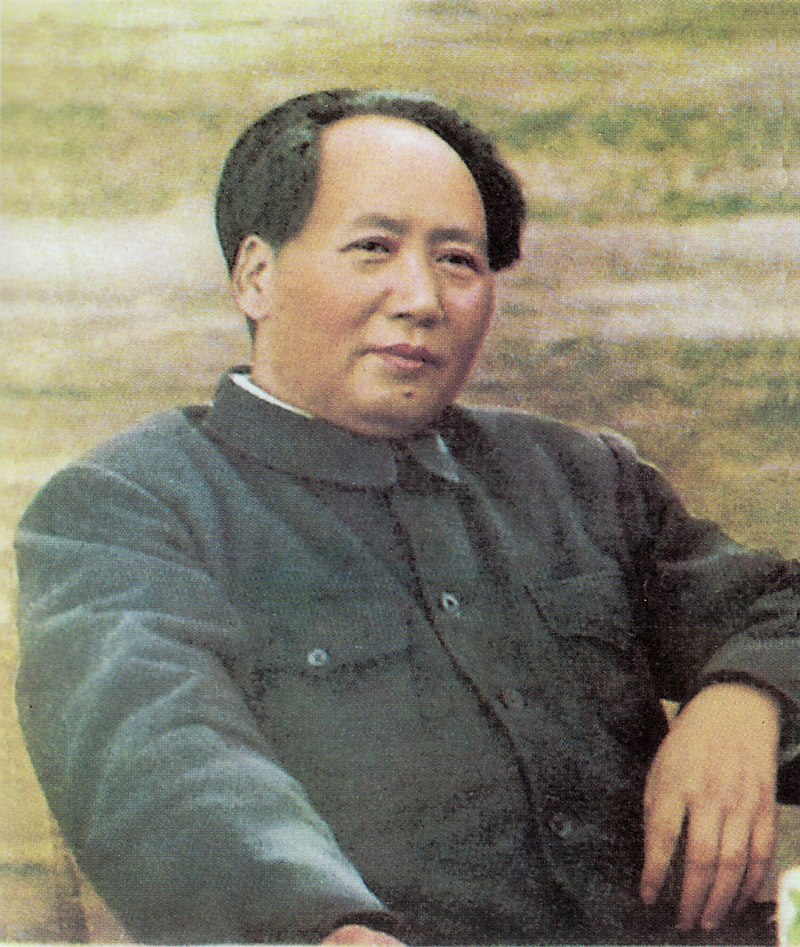

コメント
私は、学生時代から古典文学を苦手として居りまして、漢文も日本の古文も解りたいのです。しかし、苦手で、老子道徳経の漢文と読み下し文と判りやすい現代語訳が書いて有る書籍を手に入れたいのですが、どの書籍が良いでしょうか?
「老子道徳経の漢文と読み下し文」と「現代語訳が書いて有る書籍」はどこにでも転がっていますしどれ選んでも同じです。「判りやすい」かどうかは読み手次第ですから何とも言えません。